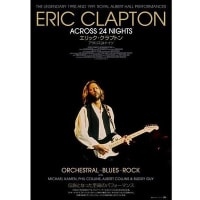久々に書かねばならない!と思った映画にであった。ヴィゴ・モーテンセン特集の一つ、アルベール・カミュ原作の「涙するまで、生きる」だ。
いつものように、何の気なしに、見れる映画をチョイスして、日曜日にこれを見る!と決めていた。その前日に、例のとんでもないことが起こった。フランスはパリで起こった同時多発テロだ。非道この上ない事件は、銃口を、金曜日の夜の、週末を楽しんでいた市民に向けて、放たれた。コンサートを見に来た人、食事を楽しんでいた人、サッカーを観戦に来た人、不条理にも、非道にも、理不尽にも、命を奪われた。この人たちの命を奪うことに、何の躊躇もなかった、というような様子を聞いて、やりきれなさでいっぱいになった。
そして、もやもやと何とも言えないいやーーな気持ちを持ったままで鑑賞となったのが、この映画であった。アルジェリアが舞台。アルジェリアで生まれ、アルジェリアで育ったカミュの分身ともいえる、ダリュが主人公。間違いなくフランス人であるが、故郷はアルジェリアだ。
アルジェリアは19世紀前半にフランスの植民地になったあと、本国の一部として組み込まれた。もちろん、先住民は入植者によって支配され、いわゆる帝国主義時代の代表的な宗主国と植民地の関係になった。第一次世界大戦、第二次世界大戦の時は、もちろんフランス軍の兵士として戦い、その後の独立運動の指導者となっていく。
第二次大戦後、世界各地で、独立運動の嵐が吹き荒れ、アジア諸国で様々な国が独立を果たす。フランスは?と考えると、ちょっと毛色が違ってくるかもしれない。フランス自体がナチスの支配下にあったからだ。他の戦勝国と違って、フランスは戦中、ナチスの支配下にいた。その真っ最中に作られた映画が、私の生涯のベスト1の「天井桟敷の人々」だ。支配もし、支配もされてきた。じゃあ、支配される側に寄り添えるかというと、何とも言えない。
見る前は、そんなことは思いもしなかったのだが、見ているうちに、いろいろな考えが次々と思い浮かんできた。さて、映画。
ダリュは元兵士。妻を亡くし、今は地元の子供たちを相手に、先生をしている。生きる気力にあふれているとは到底言い難い。なんとなく生きていると言う風に見える。そこに、意外な訪問者がやってきた。憲兵が、いとこを殺害したという男を連れてきた。山を越えた街に連行して、裁判を受けさせろ、との指示を伝える。そんな指示には従えないと強く訴えるが、男を置いて、憲兵は行ってしまう。厄介者を押し付けられてしまう。
男は貧しい暮らしの中でカツカツに生きてきたが、いとこに麦を盗まれ、いとこを殺してしまった。「目には目を」の原則の中、男は殺されても仕方がない。しかし、もし自分が親戚に殺されれば、その仇を弟が討たなければならなくなる。連鎖は終わらない。何も語らなかった男だが、裁判をする街に向かう中で、徐々に心を開き、ダリュに語っていくのだ。
この連鎖を終わらせるためには、自分が裁判を受けて、フランス人に処刑されるのがいい・・・。その結末を男は選んだ。死ぬために向う。
二人の旅路には、なぜか次々と、トラブルが舞い込んでくる。典型的な巻き込まれ型のお話だ。しかし、その苦難を乗り越えるうちに、二人の間に絆が生まれてくる。名前を聞かなかったのは死刑になるのがわかっていたからか。でも、長男だと聞くと、「名前はモハメドか・・」と、語りかける。結婚したかったというモハメド。「女って?」とお茶目に聞く。
モハメドのことを思いやりながら、自分のことを顧みるダリュ。アルジェで生まれたフランス人。アルジェリア人からはフランス人とみられ、フランス人からはアルジェリア人と見下される。アイデンティティを模索するダリュの目が空虚に見えてくる。
この後、彼らを待ち受けるのは、アルジェリア戦争だ。それを経て、アルジェリアは独立を果たす。モハメドに生きることを示唆し、復讐の連鎖を終わらせたことと、アルジェリアが一個の国として独立していったことがダブって見えてくる。
フランス・パリは魅力的な街だ。歴史がその最大の要因だと思っている。しかし、今回のこのテロ事件は、歴史を汚した。テロにあってしかるべきものなどない。フランスのたどった歴史を顧みながら、そんなことを思った。
今日明日の上映だが、これはぜひとも見ていただきたい作品。ヴィゴのマルチな才能と、哀しげなまなざしがものすごく印象的だ。


◎◎◎◎○
「涙するまで、生きる」
監督 ダビド・オールホッフェン
原作アルベール・カミュ
出演 ヴィゴ・モーテンセンダリュ レダ・カティブモハメド
いつものように、何の気なしに、見れる映画をチョイスして、日曜日にこれを見る!と決めていた。その前日に、例のとんでもないことが起こった。フランスはパリで起こった同時多発テロだ。非道この上ない事件は、銃口を、金曜日の夜の、週末を楽しんでいた市民に向けて、放たれた。コンサートを見に来た人、食事を楽しんでいた人、サッカーを観戦に来た人、不条理にも、非道にも、理不尽にも、命を奪われた。この人たちの命を奪うことに、何の躊躇もなかった、というような様子を聞いて、やりきれなさでいっぱいになった。
そして、もやもやと何とも言えないいやーーな気持ちを持ったままで鑑賞となったのが、この映画であった。アルジェリアが舞台。アルジェリアで生まれ、アルジェリアで育ったカミュの分身ともいえる、ダリュが主人公。間違いなくフランス人であるが、故郷はアルジェリアだ。
アルジェリアは19世紀前半にフランスの植民地になったあと、本国の一部として組み込まれた。もちろん、先住民は入植者によって支配され、いわゆる帝国主義時代の代表的な宗主国と植民地の関係になった。第一次世界大戦、第二次世界大戦の時は、もちろんフランス軍の兵士として戦い、その後の独立運動の指導者となっていく。
第二次大戦後、世界各地で、独立運動の嵐が吹き荒れ、アジア諸国で様々な国が独立を果たす。フランスは?と考えると、ちょっと毛色が違ってくるかもしれない。フランス自体がナチスの支配下にあったからだ。他の戦勝国と違って、フランスは戦中、ナチスの支配下にいた。その真っ最中に作られた映画が、私の生涯のベスト1の「天井桟敷の人々」だ。支配もし、支配もされてきた。じゃあ、支配される側に寄り添えるかというと、何とも言えない。
見る前は、そんなことは思いもしなかったのだが、見ているうちに、いろいろな考えが次々と思い浮かんできた。さて、映画。
ダリュは元兵士。妻を亡くし、今は地元の子供たちを相手に、先生をしている。生きる気力にあふれているとは到底言い難い。なんとなく生きていると言う風に見える。そこに、意外な訪問者がやってきた。憲兵が、いとこを殺害したという男を連れてきた。山を越えた街に連行して、裁判を受けさせろ、との指示を伝える。そんな指示には従えないと強く訴えるが、男を置いて、憲兵は行ってしまう。厄介者を押し付けられてしまう。
男は貧しい暮らしの中でカツカツに生きてきたが、いとこに麦を盗まれ、いとこを殺してしまった。「目には目を」の原則の中、男は殺されても仕方がない。しかし、もし自分が親戚に殺されれば、その仇を弟が討たなければならなくなる。連鎖は終わらない。何も語らなかった男だが、裁判をする街に向かう中で、徐々に心を開き、ダリュに語っていくのだ。
この連鎖を終わらせるためには、自分が裁判を受けて、フランス人に処刑されるのがいい・・・。その結末を男は選んだ。死ぬために向う。
二人の旅路には、なぜか次々と、トラブルが舞い込んでくる。典型的な巻き込まれ型のお話だ。しかし、その苦難を乗り越えるうちに、二人の間に絆が生まれてくる。名前を聞かなかったのは死刑になるのがわかっていたからか。でも、長男だと聞くと、「名前はモハメドか・・」と、語りかける。結婚したかったというモハメド。「女って?」とお茶目に聞く。
モハメドのことを思いやりながら、自分のことを顧みるダリュ。アルジェで生まれたフランス人。アルジェリア人からはフランス人とみられ、フランス人からはアルジェリア人と見下される。アイデンティティを模索するダリュの目が空虚に見えてくる。
この後、彼らを待ち受けるのは、アルジェリア戦争だ。それを経て、アルジェリアは独立を果たす。モハメドに生きることを示唆し、復讐の連鎖を終わらせたことと、アルジェリアが一個の国として独立していったことがダブって見えてくる。
フランス・パリは魅力的な街だ。歴史がその最大の要因だと思っている。しかし、今回のこのテロ事件は、歴史を汚した。テロにあってしかるべきものなどない。フランスのたどった歴史を顧みながら、そんなことを思った。
今日明日の上映だが、これはぜひとも見ていただきたい作品。ヴィゴのマルチな才能と、哀しげなまなざしがものすごく印象的だ。


◎◎◎◎○
「涙するまで、生きる」
監督 ダビド・オールホッフェン
原作アルベール・カミュ
出演 ヴィゴ・モーテンセンダリュ レダ・カティブモハメド