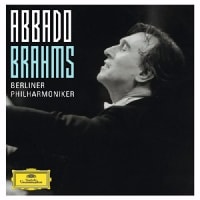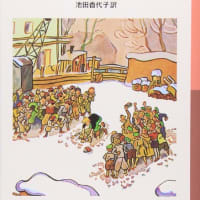【ムスカリと春】
さて、今回は愛榮のターンですね♪(^^)
といっても、言い訳事項として「韓国語わかんないww」っていう以外では、特に何も書くことなかったり
ええと、なのでどうしようかなと思ったんですけど、まあ本当はあとがき☆にでも書こうかなって思ってたことを前倒し的に少し書いてしまおうかと。。。
まあ、愛榮のことというよりもそれは、六花のⅠのほうで主人公だった葵とリョウのことなんですけど(笑)
なんていうか、自分でも書いててたまーに、恋愛の頂点にある時にお話が終わってその後結婚したらしい……くらいのが、実はちょうどいいのかな、なんて(^^;)
簡単にいっちゃえば、【悲報】かつてのフィギュアスケートの天才、結婚してどんどん凡人にwwみたいな、なんかそういう話の流れになってるんじゃないかな~という気がしたり。。。
葵もまあ、なんというかその後は振付師をしつつ平凡な主婦になった的な??
もちろん、館神コーチに孫を抱っこさせたいという野望(?)が自分的に叶ったので、これはこれでいいのかなってわたし的に思ったりはするんですけれど(笑)
そんで、なんか三人ともすごいスケーターに育っていくみたいなので……わたしがもし、今の「真・四回転時代」を迎えてからこの小説書き始めてたら、たぶん六花のⅠの時からほとんど全員もっとバンバントゥループとサルコウ以外の四回転を跳んでもらってたと思います。
いえ、リョウに関してはほんともう……全種類の四回転が跳べるとか、その上IQが187あるとか、どう考えても設定盛りすぎだろwwって自分に突っ込み入れながら書いてたので、Ⅰを書き終わったあと、しょーまくんが四回転フリップを決めたりとか、ぼーやんくんが四回転ルッツを跳んだりするのを見て――「えへっ。実はちっとも盛りすぎじゃなかったんだ 」と思ったという(笑)
」と思ったという(笑)
しかも、極めつけがチェンくんですよwwフリーで5クワド達成したってだけじゃなく、小さい頃からバレエやってたりピアノ弾けたり、自分でも振付とかしちゃったり、将来は医者になりたいとか言ってたり……いえ、チェンくんのことを先に知ってたら、リョウのこの設定でもちっとも盛りすぎじゃないと思って、むしろ焦ってたと思います(^^;)
なので、光くんはある意味ちょっと残念だったのかなって思ったりもしています。。。
なんでかっていうと、書きはじめた時から今の「真・四回転時代」が到来していたら――プログラムのほうももっと華々しいものになってたのかなって思ったりするし、これは剛くんや礼央くんにしてもそうなんですよね。
そんで、この中で光くんは四回転ルッツ、剛くんは四回転フリップ、礼央はルカと同じく四回転ループを練習して跳べるようになったっていうことにするとか……まあ、でもわたし、フィクションなのにそのあたりのことは現実的に考えて、「そんな簡単にぽんぽん多種類のクワドを跳べるかよ 」との思いもあり、光くんも剛も礼央も結局トゥループとサルコウだけで攻めて、あとは表現力に磨きをかける――みたいな感じになっちゃったのかなという気がします(^^;)
」との思いもあり、光くんも剛も礼央も結局トゥループとサルコウだけで攻めて、あとは表現力に磨きをかける――みたいな感じになっちゃったのかなという気がします(^^;)
あー、あとこれははっきり言ってどうでもいいことなんですけど、わたし文章打ってる時に結構誤字が多くて……フィギュアスケートって書くところをファギュアスケートって書いてたりとか、インタビューがイタンビューになってたりとか、そういうのが結構あるんですけど、その中でたまーに四回転と書くところを三回転って書いてたりすることがあって――自分的にその打ち間違いでちょっと受けたのが……ルカの四回転ループのところを三回くらい三回転ループとか書いちゃってて、直しながら「ぷぷぷ☆(ΦωΦ)」と笑っちゃったりとか。。。
いえ、「俺の必殺技は三回転ループだ 」とか仮に大威張りで言ってたら、「え?それが一体どーしたの??
」とか仮に大威張りで言ってたら、「え?それが一体どーしたの?? 」的になるんじゃないかな~なんて、そう思ったりして(笑)
」的になるんじゃないかな~なんて、そう思ったりして(笑)
まあ、それはさておき、葵とリョウの三人の子供たちの時代には、きっと彼らも多種類のクワドをバンバン跳んでるんじゃないかなっていう気がします。蘭は前にどっかで四回転トゥループの次は四回転サルコウに挑戦したいって言ってた気がするんですけど、今はまだ小さい愛ちゃんもまた、将来大きくなってのち、じいじの館神コーチの元でジャンプを教えてもらったりするんじゃないかなって思います♪(^^)
それではまた~!!
ダイヤモンド・エッジ<第二部>-【68】-
ザグレブオリンピックのあった年の世界フィギュア選手権で優勝したのは、男子が小早川圭、そして女子が金愛榮だった。
ふたりとも、オリンピックでの不完全燃焼な演技の雪辱戦としての世界選手権だった。オリンピックで金メダルを取った選手はそこで達成感の頂点を味わうため、そのあとにある世界選手権ではモチべーションの落ちていることが多いものだが、その中で光も蘭も健闘はした。けれど、オリンピックの時の演技が最高潮であったとすると、そこから全体として何かが落ちてきている感の否めない演技ではあった。
結局のところ、この世界選手権で光は銅メダル、蘭は銀メダルだった。男子の銀メダルはレオン・アーヴィング、女子の銅メダルはリュドミラ・ペトロワだった。レオンはいつも通りの安定した演技を見せ、リュドミラ・ペトロワはやはり、オリンピックで力を使い果たしてしまったのか、フリーではエイトトリプルが決まらず、ジャンプをふたつミスした。
とはいえ、光は最後の世界選手権で表彰台に上がれたというだけでも十分満足であり、バックステージではレオンや圭と仲良く互いの健闘を称えあった。蘭は金愛榮に負けて悔しくはあったが、妙にそのことに納得してもいた。自分がもし彼女と逆の立場だったとしたら、やはり死力を尽くしてオリンピックでの雪辱を晴らそうとしたろうからだ。
(お互い、そういう時の相手には勝てないってことか……)
そう思い、蘭は素直に金愛榮のことをフラワーセレモニーでもバックステージに下がってきてからも祝福した。リュドミラも「何故か不思議と今回は銅メダルでも悔しくない」と言っており、「むしろメダルが取れただけでも幸運だった」とさえ言っているのを聞いて、オリンピック後、やはり彼女もモチベーションが下がっていたのだろうと蘭は察した。
この世界選手権では、試合前の記者会見でサーシャ・アルツェバルスカヤが引退を表明していた。引退の理由は、「オリンピックで思ったような成績が残せなかったから」というものだったが、実際はラリサに破門されたも同然だったと言ったほうがいいのかもしれない。破門、などと言っても、ラリサは何も薬物のことを聞いて冷たく弟子のことを突き放したというわけではない。
ただし、マリアとリュドミラからサーシャの薬物問題を聞かされてラリサが怒り狂ったというのは事実である。また、オリンピックでは上位四名の選手の他に無作為で一名選ばれてドーピング検査を受けるわけだが、この時選ばれたのはサーシャではなくカナダのベアトリクス・アディントンだった。
もしこの時、サーシャが選ばれていて薬物が検出されたとしたら、とてつもない大スキャンダルに発展していたことだろう。オリンピック後、ラリサはモスクワへ戻ってのち、そのことを彼女に問い詰めた。そして泣きながらひたすらあやまるサーシャに引退を勧め、矯正施設に入るよう諭したのだ。「わたしはあなたのことを見捨てるわけじゃないのよ。むしろ小さい時から見てきたあなたのことが可愛いと思えばこそ、こう言うのよ」と、そう言って……。
また、マリア・ラヴロワはこの大会で、リュドミラに迫る勢いで高得点を叩きだし、第四位だった。ふたりは仲直りして親友同士に戻るのと同時、再びライバルとして競いはじめたのだ。今は一歩も二歩も先を行っているのはリュドミラのほうではある。けれどマリアもそんな彼女にこれ以上引き離されまいとして、オリンピック後はリュドミラ以上に練習に励んでいたのだ。
そして金愛榮だが、オリンピックの女子シングルの試合が終わるのと同時に――ボブ・カーティスがアリーナ席の最前列にいた例のストライプのプレゼントを毎回くれる婦人に声をかけた結果として、次のことがわかっていた。
なんといっても、カーティスは韓国語など出来ないため、リョウが自分で開発した翻訳機を使って彼女と会話することになった。
「ワタシハエヨン・キムノコーチノリョウ・コバヤカワノダイリニンデス」
カーティスの英語が韓国語に翻訳されても、白髪頭でてっぺんのほうの毛髪が薄い初老の女性は、ただひたすらに首を傾げるばかりだった。何分、カーティスはボディガードだけあって体型も顔つきもいかつい(丸禿げでいつもサングラスをかけている)。当然女性のほうではそれだけでも彼のことを不審に思う理由は十分だったといえる。
「What country are you from?」(あなたの出身国は?)
実をいうと彼女――佐野律子は、日本人で韓国語などさっぱりしゃべれなかったのだった。また、英語のほうもまるで堪能ではなかったが、それでも男が言った言葉については大体のところ理解した。
「From Japan」
律子がそう答えると、カーティスは驚き、変換する言語を日本語に切り替えて、先ほどと同じ言葉をマイク部分に向かって繰り返した。
「私は金愛榮のコーチ、小早川亮の代理人です」
「ああ、そうでしたか」
律子のほうでも驚きの表情を顔に浮かべ、次のカーティスの言葉を待った。
「実は、金愛榮があなたに直接会ってお話をしたいそうです。私は彼女の元まで貴女のことを連れていくようにリョウに頼まれたのです。よろしいでしょうか?」
「はあ……」
(まさか裕福な日本人と間違われて、誘拐されるなんてこと、ないでしょうしねえ)
それでも、もし愛榮がこのオリンピックという大舞台でメダルを取れずに終わってなかったとしたら――彼女は大金持ちのコーチの家に引き取られて幸せなのだと思い、律子は彼女とは会おうと思わなかったかもしれない。
けれど、たった少しばかり前に終わった演技を見ていて、律子は涙が止まらなかった。愛榮が一番いい演技ができるようにとあれほど祈ったのに、彼女のお父さんとお母さんも天国で見守っていてくれると信じていたのに、結果的に愛榮は金メダルどころか銅メダルにも手が届かないで終わってしまったのだから。
これまでの試合であまりミスをしているのを見たことがなかっただけに、それだけ大きなプレッシャーと愛榮は戦っていたのだろうと思い、律子は胸が潰れる思いだった。ここまで来るのに彼女がどれほど努力を積み重ねてきたのか……律子には想像してみることさえ出来ない。その上、故郷に帰って慰めてくれるような家族もないのだと思うと、突然愛榮と会って彼女のお母さんのことを話してみようという気になったのだ。
そして律子がアイスアリーナの駐車場まで案内されてみると、そこにはストレッチ型リムジンがあり、その後部席の豪華さに彼女は驚いたというわけだった。あの黒人のボディガード――名前をボブ・カーティスと言うらしい――は、リョウと愛榮が戻ってくるまでにはまだ時間がかかるだろうが、暫くの間ここでお待ちください……と言い残し、車の外へ出てしまった。
その後、一渡り車内を見回し、(大金持ちのお宅に引き取られたとは聞いてたけど、ここまでとはねえ)と、驚いてしまう。おそらく地元のレンタカーでレンタルしたのだろうが、いちいちそのお金がいくらかかったかなど、小早川亮は気にしないくらいの大金持ちだという噂だった。
(天才だかなんだか知らないけど、最初はあんなちょっとおかしいタイプの人に面倒見てもらうなんて大丈夫かしらと思ったけど……まあ、奥さまのほうは至極まともそうだものね。わたしとしては、あの人より弟の圭くんのほうが好みなんだけれど……)
とはいえ、数年前に亡くなった彼女の夫は、スポーツマンでもなければ、詩情のなんたるかなどまるで理解しない唐変木だったのだが、見ていて(こんな息子がいたら良かったのにねえ)という夢をかきたてられるという、律子にとって小早川圭というのはそうした選手だったといえる。
そしてふと、律子がなんの気なしにワンサイドミラーのようになっている窓から外を覗きこむと、そこに寒い中突っ立っている体格のいい(間違いなく二メートルはある)黒人の姿を見出し、律子は「Come in!」と声をかけたのだった。本当は「寒いでしょうから、中へお入りなさい」とでも言いたかったのだが、何分英語がよくわからない。
ボブはここで必殺技とばかり、例の翻訳機に話しかけ、それを律子に聞かせた。「オキヅカイイタダキ、アリガトウゴザイマス。デスガ、コレガワタシノシゴトナノデス」……そうとまで言うのであれば仕方ないと思い、律子は彼に頭を下げてから再びドアを閉めた。
そのあと、律子は携帯を取りだし――待ち受けになっている娘の写真を見て、涙を流した。
そして外のほうで何か人の話し声がしたと思い、律子が目尻の涙を拭っていると、ドアが開いて愛榮が飛びこんできた。その手には自分がリンクに投げこんだストライプの紙バッグがあり、彼女は突然韓国語で「いつもありがとうございます。それで思ったんですけど……もしかして、あの飛行機事故の遺族の方じゃないかなって。以前あった遺族会で会ったような気がしたものですから……」そんなふうに勢いこんで話しかけたのだった。
「おい、愛榮!!その人は韓国語がわからないらしいぞ!」
「ええっ!?」
愛榮は驚いたような顔になると、律子のほうをもう一度振り返った。
「じゃあ……」
(あなたはどなたですか?)とあらためて聞くというのも失礼な気がして、愛榮は黙りこんだ。実を言うと律子は、韓国語については今も勉強中だった。けれど、主に日常会話を中心に勉強しているため、今愛榮が言ったことは「いつもありがとうございます(ハンサンカムサハム二ダ)」くらいしかわからなかったのだった。
律子は、こうするのが一番話が早いだろうと思い、携帯の待ち受けの写真を愛榮に見せた。もう二十年以上も前の写真ではあるが、面影くらいは間違いなく残っているだろう。
「お母さん(オモニ)……!!」
愛榮の黒曜石のような瞳から、どっと涙が溢れてきた。もしお母さんやお父さんがいたら、愛榮がまたオリンピックに出たところを、それも最終グループで滑っているところを見て欲しかった。その思いが新たに込みあげてきて、愛榮は涙が堰を切ったように溢れ出すのを止めることが出来なかったのだ。
「でも、どうして貴女が……母の写真を?」
韓国語がわからないということは、おそらく日本人か中国人だろうと愛榮は思い、さらに母の写真を持っているということは日本人の方に違いないと見当をつけ、日本語でそう問いかけた。
「まあ。聖美(きよみ)はあなたに日本語も教えて育てたのね……!!」
「はい。というのも、いつかわたしが大きくなった時に、就職で有利になるかもしれないと、母はそんなふうに考えてたみたいで……」
満開のサクラの下、矢がすりの袴を着た愛榮の母は、とても美しかった。手に持っている筒はおそらく卒業証書か何かが入っているに違いないと愛榮は見当をつける。けれど、愛榮の母の聖美が五歳年上の自分の父と結婚したのが確か、二十五歳の時のことだから……と考えていくと、愛榮は何かが少し不思議だった。
両親に反対されての結婚だったため、愛榮の母は旅行や観光目的で日本の地を踏む以外では、結婚後は二度と実家のほうへ戻ることはなかったのである。そして、それ以前の自分の母のことを知っているらしい女性のことを、愛榮は不思議な気持ちで見つめ返す。
「あのう、失礼な聞き方かもしれませんが、母とはどういった……?」
「わたしはね、あなたと血の繋がった祖母なのですよ」
律子もまた涙が込みあげてくるのをグッと堪えた。佐野家では父親が家長として亭主関白の権勢を揮っていたため、頑固な性格の父親が一人娘のことを勘当した時……律子としてはなす術もなかった。何分、結婚後大病を患った自分を離縁もせず辛抱強く看病してくれた夫である。当時、律子は愛する人間ふたりの間で板挟みになり、それは苦しい思いをしたものだった。
「あの飛行機事故があった時……」
込みあげてくるものを堪えきれなくなって、律子もまたハンカチをバッグから取りだし、一生懸命涙を拭った。
「テレビであなたのお父さんとお母さんの写真を見て、愕然としたわ。いつかこんな日が来るとわかっていたなら……聖美の父親も彼との結婚を反対しなかったかもしれない。簡単にいえばね、わたしの夫は自分の娘の結婚相手が韓国人だということが気に入らなかったのよ。韓国人に対して何か思うところがあるというわけじゃないの。おらそく聖美の交際してたのが中国人でも反対だったことでしょうからね。それで、娘のほうでは父に、「韓国人だからなんなの!?お父さんがそんな人種差別主義者だとは思わなかった!」って言って飛び出していったのよ。国際線のパイロットだなんて、ちゃんとした素晴らしい人じゃないのってわたしもお父さんに言ったんだけれど……ふたりは結局最後までわかりあえずに終わってしまったのね。あの人、聖美の亡くなる一年くらい前に死んだのよ。膵臓がんでね……最後、せん妄状態だった時に、「聖美、聖美」って何度も名前を呼んでたわ。ほんのちょっとボタンをかけ違ってしまっただけで、こんなことになるだなんて……わたしも、もっとどうにか出来なかったのかと思って、随分自分を責めたものよ」
「ハルモ二(おばあさま)……」
父方の祖父母はふたりともすでに亡くなっているため、愛榮はまだ自分に近い血縁がいるのだと思って、驚いた。もちろん、愛榮の父は五人兄弟だったため、親戚の数はそれなりに多いとはいえ、やはりそれと祖父母というのは愛榮にとって別の存在だった。
「日本の大使館に問い合わせた時にね、あの飛行機事故で亡くなった方々の遺族会があると聞いて、行ってみたんだけれど……あんまり苦しくて切なくてね、あなたにも声をかけようと思ったけれど、他に親戚の人たちもいたし、第一言葉が通じないだろうと思って、躊躇ってしまったのよ。第一、今更わたしが声をかけたところで、これまでお祝いひとつ送ったことがあるわけでもなしって、そんなふうに思ってしまってね……」
「ああ、それで、だったんですね。わたしのファンの振りをして、いつも行く先々の試合で応援してくださっていたのは……」
「振りってわけじゃないのよ」
そう言って、律子は涙を拭うと、初めて微笑った。
「あなたのファンなのは本当のことですもの。昔から、わたしも聖美もフィギュアスケート観戦が大好きだったのよ。男子ではね、小早川圭くんと氷室光くんを応援してたりしてね。今回のこと、とても残念だったけれど……」
(余計なことかしら)と思い、律子はここで口を噤んだ。けれど、愛榮のほうは瞳を涙で潤ませつつ、慕わしそうに律子のほうに手を伸ばすと、彼女の両手をぎゅっと握ってきたのである。
「嬉しいです。オリンピックでメダルを取れなかったことは悲しいけれど、今は嬉しい気持ちでいっぱいです。だって、まだわたしには、血の繋がったこんなに素敵なおばあさまがいただなんて……もっと早くにそうおっしゃってくださったら良かったのに」
「まあ、でも本当にびっくりだわ。そんなに日本語が上手だなんて……コーチとはいつも、日本語でお話するの?」
「その時によって、英語だったり日本語だったり……でも、コーチのお屋敷にいる時にはいつも日本語です。奥さまがコーチとお話する時はいつでも日本語なので」
リョウはふたりがお互いの存在しか目に入らないようにしっかと手を握りあっているのを見て――運転席側に「車を出せ」とスピーカーを通して伝えた。ちなみに、ボブ・カーティスはすでに助手席のほうに収まっている。
愛榮と彼女の母方の祖母である律子とは、リョウと愛榮が宿泊しているスイートルームで、その後も食事しながら三時間半ほどもしゃべり続け……その間、リョウは隣の続き部屋のほうで論文の執筆に取り組んでいた。
リョウがこの日驚いたのは、愛榮が囲み取材を受けている時に韓国スケート連盟の代表者や他のスタッフがやって来て、「先生がついていながらこれは一体どういうことですか!」と激しく詰られたことだったろうか。これまで、愛榮がどの試合でも表彰台へ上がり続けている間は、「小早川先生におかれましては……」とばかり、平身低頭に接してくることしかなかったため、リョウとしてはその態度の豹変ぶりに驚くばかりだった。他の試合はともかくとして、肝心要のオリンピックで愛榮がこけたのは、まるですべてコーチである小早川亮ひとりに責任があるとばかりの物言いだったからである。
とはいえ、リョウとしては――彼はこれまでの人生でそんなことをしたことは一度もないのだが――とにかく自分のコーチとしての能力のなさを詫びるしかなかったといえる。そして愛榮が囲み取材から解放されて戻ってくると、「小早川コーチは何も悪くありません。責めるならわたしだけにしてください……!」と、普段でも若干濡れたように見える射干玉(ぬばたま)色の瞳で訴えかけると、韓国スケート連盟の面々もぐっと黙りこむ以外なかったようである。
リョウは頭の半分では論文の文言について考えながらも……何度もふと手を止めては、今日の愛榮の演技について思いを馳せた。いや、それ以前にザグレブ入りを果たした時にまでも記憶を遡らせて、自分が愛榮のためと思いながらも、何をして・何をしてやらなかったかと、自分のコーチとしての落ち度を考え続けていたのである。
もちろん今もまだ、愛榮がオリンピックで金メダルどころか銀メダルも銅メダルも取れなかったことについて、リョウはショックを受けていた。というより、愛榮の演技直後はまだどこか、愛榮がメダルを取れなかったということが半ば現実でないように感じているところがあったのだろう。けれど、だんだんにじわじわと――次の四年後までその機会を待たねばならないというのがどんなことかを理解しはじめていたのである。
(カール・アイズナーの奴も、俺に負けたあとおそらくは、今の俺みたいな気持ちだったっていうことか……)
そう思うとますますリョウは気分が滅入ってきた。こういう時、リョウは葵と話すと心が癒され安らぐが、今は自分以上につらいであろう愛榮のことを慰め励まさねばならないという立場である。
(ああ。早くケンブリッジの屋敷に戻って、葵や愛の顔が見たいな。それで、愛榮を慰める役のほうはあいつにバトンタッチして、俺は適当に面白おかしいことでもしゃべって、愛榮のことを笑わせるといった立場を取ればいいというのなら、どうにか耐えられそうなんだが……)
けれど、愛榮が例のストライプの紙バッグおばさんの正体がわかったことで、俄然元気づいて見えたというのは、リョウにとっても嬉しいことだった。まさか血の繋がりのある母方の祖母だとまでは思っていなかったが、こんなことならもっと早くに彼女の素性を洗えば良かっただろうかと思わぬでもない。
(だが、結局のところこれで一番良かったのかもしれんな。自分の祖母がこれまで、世界中のどこで試合が開催されようとも、孫の演技を見に来てくれていたということが、愛榮には何より嬉しいことだったろうし……)
リョウが論文の執筆を中断させ、パソコンの前で腕を組んだまま、溜息を着いていると――続き部屋の開きっ放しになっているドアが二度ノックされた。
「少し、よろしいですか?」
「ああ。構わんが……」
リョウはこの時、ついいつもの癖で、パソコンの画面を切り換えると、ロックをかけた。画面上ではスーパーマリオブラザーズのマリオとルイージが走りまわり、時折兄弟でまったく息もぴったりに跳び上がると、クリボーやノコノコを蹴って倒すということが繰り返される。
「どうか愛榮のこと、これからもよろしくお願いします。わたしに出来ることなら、なんでもしますから……っ!!」
椅子に座ったままのリョウの前で、律子は半ば膝をつくようにしながら、そう彼に頼んでいた。リョウは食事のあとは席を外していたため、この二時間半ほどの間、ふたりがどんな話をしていたのかはわからない。だが、どうやらそう頼むということは、彼女が愛榮を引き取るとか、一緒に暮らすといった方向には話が進まなかったのだろうと思い、リョウはほっとする。
「やめてください、お母さん。第一、あなたがわたしに頼むことなんて本当は何もないんですよ。愛榮のことを俺はすでに家族の一員のように感じているし、うちの屋敷は広いですからね、愛榮がいて何か困るということもない。葵も、子供の面倒を愛榮に見てもらったりして、助かってるみたいですし」
「じゃあ、これからも愛榮のこと、見捨てないでいただけるんですね!?」
この段になると流石に、(このおばさん、俺のことをどんな人間だと思ってるんだ?)とリョウにしても思ったが、それと同時に自分のことをコーチとして高く買ってくれているのだろうと気づき、リョウは申し訳ない気持ちで一杯になった。それなのに、最後の最後、もっとも肝心なところで――自分と愛榮は躓いてしまったのだから。
「見捨てないも何も、愛榮もまだ十九歳ですし……次のオリンピックの時には二十三ですか。あと四年、もし愛榮が俺について来る気があるのなら、俺は自分に出来ることはなんでもしたいと思ってます。ただ、今俺も、何故最後の最後で愛榮にああいうメンタル面での弱さが出たのか、考えてたところなんです。ああ、誤解しないでください。好不調の波というのはどの選手にもあるものなので、愛榮が悪いとか、このあと彼女にそのことで説教を食らわそうとか思ってるわけではないんです。ただ俺は自分にコーチとして何か落ち度があったのではないかと思ったもんですから……」
(ああ。ではこの人は孫娘の気持ちに、本当にまるっきり気づいてないんだわ。雑誌や何かで取り沙汰されているのを見た時にはどうとも思いはしなかったけれど……愛榮のこの人を見る目つきでわかる。あの子が妻子のある人を愛してるんだってことが……)
この三時間以上もの間、律子と愛榮は彼女の恋愛についての話など一切しなかった。ただ、愛榮の尊敬よりももっと愛着のこもった眼差しを見ただけで律子にはすぐわかった。彼女にしてもこのオリンピックでメダルを取り、どれほどこの崇敬するコーチのことを喜ばせたかったことだろう。だが彼は、普段の練習では厳しいのに、愛榮のことを一切責めなかったという。むしろキツくお灸でも据えてもらったほうが気持ちが楽かもしれないとさえ彼女は言っていた。
「愛榮は、ただ小早川コーチに申し訳ない気持ちでいっぱいだと、そんなふうに申していました。自分がどうこうというより、コーチからあれほど良くしていただいたのに、目に見える結果を残せなかったことが悔やまれると……」
「ああ、いいんですよ。説明されなくても、そんなことは俺にもわかってることですから。俺の仕事はまず、次の世界選手権で愛榮のことを初めての世界女王にするっていうことです。そこから始めて、また色々と作戦を練っていかなくてはなりませんが、お母さんはまあ、いつでもうちのケンブリッジの屋敷に遊びに来たくなった時に来てください。社交辞令でもなんでもなく、本当にそうしてくださって構いませんから」
「あ、ありがとうございます……!!」
選手時代のエキセントリックなイメージとは違って、彼が至極まともな人間に見えたため、律子としても驚いたかもしれない。そして心からほっと安堵する。この人物に愛榮のことを任せておけば、自分が彼女のことを引き取るよりも、より大きなことを彼が成し遂げてくれるだろうことがわかって。
(ただ、心配には心配ではあるけれど……選手がコーチに恋をするなんていうのはよくあることでしょうけれど、愛榮はそのコーチと一緒に住んでいるんですものねえ。スケートの練習でもプライヴェートでもずっと一緒だなんて、本当に大丈夫かしら。わたしにしても、そのこと以外では何も心配ではないのだけれど……)
もちろん、律子にしても愛榮のことを引き取りたいと思う気持ちは当然ある。いや、愛榮と話している時に、一体何度そのことを言おうと口に出しかけたことだろう。けれど、この子はスケートの選手として今のままでいたほうがいいのだと思い、グッと言葉を飲み込んだ。コーチ御夫妻にも可愛がられているというのなら、自分が横から余計な嘴を挟むべきことではない。
このあと、律子は長居してしまったことをリョウに詫び、愛榮の手をぎゅっと握りしめながら、「スケートがんばってね……!」とあらためて言って、自分が一生の間で泊まることは決してないだろうと思われる豪奢なスイートルームをあとにした。
「良かったな、愛榮」
リョウはまだ涙の残る眼差しで、祖母の出ていったドアを見つめる愛榮の頭をぽんと撫でた。
「はい……!!そしてこのこともやっぱり、コーチのお陰だと思ってます。ボブにおばあさまのことを捜すように言ってくださったから……でもわたし、まさかまだ自分におばあさまがひとり残っているとは思ってもみませんでした」
リョウもまた、本来ならばふたりずついるはずの祖父母の中で、唯一今も生きているのは母方の祖母だけである。彼女は今ニューヨークの相当お金を持ってでもいないことには入れないような高級介護施設で何不自由なく暮らしている。
「俺も、実をいうと結構なおばあちゃんっ子でな。今も施設に入っているばあちゃんとは交流がある。愛榮もあの人のこと、大切にしてやれよ。あの人がうちに遊びに来る時には、いつでも航空券を手配してやるから」
「は、はい……それで、あのう、コーチ。わたし、次のシーズンに入る前に少し旅行なんてしてもいいでしょうか?オリンピックでこんな不甲斐ない結果を残しておいて、旅行だなんてと思われるかもしれないんですけど……」
リョウは旅行の時には必ず携行していく小型の湯沸かし器で湯を沸かすと、紅茶を二杯入れて、片方を愛榮に渡した。そして、テーブルの上の残った菓子類などをつまむ。
「もちろんいいさ。日本のあの人のところにでも行くのか?」
「いえ……いずれはそうしたいと思ってるんですけど、先に律子さんのこと、ソウル観光に連れだしたいなと思って。母さんがどんな場所でどんなふうに暮らしてたかとか、そんなことをお話したいと思って。コーチ、わたし、実はリンクに出る前に、とても心が揺れたんです。きっかけはたぶん、灰島選手の物凄いオーラに圧倒されたっていうことだったかもしれません。自分はどんなに努力してもあの人みたいにはなれないし、もしなれたとして……金メダルを取ってもお父さんもお母さんもいなくって、なんだか自分のこと、物凄く孤独で惨めだと思いました。自分でも演技前はそうした余計なことが頭をよぎったりしたことはなかったので、自分でもびっくりして……ジャンプを転倒したその瞬間に、律子さんと目と目が合ったんです。今にして思うと本当に不思議だけれど、わたし、あの時は自分のことをずっと応援してくれてるこの人のために滑ろうって、そんにふうに思って……」
「そうか」
紅茶にミルクピッチャーからミルクを注いでミルクティーにしながら、リョウは頷いた。そのあと愛榮が自分の元まで戻ってきて、「コーチにとってわたしはなんだったんでしょうか?」と彼女が聞いたのをリョウはもちろん覚えていたが、そのことはあえて不問にした。何故といって、リョウの判断では演技直前に混乱のあまり愛榮はそんなことを口走ってしまったのだろうと思ったからだ。
「だが、その旅行へ出かける前に世界選手権があるからな。それが終わればおばあちゃんとの旅行が待ってると思って、頑張れよ。今回おまえがメダルを取れなかったことについては……俺は今後も何か言うつもりは一切ない。起きてしまったことは起きてしまったことだからな。それよりも、ボストンへ戻ったあとは世界選手権で金メダルを取ることだけを考えろ。わかったな!?」
「は、はい……っ!!」
リョウの裁断があまりに寛容だったため、愛榮はここでもまた泣きそうになった。「おまえもミルクティーにするか?」と言って、残ったミルクをリョウは愛榮のカップに少しだけ注ぐ。
「あ、あの……コーチ。どうしてもっときつくお叱りにならないんですか?わたしがおばあちゃんと感動的な再会を果たしたとか、そういうことが理由なら……それとこれとは別のことですので……」
「はははっ。そりゃあ、おまえのことを痣が出来るくらい殴って叱り飛ばせば、演技前のあの瞬間に戻れるとでもいうのならな、俺は喜んでそうするよ。だが、繰り返すようだが起きてしまったことは起きてしまったことだ。俺自身の考えでは、その事実を厳粛に受け止めて前に進むというのが、もっとも人間らしくまっとうな道だという気がする。だが愛榮、覚悟しておけよ。四年は長いぞ」
「…………………っ!!」
いつものように「はいっ!!」とは、愛榮にも元気よく返事できなかった。何故といって、愛榮は今、フィギュアスケートに対してある確信が薄れていきつつあるからだ。メダルを取れなかったことに対する失望とともに、一気に競技に対する熱も冷めた。また同じように不安や緊張を乗り越えて試合へ臨み続けることに対する恐怖感もある……これがただ一過性の燃え尽き症候群のようなものであり、祖母と旅行するうちに癒されるものならばいいが、もしそうでなかった場合は――けれど愛榮はそれ以上のことはこの時、考えることが出来なかった。
(それよりもまずは、世界選手権だ。そしておばあちゃんとソウルを観光して、あとのことは戻ってきた時に考えよう。ああ、どちらにしても結果が同じなら、オリンピックでメダルを取って今期限りで引退とでもいうほうが、どれほど良かっただろう。そのほうがコーチだって納得してくれただろうし……)
あと四年――次のオリンピックの時、愛榮は二十三歳ということになる。そして愛榮は自分がそんな歳まで本当に頑張っていけるのだろうかと、訝った。リョウと葵にコーチになってもらって約三年。とても長かったと愛榮は感じている。そこにさらにもう一年加わったら、自分は一体どうなってしまうのだろう。そしてその一年一年、自分は本当にコーチの望むような結果を出し続けることが出来るのだろうか……。
(それに、葵先生の隣で優しく微笑むコーチのことを、わたしはこれからも見続けることになるのだわ。それにまた子供が生まれたら、ますますコーチは彼女のことを愛するようになるだろう。そんな幸せな家族の肖像の横で、嘘の微笑みばかり浮かべることになるのだとしたら、わたしはあのお屋敷を出ていかなくてはならない……)
もちろん、選手とコーチの同居状態を解消するというのは、そう問題になることではない。ボストンで一人暮らしをしてアーヴィングへは通い、そこでだけリョウと接点を持つというのでも十分だし、むしろそのほうが普通なことでもある。けれど、愛榮はそのうちのどちらを選んでも自分の心から虚しさを消すことはできないとわかっていた。そしてそうしたコーチの支えなくしては、自分がスケートを続けていかれないというのは、致命的なことだと思いもした。
(わたしはコーチに愛されたいんだ……フィギュアスケートの選手としてではなく、ひとりの女として……)
けれどその道は、あまりに苦しい荊のような道だった。決して自分を振り返りはしない、女としては決して見てくれることはない人を愛し続ける……いや、小早川亮というコーチのそばにいる限り、自分は彼のことを愛し続けるだろうと愛榮にはわかっていた。それは同じ屋敷に住んでいようと、リンク場だけで会うということにしても、どちらでも同じことだ。そして彼から独り立ちするということは、愛榮にとってフィギュアスケートをやめることを意味していた。もはや自分は小早川亮という男なくしては、スケートを続けるということになんの意味も見出すことが出来ないのだから……。
(どうしよう。こんなこと、誰にも相談できない。葵先生はもちろんのこと、エリカにも誰にも……)
以前までは、フィギュアスケートを通しての絆さえリョウとの間にあれば、彼にひとりの女として認識されなくても平気だと愛榮には思えていた。ただそばにいてコーチの姿を見、その声を聴き、彼が自分の目を見て何かを話してくれるというだけで十分幸せで、こんな毎日がずっと続いていってさえくれるのなら、他には何もいらないし、フィギュアスケートのことに関しても、血反吐を吐くほどの思いをすることすら、本当の苦しみではなかった。けれど愛榮は今、T字路に立たされている。ひとつは、このまま自分の気持ちを誤魔化し続けながら、小早川亮というスケートのコーチについて行くという道、もうひとつは、まったく別の、フィギュアスケートとは関係のない人生を歩むという道だった。
この場合難しいのは、愛榮は結局のところ、自分がどちらの道を選んだとしても後悔するだろうということだった。それに、スケートをやめた一年後……いや、半年後には後悔しているかもしれない。だからといって、誰か他のコーチについて現役復帰しようといったようには、愛榮は思えないに違いなかった。
(ああ、本当にわたし、どうしたら……どうするのが一番いいんだろう……)
愛榮はこれが恋してはいけない人に恋をした罰かと思った。だとしたら、自分ひとりだけで悩み苦しまなければいけないということなのだろう。そしてこの気持ちが罪だというのならば、愛榮は彼から離れるしかないのだとも思った。
「どうした、愛榮?なんだか顔色が悪いな。そうだ、おまえ、今日もこっちの部屋で寝ろ。俺は向こうの続き部屋のほうで寝るから」
「そんな……いいんです。コーチ、わたしに気を遣わないでください」
リョウはもう今回のザグレブオリンピックのことは、愛榮の前では口にすまいと心に決めていた。いわゆる、五輪の魔というものに呑まれてしまったのかもしれない。だが、次のオリンピックまでは四年ある……それまでに灰島蘭を倒すための算段を練り、点差を詰めていくことは十分可能だとリョウは思っていた。
「いいから、美味しいものも色々食べたし、あとは風呂にでも入って体をあっためて何も考えずにぐっすり寝ろ。俺のことをがっかりさせただのなんだの、そんなくだらんことで頭を悩ませるのももうやめるんだ。明日はエキシビション、その翌日が閉会式か。そうだな、愛榮。このオリンピックが終わったらドゥブロヴニクにでも行くか?前にも一度行っているが、なんだっけ?おまえの好きなジブリの……」
「魔女の宅急便です」
「そうだ、それだ。そのアニメのモデルになった街なんだろ?おまえ、また来たいって前にも言ってたもんな」
「はい……なんだか中世の御伽噺の国に迷いこんだみたいって思って。あ、そういえば、レオもエキシビションが終わったらドゥブロヴニクに行くって言ってたっけ。メールで、なんかお土産欲しかったら買ってきてやるって言われたんだった」
愛榮は桃のクリームパイを食べながら、ふと思い出したようにそう言った。途端、リョウが不機嫌そうに眉根を寄せる。
「レオっていうのは、ルカ・ニキシュと同点だったのに四位だったサルのことだな。おまえ、あいつと一体どの程度親しいんだ?」
「いえ、本当にただのリンクメイトっていう感じだと思います。たとえば、わたしがスケートやめたり、レオのほうがアーヴィングを去っていったりしたら、もうそれきりになるだろうなっていう感じの……本当に本当の友達だったら、それぞれの国に帰っても連絡を取りあったりするだろうけど、礼央はそういうのとは違うかな。ようするに、その程度の関係といっていいと思います」
愛榮が自分の部屋で礼央に英語を教えていた時、突然リョウが乱入してきた時のことを思いだして、愛榮はおかしくなった。『男とふたりきりで勉強なんて、絶対に駄目だ!』、『はあ!?あんた一体何考えてんだ。俺はただ英語を教えてもらってるだけなのに……』、『うるさい!とにかくここから出ていけ。勉強するんなら居間のほうで、俺や葵の目の届くところでやれ。俺はこの屋敷の主だからな。この屋敷の敷地内では俺の言うことは絶対だ』……そしてここで愛榮は(そういえば)、とあることに思い至る。
(レオも惜しいところで同点四位なんだっけ。その悔しい気持ちも今はわかるから、あとでメールしておこうかな)
そして愛榮はこの時リョウに、レオとはそれほど大した繋がりのある関係ではない――という言い方をしたものの、オリンピックが終わり、再びアーヴィングスケートクラブでの練習がはじまった時、彼がアーヴィングを去り日本へ戻ると知って非常なショックを受けた。それは他のクラブメイトもエリカも同じだったようで、愛榮はその時に初めて、同性ではなく異性であれほど親しく友人関係を築くことが出来たのは……レオが初めてだったと気づくのだった。
>>続く。
さて、今回は愛榮のターンですね♪(^^)
といっても、言い訳事項として「韓国語わかんないww」っていう以外では、特に何も書くことなかったり

ええと、なのでどうしようかなと思ったんですけど、まあ本当はあとがき☆にでも書こうかなって思ってたことを前倒し的に少し書いてしまおうかと。。。

まあ、愛榮のことというよりもそれは、六花のⅠのほうで主人公だった葵とリョウのことなんですけど(笑)
なんていうか、自分でも書いててたまーに、恋愛の頂点にある時にお話が終わってその後結婚したらしい……くらいのが、実はちょうどいいのかな、なんて(^^;)
簡単にいっちゃえば、【悲報】かつてのフィギュアスケートの天才、結婚してどんどん凡人にwwみたいな、なんかそういう話の流れになってるんじゃないかな~という気がしたり。。。
葵もまあ、なんというかその後は振付師をしつつ平凡な主婦になった的な??
もちろん、館神コーチに孫を抱っこさせたいという野望(?)が自分的に叶ったので、これはこれでいいのかなってわたし的に思ったりはするんですけれど(笑)
そんで、なんか三人ともすごいスケーターに育っていくみたいなので……わたしがもし、今の「真・四回転時代」を迎えてからこの小説書き始めてたら、たぶん六花のⅠの時からほとんど全員もっとバンバントゥループとサルコウ以外の四回転を跳んでもらってたと思います。
いえ、リョウに関してはほんともう……全種類の四回転が跳べるとか、その上IQが187あるとか、どう考えても設定盛りすぎだろwwって自分に突っ込み入れながら書いてたので、Ⅰを書き終わったあと、しょーまくんが四回転フリップを決めたりとか、ぼーやんくんが四回転ルッツを跳んだりするのを見て――「えへっ。実はちっとも盛りすぎじゃなかったんだ
 」と思ったという(笑)
」と思ったという(笑)しかも、極めつけがチェンくんですよwwフリーで5クワド達成したってだけじゃなく、小さい頃からバレエやってたりピアノ弾けたり、自分でも振付とかしちゃったり、将来は医者になりたいとか言ってたり……いえ、チェンくんのことを先に知ってたら、リョウのこの設定でもちっとも盛りすぎじゃないと思って、むしろ焦ってたと思います(^^;)
なので、光くんはある意味ちょっと残念だったのかなって思ったりもしています。。。
なんでかっていうと、書きはじめた時から今の「真・四回転時代」が到来していたら――プログラムのほうももっと華々しいものになってたのかなって思ったりするし、これは剛くんや礼央くんにしてもそうなんですよね。
そんで、この中で光くんは四回転ルッツ、剛くんは四回転フリップ、礼央はルカと同じく四回転ループを練習して跳べるようになったっていうことにするとか……まあ、でもわたし、フィクションなのにそのあたりのことは現実的に考えて、「そんな簡単にぽんぽん多種類のクワドを跳べるかよ
 」との思いもあり、光くんも剛も礼央も結局トゥループとサルコウだけで攻めて、あとは表現力に磨きをかける――みたいな感じになっちゃったのかなという気がします(^^;)
」との思いもあり、光くんも剛も礼央も結局トゥループとサルコウだけで攻めて、あとは表現力に磨きをかける――みたいな感じになっちゃったのかなという気がします(^^;)あー、あとこれははっきり言ってどうでもいいことなんですけど、わたし文章打ってる時に結構誤字が多くて……フィギュアスケートって書くところをファギュアスケートって書いてたりとか、インタビューがイタンビューになってたりとか、そういうのが結構あるんですけど、その中でたまーに四回転と書くところを三回転って書いてたりすることがあって――自分的にその打ち間違いでちょっと受けたのが……ルカの四回転ループのところを三回くらい三回転ループとか書いちゃってて、直しながら「ぷぷぷ☆(ΦωΦ)」と笑っちゃったりとか。。。
いえ、「俺の必殺技は三回転ループだ
 」とか仮に大威張りで言ってたら、「え?それが一体どーしたの??
」とか仮に大威張りで言ってたら、「え?それが一体どーしたの?? 」的になるんじゃないかな~なんて、そう思ったりして(笑)
」的になるんじゃないかな~なんて、そう思ったりして(笑)まあ、それはさておき、葵とリョウの三人の子供たちの時代には、きっと彼らも多種類のクワドをバンバン跳んでるんじゃないかなっていう気がします。蘭は前にどっかで四回転トゥループの次は四回転サルコウに挑戦したいって言ってた気がするんですけど、今はまだ小さい愛ちゃんもまた、将来大きくなってのち、じいじの館神コーチの元でジャンプを教えてもらったりするんじゃないかなって思います♪(^^)
それではまた~!!

ダイヤモンド・エッジ<第二部>-【68】-
ザグレブオリンピックのあった年の世界フィギュア選手権で優勝したのは、男子が小早川圭、そして女子が金愛榮だった。
ふたりとも、オリンピックでの不完全燃焼な演技の雪辱戦としての世界選手権だった。オリンピックで金メダルを取った選手はそこで達成感の頂点を味わうため、そのあとにある世界選手権ではモチべーションの落ちていることが多いものだが、その中で光も蘭も健闘はした。けれど、オリンピックの時の演技が最高潮であったとすると、そこから全体として何かが落ちてきている感の否めない演技ではあった。
結局のところ、この世界選手権で光は銅メダル、蘭は銀メダルだった。男子の銀メダルはレオン・アーヴィング、女子の銅メダルはリュドミラ・ペトロワだった。レオンはいつも通りの安定した演技を見せ、リュドミラ・ペトロワはやはり、オリンピックで力を使い果たしてしまったのか、フリーではエイトトリプルが決まらず、ジャンプをふたつミスした。
とはいえ、光は最後の世界選手権で表彰台に上がれたというだけでも十分満足であり、バックステージではレオンや圭と仲良く互いの健闘を称えあった。蘭は金愛榮に負けて悔しくはあったが、妙にそのことに納得してもいた。自分がもし彼女と逆の立場だったとしたら、やはり死力を尽くしてオリンピックでの雪辱を晴らそうとしたろうからだ。
(お互い、そういう時の相手には勝てないってことか……)
そう思い、蘭は素直に金愛榮のことをフラワーセレモニーでもバックステージに下がってきてからも祝福した。リュドミラも「何故か不思議と今回は銅メダルでも悔しくない」と言っており、「むしろメダルが取れただけでも幸運だった」とさえ言っているのを聞いて、オリンピック後、やはり彼女もモチベーションが下がっていたのだろうと蘭は察した。
この世界選手権では、試合前の記者会見でサーシャ・アルツェバルスカヤが引退を表明していた。引退の理由は、「オリンピックで思ったような成績が残せなかったから」というものだったが、実際はラリサに破門されたも同然だったと言ったほうがいいのかもしれない。破門、などと言っても、ラリサは何も薬物のことを聞いて冷たく弟子のことを突き放したというわけではない。
ただし、マリアとリュドミラからサーシャの薬物問題を聞かされてラリサが怒り狂ったというのは事実である。また、オリンピックでは上位四名の選手の他に無作為で一名選ばれてドーピング検査を受けるわけだが、この時選ばれたのはサーシャではなくカナダのベアトリクス・アディントンだった。
もしこの時、サーシャが選ばれていて薬物が検出されたとしたら、とてつもない大スキャンダルに発展していたことだろう。オリンピック後、ラリサはモスクワへ戻ってのち、そのことを彼女に問い詰めた。そして泣きながらひたすらあやまるサーシャに引退を勧め、矯正施設に入るよう諭したのだ。「わたしはあなたのことを見捨てるわけじゃないのよ。むしろ小さい時から見てきたあなたのことが可愛いと思えばこそ、こう言うのよ」と、そう言って……。
また、マリア・ラヴロワはこの大会で、リュドミラに迫る勢いで高得点を叩きだし、第四位だった。ふたりは仲直りして親友同士に戻るのと同時、再びライバルとして競いはじめたのだ。今は一歩も二歩も先を行っているのはリュドミラのほうではある。けれどマリアもそんな彼女にこれ以上引き離されまいとして、オリンピック後はリュドミラ以上に練習に励んでいたのだ。
そして金愛榮だが、オリンピックの女子シングルの試合が終わるのと同時に――ボブ・カーティスがアリーナ席の最前列にいた例のストライプのプレゼントを毎回くれる婦人に声をかけた結果として、次のことがわかっていた。
なんといっても、カーティスは韓国語など出来ないため、リョウが自分で開発した翻訳機を使って彼女と会話することになった。
「ワタシハエヨン・キムノコーチノリョウ・コバヤカワノダイリニンデス」
カーティスの英語が韓国語に翻訳されても、白髪頭でてっぺんのほうの毛髪が薄い初老の女性は、ただひたすらに首を傾げるばかりだった。何分、カーティスはボディガードだけあって体型も顔つきもいかつい(丸禿げでいつもサングラスをかけている)。当然女性のほうではそれだけでも彼のことを不審に思う理由は十分だったといえる。
「What country are you from?」(あなたの出身国は?)
実をいうと彼女――佐野律子は、日本人で韓国語などさっぱりしゃべれなかったのだった。また、英語のほうもまるで堪能ではなかったが、それでも男が言った言葉については大体のところ理解した。
「From Japan」
律子がそう答えると、カーティスは驚き、変換する言語を日本語に切り替えて、先ほどと同じ言葉をマイク部分に向かって繰り返した。
「私は金愛榮のコーチ、小早川亮の代理人です」
「ああ、そうでしたか」
律子のほうでも驚きの表情を顔に浮かべ、次のカーティスの言葉を待った。
「実は、金愛榮があなたに直接会ってお話をしたいそうです。私は彼女の元まで貴女のことを連れていくようにリョウに頼まれたのです。よろしいでしょうか?」
「はあ……」
(まさか裕福な日本人と間違われて、誘拐されるなんてこと、ないでしょうしねえ)
それでも、もし愛榮がこのオリンピックという大舞台でメダルを取れずに終わってなかったとしたら――彼女は大金持ちのコーチの家に引き取られて幸せなのだと思い、律子は彼女とは会おうと思わなかったかもしれない。
けれど、たった少しばかり前に終わった演技を見ていて、律子は涙が止まらなかった。愛榮が一番いい演技ができるようにとあれほど祈ったのに、彼女のお父さんとお母さんも天国で見守っていてくれると信じていたのに、結果的に愛榮は金メダルどころか銅メダルにも手が届かないで終わってしまったのだから。
これまでの試合であまりミスをしているのを見たことがなかっただけに、それだけ大きなプレッシャーと愛榮は戦っていたのだろうと思い、律子は胸が潰れる思いだった。ここまで来るのに彼女がどれほど努力を積み重ねてきたのか……律子には想像してみることさえ出来ない。その上、故郷に帰って慰めてくれるような家族もないのだと思うと、突然愛榮と会って彼女のお母さんのことを話してみようという気になったのだ。
そして律子がアイスアリーナの駐車場まで案内されてみると、そこにはストレッチ型リムジンがあり、その後部席の豪華さに彼女は驚いたというわけだった。あの黒人のボディガード――名前をボブ・カーティスと言うらしい――は、リョウと愛榮が戻ってくるまでにはまだ時間がかかるだろうが、暫くの間ここでお待ちください……と言い残し、車の外へ出てしまった。
その後、一渡り車内を見回し、(大金持ちのお宅に引き取られたとは聞いてたけど、ここまでとはねえ)と、驚いてしまう。おそらく地元のレンタカーでレンタルしたのだろうが、いちいちそのお金がいくらかかったかなど、小早川亮は気にしないくらいの大金持ちだという噂だった。
(天才だかなんだか知らないけど、最初はあんなちょっとおかしいタイプの人に面倒見てもらうなんて大丈夫かしらと思ったけど……まあ、奥さまのほうは至極まともそうだものね。わたしとしては、あの人より弟の圭くんのほうが好みなんだけれど……)
とはいえ、数年前に亡くなった彼女の夫は、スポーツマンでもなければ、詩情のなんたるかなどまるで理解しない唐変木だったのだが、見ていて(こんな息子がいたら良かったのにねえ)という夢をかきたてられるという、律子にとって小早川圭というのはそうした選手だったといえる。
そしてふと、律子がなんの気なしにワンサイドミラーのようになっている窓から外を覗きこむと、そこに寒い中突っ立っている体格のいい(間違いなく二メートルはある)黒人の姿を見出し、律子は「Come in!」と声をかけたのだった。本当は「寒いでしょうから、中へお入りなさい」とでも言いたかったのだが、何分英語がよくわからない。
ボブはここで必殺技とばかり、例の翻訳機に話しかけ、それを律子に聞かせた。「オキヅカイイタダキ、アリガトウゴザイマス。デスガ、コレガワタシノシゴトナノデス」……そうとまで言うのであれば仕方ないと思い、律子は彼に頭を下げてから再びドアを閉めた。
そのあと、律子は携帯を取りだし――待ち受けになっている娘の写真を見て、涙を流した。
そして外のほうで何か人の話し声がしたと思い、律子が目尻の涙を拭っていると、ドアが開いて愛榮が飛びこんできた。その手には自分がリンクに投げこんだストライプの紙バッグがあり、彼女は突然韓国語で「いつもありがとうございます。それで思ったんですけど……もしかして、あの飛行機事故の遺族の方じゃないかなって。以前あった遺族会で会ったような気がしたものですから……」そんなふうに勢いこんで話しかけたのだった。
「おい、愛榮!!その人は韓国語がわからないらしいぞ!」
「ええっ!?」
愛榮は驚いたような顔になると、律子のほうをもう一度振り返った。
「じゃあ……」
(あなたはどなたですか?)とあらためて聞くというのも失礼な気がして、愛榮は黙りこんだ。実を言うと律子は、韓国語については今も勉強中だった。けれど、主に日常会話を中心に勉強しているため、今愛榮が言ったことは「いつもありがとうございます(ハンサンカムサハム二ダ)」くらいしかわからなかったのだった。
律子は、こうするのが一番話が早いだろうと思い、携帯の待ち受けの写真を愛榮に見せた。もう二十年以上も前の写真ではあるが、面影くらいは間違いなく残っているだろう。
「お母さん(オモニ)……!!」
愛榮の黒曜石のような瞳から、どっと涙が溢れてきた。もしお母さんやお父さんがいたら、愛榮がまたオリンピックに出たところを、それも最終グループで滑っているところを見て欲しかった。その思いが新たに込みあげてきて、愛榮は涙が堰を切ったように溢れ出すのを止めることが出来なかったのだ。
「でも、どうして貴女が……母の写真を?」
韓国語がわからないということは、おそらく日本人か中国人だろうと愛榮は思い、さらに母の写真を持っているということは日本人の方に違いないと見当をつけ、日本語でそう問いかけた。
「まあ。聖美(きよみ)はあなたに日本語も教えて育てたのね……!!」
「はい。というのも、いつかわたしが大きくなった時に、就職で有利になるかもしれないと、母はそんなふうに考えてたみたいで……」
満開のサクラの下、矢がすりの袴を着た愛榮の母は、とても美しかった。手に持っている筒はおそらく卒業証書か何かが入っているに違いないと愛榮は見当をつける。けれど、愛榮の母の聖美が五歳年上の自分の父と結婚したのが確か、二十五歳の時のことだから……と考えていくと、愛榮は何かが少し不思議だった。
両親に反対されての結婚だったため、愛榮の母は旅行や観光目的で日本の地を踏む以外では、結婚後は二度と実家のほうへ戻ることはなかったのである。そして、それ以前の自分の母のことを知っているらしい女性のことを、愛榮は不思議な気持ちで見つめ返す。
「あのう、失礼な聞き方かもしれませんが、母とはどういった……?」
「わたしはね、あなたと血の繋がった祖母なのですよ」
律子もまた涙が込みあげてくるのをグッと堪えた。佐野家では父親が家長として亭主関白の権勢を揮っていたため、頑固な性格の父親が一人娘のことを勘当した時……律子としてはなす術もなかった。何分、結婚後大病を患った自分を離縁もせず辛抱強く看病してくれた夫である。当時、律子は愛する人間ふたりの間で板挟みになり、それは苦しい思いをしたものだった。
「あの飛行機事故があった時……」
込みあげてくるものを堪えきれなくなって、律子もまたハンカチをバッグから取りだし、一生懸命涙を拭った。
「テレビであなたのお父さんとお母さんの写真を見て、愕然としたわ。いつかこんな日が来るとわかっていたなら……聖美の父親も彼との結婚を反対しなかったかもしれない。簡単にいえばね、わたしの夫は自分の娘の結婚相手が韓国人だということが気に入らなかったのよ。韓国人に対して何か思うところがあるというわけじゃないの。おらそく聖美の交際してたのが中国人でも反対だったことでしょうからね。それで、娘のほうでは父に、「韓国人だからなんなの!?お父さんがそんな人種差別主義者だとは思わなかった!」って言って飛び出していったのよ。国際線のパイロットだなんて、ちゃんとした素晴らしい人じゃないのってわたしもお父さんに言ったんだけれど……ふたりは結局最後までわかりあえずに終わってしまったのね。あの人、聖美の亡くなる一年くらい前に死んだのよ。膵臓がんでね……最後、せん妄状態だった時に、「聖美、聖美」って何度も名前を呼んでたわ。ほんのちょっとボタンをかけ違ってしまっただけで、こんなことになるだなんて……わたしも、もっとどうにか出来なかったのかと思って、随分自分を責めたものよ」
「ハルモ二(おばあさま)……」
父方の祖父母はふたりともすでに亡くなっているため、愛榮はまだ自分に近い血縁がいるのだと思って、驚いた。もちろん、愛榮の父は五人兄弟だったため、親戚の数はそれなりに多いとはいえ、やはりそれと祖父母というのは愛榮にとって別の存在だった。
「日本の大使館に問い合わせた時にね、あの飛行機事故で亡くなった方々の遺族会があると聞いて、行ってみたんだけれど……あんまり苦しくて切なくてね、あなたにも声をかけようと思ったけれど、他に親戚の人たちもいたし、第一言葉が通じないだろうと思って、躊躇ってしまったのよ。第一、今更わたしが声をかけたところで、これまでお祝いひとつ送ったことがあるわけでもなしって、そんなふうに思ってしまってね……」
「ああ、それで、だったんですね。わたしのファンの振りをして、いつも行く先々の試合で応援してくださっていたのは……」
「振りってわけじゃないのよ」
そう言って、律子は涙を拭うと、初めて微笑った。
「あなたのファンなのは本当のことですもの。昔から、わたしも聖美もフィギュアスケート観戦が大好きだったのよ。男子ではね、小早川圭くんと氷室光くんを応援してたりしてね。今回のこと、とても残念だったけれど……」
(余計なことかしら)と思い、律子はここで口を噤んだ。けれど、愛榮のほうは瞳を涙で潤ませつつ、慕わしそうに律子のほうに手を伸ばすと、彼女の両手をぎゅっと握ってきたのである。
「嬉しいです。オリンピックでメダルを取れなかったことは悲しいけれど、今は嬉しい気持ちでいっぱいです。だって、まだわたしには、血の繋がったこんなに素敵なおばあさまがいただなんて……もっと早くにそうおっしゃってくださったら良かったのに」
「まあ、でも本当にびっくりだわ。そんなに日本語が上手だなんて……コーチとはいつも、日本語でお話するの?」
「その時によって、英語だったり日本語だったり……でも、コーチのお屋敷にいる時にはいつも日本語です。奥さまがコーチとお話する時はいつでも日本語なので」
リョウはふたりがお互いの存在しか目に入らないようにしっかと手を握りあっているのを見て――運転席側に「車を出せ」とスピーカーを通して伝えた。ちなみに、ボブ・カーティスはすでに助手席のほうに収まっている。
愛榮と彼女の母方の祖母である律子とは、リョウと愛榮が宿泊しているスイートルームで、その後も食事しながら三時間半ほどもしゃべり続け……その間、リョウは隣の続き部屋のほうで論文の執筆に取り組んでいた。
リョウがこの日驚いたのは、愛榮が囲み取材を受けている時に韓国スケート連盟の代表者や他のスタッフがやって来て、「先生がついていながらこれは一体どういうことですか!」と激しく詰られたことだったろうか。これまで、愛榮がどの試合でも表彰台へ上がり続けている間は、「小早川先生におかれましては……」とばかり、平身低頭に接してくることしかなかったため、リョウとしてはその態度の豹変ぶりに驚くばかりだった。他の試合はともかくとして、肝心要のオリンピックで愛榮がこけたのは、まるですべてコーチである小早川亮ひとりに責任があるとばかりの物言いだったからである。
とはいえ、リョウとしては――彼はこれまでの人生でそんなことをしたことは一度もないのだが――とにかく自分のコーチとしての能力のなさを詫びるしかなかったといえる。そして愛榮が囲み取材から解放されて戻ってくると、「小早川コーチは何も悪くありません。責めるならわたしだけにしてください……!」と、普段でも若干濡れたように見える射干玉(ぬばたま)色の瞳で訴えかけると、韓国スケート連盟の面々もぐっと黙りこむ以外なかったようである。
リョウは頭の半分では論文の文言について考えながらも……何度もふと手を止めては、今日の愛榮の演技について思いを馳せた。いや、それ以前にザグレブ入りを果たした時にまでも記憶を遡らせて、自分が愛榮のためと思いながらも、何をして・何をしてやらなかったかと、自分のコーチとしての落ち度を考え続けていたのである。
もちろん今もまだ、愛榮がオリンピックで金メダルどころか銀メダルも銅メダルも取れなかったことについて、リョウはショックを受けていた。というより、愛榮の演技直後はまだどこか、愛榮がメダルを取れなかったということが半ば現実でないように感じているところがあったのだろう。けれど、だんだんにじわじわと――次の四年後までその機会を待たねばならないというのがどんなことかを理解しはじめていたのである。
(カール・アイズナーの奴も、俺に負けたあとおそらくは、今の俺みたいな気持ちだったっていうことか……)
そう思うとますますリョウは気分が滅入ってきた。こういう時、リョウは葵と話すと心が癒され安らぐが、今は自分以上につらいであろう愛榮のことを慰め励まさねばならないという立場である。
(ああ。早くケンブリッジの屋敷に戻って、葵や愛の顔が見たいな。それで、愛榮を慰める役のほうはあいつにバトンタッチして、俺は適当に面白おかしいことでもしゃべって、愛榮のことを笑わせるといった立場を取ればいいというのなら、どうにか耐えられそうなんだが……)
けれど、愛榮が例のストライプの紙バッグおばさんの正体がわかったことで、俄然元気づいて見えたというのは、リョウにとっても嬉しいことだった。まさか血の繋がりのある母方の祖母だとまでは思っていなかったが、こんなことならもっと早くに彼女の素性を洗えば良かっただろうかと思わぬでもない。
(だが、結局のところこれで一番良かったのかもしれんな。自分の祖母がこれまで、世界中のどこで試合が開催されようとも、孫の演技を見に来てくれていたということが、愛榮には何より嬉しいことだったろうし……)
リョウが論文の執筆を中断させ、パソコンの前で腕を組んだまま、溜息を着いていると――続き部屋の開きっ放しになっているドアが二度ノックされた。
「少し、よろしいですか?」
「ああ。構わんが……」
リョウはこの時、ついいつもの癖で、パソコンの画面を切り換えると、ロックをかけた。画面上ではスーパーマリオブラザーズのマリオとルイージが走りまわり、時折兄弟でまったく息もぴったりに跳び上がると、クリボーやノコノコを蹴って倒すということが繰り返される。
「どうか愛榮のこと、これからもよろしくお願いします。わたしに出来ることなら、なんでもしますから……っ!!」
椅子に座ったままのリョウの前で、律子は半ば膝をつくようにしながら、そう彼に頼んでいた。リョウは食事のあとは席を外していたため、この二時間半ほどの間、ふたりがどんな話をしていたのかはわからない。だが、どうやらそう頼むということは、彼女が愛榮を引き取るとか、一緒に暮らすといった方向には話が進まなかったのだろうと思い、リョウはほっとする。
「やめてください、お母さん。第一、あなたがわたしに頼むことなんて本当は何もないんですよ。愛榮のことを俺はすでに家族の一員のように感じているし、うちの屋敷は広いですからね、愛榮がいて何か困るということもない。葵も、子供の面倒を愛榮に見てもらったりして、助かってるみたいですし」
「じゃあ、これからも愛榮のこと、見捨てないでいただけるんですね!?」
この段になると流石に、(このおばさん、俺のことをどんな人間だと思ってるんだ?)とリョウにしても思ったが、それと同時に自分のことをコーチとして高く買ってくれているのだろうと気づき、リョウは申し訳ない気持ちで一杯になった。それなのに、最後の最後、もっとも肝心なところで――自分と愛榮は躓いてしまったのだから。
「見捨てないも何も、愛榮もまだ十九歳ですし……次のオリンピックの時には二十三ですか。あと四年、もし愛榮が俺について来る気があるのなら、俺は自分に出来ることはなんでもしたいと思ってます。ただ、今俺も、何故最後の最後で愛榮にああいうメンタル面での弱さが出たのか、考えてたところなんです。ああ、誤解しないでください。好不調の波というのはどの選手にもあるものなので、愛榮が悪いとか、このあと彼女にそのことで説教を食らわそうとか思ってるわけではないんです。ただ俺は自分にコーチとして何か落ち度があったのではないかと思ったもんですから……」
(ああ。ではこの人は孫娘の気持ちに、本当にまるっきり気づいてないんだわ。雑誌や何かで取り沙汰されているのを見た時にはどうとも思いはしなかったけれど……愛榮のこの人を見る目つきでわかる。あの子が妻子のある人を愛してるんだってことが……)
この三時間以上もの間、律子と愛榮は彼女の恋愛についての話など一切しなかった。ただ、愛榮の尊敬よりももっと愛着のこもった眼差しを見ただけで律子にはすぐわかった。彼女にしてもこのオリンピックでメダルを取り、どれほどこの崇敬するコーチのことを喜ばせたかったことだろう。だが彼は、普段の練習では厳しいのに、愛榮のことを一切責めなかったという。むしろキツくお灸でも据えてもらったほうが気持ちが楽かもしれないとさえ彼女は言っていた。
「愛榮は、ただ小早川コーチに申し訳ない気持ちでいっぱいだと、そんなふうに申していました。自分がどうこうというより、コーチからあれほど良くしていただいたのに、目に見える結果を残せなかったことが悔やまれると……」
「ああ、いいんですよ。説明されなくても、そんなことは俺にもわかってることですから。俺の仕事はまず、次の世界選手権で愛榮のことを初めての世界女王にするっていうことです。そこから始めて、また色々と作戦を練っていかなくてはなりませんが、お母さんはまあ、いつでもうちのケンブリッジの屋敷に遊びに来たくなった時に来てください。社交辞令でもなんでもなく、本当にそうしてくださって構いませんから」
「あ、ありがとうございます……!!」
選手時代のエキセントリックなイメージとは違って、彼が至極まともな人間に見えたため、律子としても驚いたかもしれない。そして心からほっと安堵する。この人物に愛榮のことを任せておけば、自分が彼女のことを引き取るよりも、より大きなことを彼が成し遂げてくれるだろうことがわかって。
(ただ、心配には心配ではあるけれど……選手がコーチに恋をするなんていうのはよくあることでしょうけれど、愛榮はそのコーチと一緒に住んでいるんですものねえ。スケートの練習でもプライヴェートでもずっと一緒だなんて、本当に大丈夫かしら。わたしにしても、そのこと以外では何も心配ではないのだけれど……)
もちろん、律子にしても愛榮のことを引き取りたいと思う気持ちは当然ある。いや、愛榮と話している時に、一体何度そのことを言おうと口に出しかけたことだろう。けれど、この子はスケートの選手として今のままでいたほうがいいのだと思い、グッと言葉を飲み込んだ。コーチ御夫妻にも可愛がられているというのなら、自分が横から余計な嘴を挟むべきことではない。
このあと、律子は長居してしまったことをリョウに詫び、愛榮の手をぎゅっと握りしめながら、「スケートがんばってね……!」とあらためて言って、自分が一生の間で泊まることは決してないだろうと思われる豪奢なスイートルームをあとにした。
「良かったな、愛榮」
リョウはまだ涙の残る眼差しで、祖母の出ていったドアを見つめる愛榮の頭をぽんと撫でた。
「はい……!!そしてこのこともやっぱり、コーチのお陰だと思ってます。ボブにおばあさまのことを捜すように言ってくださったから……でもわたし、まさかまだ自分におばあさまがひとり残っているとは思ってもみませんでした」
リョウもまた、本来ならばふたりずついるはずの祖父母の中で、唯一今も生きているのは母方の祖母だけである。彼女は今ニューヨークの相当お金を持ってでもいないことには入れないような高級介護施設で何不自由なく暮らしている。
「俺も、実をいうと結構なおばあちゃんっ子でな。今も施設に入っているばあちゃんとは交流がある。愛榮もあの人のこと、大切にしてやれよ。あの人がうちに遊びに来る時には、いつでも航空券を手配してやるから」
「は、はい……それで、あのう、コーチ。わたし、次のシーズンに入る前に少し旅行なんてしてもいいでしょうか?オリンピックでこんな不甲斐ない結果を残しておいて、旅行だなんてと思われるかもしれないんですけど……」
リョウは旅行の時には必ず携行していく小型の湯沸かし器で湯を沸かすと、紅茶を二杯入れて、片方を愛榮に渡した。そして、テーブルの上の残った菓子類などをつまむ。
「もちろんいいさ。日本のあの人のところにでも行くのか?」
「いえ……いずれはそうしたいと思ってるんですけど、先に律子さんのこと、ソウル観光に連れだしたいなと思って。母さんがどんな場所でどんなふうに暮らしてたかとか、そんなことをお話したいと思って。コーチ、わたし、実はリンクに出る前に、とても心が揺れたんです。きっかけはたぶん、灰島選手の物凄いオーラに圧倒されたっていうことだったかもしれません。自分はどんなに努力してもあの人みたいにはなれないし、もしなれたとして……金メダルを取ってもお父さんもお母さんもいなくって、なんだか自分のこと、物凄く孤独で惨めだと思いました。自分でも演技前はそうした余計なことが頭をよぎったりしたことはなかったので、自分でもびっくりして……ジャンプを転倒したその瞬間に、律子さんと目と目が合ったんです。今にして思うと本当に不思議だけれど、わたし、あの時は自分のことをずっと応援してくれてるこの人のために滑ろうって、そんにふうに思って……」
「そうか」
紅茶にミルクピッチャーからミルクを注いでミルクティーにしながら、リョウは頷いた。そのあと愛榮が自分の元まで戻ってきて、「コーチにとってわたしはなんだったんでしょうか?」と彼女が聞いたのをリョウはもちろん覚えていたが、そのことはあえて不問にした。何故といって、リョウの判断では演技直前に混乱のあまり愛榮はそんなことを口走ってしまったのだろうと思ったからだ。
「だが、その旅行へ出かける前に世界選手権があるからな。それが終わればおばあちゃんとの旅行が待ってると思って、頑張れよ。今回おまえがメダルを取れなかったことについては……俺は今後も何か言うつもりは一切ない。起きてしまったことは起きてしまったことだからな。それよりも、ボストンへ戻ったあとは世界選手権で金メダルを取ることだけを考えろ。わかったな!?」
「は、はい……っ!!」
リョウの裁断があまりに寛容だったため、愛榮はここでもまた泣きそうになった。「おまえもミルクティーにするか?」と言って、残ったミルクをリョウは愛榮のカップに少しだけ注ぐ。
「あ、あの……コーチ。どうしてもっときつくお叱りにならないんですか?わたしがおばあちゃんと感動的な再会を果たしたとか、そういうことが理由なら……それとこれとは別のことですので……」
「はははっ。そりゃあ、おまえのことを痣が出来るくらい殴って叱り飛ばせば、演技前のあの瞬間に戻れるとでもいうのならな、俺は喜んでそうするよ。だが、繰り返すようだが起きてしまったことは起きてしまったことだ。俺自身の考えでは、その事実を厳粛に受け止めて前に進むというのが、もっとも人間らしくまっとうな道だという気がする。だが愛榮、覚悟しておけよ。四年は長いぞ」
「…………………っ!!」
いつものように「はいっ!!」とは、愛榮にも元気よく返事できなかった。何故といって、愛榮は今、フィギュアスケートに対してある確信が薄れていきつつあるからだ。メダルを取れなかったことに対する失望とともに、一気に競技に対する熱も冷めた。また同じように不安や緊張を乗り越えて試合へ臨み続けることに対する恐怖感もある……これがただ一過性の燃え尽き症候群のようなものであり、祖母と旅行するうちに癒されるものならばいいが、もしそうでなかった場合は――けれど愛榮はそれ以上のことはこの時、考えることが出来なかった。
(それよりもまずは、世界選手権だ。そしておばあちゃんとソウルを観光して、あとのことは戻ってきた時に考えよう。ああ、どちらにしても結果が同じなら、オリンピックでメダルを取って今期限りで引退とでもいうほうが、どれほど良かっただろう。そのほうがコーチだって納得してくれただろうし……)
あと四年――次のオリンピックの時、愛榮は二十三歳ということになる。そして愛榮は自分がそんな歳まで本当に頑張っていけるのだろうかと、訝った。リョウと葵にコーチになってもらって約三年。とても長かったと愛榮は感じている。そこにさらにもう一年加わったら、自分は一体どうなってしまうのだろう。そしてその一年一年、自分は本当にコーチの望むような結果を出し続けることが出来るのだろうか……。
(それに、葵先生の隣で優しく微笑むコーチのことを、わたしはこれからも見続けることになるのだわ。それにまた子供が生まれたら、ますますコーチは彼女のことを愛するようになるだろう。そんな幸せな家族の肖像の横で、嘘の微笑みばかり浮かべることになるのだとしたら、わたしはあのお屋敷を出ていかなくてはならない……)
もちろん、選手とコーチの同居状態を解消するというのは、そう問題になることではない。ボストンで一人暮らしをしてアーヴィングへは通い、そこでだけリョウと接点を持つというのでも十分だし、むしろそのほうが普通なことでもある。けれど、愛榮はそのうちのどちらを選んでも自分の心から虚しさを消すことはできないとわかっていた。そしてそうしたコーチの支えなくしては、自分がスケートを続けていかれないというのは、致命的なことだと思いもした。
(わたしはコーチに愛されたいんだ……フィギュアスケートの選手としてではなく、ひとりの女として……)
けれどその道は、あまりに苦しい荊のような道だった。決して自分を振り返りはしない、女としては決して見てくれることはない人を愛し続ける……いや、小早川亮というコーチのそばにいる限り、自分は彼のことを愛し続けるだろうと愛榮にはわかっていた。それは同じ屋敷に住んでいようと、リンク場だけで会うということにしても、どちらでも同じことだ。そして彼から独り立ちするということは、愛榮にとってフィギュアスケートをやめることを意味していた。もはや自分は小早川亮という男なくしては、スケートを続けるということになんの意味も見出すことが出来ないのだから……。
(どうしよう。こんなこと、誰にも相談できない。葵先生はもちろんのこと、エリカにも誰にも……)
以前までは、フィギュアスケートを通しての絆さえリョウとの間にあれば、彼にひとりの女として認識されなくても平気だと愛榮には思えていた。ただそばにいてコーチの姿を見、その声を聴き、彼が自分の目を見て何かを話してくれるというだけで十分幸せで、こんな毎日がずっと続いていってさえくれるのなら、他には何もいらないし、フィギュアスケートのことに関しても、血反吐を吐くほどの思いをすることすら、本当の苦しみではなかった。けれど愛榮は今、T字路に立たされている。ひとつは、このまま自分の気持ちを誤魔化し続けながら、小早川亮というスケートのコーチについて行くという道、もうひとつは、まったく別の、フィギュアスケートとは関係のない人生を歩むという道だった。
この場合難しいのは、愛榮は結局のところ、自分がどちらの道を選んだとしても後悔するだろうということだった。それに、スケートをやめた一年後……いや、半年後には後悔しているかもしれない。だからといって、誰か他のコーチについて現役復帰しようといったようには、愛榮は思えないに違いなかった。
(ああ、本当にわたし、どうしたら……どうするのが一番いいんだろう……)
愛榮はこれが恋してはいけない人に恋をした罰かと思った。だとしたら、自分ひとりだけで悩み苦しまなければいけないということなのだろう。そしてこの気持ちが罪だというのならば、愛榮は彼から離れるしかないのだとも思った。
「どうした、愛榮?なんだか顔色が悪いな。そうだ、おまえ、今日もこっちの部屋で寝ろ。俺は向こうの続き部屋のほうで寝るから」
「そんな……いいんです。コーチ、わたしに気を遣わないでください」
リョウはもう今回のザグレブオリンピックのことは、愛榮の前では口にすまいと心に決めていた。いわゆる、五輪の魔というものに呑まれてしまったのかもしれない。だが、次のオリンピックまでは四年ある……それまでに灰島蘭を倒すための算段を練り、点差を詰めていくことは十分可能だとリョウは思っていた。
「いいから、美味しいものも色々食べたし、あとは風呂にでも入って体をあっためて何も考えずにぐっすり寝ろ。俺のことをがっかりさせただのなんだの、そんなくだらんことで頭を悩ませるのももうやめるんだ。明日はエキシビション、その翌日が閉会式か。そうだな、愛榮。このオリンピックが終わったらドゥブロヴニクにでも行くか?前にも一度行っているが、なんだっけ?おまえの好きなジブリの……」
「魔女の宅急便です」
「そうだ、それだ。そのアニメのモデルになった街なんだろ?おまえ、また来たいって前にも言ってたもんな」
「はい……なんだか中世の御伽噺の国に迷いこんだみたいって思って。あ、そういえば、レオもエキシビションが終わったらドゥブロヴニクに行くって言ってたっけ。メールで、なんかお土産欲しかったら買ってきてやるって言われたんだった」
愛榮は桃のクリームパイを食べながら、ふと思い出したようにそう言った。途端、リョウが不機嫌そうに眉根を寄せる。
「レオっていうのは、ルカ・ニキシュと同点だったのに四位だったサルのことだな。おまえ、あいつと一体どの程度親しいんだ?」
「いえ、本当にただのリンクメイトっていう感じだと思います。たとえば、わたしがスケートやめたり、レオのほうがアーヴィングを去っていったりしたら、もうそれきりになるだろうなっていう感じの……本当に本当の友達だったら、それぞれの国に帰っても連絡を取りあったりするだろうけど、礼央はそういうのとは違うかな。ようするに、その程度の関係といっていいと思います」
愛榮が自分の部屋で礼央に英語を教えていた時、突然リョウが乱入してきた時のことを思いだして、愛榮はおかしくなった。『男とふたりきりで勉強なんて、絶対に駄目だ!』、『はあ!?あんた一体何考えてんだ。俺はただ英語を教えてもらってるだけなのに……』、『うるさい!とにかくここから出ていけ。勉強するんなら居間のほうで、俺や葵の目の届くところでやれ。俺はこの屋敷の主だからな。この屋敷の敷地内では俺の言うことは絶対だ』……そしてここで愛榮は(そういえば)、とあることに思い至る。
(レオも惜しいところで同点四位なんだっけ。その悔しい気持ちも今はわかるから、あとでメールしておこうかな)
そして愛榮はこの時リョウに、レオとはそれほど大した繋がりのある関係ではない――という言い方をしたものの、オリンピックが終わり、再びアーヴィングスケートクラブでの練習がはじまった時、彼がアーヴィングを去り日本へ戻ると知って非常なショックを受けた。それは他のクラブメイトもエリカも同じだったようで、愛榮はその時に初めて、同性ではなく異性であれほど親しく友人関係を築くことが出来たのは……レオが初めてだったと気づくのだった。
>>続く。