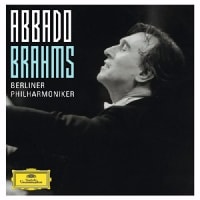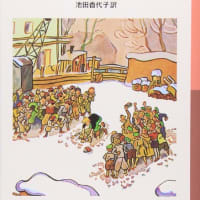今回は前回と違って、本文のほうが短めです(^^;)
なので、このくらい前文に使える時に一度、『春の祭典』について触れておこうかなと思いました。
この小説の中で言及のあるのが、モーリス・ベジャール振付の『春の祭典』とピナ・バウシュの『春の祭典』、それと二ジンスキー振付のものなのですが、とりあえず順番に動画を貼っていってみますねm(_ _)m
Stravinsky- Rite of Spring "Opening"
Stravinsky- Rite of Spring "Sacrificial Dance"
ピナ・バウシュについて描かれた映画『ピナ・バウシュ~踊り続けるいのち~』をご覧になった方は、『春の祭典』が中途半端なところまでしか描かれていなかったので、「えっ!?この続きどうなるの!?
 」って欲求不満になったかもしれません。でも続きの映像を見てみると、何故映画のほうに続きが入ってなかったのかがわかりますよね(^^;)
」って欲求不満になったかもしれません。でも続きの映像を見てみると、何故映画のほうに続きが入ってなかったのかがわかりますよね(^^;)そして、次の文章は『怖がらずに踊ってごらん』からの『春の祭典』についての抜粋箇所です。
>>もっぱら純粋なエロスの祭として解釈される流行に対抗して、ピナ・バウシュの『春の祭典』は、本来の<犠牲>という筋を拠りどころにし、それを死刑宣告される女性の観点から描く。それは不安と同情に満ち、しかしはじけるようなエロティシズムと性であふれていた。
舞台は、床に泥が厚くばらまかれ、人工的につくられた森の空き地。中央に置かれた赤く輝く布の上に、一人の若い女性が横たわっている。曲の最初の何小節かで、アンサンブルは次第にフルメンバー(初演の時は十三組の男女)に達する。初めはかなりの間、それぞれ神経質に踊る女性たちだけ、その後でようやく男のダンサーたちが加わる。赤い布はしだいに重要な役割をおびてくる。それは犠牲(いけにえ)のシンボルであり、いけにえになる、あるいはいけにえを決定する、つまり死刑執行人になるということが、男たちと女たちに呼び起こす感情のすべての触媒となる。魔術的な魅惑の混ざった恐怖、絶望、戦慄。最後に、その布はいけにえのための赤い衣装となり、一人の女性から他の女性へとおどおど、おずおず手渡され、ついに不幸な最後の女性の手に残ってしまう。その女性がフィナーレで、荒々しく抗うように、死の舞踏を踊るのだ。その周りでは世界が硬直していくように見える。
その死との闘いの踊りのさなか、透明の赤い衣装がダンサーの身体から滑り落ち、乳房がむき出しになった。初日の客は不(幸)運な偶然だと思い、それが集団から死刑宣告された少女の寄るべなさをいっそう効果的に際立たせた。しかし上演が続くにつれ、それは女性の運命への観客の緊張と関心を高めるための、抜け目のないドラマトゥルギー上の手段であることが判明する。内部事情は知らないが、もちろん、初日に衣装がずりおちたのは実際に計画されてはいなかったことで、ピナ・バウシュが偶然に与えられた機会を意識的につかまえたのだ、という可能性もある。のちに彼女はよく、偶然や事故ですらドラマトゥルギー上で効果的に利用できるし、振付に組み込むこともできる、と語っている。
(『ピナ・バウシュ~怖がらずに踊ってごらん~』ヨッヘン・シュミット著、谷川道子さん訳/フィルムアート社より)
女性の服がはだけたのは、実はアクシデントだったんですね!

でもこれ、初めて舞台を見た方は物凄い衝撃だっただろうなあって思います(^^;)
そしてストラヴィンスキーの『春の祭典』のような音楽に振付した、また振付しようと思ったベジャールさんやピナって本当にすごいなってあらためて思うんですよね。。。
いえ、わたしに音楽的才覚がないからかもしれませんが、ストラヴィンスキーの『春の祭典』って、音楽だけ聴いてるとほんと、心臓に悪い感じがします

初演の時には大混乱が起きた……というのは、なんか本当に物凄く頷けるというか(^^;)
そしてわたし、ニジンスキー「らしさ」についてなんてほんとはわかってないのですけど、ニジンスキー振付の『春の祭典』は、すごく「らしい」感じがして、これを彼がどんなふうに踊ったのかが何故かわかる感じのするのが不思議です。。。
Joffrey Ballet 1989 Rite of Spring (1 of 3)
Joffrey Ballet Rite of Spring 1987 (2 of 3)
Joffrey Ballet 1987 Rite of Spring (3 of 3)
なんていうか、とりわけダンスって、「これを見てこう感じなさいとか、ああ感じなさい」という制約のない、本当に自由なものだと思うので――ピナ・バウシュさんについて書かれた本の↑の文章のとおりに感じたり考えたりすべきなのだ……と思う方ももしかしたらおられるかもしれないのですが、正直、そのあたりはあんまし関係ないですよね。
なんの先入観もなく見た場合、それこそ見た人によって十人十色の意見や感想があって当然だと思うので……でも、それでも見た人が大体共通項として<犠牲>ということは感じるし、「犠牲になるなんてわたしは嫌よ!」、「わたしだって嫌よ!」、「じゃああなたがなりなさいよ!」といった押しつけあいとか――実際、人間関係あるあるですよね

誰かがそうしたスケープゴートの役を引き受けてくれることで、たとえば四十人学級だったら残りの三十九人は救われるとか、人間というのは本当に恐ろしいものだなと感じるのと同時に、その同じ恐ろしいものが自分の中にもあって、その役目が自分に回ってこないようにと神経症になる寸前まで物凄く気を遣っていたりとか……この魂の神経を揺すぶられるような生の感覚を呼び起こすという点で、ピナ・バウシュさんは本当に天才だな~と思います

>>「春とは一体何であろうか?それは冬のマントの下で長い間眠っていた巨大で原始的な力にほかならない。そう、春は突如として湧き起こり、植物、動物、人間それぞれの世界を、燃え立たせるのである。
人間の愛というものは、その肉体面において、宇宙を創造した神の愛の行為、そして神がそこから得る悦びを象徴している。人間の精神に関する逸話の国境が少しずつ消えてゆき、世界の分化について語り始めることができるときには、普遍性のない民族的情趣はことごとく捨て去り、人間の本質的な力を取り戻すことにしよう。いかなる大陸にあっても、どんな風土であろうと、あらゆる時代に共通の力を。
どうかこのバレエが、あらゆる絵画的な技巧から解き放たれ、肉体の深淵における男と女の結合、天と地の融合、春のように永遠に続く生と死の讃歌とならんことを!」
(モーリス・ベジャール)
――東京バレエ団さまのHPよりm(_ _)m――
こちらもまた有名な、モーリス・ベジャールさん振付の『春の祭典』。
いやあ、すごいですよね~
 なんの前置きもなしにこんなの見せられたら、衝撃のあまりもう言葉もない気がします。。。
なんの前置きもなしにこんなの見せられたら、衝撃のあまりもう言葉もない気がします。。。なんにしても、↓で蘭や光くんが見てるのはこんな感じの映像だということでよろしくお願いします(何ヲ??
 )
)それではまた~!!

ダイヤモンド・エッジ<第二部>-【17】-
かなりのところ大雑把にではあるが、蘭と光とは館神邸の大掃除を済ませると、重箱やタッパなどにお節料理の品を詰めて風呂敷に包み――「じゃあね、恭一郎!良いお年をー」と言って、館神邸をあとにしていた。
もちろん、その前に年越蕎麦のつゆは作ってあるだのといった、一通りのレクチャーは蘭も恭一郎にしてある。そして恭一郎はといえば、「いいから、そんなものは見ればわかる。それより環境が変わって風邪を引かんようにな」などと、若干ずれたことを言っていたかもしれない。
「あーあ。恭一郎かわいそっ。もう四十過ぎたいいおっさんなのに、ひとりぼっちで年越しなんて」
蘭は光のヴェセルの助手席に乗りこむと、シートベルトを締めながら赤い屋根の洋館を塀越しに振り返る。
「うん。わるいと思ってるよ。でも、こんなのもあと何年かだけだってコーチもわかってると思うから……俺が蘭と結婚したら、子供も連れてさ、年越しは必ず館神邸でって、今から約束しておくよ」
「うん。でもそんなこと言って、あとで喧嘩になったりしたらやだね。『あの時そう言ったじゃないのォォォッ!!』とか言って。たぶんわたしその頃にはきっと、こめかみのあたりにピップエレキバンとか貼ってそう」
「それで、若干つり目なんだね」
「そうそう。その頃には光、近所の人みんなに言われてるんだよ。『なんの因果であの人もあんなのと結婚したんだろうねえ』って」
「そっか。じゃあ俺はその頃、生活疲れかなんかで、頬なんかすっかり痩せこけてるんだろうな」
「そうなの。間違ってジャイ子と結婚した時ののび太くんみたいにね」
この時すでに光は車を発進させて大きな通りに出ていたのだが――笑いが堪えきれなくなって、あやうくハンドル操作を誤るところだった。前に蘭が言っていたとおり、こんな年末に事故でも起こそうものなら、新聞沙汰になってしまう。
「移動するのに十分もかからないのに、事故に遭ったりしたら悲惨だから、蘭少し黙っててくれる?」
「はいはーい」
そう言いながらも蘭は、もちろん『人が吹きだすような変なことを言うな』の意であるとわかっているため、全然違う話題を光に振る。
「そういえばさあ、光。石原のぞみのこと、どう思う?」
「……石原って、全日本で蘭に次いで二位だった?」
「うん。モデルみたいにすらーっと背が高くて、結構可愛い子。全日本の時にロッカーで一緒になったら、自分はあんたと違って可愛いから、スケートする以外にも誘惑されることが多くて大変だ……とかほざいてた子」
「ふうん。っていうか蘭。なんで俺にそんなこと聞くの?」
「んー、だからね、わたしが思うには光と並んで絵になるのは、石原のぞみみたいな子だなーと思って。で、光は初対面の人のことは特に相手を美化して見るでしょ。だから本当は腹黒い女の子の策略とかに全然気づかなくって、向こうでも結婚するまでそういうの隠してるから全然わかんなくって、結婚してからそういうのがわかってきて……もしそんなことになったら、光だったらどうするのかなってシミュレーションしてみたいと思って」
「難しいことを聞くねえ」
もちろん光も、石原のぞみが「メイク落としたすっぴんのほうが化物みたい」と言ったと知っている。だが、女子シングルフリー翌日の新聞に彼女が蘭と握手しているところがでかでかと出ていたところを見ると――そう悪い子でもないのではと、そんな気がしてしまう。
「でも、一度結婚しちゃったら、もうそう簡単に取消はきかないよ。どんな素晴らしい女性と結婚しても、結局は何かしらあとから不満が出てきたりするものなんじゃないか?それで、その頃には『結婚なんて所詮そんなものだ』って自分に言い聞かせて諦めるんじゃないかな。それでも本当に我慢できないとなったら……それで、子供もいなければ離婚することを考えるんだろうけど」
「そっかー。だって光、義理のお姉さんと実のお母さんの間に挟まって云々って昔言ってたじゃない。それで、そんな繊細なことが理由で家まで出たりとかして……だったらわたしと上手くいかなかったらどうするつもりなのかなーと思ったもんだから」
ちょうどここで、車がマンションの駐車場入口に到着する。蘭は運転免許を取りにいこうかどうしようか今迷っているのだが、ちょうど来年がオリンピックシーズンに当たるため、免許を取るにしてもオリンピックが終わってからだと、そう考えていた。
光がいつもながら狭い駐車場の白線の間にピタリと車を停めると、蘭としては「おおー!」と驚いてしまう。
「いちいちそんなビックリすることでもないだろ?」
「だって、光さんてば縦列駐車なんかがほんとにお上手なんですもん!スーパーの駐車場とかでもどんな狭いスペースにもピタッっと止めちゃうから」
「誰でもやってることだよ。それより、早く下りて。風呂敷は俺が持つから」
蘭は言われたとおり、膝の上に置いていた風呂敷をそのまま光に渡した。今日の蘭は、膝丈のミニのワンピースにそれよりも少し短い丈のダッフルコートを着ている。なんでも光はこういうのが好きらしいのだが、足許が寒いため、蘭は50デニールのストッキングをはいていた。
そして肩にショルダーバッグをかけ、彼氏の部屋にお泊りするため、光と一緒にマンションのエレベーターで七階まで上がっていく。ちなみに、光のキィリングを見ても例のピグモンはもうついていない。『そのキィホルダー受ける~!』、『彼女からもらったんだ』、『おまえの彼女、正気じゃないんじゃね?』……といった会話がなされるのを避けるため、昔懐かしいホネホネロックのキィホルダーを新たにプレゼントしたのだった。
「相変わらず綺麗に片付いてますねー、わたしの部屋とは大違い!!」
「そりゃそうだよ。蘭が来るって前もってわかってるから、綺麗に掃除しといたんだ」
そう言って光は、枯れてしまったサフィニアやクチナシの花のかわりに新しく買ったカトレアやデンドロビウムの鉢のあたりを何気なく見る。だが、蘭ほうからは「えーっ、蘭だー。わたしの名前が蘭だから?」といったような反応は一切ない。
「それにしても、また花の鉢が増えてますねー、光さん。シクラメンとかポインセチアとか……まあ、わたしも冬になると意味もなくつい買いそうになっちゃうけど。シクラメンって生命力が凄いんですよ。智子さんと一緒に暮らしてた頃、ほとんどろくに手入れもしてないのに毎年必ず咲いてましたもん」
「うん。館神コーチの屋敷の庭の水仙とかもさ、去年に続いてまた当たり前みたいに咲いて、結構びっくりした。もちろん多年草なんだから当たり前なんだけど……それでもやっぱり花にも人格があるように感じるくらい嬉しかったっけ。まあ、ちょうどスケートのシーズンが終わって春になる頃に咲くから、そのせいもあるのかもしれないけど」
「ふふっ。じゃあ今度、そんな光さんには水栽培用のヒヤシンスをプレゼントしてあげようっと」
「水栽培って?」
「えーっと、だからようするに、透明なコップとかビーカーみたいのに水入れて、ヒヤシンスの球根を育てるんですよ。お部屋のインテリアとしてもちょっと可愛い感じ。根っこのほうが透けて見えるから見ようによっては不気味かもしれないけど」
「もしかして、それも智子さんが?」
「うん、そうそう。智子さん、お花の好きな人だったんです。だからお花屋さんとかで死にかかってるような値下げされてる鉢植えをよく買ってきては甦らせてたんですよ。クレマチスとかクチナシも、花が駄目になってるようなのを買ってきて、来年また咲かせてみたりとか……」
「そうなんだ。クレマチスとクチナシは花が終わったあとに剪定して肥料もあげておいたし……これで来年も咲くかなあと思うけど、実際は来年になってみないとわかんないと思ったり」
「咲きますよ、きっと。光先輩は名前が光だから」
(それは関係ないだろ)と思いつつ、光は黙っておいた。三段になった花台の上の花のひとつひとつを見ていき、蘭がとうとうオレンジ色のデンドロビウムとピンク色のカトレアに気づく。
「あー、あの、こういうことされるとめっちゃ恥かしいかも……」
「ああ、名前と一緒だから?」
「だってわたし、なんか蘭の花ってあんまり好きじゃないんだもの。だから自分の名前もあんまり好きじゃなかった。智子さんに言ったら、草冠に東の門って書いて蘭っていうのは、いい名前だって言ってたけど。なんだっけな。天使とか神さまっていうのは、東からやって来るものなんだって。たぶんそれ、小さかったわたしに聞かせるための、智子さんの創作だったんじゃないかとは思うんだけど……」
「蘭っていい名前だよ。花だって綺麗なのや可愛いのが多いし……」
「まあね。わたしがそういう花のような美人かなんかだったら良かったんだろうけど……」
蘭が観葉植物のアジアンタムをいじっていると、不意に光が横からキスしてくる。
「ん……」
緑色のラグの上に押し倒されると、(あー、やっぱりこうなったか)と思いつつ、とりあえず蘭は光の好きなようにさせておいた。けれど、不意に彼は体を離すと「ごめん」と言った。それから冷蔵庫の中を漁ってそばの材料を取り出し、まな板をセットすると、まずはネギを切り始める。
「いいですよ、わたし、やるし……」
「いや、いいよ。蕎麦くらいなら俺でも作れるし……あと、夕方になったら鮨屋の出前の人、来るから。一応オードブルっぽいものは前もって買っておいて冷蔵庫に入ってたり。蘭は他に食べたいものとかある?買いに行くとしたら今のうちだから」
「ううん、べつに。光のおうちって野菜とかお肉とか、一人暮らしとは思えないくらい色々ストックしてあるんだもの。他に何か食べたくなったら自分で作って食べるからいいよ」
「そっか。じゃあ、あとは座って待ってて」
(へんなのー)と思いながらも、蘭は部屋にあった園芸関係の本を見たり、CDや漫画本やDVDの並んだ棚を見て過ごした。その中に、蘭は自分が決して見逃せないもの――モーリス・ベジャールの『春の祭典』のDVDがあるのを見て、もう一度光の元へ戻ってくると、彼にまとわりつきはじめる。
「モーリス・ベジャールの『春の祭典』、どうしたの?」
「ああ、サーシャからもらったんだよ。『春の祭典』を滑るんだったら、見ておいたほうがいいって言われて……たぶん、アランもDVD持ってるとは思うんだけどね」
「あれ見ながらごはん食べるのとか、光はいや?」
「ううん。全然いいけど……」
突然蘭のテンションが上がったのを感じて、光としても嬉しくなる。そもそも、今季のフリーを『春の祭典』にしようと思ったのは、蘭と初めてキスした時――見ていたのが、マリインスキー・バレエの『春の祭典』だったからだと光は思いだす。
光は鍋に鶏もも肉を入れ、そこにめんつゆとみりんを入れてつゆを作っておくと、蘭とソファに座ってベジャールの『春の祭典』を見ることにした。先ほどとは違って、急に蘭が親密な様子を見せるのに光は気づいていた。いつもバレエに絡む話が出ると蘭がこういう状態になるとわかっていたとはいえ、何分光のほうでは知識が足りないもので、うまく話を繋げられないことがあまりに多かったのである。
これからバレエの後半に差しかかるというところで、呼び鈴が鳴り――鮨屋の出前とわかっている光は、「いいところだったのに」と思いつつ、財布を手にして玄関へ向かった。蘭のほうではテレビの画面にすっかり釘付けになっていたものの、それでも光が戻ってくると「巻き戻そっか?」と聞く。
「いや、いいよ。前にも二回くらい見てるから……」
光としてはすでにお腹がすいているため、すぐにも寿司を食べたかったとはいえ、蘭が夢中になって見ているのがわかるため、あともう少し待つということにした。モーリス・ベジャールの『春の祭典』は、根源的・原始的な男女の性を描いているといってよく、冬という長く暗い季節に抑圧されたエネルギーが、春の芽生えとともに動物的なまでに解放される……光の見た印象としては、芸術的な領域にまで高められた生ぐさくも高尚なセックス――といった印象だったが、蘭がこれを見て今何をどう感じているかは光には想像してみることも出来ない。
「あーっ、やっぱりベジャールって最っ高~!!」
蘭はDVDを見終わるとそんなふうに叫んでいた。光のほうでは冷蔵庫からオードブルの皿を出し、特上の寿司を並べたりといった準備をし、茶を淹れるためにお湯もわかそうかというところだった。
「その、俺さ……他に、ニジンスキー版の『春の祭典』も見たりして、そしたらニジンスキーのことにも結構興味がわいて、色々調べたり……蘭がもし、バレエのことを話すたんびにそんなに目の色を変える感じじゃなかったとしたら、俺もこんなに興味を持ったりすることはなかったと思うんだ。だから、蘭にお礼を言っておこうと思って……」
「べつに、光がわたしに礼を言うほどのことは何もないってば」
蘭もまた光の手伝いをして、テーブルに皿を並べたりしはじめる。
「でもニジンスキーは一度知るとはまっちゃうよね、どうしても。『わたしは林檎を食べる。わたしは林檎ではない。わたしは神だ』とか、天才じゃなかったら絶対出てこないと言葉だと思うし。あ、じゃあもしかしてそのせい?今季の光のショートが『牧神の午後』なのって……」
「あれはさ、前にミカエルの振付で小早川亮が滑ってるだろ?それ以来、男子では誰も滑ってないと思うんだけど――ほら、写真に残ってるニジンスキーが着てたのとまったく同じ格好で小早川亮が滑ってて。だから、俺もちょっとどうかなって思ったんだけど、アランに相談したら「挑戦してみよう」って言われて、それで決まったんだ。実際、サーシャには色んなことを教えてもらって、すごく感謝してる。ほら、蘭が彼とパ・ト・ドゥなんかですごく体をくっつけてるから……それが面白くないとか、最初は色々思うところがあったんだけど」
蘭は、バレエの帰りに時々光が不機嫌だったのを思いだして、おかしくなった。
「だって、サーシャは完璧なプロの職業舞踊手ですもん。わたしなんより遥かに優秀で可愛いバレリーナたちを相手に何百回も公演やってるんですよ?そのことに比べたら、物の数にも入りませんて」
「うん、蘭の側ではそういう考えだっていうのはもちろんわかってたけど……でもやっぱり、なんか面白くなかった」
あくまでも光がムスっとしているのを見て、(じゃあ、今日はサービスしてあげよう)などと、蘭としてはそんなふうに思うばかりだった。そしてあとはテレビで芸術性のかけらもない番組の数々を見ながらふたりは食事をし、他愛もないことを話しては笑って――紅白歌合戦が終わり、ゆく年くる年がはじまる頃、光は例の指輪を持ちだしてきて、蘭に渡したのだった。
「あー、あの、これってもしかして、なんていうか……」
中を開けて見る前に、それが指輪のケースであることがわかって、蘭としては戸惑ってしまう。
「本当は、クリスマスプレゼントとして買ったものなんだけど、去年プレゼントしたのがネックレスだったことを思うと、指輪以外なんか思い浮かばなくて。もちろん、婚約指輪とか、そういう意味のものとして蘭が受けとってくれると嬉しいけど……でもそういうのが重いと思ったら、そんなに深い意味のないものだと思ってくれていいから」
「わあ、綺麗……」
左手の薬指にあんまりピッタリ収まったので、蘭としても驚いた。少し太めのプラチナリングで、細かいデザインが施された中央にダイヤモンドが埋まっている。
「あのう……こんな時に『これ、いくらだったの?』なんて聞かないほうがいいってわかってるんですけど、べつにわたし、こんなに高価なものを買ってもらわなくても、タッパ十個セットとかで十分満足だったのに……」
蘭にしても、ここまで来るプロセスがあったからそう言えるのであって、もしそれがなかったら、「こんな高価なもの、もらえないし!」と即座に返そうとしたかもしれない。けれど、指輪のケースを開けた瞬間蘭がすぐ思いだしたのは恭一郎の『他のことでは光に譲ってやるんだぞ』という言葉と、先ほどベジャールの春の祭典を見たことや、光がニジンスキーの話をしたことなどだった。
「蘭はさ、次のオリンピックが終わっても、最低でももう四年は現役を続けようと思ってるだろ?でもそれって、俺と結婚しても両立させられないかなって思うんだけど……」
「む、無理ですよ!スケートやってる間は、それが他の何より一番の優先事項になっちゃうし……光先輩だって、わかってるでしょ?今だってそういうことでお互い、たまにギスギスすることがあるのに。そういう時にずっと一緒にいたら、つい思わず言いたくもないこと言っちゃったり、いつもなら言わないで済むようなことを言ってあとから後悔したりとか……わたし、光とそういうことになるのだけは絶対嫌なんです」
「だからさ、俺はもう次のオリンピックで引退するつもりだし……そしたら、ある程度は蘭のこと、支えられるんじゃないかと思って。ただ、もしアイスショーとかに出るとしたら難しいかもしれないけど、今はスケートのコーチもいいかなと思ったりしてるんだ。その部分は俺が蘭に合わせるから……」
「そんな……わたし、光にそんなことさせられないって思うし、わたしの頭の中の理想としては、スケートの現役選手でいられるのなんて限界があるから、そしたら、そのあとだったらいくらでも……」
蘭がどこか必死な様子で薬指の指輪を外そうとするのを、光は止めた。
「それは、べつにそんな深い意味のないものだと思って、取っておいて。一種の俺の自己満足みたいなものだし……あとは、蘭が他の男のところにいかないためのおまじないみたいなものかな」
――このあと、蘭は綺麗に整ったベッドの上で光に服を脱がせてもらうと、彼にあるサービス行為をした。そして、除夜の鐘が鳴り終わってからの<姫はじめ>が終わった時、光は自分とぴったり寄りそうように寝ている恋人にこう聞いたのだった。
「蘭はもしかして、バレエダンサーの男の人が一番の理想だったりする?」
「……なんでそんなこと、聞くの?」
蘭はすでに半分眠かったため、うまく頭が働かないままにそう聞いた。前に光とセックスしたのがグランプリファイナルが終わったあとだったため、そうとわかっていて相手の求めに応えないとこういう結果になるのだと、そう感じていた。
「だって、そうだろ?蘭はバレエのことに関する何かを聞くと、目の色がすっかり変わっちゃうし……っていうことは、本当の理想はそうなのかなと思って」
「ううん、全然。だって、美貴先生のバレエスタジオにいた数少ない男の子って――全員カマっぽいか、気弱で内気か、男らしくてもナルシストとか……なんかそんな子ばっかりだったんだもん。だから、そういう憧れとかっていうのは全然ない。もちろんバレエのことは大好きだし、バレエの中の王子さまたちには心ときめくけど、それは王子さまにであって、それを踊ってるバレエダンサーに対してじゃないもの」
「そっか。なんかそれ聞いて安心した」
光は蘭の腰のあたりを抱くと、ほっとして、彼女の額のあたりを前髪越しにキスする。
「俺、根拠なんて全然ないけど、今年はすごくいいことがある気がする。だって、新年早々こんなにいいことがあったわけだしさ」
けれど、光のそんな独り言のような言葉を、蘭はもう聞いていなかった。そして光はそんな彼女のことを抱きしめたまま、これからも毎日がこんな感じならいいのにと、強くそう感じる。ごそごそと寝ている蘭の左手を探ると、指輪がまだ嵌まっていることにも、光としては強い満足感を覚えた。
それから光はふと、蘭がきのう車の中でしていた質問のことを思いだす。もし自分と結婚したあとに不満な点が出てきたらどうするつもりなのか……といったような主旨の質問だ。
(蘭は全然わかってないみたいだけど――あの質問はそもそも前提が間違ってる。俺が蘭のことを好きになったのはそもそもが、毎日のように長時間一緒にいるようになって、裏も表もよく知ってからのことだったわけだから……蘭にまだ何か隠してることがあったにしても、それはたぶん離婚する理由にまで発展するような欠点だとは俺には思えない)
そして蘭のほうでは、光よりも先に起きて朝のごはん支度をしながら、昨夜の光の質問のことを思いだして、こう思っていた。バレエの舞台のような夢の世界にしか存在しないと思っていた男がすぐ隣にいるのに、どうしてバレエダンサーのことなんか、彼が聞いてきたのだろうと……。
>>続く。