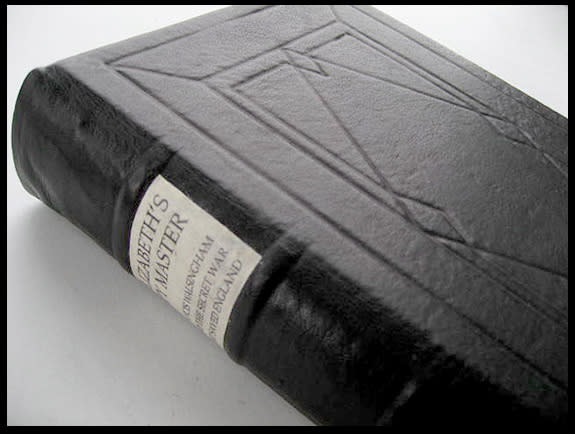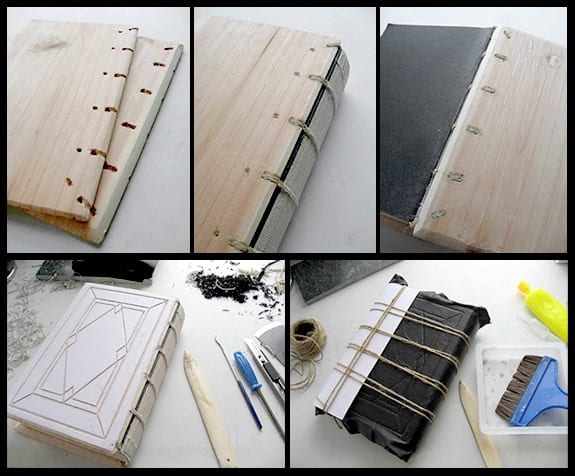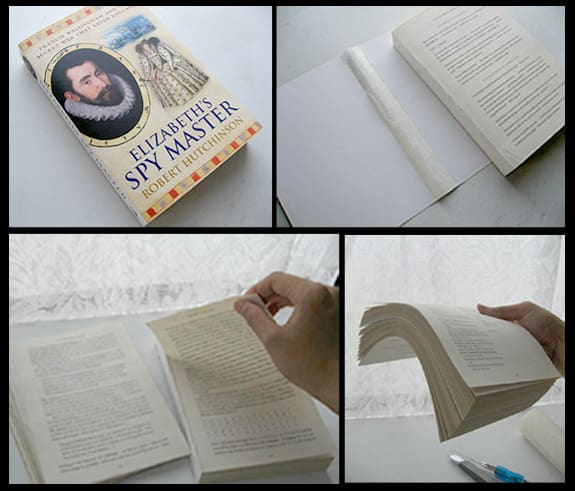京都シネマで上映中の『テンペスト』を観てまいりました。
嗚呼、消化不良。
ジュリー・テイモア監督の映画デヴュー作『タイタス』はワタクシの大好きな作品でございます。『タイタス』と同じくシェイクスピア劇を原作とする本作はしかし、所々に光るものをかいま見せつつも、全体としてはちぐはぐな仕上がりになってしまっておりました。
モッタイナイのひと言でございます、衣装、ロケーション、そしてとりわけ俳優陣が素晴らしかっただけに。
The Tempest Movie Trailer Official (HD)
題材からしてCGを盛大に使いたくなるお気持ちはわかります。しかしその使い方がいまいちこなれていないと言いますか、全体的に小うるさく感じられてしまいました。特に妖精エアリエルの動かし方はいただけません。残像を引きながら無駄に画面上を瞬間移動するのなんて、もうCG創成期じゃないんだからこういうのはよそうよ、と思ってしまいました。
ベン・ウィショー演じるエアリエル自身は、まっちろけで、中性的で、ぼさぼさ頭で、それはそれは可愛かったんですけれどね。水の中から現れる演出や半透明の姿もよろしうございましたし。船に火をかけたり蜂の群になってキャリバンたちを追い回す時の悪魔的な笑い顔も、助けてもらった恩をもう忘れたのか、とプロスペラになじられるシーンでの、先生に叱られているいたずら小僧のような表情も、また「ご主人様、私を愛してくださっていますか?」という台詞におけるしんみりした切実なトーンも実によかった。ベン・ウィショーの他の作品はワタクシ未鑑賞でございますが、なかなか芸達者な役者さんのようですね。

だからこそ、最後にプロスペラがエアリエルを解放してやる所を、役者よりもCGがキモと言わんばかりの何の感慨もない描き方にしてしまったことが残念でなりません。ここも絵的にはまあ綺麗だったんでございますけれども、プロスペラとエアリエルの間に主人と下僕という以上の親密な雰囲気があっただけに「かわいいエアリエル、これが最後のつとめだぞ。あとは大気の中に自由に飛び去るがいい。達者でな」(白水社版)、この台詞をつぶやいて、飛び去るエアリエルを見つめるプロスペラという絵がぜひとも見たかったのですよ。
また最後の「これにて私の術は破れ...」の長台詞を、俳優が語るのではなく、エンドロールとともに流れる歌にしたというのも、独創的といえば独創的ではありますけれども、やっぱりヘレン・ミレンが朗々と語るのを聞きたかった。こんな所にも消化不良感が残ります。
それから音楽の唐突な使い方、これだけはどうあっても擁護できません。とりわけ-----これは『タイタス』でもその兆候がありましたが-----所々これみよがしにかき鳴らされるエレキギター使いはダサすぎます。エアリエルが「王の船に乗り込み、舳先に行き、ともに行き、甲板に行き、船室に行き、火の玉に変身して連中を仰天させて」やる場面など、視覚的には悪くないのに、ぎょわんぎょわわ~んといういかにも大変なことになってます的なエレキ音のせいで、非常に安っぽいシーンになってしまいました。モッタイナイ。
所々、これは!と思う演出もあったのですよ。プロスペラが描く魔法陣を強風にたなびく炎の輪とその焼け跡で表現したり、プロスペラが岩屋の書斎でフラスコの中に黒い羽根を落とすと同時に、ナポリ公たちのもとには真っ黒な怪鳥ハーピー(に扮したエアリエル)が現れる所なんぞは、これこそ映画ならではの表現よな、とワクワクいたしました。そのセンスが作品全体に行き届いていてくれたらよかったのですが。
本作で最もユニークな、それゆえ最も評価したい点は、言うまでもなく主人公であるミラノ大公プロスペローを女性に置き換えたという点でございます。これによって、プロスペラ(プロスペロー)と他のキャラクターたち、とりわけ娘のミランダ、奴隷キャリバン、そして使い魔エアリエルとの関係に、原作にはないニュアンスが付されておりました。復讐に燃える魔術師であり、娘を思いやる母親でもあるプロスペラを演じるヘレン・ミレン、凛としたたたずまいに格調高い台詞回しで他を圧するかと思えば、一人娘に対する深い情愛をふとした台詞や所作に表すさすがの名演でございます。
ヘレン・ミレンのみならず俳優陣はみな素晴らしく、CGの全く使われていない役者同士のかけあいのシーンはたいへん見ごたえがございました。老臣ゴンザーローが喋るたびに王弟セバスチャンが絶妙のタイミングでへらへらと茶々を入れて来る所なんてまあ、各々の人物の個性がテンポよく表現されていてお見事でございました。
ちなみにいかにも誠実で人の良さそうなゴンザーローを演じるのはトム・コンティ、はい、『戦メリ』のろーれんすさんでございますね。セバスチャン役は当ブログではそこそこおなじみなアラン・カミング。軽薄で辛辣で斜に構えておりながらもどこか間が抜けている感じがたいへんよろしいかと笑。

それからキャリバン役のジャイモン・フンスー、野太い声に堂々とした体躯で、非常に存在感のある「化け物」を造形しておりました。「俺は夢の続きが見たくて泣く」の所や、最後にゆっくり岩屋から出て行くシーンに漂うもの悲しさが印象的なだけに、ドタバタ喜劇の部分でそのまんまドタバタしているだけなのがちと残念な所。いっそ喜劇的要素は呑んだくれ2人につめこんで、徹底的にシリアスなキャリバンにした方がよかったのではないかしらん。
そんなわけで一長一短の感がある本作ではございますが、好き嫌いで言うならば、映像美術的には高い完成度を誇るものの観客置いてけぼり感もたいそうであったピーター・グリーナウェイの『プロスペローの本』よりも、もともとの戯曲の持つ娯楽性に配慮した本作の方がワタクシは好きでございます(デレク・ジャーマン作は未見)。DVDがレンタル屋の棚に並んだらもう一度じっくり鑑賞したいとも思っております。
テイモア監督には本作の不評にめげず、また古典劇を手がけてほしい所です。ただ、本作のCG使いを見ますと、何をやってもいいけど『夏の夜の夢』には手を出さないでいただきたいと願わずにはいられません。
ところで本作の日本版ポスターおよびキャッチコピーは素晴らしい出来映えでございますね。『タイタス』の「復讐は、女のたしなみ」というコピーも秀逸でしたけれども、ひょっとすると同じコピーライターさんが手がけられたのかしらん。重厚かつシンプルなドレスに身を包んだヘレン・ミレンの立ち姿と「私に抱かれて、世界よ眠れ」の一文、一編の詩のような作品でございます。まあ、海外版ポスターの方がこの映画の雰囲気に忠実ではありますけれどもね。
嗚呼、消化不良。
ジュリー・テイモア監督の映画デヴュー作『タイタス』はワタクシの大好きな作品でございます。『タイタス』と同じくシェイクスピア劇を原作とする本作はしかし、所々に光るものをかいま見せつつも、全体としてはちぐはぐな仕上がりになってしまっておりました。
モッタイナイのひと言でございます、衣装、ロケーション、そしてとりわけ俳優陣が素晴らしかっただけに。
The Tempest Movie Trailer Official (HD)
題材からしてCGを盛大に使いたくなるお気持ちはわかります。しかしその使い方がいまいちこなれていないと言いますか、全体的に小うるさく感じられてしまいました。特に妖精エアリエルの動かし方はいただけません。残像を引きながら無駄に画面上を瞬間移動するのなんて、もうCG創成期じゃないんだからこういうのはよそうよ、と思ってしまいました。
ベン・ウィショー演じるエアリエル自身は、まっちろけで、中性的で、ぼさぼさ頭で、それはそれは可愛かったんですけれどね。水の中から現れる演出や半透明の姿もよろしうございましたし。船に火をかけたり蜂の群になってキャリバンたちを追い回す時の悪魔的な笑い顔も、助けてもらった恩をもう忘れたのか、とプロスペラになじられるシーンでの、先生に叱られているいたずら小僧のような表情も、また「ご主人様、私を愛してくださっていますか?」という台詞におけるしんみりした切実なトーンも実によかった。ベン・ウィショーの他の作品はワタクシ未鑑賞でございますが、なかなか芸達者な役者さんのようですね。

だからこそ、最後にプロスペラがエアリエルを解放してやる所を、役者よりもCGがキモと言わんばかりの何の感慨もない描き方にしてしまったことが残念でなりません。ここも絵的にはまあ綺麗だったんでございますけれども、プロスペラとエアリエルの間に主人と下僕という以上の親密な雰囲気があっただけに「かわいいエアリエル、これが最後のつとめだぞ。あとは大気の中に自由に飛び去るがいい。達者でな」(白水社版)、この台詞をつぶやいて、飛び去るエアリエルを見つめるプロスペラという絵がぜひとも見たかったのですよ。
また最後の「これにて私の術は破れ...」の長台詞を、俳優が語るのではなく、エンドロールとともに流れる歌にしたというのも、独創的といえば独創的ではありますけれども、やっぱりヘレン・ミレンが朗々と語るのを聞きたかった。こんな所にも消化不良感が残ります。
それから音楽の唐突な使い方、これだけはどうあっても擁護できません。とりわけ-----これは『タイタス』でもその兆候がありましたが-----所々これみよがしにかき鳴らされるエレキギター使いはダサすぎます。エアリエルが「王の船に乗り込み、舳先に行き、ともに行き、甲板に行き、船室に行き、火の玉に変身して連中を仰天させて」やる場面など、視覚的には悪くないのに、ぎょわんぎょわわ~んといういかにも大変なことになってます的なエレキ音のせいで、非常に安っぽいシーンになってしまいました。モッタイナイ。
所々、これは!と思う演出もあったのですよ。プロスペラが描く魔法陣を強風にたなびく炎の輪とその焼け跡で表現したり、プロスペラが岩屋の書斎でフラスコの中に黒い羽根を落とすと同時に、ナポリ公たちのもとには真っ黒な怪鳥ハーピー(に扮したエアリエル)が現れる所なんぞは、これこそ映画ならではの表現よな、とワクワクいたしました。そのセンスが作品全体に行き届いていてくれたらよかったのですが。
本作で最もユニークな、それゆえ最も評価したい点は、言うまでもなく主人公であるミラノ大公プロスペローを女性に置き換えたという点でございます。これによって、プロスペラ(プロスペロー)と他のキャラクターたち、とりわけ娘のミランダ、奴隷キャリバン、そして使い魔エアリエルとの関係に、原作にはないニュアンスが付されておりました。復讐に燃える魔術師であり、娘を思いやる母親でもあるプロスペラを演じるヘレン・ミレン、凛としたたたずまいに格調高い台詞回しで他を圧するかと思えば、一人娘に対する深い情愛をふとした台詞や所作に表すさすがの名演でございます。
ヘレン・ミレンのみならず俳優陣はみな素晴らしく、CGの全く使われていない役者同士のかけあいのシーンはたいへん見ごたえがございました。老臣ゴンザーローが喋るたびに王弟セバスチャンが絶妙のタイミングでへらへらと茶々を入れて来る所なんてまあ、各々の人物の個性がテンポよく表現されていてお見事でございました。
ちなみにいかにも誠実で人の良さそうなゴンザーローを演じるのはトム・コンティ、はい、『戦メリ』のろーれんすさんでございますね。セバスチャン役は当ブログではそこそこおなじみなアラン・カミング。軽薄で辛辣で斜に構えておりながらもどこか間が抜けている感じがたいへんよろしいかと笑。

それからキャリバン役のジャイモン・フンスー、野太い声に堂々とした体躯で、非常に存在感のある「化け物」を造形しておりました。「俺は夢の続きが見たくて泣く」の所や、最後にゆっくり岩屋から出て行くシーンに漂うもの悲しさが印象的なだけに、ドタバタ喜劇の部分でそのまんまドタバタしているだけなのがちと残念な所。いっそ喜劇的要素は呑んだくれ2人につめこんで、徹底的にシリアスなキャリバンにした方がよかったのではないかしらん。
そんなわけで一長一短の感がある本作ではございますが、好き嫌いで言うならば、映像美術的には高い完成度を誇るものの観客置いてけぼり感もたいそうであったピーター・グリーナウェイの『プロスペローの本』よりも、もともとの戯曲の持つ娯楽性に配慮した本作の方がワタクシは好きでございます(デレク・ジャーマン作は未見)。DVDがレンタル屋の棚に並んだらもう一度じっくり鑑賞したいとも思っております。
テイモア監督には本作の不評にめげず、また古典劇を手がけてほしい所です。ただ、本作のCG使いを見ますと、何をやってもいいけど『夏の夜の夢』には手を出さないでいただきたいと願わずにはいられません。
ところで本作の日本版ポスターおよびキャッチコピーは素晴らしい出来映えでございますね。『タイタス』の「復讐は、女のたしなみ」というコピーも秀逸でしたけれども、ひょっとすると同じコピーライターさんが手がけられたのかしらん。重厚かつシンプルなドレスに身を包んだヘレン・ミレンの立ち姿と「私に抱かれて、世界よ眠れ」の一文、一編の詩のような作品でございます。まあ、海外版ポスターの方がこの映画の雰囲気に忠実ではありますけれどもね。