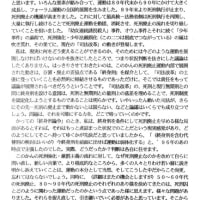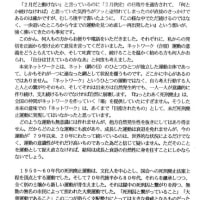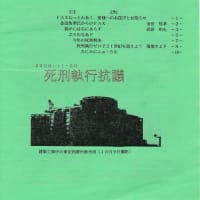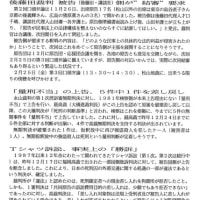(その1)から続く
二、現在の死刑廃止の流れと死刑囚
'79年以降開始された新たな運動において、「死刑囚とのかかわり」ということは、様々な論議を生んだ。
まず、「死刑囚との直接のかかわりは運動を広げるのにマイナス。制度の廃止を主体としていく。」「まず無実の死刑囚にかかわっていく。そのほうが運動が広がりやすい。」という主張があった。これらはその後の運動が実際にその正反対の方向にすすんで現在に至っているので、今あらためて議論する必要はないだろう。しかし何か問題なのかはおさえておく必要がある。単に「死刑囚にかかわればよい」というものではなく、「無実か有実か」という問題でもないからだ。
「死刑囚にかかわる」ということは、死刑囚のおかれた、裁判をはじめとする状況をともに引き受けるということであり、つまり死刑廃止運動が、「死刑」の具体的な運用局面(制度一般だけでなく)にたえず向き合っているということである。
つまりそれだけ「足腰の強い」運動をやるということなのだ。
また、「まず無実」ということの誤りは、「有実のほうが重要」ということではなく、死刑攻撃においては、有実、無実をとわず、すべての場合において権力は、「死刑」にすることの正当性を確保するためにあらゆる形でのデッチ上げ、事実歪曲を行なうからであり、 「事実を争う」ことは、死刑裁判全般に妥当することだからだ。「無実は事実を争い、有実は情状に訴える」というような考え方は、死刑攻撃の本質を理解しないものといえるだろう。
これらの議論を克服することが、運動の前進につながったのは、ある意味で当然のことであった。これらの議論は世間一般の、死刑囚への偏見を前提にしており、死刑廃止運動とは、その偏見とのたたかいでもあるからだ。
「死刑囚とともに、死刑攻撃とたたかう」ことがはっきりと運動の中心に据えられたのは'86年末の最高裁をめぐる死刑確定阻止の大衆的なとりくみからだった。それに至'83年からの最高裁での死刑事件審理をめぐる攻防については、第30号('88年8月)までの『沈黙の声』にくわしい。(合冊版第1、2集あります。第1集は残部僅少!)
'86年、戦後 (おそらく戦前も)初の「年間死刑確定ゼロ」をもたらした、最高裁死刑弁論阻止のたたかいは、全国に様々なかたちで死刑廃止運動が広がっていくステップにもなった。それは留年神戸での第二回死刑廃止運動全国合宿の成功、死刑廃止全国ネットワークの結成に結実する。(神奈川での第一回全国合宿は、それへの「布石」。)
死刑確定の権力側のスケジュールをも左右する('86年の「東アジア反日武装戦線」への死刑重刑確定攻撃は、「天皇在位60年」のこの年に彼らへの弾圧を完成させるという政治目的があった)、死刑廃止運動の前進にたいする権力側の対応は、やはり死刑囚の圧殺と隔離分断―『死刑確定ラッシュ』であった。これに運動側は、死刑廃止の会、日本死刑囚会議=麦の会を中心とする最高裁の死刑事件裁判への結集と抗議、そして死刑執行、確定者処遇をめぐる法務省交渉によって、対応してきた。
「死刑囚とともに、死刑とたたかう」運動は、制度のみの廃止ではなく、〈人を殺さず、共に生きる〉社会をめざした死刑廃止運動を、裁判あるいは確定後の獄中で、あくまで死刑」を拒否して生き続ける死刑囚の仲間達とともに、展開してきたのである。
'86年から'90年にかけての時期に、こうした死刑とのたたかいを背景に、死刑囚とのつながりを媒介として、運動の輪が徐々に全国各地へと広がっていったのである。それは、ネットワークに結実するとともに、のちのフォーラム全国化にもつながるものだった。
(その3)に続く