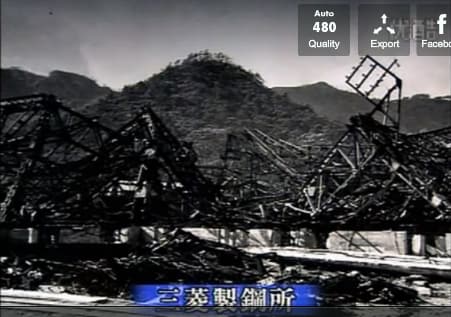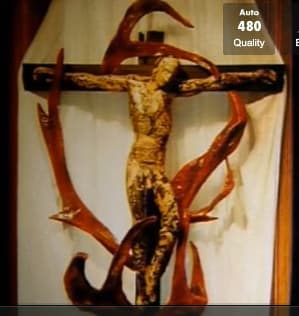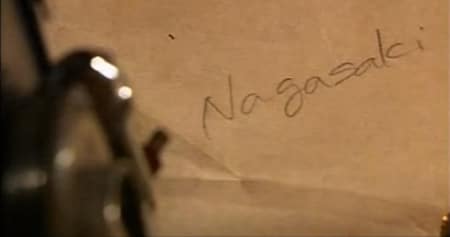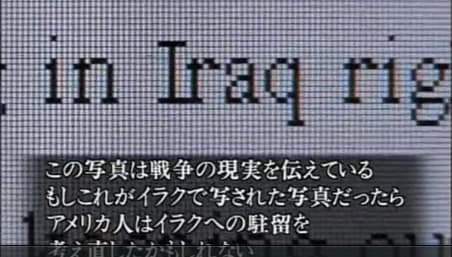今日の主人公さん。

後ろから見たら、

さらに真後ろから見たら、

あなたはいったい…、

このモヤモヤを、蜘蛛の巣かなにかの埃だと勘違いして、お箸で取ろうとしたら…毛の一部だった…。

いい加減にせんかっ!とばかりに、頭を上げて、フリフリしながら怒ってた。

今日もたいへんに良いお天気で、乾いた風が心地良い、なんとも過ごしやすい一日だった。
これがもし今年の夏の特徴ならば、これはもう、冬の超~厳しく、超~長かった寒さに耐えたご褒美か?などと、都合よく考えてしまう。
日中は25℃ぐらい、朝晩は17℃ぐらい。
エアコンはもちろんのこと、扇風機すら要らない。
トマトは今日も順調に育ち、

ちょっとこのトマトは順調過ぎていて、わたしのコブシの二つ分ぐらいある。

そろそろブラックベリーは終焉を迎え、

そのすぐ横では、オクラの花がボチボチ咲き始めた。

リスたちが、両手で抱えて食い荒らす松ぼっくり。この季節、ドライブウェイに食べカスが一面に散らばる。

ショーティの墓守りをしてくれてるカエルの夫婦も、炎天下ではなく心地良さげ。

前庭トマトと裏庭アルゴラのサラダ、そして裏庭コマツナのニンニクショウガさっと炒め。

ごちそうさま。

後ろから見たら、

さらに真後ろから見たら、

あなたはいったい…、

このモヤモヤを、蜘蛛の巣かなにかの埃だと勘違いして、お箸で取ろうとしたら…毛の一部だった…。

いい加減にせんかっ!とばかりに、頭を上げて、フリフリしながら怒ってた。

今日もたいへんに良いお天気で、乾いた風が心地良い、なんとも過ごしやすい一日だった。
これがもし今年の夏の特徴ならば、これはもう、冬の超~厳しく、超~長かった寒さに耐えたご褒美か?などと、都合よく考えてしまう。
日中は25℃ぐらい、朝晩は17℃ぐらい。
エアコンはもちろんのこと、扇風機すら要らない。
トマトは今日も順調に育ち、

ちょっとこのトマトは順調過ぎていて、わたしのコブシの二つ分ぐらいある。

そろそろブラックベリーは終焉を迎え、

そのすぐ横では、オクラの花がボチボチ咲き始めた。

リスたちが、両手で抱えて食い荒らす松ぼっくり。この季節、ドライブウェイに食べカスが一面に散らばる。

ショーティの墓守りをしてくれてるカエルの夫婦も、炎天下ではなく心地良さげ。

前庭トマトと裏庭アルゴラのサラダ、そして裏庭コマツナのニンニクショウガさっと炒め。

ごちそうさま。