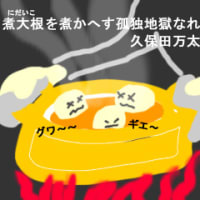昨日のきつね君の記事とは大違いです。
うっかり宣伝するのを忘れていたおすすめリサイタルのお知らせです♪
あさって、1月30日(金)、内藤明美さんがシューベルトの「冬の旅」を歌います。
山崎裕視氏が書かれた文章を、許可を得て引用させていただきます。
Einen Weiser seh’ ich stehen
眼の前に道しるべが立っている
女性歌手の“冬の旅”
山崎 裕視
三十数年前、柳兼子先生のもとに稽古に通っていた時期があった。先生は既に八十歳を越えておられたが、その歌に対する姿勢は言葉のわずかな陰翳や間合いを聊かもゆるがせにせぬ厳しいもので、若い私は一瞬も気が抜けなかった。しかし、稽古の合間に先生から伺う昔語りの実に楽しかったことを覚えている。今となって思えば、豊富な歴史の証言に触れるきわめて貴重な時間であった。先生が傾倒したシューマン・ハインクやスレザークのこと、ペッツォールドやサルコリー、三浦環や山田耕筰、信時潔といった日本洋楽界の黎明期を拓いた多くの先達のことを、まるで昨日のことのように語ってくださったものだ。
ある時、ふとこう仰言った。
「日本人で最初に“冬の旅”を歌ったのは矢田部(勁吉)さんですよ。」
なるほどと心に刻みはしたが、その時の私はうかつにも、柳先生御自身が“冬の旅”を演奏されたかどうかについてはまるで思いが至らなかった。1970年代のリート演奏の常識にとらわれていた私には、女性が“冬の旅”を歌うことは想像の外であったからかも知れない。ずっと後年(先生の長逝後)、山根銀二の評論集の中に柳兼子独唱会“冬の旅”に関する批評を見つけた時は驚いた。そして、先生の“冬の旅”観を尋ねる機会を逸していたことをとても悔やんだ。
シューベルトは“冬の旅”を本来高声の為に作曲した。しかし、初演したミヒャエル・フォーグル以降この歌曲集は男性の低声歌手が歌うべきものという印象が世に広まってしまった。確かに、ジングシュピール的な明るさと快活さを背景にした“美しい水車小屋の娘”に較べると、“冬の旅”は作曲者自身が「ぞっとする歌の連作(ein Zyklus schauerlicher Lieder)」と呼んだように、陰鬱で暗い色調が全曲を貫いている。厳しい冬のさなかの旅立ちからして、遍歴職人の常識を逸脱した異常な設定であり、死と対峙しながら歩み続けねばならぬ極限の精神状態が語られていく。フォーグルの系譜につながるバリトン歌手こそがこの歌曲集にふさわしいと、多くの人々が思い込んだのも無理はない。また典型的な男性社会であったツンフト制度の中の遍歴(Wanderschaft)に対してドイツ人が抱き続けた郷愁と思い入れが、この歌曲集を「男歌」の象徴的な存在と看做すまでになった要因ではなかろうか。
リート演奏におけるジェンダーの壁は、長く女性歌手たちの前に堅固に立ちはだかっていた。不世出のリート歌手 エレナ・ゲルハルト(メゾ・ソプラノ)がシューベルト没後百年(1928)に因んで取り組んだ“冬の旅”全曲演奏は、女性歌手にもこの作品が見事に表現し得ることを示した嚆矢であった。ゲルハルトの“冬の旅”の録音は残念ながら断片的にしか遺されていないが、この歌手の実に知的で鋭利な表現が聴ける。ゲルハルトより五歳若いロッテ・レーマン(ソプラノ)もまたこの歌曲集をしばしば演奏して高い評価を得た。レーマンが吹き込んだ全曲録音を聴く時、現代の耳は、最初の数分間は彼女の発音やリズム、フレージングの大まかさに当惑する。だが、やがて次第にそれらを忘れて引き込まれていき、気がつくと終曲まで導かれる。これもまた至芸である。
わが国の“冬の旅”演奏史上、前後三回の柳兼子独唱会と並んで異彩を放つのが、終戦直後に日比谷公会堂で行われた三浦環による全曲演奏(邦訳による)である。戦争中、山中湖畔に疎開しながら三浦環自身が日本語訳をつけたという。翌年(1946)、死の直前に彼女は“美しき水車小屋の娘”全曲(これも自らの邦訳詩)を演奏している。偉大な「お蝶夫人」がその最晩年に、シューベルトに何を求め、表現したかったのかと思いを馳せる。
第二次世界大戦後のリート演奏は著しく変化する。戦前の歌手たちに見られた恣意的なルバートやポルタメント、テンポの変化などは旧風として廃れていき、かわって詩人や作曲家の意図を研究し、そこから演奏家の解釈を導き出そうとする傾向が強まってくる。リーダーアーベント(歌曲リサイタル)の曲目構成にもまた大きな変化が現れた。様式的、内容的な統一感が尊重され、曲目配置にも演奏家は一定の主張を込めるようになる。選曲の動機付けや学究的姿勢が問われる時代が訪れたのである。このような潮流の変化は、“冬の旅”を再び女性歌手の手の届かぬところへ運び去っていく。かつては女声によってもしばしば歌われていた三大歌曲集中の有名ナンバーでさえ、彼女たちは近づくことを止めてしまった。エリーザベト・シューマンのような可憐なソプラノが「春の夢」や「何処へ」を歌うことに人々は違和感を覚えはじめたのだ。フィッシャー・ディースカウの、「幸いなことに今日の我々は、演奏会におけるこのようなズボン役流儀に対してアレルギー反応を示す(シューベルト歌曲の軌跡/1971)」と言うような考えがリート演奏における時代精神として浸透していった。
だが、一つの思潮がある時代を席巻はしても、永久に続くことはない。視点を変えた芸術表現への模索は常に行われていく。
1980年代初頭、ウィーンの楽友協会から“冬の旅”を歌うことを依頼されたクリスタ・ルートヴィヒ(メゾ・ゾプラノ)は大いに戸惑った。だが、ハンス・ホッターの励ましを受けて彼女はこの歌曲集に取り組んでいく。ルートヴィヒの回想録につづられた“冬の旅”観を引用してみよう。
大きな一身上の痛手を耐え忍んでいるひとりの人間の物語は本来、その心が己が内なる冬の凍てつく荒野に旅立とうとするきっかけにしか過ぎない。男性だけがそれを経験するわけではない。重要なことは、聴衆と共にさすらいの旅に出て、シューベルトの音楽の根底にある雰囲気へと精神的に導くことにある。 (中略)
これらの歌曲を体験する上で最も大切なことは、私たちすべてが行かねばならない救済(道程)の探求である。ゲーテがミニョンに語らせた、「…男や女を問わず」という言葉を引用したいと思う。“冬の旅”の歌い手は男性であろうと女性であろうと、音楽や詩を、さらには人間的な情動をはるかに超えた状態にまで自己と聴衆を置かねばならない。それは私たちを、意識するかしないかに関わらず、もはや戻ることのできぬ目標に向かって一歩ずつ近づける連れ立ちの旅なのである。
1982年11月、ルートヴィヒは彼女の初めての“冬の旅”全曲演奏をウィーンで行った。彼女の成功は他の女性歌手達に大きな刺激を与えた。ブリギッテ・ファスベンダーなどのメゾ・ソプラノ歌手がまずこれに続き、やがて軽目のソプラノ歌手の中にも“冬の旅”を歌う人々が現れてくる。さらに彼女らは、従来男声によって独占されていた他の作品にも意欲的に進出していく。男女の差異を超えた人間的なものへの共感が、この新しい流れの「道しるべ」となっていることは疑いもない。
初めて知ることばかりです。なるほど、そういう歴史があったのかと思いました。
私には「深く理解する」ことはできそうもありませんけど、とにかく楽しみです。
 ( 背景の絵、ちょっと雪が深すぎて、ドイツというより新潟・・・・・?)
( 背景の絵、ちょっと雪が深すぎて、ドイツというより新潟・・・・・?)