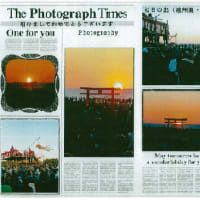東北にも桜が咲いたそう。多くの方へ、桜のエネルギーが届きますように。
先日の日曜日、仕事を済ませて「細江神社」というところへ行ってきました。

ここは、浜名湖の奥、気賀という場所にある“地震厄除け”神社。
めずらしですよね、“地震厄除け”とは。
これにはちゃんと歴史の裏付けがあるんですよ。

境内にあった絵。浜名湖が描かれており、下の方で指差している所が、
浜名湖の入り口で、「角避比古(つのさくひこ)神社」。
このご神体が、前回お話した“明応地震(1498年)”の時に発生した津波により
浜名湖の奥の方へ流されてしまい(絵で言うと上の方)、最終的にこの地域に漂着
しました。「角避比古神社」も流されてしまったため、ご神体を
この「細江神社」に祭るようになったといういわれがあります。
そして、右手奥のお社は「藺草(いぐさ)神社」。こちらにも興味深い話があるんです。
明応地震から209年後の1707年、「宝永地震」というこれまた大きな地震
(M8.4~8.7)があったとき、高潮(津波かどうかは不明)が浜名湖周辺に押し寄せ
たため、田んぼに塩が入ってしまい、稲が作れなくなってしまいました。
その時の領主が、大分の領主へ相談したところ、琉球藺(りゅうきゅうい)という
のが塩に強くていいと教えられ、それから浜名湖周辺では琉球藺が盛んに栽培
されるようになったそうです。藺草(いぐさ)とは、畳表の材料のこと。
「藺草神社」は、その時の領主の功績を称えて建立されたのだそうです。
過去の地震の痕跡は、意外と身近なところにあったりして。
つづく