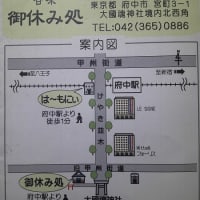平成2年に鷹へ入ったぼくが憧れた企画が鷹12月号の「同人自選一句」である。鷹にはいろいろ優れた企画があるのだが、ここにはやく一句を載せたいと思ったものである。
今年の鷹12月号のこの欄には514名が一句ずつ載せている。
その中から書いてみたい句をいくつか取り上げる。
凡人に凡の日数や貝風鈴 明石令子
「凡人に凡の日数」、だいたいの人がこういう日々を過ごしているだろう。ほとんど変化のない生活ゆえそれを凡と敢えていうことで際立たせようとする。俳句は凡の日々に楔を打つようなささやか営為。貝風鈴は重たくいやいや鳴るようなところがありこの句の雰囲気を盛り立てる。
東京も暑からむ二円貼り足す 安食亨子
ここへ出す一句を多くの同人は主宰から褒められたものを使うことが多い。この句も主宰が激賞したことが記憶に新しい。切手という言葉を使わず切手を述べたこと、二円という現代性、「東京も暑からむ」という展開の巧妙さなど力を抜いた表現はあっぱれ。
常磐木の落葉や生家絵に残す 阿部逑美
老朽化したため家を壊すのか作者が家を離れる事情があるのか。「絵に残す」が新鮮。
折れさうな半玉の首花氷 荒木かず枝
女が自分より若いきれいな女を見ての感慨。作者は女衒ではなさそうだがそういう視点で値踏みしているようなところがおもしろい。よもや恋愛感情(同性愛)ではないとみるがそう詠んでもいい。
はづかしく死にたる津島修治の忌 有澤榠樝
読んだ瞬間はっとした。太宰治の本名を出して青森の津島家の世間に対しての顔向けできない心理を描いたところが秀逸。津島家にとってかくも世間体の悪い事件はなかったはずである。
貝塚の如し晩夏のわが書斎 安藤辰彦
貝塚を見たことがないのだが想像してその雑駁さがわかる。食べたあとの残骸である。書斎の雑然としたさまも思いがけない比喩を得てよく見える。
歩きつつ上着脱ぎけり春の鳶 飯島美智子
「歩きつつ上着脱ぎけり」、暑いのである。手際よくあっさり述べて自分と周囲の空気を端的に出している。季語を空に求めたのも春を感じさせ絶妙。
牛頭馬頭の娑婆に蠢く朧かな 砂金祐年
「牛頭馬頭」とはよく言ったものである。この言葉は当然、「牛飲馬食」を感じさせる。必要以上飲み食いする欲望の虜の人間どもを戯画化している。仏教的倫理観に反する人間どもの中に自分も入れている作者は痛快な奴だろう。春になったら一度飲みたい、牛頭馬頭になって。
通し土間ぬけて二の蔵雀の子 石原由貴子
宮尾登美子の書くような古風な旧家のたたずまいがいい。一歩一歩緊張しながら奥へ歩いてゆく気分にさせてくれる。
髭を剃りやれば寝息や冬ぬくし 井原仁子
定年してから1000円床屋ばかり使っているので髭を剃ってもらったことがない。時間はたくさんあるのでお金を貯めて髭を剃ってもらいたくなった。仕事に倫理観のある人の句はあたたかい。
陶枕に覚めてアジアの端の端 岩永佐保
陶枕というと中国を感じる。その文化が海を渡って伝わってきた歴史と極東の島国という立地とを網羅した内容。冷めたユーモアが光る。
いとほしむごとく蟷螂夫を食む 植苗子葉
俗に「食べたいほど可愛い」というが蟷螂はほんとうに食うという。作者がほんとうにこの光景を見たのか知らぬが見て来たように書けている。「夫を食む」がいい。
癌告知毎度簡潔百日紅 上村慶次
「毎度簡潔」ということで医者も患者もかなり達観して事に当たっているのがわかる。作者は癌を手懐けて生きている。百日紅は癌の猛威とも作者の闘争心の象徴とも取れる深みのある季語。
主婦たのし家に薫風招き入れ 内田遊木
風だけでなく近所の主婦も招き入れたのだろう。たぶん夫の留守のできごと。そんな気分もあって読むほうも楽しい。
千年の楠のふところ風薫る うちの純
付き過ぎといえば付き過ぎの季語なのだが「千年の楠のふところ」までいうともう「風薫る」しかないじゃないか、と思わせる。どっぷりと木の匂いが感じられる至福のとき。
蛍見の妻送り出し先に寝る 遠藤蕉魚
新婚ではないのである。生きていてくれればお互い何をしてもいいという長い年月を経た夫婦である。この夫はたぶんぼくと一緒で8時には床に就く。
凍星やコンビニに足る街あかり 大石香代子
コンビニが一番明るい街。街の小ささがよくわかる。灯りのないところは闇、闇は空とすぐつながる。さみしいけれど空気の冴えた街。
春風や研屋のほかす濁り水 大久保朱鷺
研屋は流したりしない、ほかすのである。俳句は一語の選択で極上になるということを示したモデルのような句。
父の寡黙母の沈黙軒風鈴 尾形忍
喧嘩ではなかろう。年を取ってそう口を開かない夫婦なのだろう。家の中で相手の気配を感じていればいいという関係。風鈴がときどき鳴ればいいのである。
短日の棚田一枚ずつ翳る 小川和惠
生れが伊那の百姓、それも水田中心だったのでこういう句は郷愁を感じてならない。
体内を燃やす呼吸や夏来たる 小川軽舟
夏になると確かに人間も内燃機関と感じる。空気を取り込んで肺で燃やす。燃やすので食欲が増す。主宰は食欲を謳歌したのだと思う。門弟たちを元気にしようという配慮も少しはあったか。
本閉ぢて西日に机明け渡す 小竹万理子
最初からそう勉強したくないのではないか。西日のせいにした気取った言い方がおかしい。
青葉木莵父なら何と答へるか 加儀真理子
青葉木莵は夜行性の鳥でありそう元気な声を出さない。そんなところから作者が置かれている局面がやるせなくむつかしいことが想像される。その内容はわからないが困難が象徴化されていて手応えがある一句である。
罵つて泣いてマフラーして帰る 柏倉健介
作者ではなく付き合っている女性のことか。作者が罵られ、ついでに泣かれ「嫌い」などと言われて見送っている場面。この言葉のテンポのよさだと笑って機嫌を直すのもはやく、またすぐやって来そう。あるいは作者のほうから詫びを入れつつ会いに行くか。どっちにしても若いっていいなあ。