ようこそRAIN PEOPLES!超バラバラ妄想小説『雨族』の世界へ! since1970年代
「雨族」
断片28-風のなかで眠る女
「2章・パリのまねき猫」~2.二十歳までの僕の二つの恋への関わり方
大学に入ってすぐ、僕がまだ十八才だった頃、コンビニエンス・ストアのアルバイトで知り合った女の子と蓼科の伯父の別荘に二人だけで旅行した事があった。
その頃、僕は凄く退屈していた。おそらく今までの人生で一番、退屈を感じたのは大学時代の四年間だったと思う。退屈であるというのは、元気と体力に、とても重要な要素を置いている。
精神的にも肉体的にもタフではないと退屈である事を余り気にしないのだ。
今の僕は十八歳の頃の僕に比べて状況的には一万倍位退屈だと思う。ところが僕は退屈さを感じていない。何故だ?ただ生きていること自体が、もう充分苦しい事に気づいているからだ。
今の僕は雨上がりの道路に吹き出す下水のようなもんだ。何の価値も無く、苦しんで苦しんで生きて行く、ドブ水。退屈なんて発想さえ消え失せた。
ところが大学時代の四年間は退屈という幻想に目一杯、覆い尽くされていた。まるで途方もなく広く深く真っ白い空間に、たった一人で今にもパチンと弾けそうなくらいの元気とともに置き去りにされたスーパーマンのような気分だった。
何でもしたいが何も起こらないのだ。何でも出来るんだが何もしたくないのだ。起こってくれるのを、ひたすら待つ。その根性が巨大な退屈を招いた。
世の中、何もしないで、そうそう刺激的な出来事が起る訳がない。得てして待ってる時には何も起らず、待つのをあきらめて身体中に虚無がはびこった時に何かが起る。その時は、起きた出来事に対処する元気が消え失せているのだ。
まあ、話をもとにもどさなきゃ。とにかく僕は十八才の夏休みに蓼科の緑山ロッジというところにある親戚の別荘を借りて女の子と泊まり込んだ。
その女の子の顔は凄くよく憶えている。
目と唇がとても大きくてスキッ歯をしていた。色が白く顎がきゅっと細かった。全体的に卵形の顔で直線的な短い髪の毛が、彼女の透明感があり、かつ野性的でアンバランスな雰囲気を際立たせていた。そしてスリムでとてもスタイルのいい女の子だった。
僕は、その女の子の事が少し好きだったけど、何だか面倒くさかった。僕を強烈に求めてくるようなので、とても疲れたし、だから、とても面倒くさかった。その女の子が僕の事をどんな風に考えていたのか、想像もつかなかった。
実を言うと面倒くさいので想像さえもしたくなかったのだ。しかし外面的には僕たちは、人の羨むような輝く恋愛のただ中にあるように見えたと思う。友人たちに僕はいつも羨ましがられていた。
「お前は、いいな、やりたい時にすぐできる穴があってよぅ。それもあんなに上玉の女だろぅ」とか言われてね。
たいていの恋人のいない若い男は、そういう考え方をする。そういう奴らの中で「ちょっとお前の女を貸せよ」と言う奴がいる。「俺にもやらせろよ」と言う意味だ。
僕は、そういう言い方は、女の子をとても侮辱していると思う。女の子は僕のものじゃないし、僕にやらせろと言うのは筋違いで彼女に自分で言うべきなのだ。
でも僕に頼むという彼らの気持ちもよくわかった。奴らはシャイなのだ。そして、まさか僕が本当に彼女を与えるとは思っていないのだ。
空想と刺激的な言葉で彼らはかなわぬ望みの一部分を吐き出しているだけの事だ。そして、そんな時期もすぐに消え去る。たいていの者はどこかにきちんと納まって行く。
若き日の自然な空想と刺激的な汚い言葉は現実的なローンの返済や子供の養育なんかに押し潰され、狭苦しい家族世界の中で収縮していく。粉微塵になる。
とにかく僕は、その上玉の女の子と三ヶ月間、仲むつまじくキャンパスのあちらこちらに出没したり、山手線の気の向いた駅で適当に降りて、あても無く歩いたり、自主上映の映画を巡ったりしながら交際し、とうとう二人きりで親戚の別荘に泊まり込んでしまったのだ。
と、外面的にはとても順調で相思相愛のありふれた恋愛に見える。しかし違った。彼女は魔女だったのです。とは言わないが、それに近い。僕は三十三才になった今でも彼女の存在を疑っている。
その夜、・・・つまり別荘に泊まった最初で最後の夜・・・我々は限りなく二人きりで、電気を消して、テーブルの中央に蝋燭を立てて、その光にお互いの顔を寄せ合いながら、いろいろな話をした。その殆んどが、今の我々の恋についてだった。
彼女は、こう言った。
「私たちは神聖な輝くような恋に、じっと息を潜めて向かい合っているのよ。大きな金色の火の渦の真ん中にいるの。誰か、他の人が近付いてくればメリメリと私たちの秘めた若き恋の青い炎に身を焦がされ燃えちゃうのよ」
僕は、とても馬鹿馬鹿しくなって目をきょろきょろさせながら、あくびのような微笑みを浮かべて女の子を観察していた。「僕は何をしているんだ」という気持ちが粘着質の黒い大気みたいに僕をギュウギュウと包み込んでいた。
彼女は何を思っているのか?想像もつかない薄気味悪さがあった。こうして交際する事が異性観察という目的だけではない。何か論理的でない強烈な感情のうねりを、僕は彼女の中に感じて身震いした。この女は狂っているのじゃないか、とまで思った。
それが恋という感情なのだとは、その時の僕の理解の許容度を越えていたのだ。僕は全く毛穴一つ程も彼女のことを愛しては、いなかった。なぜ、僕が彼女と交際していたのか?答えは簡単だ。退屈と好奇心。それだけだった。SEXの事も殆んど考えなかった。SEXと性欲については、のちのちを考えると、凄く面倒くさかった。
それでも、やはり僕は彼女の身体を蝋燭の灯かりの下で調べた。彼女は完全に処女だった。僕が無理矢理、指を突っ込むと、べとつく血を流した。彼女は、そうされながら僕に言った。
「あなたは特別な人よ。本当に特別な人よ」
「どういう意味なの?」
と、血を拭きながら僕が聞くと、
「そういう意味よ。特別な人だってこと。あなたは、それをうまく摑んで使うのよ。どこが特別かをね。しくじると、ひどい事になるわよ」
僕は彼女が何について何を言いたいのか、まるで分からなかった。僕は彼女の身体から手を放し、彼女に衣服を着せて再びテーブルの蝋燭越しに向かい合ってから尋ねた。
「どうなるの?」
彼女は高貴に、すんっと鼻を斜め上に向けて表情にシャープな影を作って言った。
「雨族」
僕のからだから、あらゆるパワーが抜け落ちていった。何だか、ぞっとした。
夜明けまで僕と彼女はテーブル越しに向かい合い、それぞれ自分の腕の中に顔を埋めてうとうとと過した。
彼女は、次の日、僕と一緒に諏訪湖でボートに乗り、転覆して死んでしまった。僕は泳いで泳いで泳ぎまくって助かった。彼女は泳ぐ間もなく心臓マヒで、ほぼ一瞬にしてこの世から去ってしまった。後処理が、とても面倒くさかった。
僕は警察で事情聴取を受け、彼女の両親に会い、葬式も最後の焼却まで付き合った。しかし、今だに彼女という実体が、この世に存在していたという確信が持てない。
彼女が死んでから一年後にやはり、そういう思いにかられて彼女の住んでいた家を訪れた事がある。しかし、そこには何もなかった。いや、何もない訳じゃなかった。あってはいけないものが、あったのだ。
雑木林である。一年前には確かに僕は、そこで葬式に立ち合ったのだ。しかし、そこには何十年もの風雨にさらされた朽ちかけた雑木林が否応なく実在していた。戦慄の雑木林である。
そういえば彼女が僕にくれた何通かの手紙もどこかに消えていた。彼女は何か違う世界の幻影だったのじゃないのか、そんな気がする。でも、彼女は十七才で処女のままだったのだ。
断片28 終
This novel was written by kipple
(これは小説なり。フィクションなり。妄想なり。)










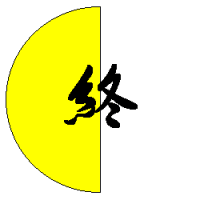
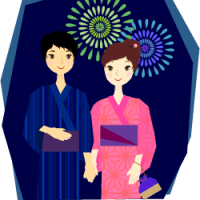
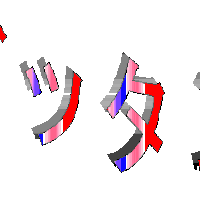


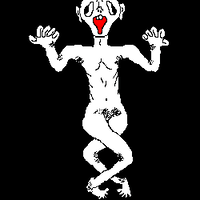
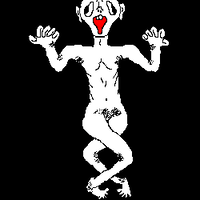
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます