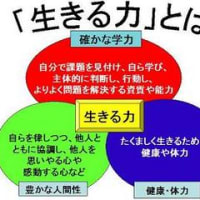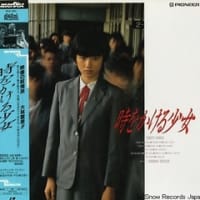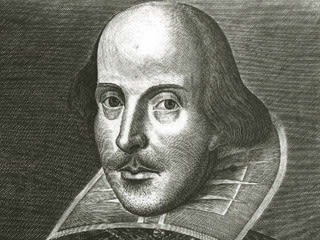
クレタ人がクレタ人はうそつきだと言った。
古代ギリシャのクレタ島出身の哲学者の言葉です。
この言葉を文字通りに読めば混乱してしまいますね。
クレタ人がうそつきであるならば、クレタ人はうそつきだと言ったクレタ人の言葉はうそとなり、クレタ人は正直だとなるはず。
だけど、そうすると、そう言ったクレタ人の発言は本当だとしなければならず、だとすると、クレタ人はうそつきになってしまう・・・ん!?頭がこんがらがってしまうな。
古代ギリシャ人はこのような理屈を好みました。弁論術とレトリックが古代ギリシャに発展したのです。
レトリックは修辞学と言われ、言葉を飾り、他者に言葉の説得力をもたせたり、心理的な効果を生む機能を有しています。
世界史で習っただろうけど、古代ギリシャ、特にアテネを中心に都市国家(ポリス)が形成されます。
つまり、一都市が一国家を構成するわけで、都市の市民は同時に政治家として、ポリスの政治に参加する直接民主政であったわけですね。
そうすると、市民は政治のためにアゴラ(広場)に集まり、各々の論を展開する必要がありました。当然、雄弁な人間が議論を征し、多数の賛同を得て、政治が動かされていくことになりますね。
従って、政治家には弁論術とレトリックが必須とされ、市民の子どもたちには、そういう技術を教える家庭教師をつけることになります。
そういう家庭教師たちはソフィストと呼ばれます。家庭教師たちは子どもたちに弁論術やレトリックを教え、生計をたてるわけです。
教育を意味する英語pedagogyはギリシャ語でpaidagogosと言いますが、paid(こども)-agogos(導く)の合成語で、こどもを導く術だったわけですね。
こうして古代ギリシャでは理屈が隆盛をみるわけです。
ゼノンの逆説というのも有名で、アキレウスという人間と亀が競争しても、亀が先にスタートを切れば、「アキレウスは亀に追いつけない」という理屈(なぜか分かるかな?少し自分で考えてみてね)
ある裁判の記録が残っていて、弁論術を習っていた先生に授業料を払わなかったために裁判となった際のもの。
「先生は私に誰をも説得できる術を教えてくれたのだから、私は先生に対して自分が払わなくてもすむように説得できるはずだから、払わなくて済むし、仮に説得できなければ、わたしは先生から誰をも説得できる術を学んでいないのだから、払う必要もなくなりますね」
これに対して先生は「もしお前が私を説得できたのなら、わたしは約束を履行したのだから、授業料を払わなくてはならないだろうな。逆にお前が説得できないときには、払うことになるということだ」と反論。
こういう理屈は詭弁となりえますね。そういえば、こんな詭弁がありました。黒人は白い歯をもつのだから、黒は白でありうるという主張のようなもの。
こういう弁論術とレトリックの文化は中世に入り、キリスト教に吸収され、神学となっていきます。中世の神学はスコラ学(スコラは学校の語源になります)と呼ばれますが、そこでは、「待ち針の先に天使は何人とまれるのか」とか、「しびんは臭い」と「しびんよ、お前はくさい」は同じことを意味するかといったことが真面目に議論されたわけです。
こういう詭弁に向う危険もありながら、ヨーロッパで言葉と論理が重視される伝統を生むのです。
フランスでは高校3年段階で国語教育の集大成として哲学を学び、試験では哲学が課されます。たとえば、「経済的価値と人間的価値は両立するか」ということに哲学者の言葉を活用しながら論じなければなりません。
そういえば、シェイクスピアの『ハムレット』の一節に、ボローニアスがハムレットのもつ本に関心をもち、何を読んでいるのかを尋ねて、ハムレットは「言葉、言葉、言葉」と言ったということが書かれていますが、ヨーロッパは言葉に強いこだわりのある文化をもっていることは言うまでもありません。
わが国の政治家や官僚が「詭弁」に近い発言をするのに接する時、そういう詭弁を見抜き反論しうる弁論術を私達ももっておきたいね。
古代ギリシャのクレタ島出身の哲学者の言葉です。
この言葉を文字通りに読めば混乱してしまいますね。
クレタ人がうそつきであるならば、クレタ人はうそつきだと言ったクレタ人の言葉はうそとなり、クレタ人は正直だとなるはず。
だけど、そうすると、そう言ったクレタ人の発言は本当だとしなければならず、だとすると、クレタ人はうそつきになってしまう・・・ん!?頭がこんがらがってしまうな。
古代ギリシャ人はこのような理屈を好みました。弁論術とレトリックが古代ギリシャに発展したのです。
レトリックは修辞学と言われ、言葉を飾り、他者に言葉の説得力をもたせたり、心理的な効果を生む機能を有しています。
世界史で習っただろうけど、古代ギリシャ、特にアテネを中心に都市国家(ポリス)が形成されます。
つまり、一都市が一国家を構成するわけで、都市の市民は同時に政治家として、ポリスの政治に参加する直接民主政であったわけですね。
そうすると、市民は政治のためにアゴラ(広場)に集まり、各々の論を展開する必要がありました。当然、雄弁な人間が議論を征し、多数の賛同を得て、政治が動かされていくことになりますね。
従って、政治家には弁論術とレトリックが必須とされ、市民の子どもたちには、そういう技術を教える家庭教師をつけることになります。
そういう家庭教師たちはソフィストと呼ばれます。家庭教師たちは子どもたちに弁論術やレトリックを教え、生計をたてるわけです。
教育を意味する英語pedagogyはギリシャ語でpaidagogosと言いますが、paid(こども)-agogos(導く)の合成語で、こどもを導く術だったわけですね。
こうして古代ギリシャでは理屈が隆盛をみるわけです。
ゼノンの逆説というのも有名で、アキレウスという人間と亀が競争しても、亀が先にスタートを切れば、「アキレウスは亀に追いつけない」という理屈(なぜか分かるかな?少し自分で考えてみてね)
ある裁判の記録が残っていて、弁論術を習っていた先生に授業料を払わなかったために裁判となった際のもの。
「先生は私に誰をも説得できる術を教えてくれたのだから、私は先生に対して自分が払わなくてもすむように説得できるはずだから、払わなくて済むし、仮に説得できなければ、わたしは先生から誰をも説得できる術を学んでいないのだから、払う必要もなくなりますね」
これに対して先生は「もしお前が私を説得できたのなら、わたしは約束を履行したのだから、授業料を払わなくてはならないだろうな。逆にお前が説得できないときには、払うことになるということだ」と反論。
こういう理屈は詭弁となりえますね。そういえば、こんな詭弁がありました。黒人は白い歯をもつのだから、黒は白でありうるという主張のようなもの。
こういう弁論術とレトリックの文化は中世に入り、キリスト教に吸収され、神学となっていきます。中世の神学はスコラ学(スコラは学校の語源になります)と呼ばれますが、そこでは、「待ち針の先に天使は何人とまれるのか」とか、「しびんは臭い」と「しびんよ、お前はくさい」は同じことを意味するかといったことが真面目に議論されたわけです。
こういう詭弁に向う危険もありながら、ヨーロッパで言葉と論理が重視される伝統を生むのです。
フランスでは高校3年段階で国語教育の集大成として哲学を学び、試験では哲学が課されます。たとえば、「経済的価値と人間的価値は両立するか」ということに哲学者の言葉を活用しながら論じなければなりません。
そういえば、シェイクスピアの『ハムレット』の一節に、ボローニアスがハムレットのもつ本に関心をもち、何を読んでいるのかを尋ねて、ハムレットは「言葉、言葉、言葉」と言ったということが書かれていますが、ヨーロッパは言葉に強いこだわりのある文化をもっていることは言うまでもありません。
わが国の政治家や官僚が「詭弁」に近い発言をするのに接する時、そういう詭弁を見抜き反論しうる弁論術を私達ももっておきたいね。