クイズ!!ガリ勉というテレビ朝日の番組が面白い。
あるテーマが与えられて、そのテーマから出題されるので出演者は予習してくる。クイズに正答するだけでなく、そのテーマについての雑学を披露し、それもポイントに加えるというもの。
番組の途中で何時間勉強したか、どういうふうに勉強したかを見せてくれるのですね。
その洒落というか、勉強というおさらばしたい分野を洒脱なギャグにしてしまっているのですね。
見ていて、やるな~と思いましたね。
こんなギャグめいた番組を教育的に考えてしまうのだから、職業病だね(笑)
勉強時間が成績に直結するものではないし、記憶するのにどういう手法をとるかという観点からみると面白い。
池田は教育学者のくせに暗記学習を容認するのかと言われそうだけど、あくまでもギャグだし、暗記学習が今日の学習スタイルであることに変わりない(変わらない)現在、どういうスタイルで学習しているのをみるのかという実見の場にしているにすぎません。
それに思い起こしてみると、自分で調べていくと、あれこれ人に雑学みたいに話したくなるでしょう。そういう場面を番組に仕掛けているのも、なかなか笑えるよね。
興味深いのは、ノートの取り方。テキストに直接にメモする人もいけたれど、大体がノートづくりを行っていました。
すると、(1)ノートに、用語を書いて、それを詳細に説明する独自の用語集を作っているひともいれば、(2)系図形式を織り込みながら図式化して視覚化するノートづくりもあり、(3)現地に赴き、現地の写真を織り込みながらノートづくりをしているひともいました。
ノートづくりという作業は無断のように思うかもしれないけれど、学習内容をあとからみたときに確認しやすく、思考の足跡を追うのに効果的です。
授業でいえば、授業の流れを思い起こすのに適切なのですね。
このノートづくりは、小学校ではしっかり指導するようですが、中高に上がるに従って、指導しなくなります。
教育学者らしく、簡単にですが、ノートづくりのポイントを述べておくと、(1)赤鉛筆、青鉛筆そして黒鉛筆の三色を使い分けさせる学習習慣を身につかせて、重要度に合わせて鉛筆を使い分けることをルール化すること、(2)授業内容のポイントを図式化しながら、見やすくまとめさせること、決まった記号を使い、→や⇔などを使い分ける癖をつけさせることの2点を挙げておきましょう。
最初は板書をノートするところから始めて、徐々に生徒のオリジナルの記号やルールを促していくようにするといいですね。
あなどれないよ、ノートづくりは。特に、授業開始直後の4月くらいには、近年、学生さんからどうやってノートをとっていいか分かりませんという質問がありますが、恐らく、学習スタイルの確立というか、学習の構えが整わないまま来てしまったのだと思います。
もしかしたら、大学の教員にも板書スキルやノートづくりの指導法が必要な時代がくるのかもね。
※ちなみに、暗記学習にしないためには意味を問うのがひとつ。昨日のテーマは、「大奥」でしたが、大奥の女性をひとり取り上げて、その人物の生き方から江戸時代の特徴を説明しなさいとすればどうだろう?
ただ覚えてるだけではだめで、知識を構造的に組み合わせる必要が出てきますよね。大学の試験は、このことが大切なんですね。
あるテーマが与えられて、そのテーマから出題されるので出演者は予習してくる。クイズに正答するだけでなく、そのテーマについての雑学を披露し、それもポイントに加えるというもの。
番組の途中で何時間勉強したか、どういうふうに勉強したかを見せてくれるのですね。
その洒落というか、勉強というおさらばしたい分野を洒脱なギャグにしてしまっているのですね。
見ていて、やるな~と思いましたね。
こんなギャグめいた番組を教育的に考えてしまうのだから、職業病だね(笑)
勉強時間が成績に直結するものではないし、記憶するのにどういう手法をとるかという観点からみると面白い。
池田は教育学者のくせに暗記学習を容認するのかと言われそうだけど、あくまでもギャグだし、暗記学習が今日の学習スタイルであることに変わりない(変わらない)現在、どういうスタイルで学習しているのをみるのかという実見の場にしているにすぎません。
それに思い起こしてみると、自分で調べていくと、あれこれ人に雑学みたいに話したくなるでしょう。そういう場面を番組に仕掛けているのも、なかなか笑えるよね。
興味深いのは、ノートの取り方。テキストに直接にメモする人もいけたれど、大体がノートづくりを行っていました。
すると、(1)ノートに、用語を書いて、それを詳細に説明する独自の用語集を作っているひともいれば、(2)系図形式を織り込みながら図式化して視覚化するノートづくりもあり、(3)現地に赴き、現地の写真を織り込みながらノートづくりをしているひともいました。
ノートづくりという作業は無断のように思うかもしれないけれど、学習内容をあとからみたときに確認しやすく、思考の足跡を追うのに効果的です。
授業でいえば、授業の流れを思い起こすのに適切なのですね。
このノートづくりは、小学校ではしっかり指導するようですが、中高に上がるに従って、指導しなくなります。
教育学者らしく、簡単にですが、ノートづくりのポイントを述べておくと、(1)赤鉛筆、青鉛筆そして黒鉛筆の三色を使い分けさせる学習習慣を身につかせて、重要度に合わせて鉛筆を使い分けることをルール化すること、(2)授業内容のポイントを図式化しながら、見やすくまとめさせること、決まった記号を使い、→や⇔などを使い分ける癖をつけさせることの2点を挙げておきましょう。
最初は板書をノートするところから始めて、徐々に生徒のオリジナルの記号やルールを促していくようにするといいですね。
あなどれないよ、ノートづくりは。特に、授業開始直後の4月くらいには、近年、学生さんからどうやってノートをとっていいか分かりませんという質問がありますが、恐らく、学習スタイルの確立というか、学習の構えが整わないまま来てしまったのだと思います。
もしかしたら、大学の教員にも板書スキルやノートづくりの指導法が必要な時代がくるのかもね。
※ちなみに、暗記学習にしないためには意味を問うのがひとつ。昨日のテーマは、「大奥」でしたが、大奥の女性をひとり取り上げて、その人物の生き方から江戸時代の特徴を説明しなさいとすればどうだろう?
ただ覚えてるだけではだめで、知識を構造的に組み合わせる必要が出てきますよね。大学の試験は、このことが大切なんですね。












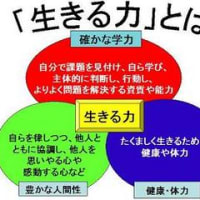




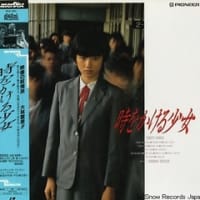


ノートって大事ですよね。現在、大学4年なのですが、ようやく気づきました。
「暗記学習にしないために~」の箇所ですが、大変、参考になりました。知識を構造的にですか。
なるほど~
ノートのとり方ですが、学問分野によって多少の違いがあるかもしれませんが、概ね、意味を理解できるよう構造的に把握することが大切であることは、分野を問わず言えることだと考えています。