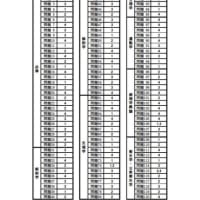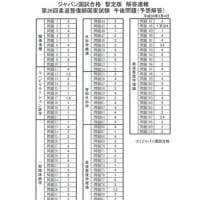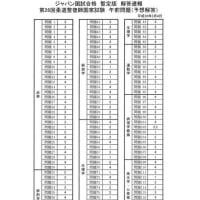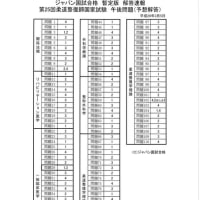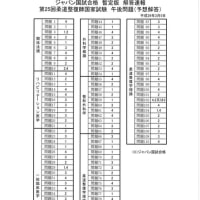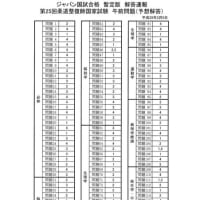おはようございます、佐藤です。
国家試験本番まであと10日ですね!!
受験生のみなさん、体調管理を含め体制は万全でしょうか。
さて、ジャパン国試合格では来る来月の国家試験前日、
来月3月1日(土)に「前日講習会」を実施致します。
9:30 ~ 12:45(90分×2コマ)、
柔整理論の必修問題 と 臨床系科目 の 最終チェックを行います。
※ 受講料 5.000円
定員になり次第、受付を終了させて頂きますので
どうぞお早目にお申し込みくださいませ。
また、お申し込みはFAXでのみ受け付けております。
では本日はジャパン国試合格の「校内模試」から
必修問題を11問出題致します。
<解剖学>
問題 下顎の挙上に働かないのはどれか。
1. 咬 筋
2. 側頭筋
3. 内側翼突筋
4. 外側翼突筋
【解答】 4 【解剖】p.78
外側翼突筋は下顎の前方移動である。側頭筋は挙上に加え、下顎の後方移動を行う。
<生理学>
問題 ABO式血液型で凝集原Aと凝集原Bとの両方を持っているのはどの血液型か。
1. A型
2. B型
3. AB型
4. O型
【解答】 3 【生理】p.31
凝集素:抗体
凝集原:抗原
<運動学>
問題 8 人体各部のてこの構造について、第2のてこ(力のてこ)の特徴はどれか。
1. 力点と支点の中央に荷重点がある。
2. 力点と荷重点の中央に支点がある。
3. 支点と荷重点の中央に力点がある。
4. 支点に対して力点と荷重点が同位置にある。
【解答】 1 【運動】p.13~15(13~15)
てこの構造を覚える際は、中央に支点、荷重点、力点のうち、何が当てはまるかで判断すること。第2のてこは、荷重点が中央にある。荷物(にもつ)の2(に)と覚えること。また、支点に対して力点と荷重点が一緒になることは通常ありえなく、てこの構造として成立しない。
<病理学概論>
問題 9 滲出物中に大量の好中球が含まれるのはどれか。
1. 漿液性炎
2. 化膿性炎
3. カタル性炎
4. 肉芽腫性炎
【解答】 2 【病理】p.68~70 (66~67)
滲出を主体とする炎症を滲出性炎という。滲出物の成分によって細分類される。なかでも、好中球の滲出が多い滲出性炎を化膿性炎といい、膿瘍、蓄膿症、蜂窩織炎が含まれる。血漿などの液成分が滲出の主体であれば漿液性炎、粘液の分泌や粘膜の損傷を認めないものをカタル性炎、赤血球を多く含むものは出血性炎とよばれる。肉芽腫性炎(特異性炎)は、類上皮細胞の出現をみる肉芽腫を形成する炎症で、滲出性炎とは別種である。
<衛生学・公衆衛生学>
問題10 金属製器具の消毒に使われるのはどれか。
1. 日光消毒
2. 次亜塩素酸ナトリウム
3. 煮 沸
4. ポピドンヨード
【解答】 3 【衛生】p.49
1.日光消毒(赤外線や紫外線):寝具や着衣などの消毒に適している。
2.4.次亜塩素酸ナトリウム・ポピドンヨードは金属腐食性があり不適である。
<関係法規>
問題 インフォームド・コンセントについて直接関係ないのはどれか。
1. 十分な説明
2. 理解と納得
3. 情報の提供
4. プライバシーの保護
【解答】 4 【法規】p.4
インフォームド・コンセントの内容を柔道整復師にあてはめて考えれば次のようになる。
「個々の対象者が柔道整復師から受ける施術などにより、どの程度の回復や生活の質を向上できるのか(プラスの要因)とそれに伴う費用や不快感や、苦痛の精神的身体的負担等(マイナスの要因)などの説明を十分に受け、施術などを受けるかどうかを選択決定できるよう、説明や情報をうけることである」。
<リハビリテーション医学>
問題 身体計測について正しい組合せはどれか。
1. 上腕長 ―― 肩峰~上腕骨内側上顆
2. 前腕長 ―― 肘頭~尺骨茎状突起
3. 棘果長 ―― 上前腸骨棘~外果
4. 転子果長 ―― 大転子~内果
【解答】 2 【リハ】p.52
1.肩峰~上腕骨外側上顆
3.上前腸骨棘~内果
4.大転子~外果
<一般臨床医学>
問題 マン・ウェルニッケ(Mann-Wernicke)姿勢になる疾患はどれか。
1. パーキンソン病
2. 脳血管障害
3. うっ血性心不全
4. 胆石症
【解答】 2 【臨床】p.9~11(10~11)
マン・ウェルニッケ姿勢とは、麻痺側の前腕は強く屈曲し、下肢は痙性となって足底側へ屈曲した姿勢で、脳血管障害患者でみられる。
1.頭を前屈し肘関節を曲げて、独特の前かがみ姿勢をとる。
3.重症心疾患や肺疾患では横臥すると肺静脈循環血液量が増加して右心負荷が増悪し呼吸困難が強くなって苦しくなる。そこで、ベッド上で座ったり(起坐位)、胸の前に布団を当ててもたれかかるようにしていたりする。
4.激痛のために、身体をエビのように折り曲げるエビ姿勢をとる。
<外科学概論>
問題 代謝性アルカローシスとなるのはどれか。
1. 糖尿病
2. 喘 息
3. 胃液吸引
4. 抗利尿剤の過剰投与
【解答】 3 【外科】p.63(64) 基本A
[基] 6.物質の摂取と排泄
Ⅰ型糖尿病患者ではインスリンが欠乏しているため、肝臓や筋といった組織が血糖を取り込むことができず、血管内は高血糖であるが細胞内は逆に低血糖状態となっている。そのため、β酸化によってTCAサイクルと呼吸鎖を動かすこととなり、血中にケトン体が遊離する。このケトン体によってアシドーシスとなる。利尿剤の過剰投与によってCl‐ が喪失すると腎臓におけるHCO3‐ の再吸収が刺激されるので代謝性アルカローシスとなる。閉塞性無気肺などの上気道閉塞が起こっているときは呼吸性アシドーシスとなる。肺気腫や喘息でも同様の病態が生じる。
<整形外科学>
問題 変形性膝関節症について誤っているのはどれか。
1. 変形性関節症の中で最も多い。
2. 歩行開始時の疼痛を訴えることが多い。
3. 内側に強い変化を生じるものが多い。
4. 膝の伸展拘縮のため屈曲が制限される。
【解答】 4 【整形】p.245
変形性膝関節症では屈曲拘縮が優位でそのために完全伸展が困難となる。運動開始時の疼痛があるが、進行例では運動中にも疼痛が続く。
<柔道整復学理論>
問題 骨折の固有症状について誤っているのはどれか。
1. 軋轢音 ―― 異常運動の際に明確に聴取できる。
2. 異常可動性 ―― 長骨の完全骨折で著明にみられる。
3. 二次性転位 ―― 外力、筋の牽引力、患肢の重量で発生する。
4. 捻転転位 ―― 骨の長軸上で回旋して末梢骨片が転位したもの。
【解答】 1 【柔理】p.32~33
軋轢音は、異常可動性に伴い骨折端が触れ合い音を出すが、耳で聴取することは難しく指などを当てかすかに触知できるものである。また、軋轢音は異常可動性に伴い必ず証明されるものではない。
講習会の詳細については、当校HPからご覧ください。
http://jkokushi.jp/
国家試験本番まであと10日ですね!!
受験生のみなさん、体調管理を含め体制は万全でしょうか。
さて、ジャパン国試合格では来る来月の国家試験前日、
来月3月1日(土)に「前日講習会」を実施致します。
9:30 ~ 12:45(90分×2コマ)、
柔整理論の必修問題 と 臨床系科目 の 最終チェックを行います。
※ 受講料 5.000円
定員になり次第、受付を終了させて頂きますので
どうぞお早目にお申し込みくださいませ。
また、お申し込みはFAXでのみ受け付けております。
では本日はジャパン国試合格の「校内模試」から
必修問題を11問出題致します。
<解剖学>
問題 下顎の挙上に働かないのはどれか。
1. 咬 筋
2. 側頭筋
3. 内側翼突筋
4. 外側翼突筋
【解答】 4 【解剖】p.78
外側翼突筋は下顎の前方移動である。側頭筋は挙上に加え、下顎の後方移動を行う。
<生理学>
問題 ABO式血液型で凝集原Aと凝集原Bとの両方を持っているのはどの血液型か。
1. A型
2. B型
3. AB型
4. O型
【解答】 3 【生理】p.31
凝集素:抗体
凝集原:抗原
<運動学>
問題 8 人体各部のてこの構造について、第2のてこ(力のてこ)の特徴はどれか。
1. 力点と支点の中央に荷重点がある。
2. 力点と荷重点の中央に支点がある。
3. 支点と荷重点の中央に力点がある。
4. 支点に対して力点と荷重点が同位置にある。
【解答】 1 【運動】p.13~15(13~15)
てこの構造を覚える際は、中央に支点、荷重点、力点のうち、何が当てはまるかで判断すること。第2のてこは、荷重点が中央にある。荷物(にもつ)の2(に)と覚えること。また、支点に対して力点と荷重点が一緒になることは通常ありえなく、てこの構造として成立しない。
<病理学概論>
問題 9 滲出物中に大量の好中球が含まれるのはどれか。
1. 漿液性炎
2. 化膿性炎
3. カタル性炎
4. 肉芽腫性炎
【解答】 2 【病理】p.68~70 (66~67)
滲出を主体とする炎症を滲出性炎という。滲出物の成分によって細分類される。なかでも、好中球の滲出が多い滲出性炎を化膿性炎といい、膿瘍、蓄膿症、蜂窩織炎が含まれる。血漿などの液成分が滲出の主体であれば漿液性炎、粘液の分泌や粘膜の損傷を認めないものをカタル性炎、赤血球を多く含むものは出血性炎とよばれる。肉芽腫性炎(特異性炎)は、類上皮細胞の出現をみる肉芽腫を形成する炎症で、滲出性炎とは別種である。
<衛生学・公衆衛生学>
問題10 金属製器具の消毒に使われるのはどれか。
1. 日光消毒
2. 次亜塩素酸ナトリウム
3. 煮 沸
4. ポピドンヨード
【解答】 3 【衛生】p.49
1.日光消毒(赤外線や紫外線):寝具や着衣などの消毒に適している。
2.4.次亜塩素酸ナトリウム・ポピドンヨードは金属腐食性があり不適である。
<関係法規>
問題 インフォームド・コンセントについて直接関係ないのはどれか。
1. 十分な説明
2. 理解と納得
3. 情報の提供
4. プライバシーの保護
【解答】 4 【法規】p.4
インフォームド・コンセントの内容を柔道整復師にあてはめて考えれば次のようになる。
「個々の対象者が柔道整復師から受ける施術などにより、どの程度の回復や生活の質を向上できるのか(プラスの要因)とそれに伴う費用や不快感や、苦痛の精神的身体的負担等(マイナスの要因)などの説明を十分に受け、施術などを受けるかどうかを選択決定できるよう、説明や情報をうけることである」。
<リハビリテーション医学>
問題 身体計測について正しい組合せはどれか。
1. 上腕長 ―― 肩峰~上腕骨内側上顆
2. 前腕長 ―― 肘頭~尺骨茎状突起
3. 棘果長 ―― 上前腸骨棘~外果
4. 転子果長 ―― 大転子~内果
【解答】 2 【リハ】p.52
1.肩峰~上腕骨外側上顆
3.上前腸骨棘~内果
4.大転子~外果
<一般臨床医学>
問題 マン・ウェルニッケ(Mann-Wernicke)姿勢になる疾患はどれか。
1. パーキンソン病
2. 脳血管障害
3. うっ血性心不全
4. 胆石症
【解答】 2 【臨床】p.9~11(10~11)
マン・ウェルニッケ姿勢とは、麻痺側の前腕は強く屈曲し、下肢は痙性となって足底側へ屈曲した姿勢で、脳血管障害患者でみられる。
1.頭を前屈し肘関節を曲げて、独特の前かがみ姿勢をとる。
3.重症心疾患や肺疾患では横臥すると肺静脈循環血液量が増加して右心負荷が増悪し呼吸困難が強くなって苦しくなる。そこで、ベッド上で座ったり(起坐位)、胸の前に布団を当ててもたれかかるようにしていたりする。
4.激痛のために、身体をエビのように折り曲げるエビ姿勢をとる。
<外科学概論>
問題 代謝性アルカローシスとなるのはどれか。
1. 糖尿病
2. 喘 息
3. 胃液吸引
4. 抗利尿剤の過剰投与
【解答】 3 【外科】p.63(64) 基本A
[基] 6.物質の摂取と排泄
Ⅰ型糖尿病患者ではインスリンが欠乏しているため、肝臓や筋といった組織が血糖を取り込むことができず、血管内は高血糖であるが細胞内は逆に低血糖状態となっている。そのため、β酸化によってTCAサイクルと呼吸鎖を動かすこととなり、血中にケトン体が遊離する。このケトン体によってアシドーシスとなる。利尿剤の過剰投与によってCl‐ が喪失すると腎臓におけるHCO3‐ の再吸収が刺激されるので代謝性アルカローシスとなる。閉塞性無気肺などの上気道閉塞が起こっているときは呼吸性アシドーシスとなる。肺気腫や喘息でも同様の病態が生じる。
<整形外科学>
問題 変形性膝関節症について誤っているのはどれか。
1. 変形性関節症の中で最も多い。
2. 歩行開始時の疼痛を訴えることが多い。
3. 内側に強い変化を生じるものが多い。
4. 膝の伸展拘縮のため屈曲が制限される。
【解答】 4 【整形】p.245
変形性膝関節症では屈曲拘縮が優位でそのために完全伸展が困難となる。運動開始時の疼痛があるが、進行例では運動中にも疼痛が続く。
<柔道整復学理論>
問題 骨折の固有症状について誤っているのはどれか。
1. 軋轢音 ―― 異常運動の際に明確に聴取できる。
2. 異常可動性 ―― 長骨の完全骨折で著明にみられる。
3. 二次性転位 ―― 外力、筋の牽引力、患肢の重量で発生する。
4. 捻転転位 ―― 骨の長軸上で回旋して末梢骨片が転位したもの。
【解答】 1 【柔理】p.32~33
軋轢音は、異常可動性に伴い骨折端が触れ合い音を出すが、耳で聴取することは難しく指などを当てかすかに触知できるものである。また、軋轢音は異常可動性に伴い必ず証明されるものではない。
講習会の詳細については、当校HPからご覧ください。
http://jkokushi.jp/