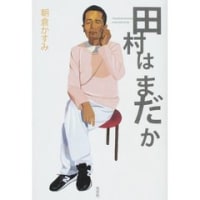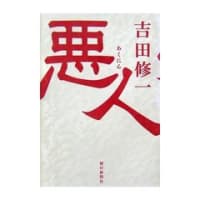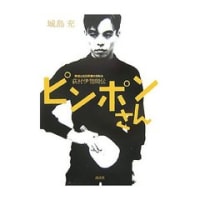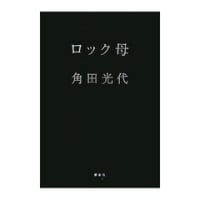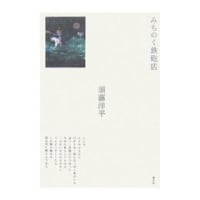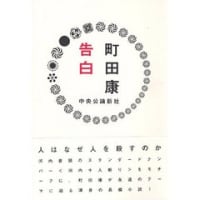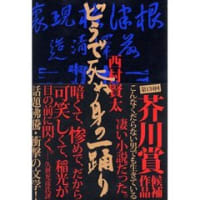尾辻克彦『父が消えた』(河出文庫)
尾辻克彦はフェチである。
どうもそうではないかとうすうす感づいたのは、ぼくが高校生のころ。『肌ざわり』というエロチックなタイトルの小説集を読んだときだった。
父と娘の胡桃子のとある一日を描いた話で、中身はちっともエロチックではなかったけれど、「鍋の中でトマトシチュウがじっとしていた」なんていう文章に鳥肌が立った。ものを見る目が肉感的で、どこかこそばゆいのである。読んでいるうち、尾辻克彦の手が知らぬ間にもぞもぞ伸びてきて背中をなでられているような感じ。
ところで、尾辻克彦が、ニセ札をつくって逮捕された赤瀬川原平その人であることも、『肌ざわり』が出た翌年つまり1981年、「父が消えた」で芥川賞をとり、ときの人になったことも、もちろん知っていたのだが、この表題作を収めた単行本が文藝春秋から発刊され、5年後に文庫本が出ていたにもかかわらず、どうしたことか、ぼくは読まずにきてしまった。まったくもって迂闊だった。
おかげで最近は手に入りにくくなっていたらしい。それがたまたま入った本屋で立ち読みしていたら、目の前の棚に『父が消えた』が一冊、控えめな顔をして、いままさに購入されるのを待ってくれていた。その瞬間、ぼくは涙を流していたのであるが、実は3年前、新たな文庫本が出ていたのである。河出文庫さん、ありがとう。
表題作を含む5つの短編が収められていて、フェティシズムをこれでもかというくらい堪能させてくれるのが「星に触わる」。
これも父と胡桃子シリーズのひとつ。夏休みだろう、胡桃子はプールに泳ぎに行っていない。家には、ロイヤル天文同好会の会員である父、つまり「私」がひとりいて「ゴムの惑星」なるガリ版刷りの会報を鉄筆でつづっている。
ただそれだけの話なのだが、この会報の中身がすこぶる面白い。「私」はカメラに異常に精通し、大戦時に世界中のスパイに愛用された超小型カメラ「ミノックス」への偏愛ぶりが語られていく。
《戦時においては「諜報のため」という大義名分があるからまだいいのですが、平時においてはその大義名分の消失したあとに、その偏執的秘密的スタイルだけが露わになって、フェチ(フェティシズム)が一挙に露出してくるのです。もう申し開きはできません。ナチが脱げたあとにはフェチがヌルリと裸になっているのです》
ナチとフェチ。まさに尾辻克彦の面目躍如たるものがある。
さて、その「父が消えた」もまた、主人公の「私」が亡くなった父のために、八王子霊園に墓地の見学にいくという、それだけの話だが、ぼくはなんども声を上げて笑いそうになった。
なにがそんなに面白いのか。でもこれってコトバではうまく説明できそうにないなと思っていたら、作家の夏石鈴子という人が解説でこんなことを書いてくれていた。
《はい、すじとしては本当にこれだけ。確かに正しい。けれど、これでは「父が消えた」の、じんわりとおいしさがしみ出してくるような味わいや、これだけのすじで、物語を成立させ、芥川賞を受賞した尾辻克彦という人の力技は全然伝わらない。正しくても、すじだけでは困る。実際に現物を手にして読まなければ、感じることはできない。こういう単純な事実は、案外ホリエモンのような人たちには通じないものだ》
このような小説を退屈だと感じる人もいるだろう。そんなあなたはちょっと危ないかもしれない。
尾辻克彦はフェチである。
どうもそうではないかとうすうす感づいたのは、ぼくが高校生のころ。『肌ざわり』というエロチックなタイトルの小説集を読んだときだった。
父と娘の胡桃子のとある一日を描いた話で、中身はちっともエロチックではなかったけれど、「鍋の中でトマトシチュウがじっとしていた」なんていう文章に鳥肌が立った。ものを見る目が肉感的で、どこかこそばゆいのである。読んでいるうち、尾辻克彦の手が知らぬ間にもぞもぞ伸びてきて背中をなでられているような感じ。
ところで、尾辻克彦が、ニセ札をつくって逮捕された赤瀬川原平その人であることも、『肌ざわり』が出た翌年つまり1981年、「父が消えた」で芥川賞をとり、ときの人になったことも、もちろん知っていたのだが、この表題作を収めた単行本が文藝春秋から発刊され、5年後に文庫本が出ていたにもかかわらず、どうしたことか、ぼくは読まずにきてしまった。まったくもって迂闊だった。
おかげで最近は手に入りにくくなっていたらしい。それがたまたま入った本屋で立ち読みしていたら、目の前の棚に『父が消えた』が一冊、控えめな顔をして、いままさに購入されるのを待ってくれていた。その瞬間、ぼくは涙を流していたのであるが、実は3年前、新たな文庫本が出ていたのである。河出文庫さん、ありがとう。
表題作を含む5つの短編が収められていて、フェティシズムをこれでもかというくらい堪能させてくれるのが「星に触わる」。
これも父と胡桃子シリーズのひとつ。夏休みだろう、胡桃子はプールに泳ぎに行っていない。家には、ロイヤル天文同好会の会員である父、つまり「私」がひとりいて「ゴムの惑星」なるガリ版刷りの会報を鉄筆でつづっている。
ただそれだけの話なのだが、この会報の中身がすこぶる面白い。「私」はカメラに異常に精通し、大戦時に世界中のスパイに愛用された超小型カメラ「ミノックス」への偏愛ぶりが語られていく。
《戦時においては「諜報のため」という大義名分があるからまだいいのですが、平時においてはその大義名分の消失したあとに、その偏執的秘密的スタイルだけが露わになって、フェチ(フェティシズム)が一挙に露出してくるのです。もう申し開きはできません。ナチが脱げたあとにはフェチがヌルリと裸になっているのです》
ナチとフェチ。まさに尾辻克彦の面目躍如たるものがある。
さて、その「父が消えた」もまた、主人公の「私」が亡くなった父のために、八王子霊園に墓地の見学にいくという、それだけの話だが、ぼくはなんども声を上げて笑いそうになった。
なにがそんなに面白いのか。でもこれってコトバではうまく説明できそうにないなと思っていたら、作家の夏石鈴子という人が解説でこんなことを書いてくれていた。
《はい、すじとしては本当にこれだけ。確かに正しい。けれど、これでは「父が消えた」の、じんわりとおいしさがしみ出してくるような味わいや、これだけのすじで、物語を成立させ、芥川賞を受賞した尾辻克彦という人の力技は全然伝わらない。正しくても、すじだけでは困る。実際に現物を手にして読まなければ、感じることはできない。こういう単純な事実は、案外ホリエモンのような人たちには通じないものだ》
このような小説を退屈だと感じる人もいるだろう。そんなあなたはちょっと危ないかもしれない。