読だかの星を読んで 花田幸徳
宮沢賢治 「よだかの星」 を読んで僕は、
この文が人間の世界のきたなく悪い所を、鳥の世界にしたのだと思った。
よだかが身にくく、弱いために他の鳥からきらわれ、ばかにされる。
もしよだかが強かったらどうだろう。
ここを人間世界にたとえてみると、一人の貧しい家の子が遊ぼうと思って外に出た。
でも家が貧しいだけに他の子どもに相手にされない。
それどころか悪口をいわれたりする。
もし子どもが遊ぼうとしてもその子の親がとめて遊ばせないこれと同じだと思う。
よだかがみにくく生まれたために、その子が貧しい家に生まれたためにああなるのだろう。
鳥達はたかにはぺこぺこして名を聞くだけでもおそれたそれはたかが強いからであったのだ。
ちょうど、たかが会社の社長で鳥達が社員、よだかがその下ではたらくといったようだ。
よだかが自殺する、もし他の鳥がと僕は思う。
・・・全文、原文の侭掲載



・
中学一年生(13才)
国語の授業の課題として作成したる文集
個人文集 「 鷹 」
に編集した読書感想文である。
中一としては、少々幼稚なる感想文なる
然し、これが
広島の片田舎から大都会大阪に移住して来て
居住地域に於いても、学校のクラスに於いても
なかなか、仲間に入れて貰えない・・・
そんな境遇から、少年の心懐に宿った コンプレツクス
そうした背景の少年が読んだもの・・・そう理解すると
上記の少年の感想文への評価も少しは変ろうか
読書とは
読書感想は、あくまで一個のオリジナルな想いであって
普遍の想いなぞ、あり得ない
敢えて言う
著者が何を言いたいかを読むのではなく
読みし者が、著書を通して如何に己が想いを読み取るかである。
読書とは、斯の如きもの
それでいい・・と
私は、そう想う
機は熟してなかった
昭和42年(1967年)
中学に進級した
中学生とも成ると、さすが 「ポスト大人」
文庫本を手にする・・は、ファッション であった
クラスの女子生徒は皆、読書していると言う
一級上の友がき・坂尾までも、文庫本を手にしている
彼は、「ゲーテ詩集」 を、読んでいると
文庫本そのものの存在をも知らなかった私であるが
友がき・坂尾から、「ゲーテ詩集」を借りて読んだことが 始めの一歩 であった
「服が欲しい」・・と謂ったら、「学生服がある」・・と謂う親父も
事、勉強の為と謂えば金を出して呉れた
大東商店街の 永田書店、和田広文堂で品定めし購入したるは
「リルケ詩集」 「北原白秋」 「島崎藤村」 ・・・と、読んではみた
然し
読んではみたものの何ひとつ、実につかなかった
13才の私
本を読む までに、とうてい至ってなかったのである
リンク→文学少女には成れなかった
・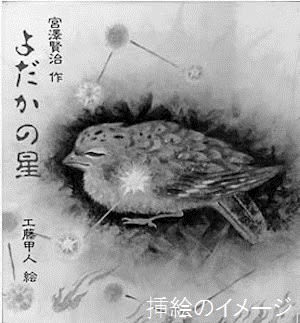
よだかの星 宮沢賢治
よだかは、実にみにくい鳥です。
顔は、ところどころ、味噌をつけたようにまだらで、くちばしは、ひらたくて、耳までさけています。
足は、まるでよぼよぼで、一間(いっけん)とも歩けません。
ほかの鳥は、もう、よだかの顔を見ただけでも、いやになってしまうという工合(ぐあい)でした。
たとえば、ひばりも、あまり美しい鳥ではありませんが、よだかよりは、ずっと上だと思っていましたので、
夕方など、よだかにあうと、さもさもいやそうに、しんねりと目をつぶりながら、首をそっ方(ぽ)へ向けるのでした。
もっとちいさなおしゃべりの鳥などは、いつでもよだかのまっこうから悪口をしました。
「ヘン。又出て来たね。まあ、あのざまをごらん。ほんとうに、鳥の仲間のつらよごしだよ。」
「ね、まあ、あのくちのおおきいことさ。きっと、かえるの親類か何かなんだよ。」
こんな調子です。
よだかでないただのたかならば、こんな生はんかのちいさい鳥は、
もう名前を聞いただけでも、ぶるぶるふるえて、顔色を変えて、からだをちぢめて、木の葉のかげにでもかくれたでしょう。
ところがよだかは、ほんとうは鷹の兄弟でも親類でもありませんでした。
かえって、よだかは、あの美しいかわせみや、鳥の中の宝石のような蜂雀の兄さんでした。
蜂雀は花の蜜をたべ、かわせみはお魚を食べ、夜だかは羽虫をとってたべるのでした。
それによだかには、するどい爪もするどいくちばしもありませんでしたから、
どんなに弱い鳥でも、よだかをこわがる筈はなかったのです。
それなら、たかという名のついたことは不思議なようですが、これは、一つはよだかのはねが無暗(むやみ)に強くて、
風を切って翔(か)けるときなどは、まるで鷹のように見えたことと、
も一つはなきごえがするどくて、やはりどこか鷹に似ていた為です。
もちろん、鷹は、これをひじょうに気にかけて、いやがっていました。
それですから、よだかの顔さえ見ると、肩をいからせて、早く名前をあらためろ、名前をあらためろと、いうのでした。
ある夕方、とうとう、鷹がよだかのうちへやって参りました。
「おい。居るかい。まだお前は名前をかえないのか。
ずいぶんお前も恥知らずだな。
お前とおれでは、よっぽど人格がちがうんだよ。たとえばおれは、青いそらをどこまででも飛んで行く。
おまえは、曇ってうすぐらい日か、夜でなくちゃ、出て来ない。
それから、おれのくちばしやつめを見ろ。そして、よくお前のとくらべて見るがいい。」
「鷹さん。それはあんまり無理です。私の名前は私が勝手につけたのではありません。神さまから下さったのです。」
「いいや。おれの名なら、神さまから貰ったのだと云ってもよかろうが、
お前のは、云わば、おれと夜と、両方から借りてあるんだ。さあ返せ。」
「鷹さん。それは無理です。」
「無理じゃない。おれがいい名を教えてやろう。
市蔵というんだ。市蔵とな。いい名だろう。
そこで、名前を変えるには、改名の披露というものをしないといけない。
いいか。それはな、首へ市蔵と書いたふだをぶらさげて、
私は以来市蔵と申しますと、口上を云って、みんなの所をおじぎしてまわるのだ。」
「そんなことはとても出来ません。」
「いいや。出来る。そうしろ。もしあさっての朝までに、お前がそうしなかったら、もうすぐ、つかみ殺すぞ。
つかみ殺してしまうから、そう思え。おれはあさっての朝早く、鳥のうちを一軒ずつまわって、お前が来たかどうかを聞いてあるく。
一軒でも来なかったという家があったら、もう貴様もその時がおしまいだぞ。」
「だってそれはあんまり無理じゃありませんか。そんなことをする位なら、私はもう死んだ方がましです。今すぐ殺して下さい。」
「まあ、よく、あとで考えてごらん。市蔵なんてそんなにわるい名じゃないよ。」
鷹は大きなはねを一杯にひろげて、自分の巣の方へ飛んで帰って行きました。
よだかは、じっと目をつぶって考えました。
一たい僕は、なぜこうみんなにいやがられるのだろう。
僕の顔は、味噌をつけたようで、口は裂けてるからなあ。
それだって、僕は今まで、なんにも悪いことをしたことがない。
赤ん坊のめじろが巣から落ちていたときは、助けて巣へ連れて行ってやった。
そしたらめじろは、赤ん坊をまるでぬす人からでもとりかえすように僕からひきはなしたんだなあ。
それからひどく僕を笑ったっけ。それにああ、今度は市蔵だなんて、首へふだをかけるなんて、つらいはなしだなあ。
あたりは、もううすくらくなっていました。
夜だかは巣から飛び出しました。
雲が意地悪く光って、低くたれています。
よだかはまるで雲とすれすれになって、音なく空を飛びまわりました。
それからにわかによだかは口を大きくひらいて、はねをまっすぐに張って、まるで矢のようにそらをよこぎりました。
小さな羽虫が幾匹も幾匹もその咽喉(のど)にはいりました。
からだがつちにつくかつかないうちに、よだかはひらりとまたそらへはねあがりました。
もう雲は鼠色(ねずみいろ)になり、向うの山には山焼けの火がまっ赤です。
夜だかが思い切って飛ぶときは、そらがまるで二つに切れたように思われます。
一疋(ぴき)の甲虫が、夜だかの咽喉にはいって、ひどくもがきました。
よだかはすぐそれを呑みこみましたが、その時何だかせなかがぞっとしたように思いました。
雲はもうまっくろく、東の方だけ山やけの火が赤くうつって、恐ろしいようです。
よだかはむねがつかえたように思いながら、又そらへのぼりました。
また一疋の甲虫が、夜だかののどに、はいりました。
そしてまるでよだかの咽喉をひっかいてばたばたしました。
よだかはそれを無理にのみこんでしまいましたが、その時、急に胸がどきっとして、夜だかは大声をあげて泣き出しました。
泣きながらぐるぐるぐるぐる空をめぐったのです。
ああ、かぶとむしや、たくさんの羽虫が、毎晩僕に殺される。
そしてそのただ一つの僕がこんどは鷹に殺される。
それがこんなにつらいのだ。
ああ、つらい、つらい。
僕はもう虫をたべないで餓(う)えて死のう。
いやその前にもう鷹が僕を殺すだろう。いや、その前に、僕は遠くの遠くの空の向うに行ってしまおう。
山焼けの火は、だんだん水のように流れてひろがり、雲も赤く燃えているようです。
よだかはまっすぐに、弟の川せみの所へ飛んで行きました。
きれいな川せみも、丁度起きて遠くの山火事を見ていた所でした。そしてよだかの降りて来たのを見て云いました。
「兄さん。今晩は。何か急のご用ですか。」
「いいや、僕は今度遠い所へ行くからね、その前一寸(ちょっと)お前に遭いに来たよ。」
「兄さん。行っちゃいけませんよ。
蜂雀もあんな遠くにいるんですし、僕ひとりぼっちになってしまうじゃありませんか。」
「それはね。どうも仕方ないのだ。もう今日は何も云わないで呉れ。
そしてお前もね、どうしてもとらなければならない時のほかはいたずらにお魚を取ったりしないようにして呉れ。
ね、さよなら。」
「兄さん。どうしたんです。まあもう一寸お待ちなさい。」
「いや、いつまで居てもおんなじだ。蜂雀へ、あとでよろしく云ってやって呉れ。さよなら。もうあわないよ。さよなら。」
よだかは泣きながら自分のお家(うち)へ帰って参りました。
みじかい夏の夜はもうあけかかっていました。
羊歯(しだ)の葉は、よあけの霧を吸って、青くつめたくゆれました。
よだかは高くきしきしきしと鳴きました。
そして巣の中をきちんとかたづけ、きれいにからだ中のはねや毛をそろえて、また巣から飛び出しました。
霧がはれて、お日さまが丁度東からのぼりました。
夜だかはぐらぐらするほどまぶしいのをこらえて、矢のように、そっちへ飛んで行きました。
「お日さん、お日さん。どうぞ私をあなたの所へ連れてって下さい。
灼(や)けて死んでもかまいません。
私のようなみにくいからだでも灼けるときには小さなひかりを出すでしょう。どうか私を連れてって下さい。」
行っても行っても、お日さまは近くなりませんでした。かえってだんだん小さく遠くなりながらお日さまが云いました。
「お前はよだかだな。なるほど、ずいぶんつらかろう。
今度そらを飛んで、星にそうたのんでごらん。お前はひるの鳥ではないのだからな。」
よだかはおじぎを一つしたと思いましたが、急にぐらぐらしてとうとう野原の草の上に落ちてしまいました。
そしてまるで夢を見ているようでした。
からだがずうっと赤や黄の星のあいだをのぼって行ったり、どこまでも風に飛ばされたり、
又鷹が来てからだをつかんだりしたようでした。
つめたいものがにわかに顔に落ちました。
よだかは眼をひらきました。
一本の若いすすきの葉から露がしたたったのでした。
もうすっかり夜になって、空は青ぐろく、一面の星がまたたいていました。
よだかはそらへ飛びあがりました。
今夜も山やけの火はまっかです。
よだかはその火のかすかな照りと、つめたいほしあかりの中をとびめぐりました。
それからもう一ぺん飛びめぐりました。
そして思い切って西のそらのあの美しいオリオンの星の方に、まっすぐに飛びながら叫びました。
「お星さん。西の青じろいお星さん。どうか私をあなたのところへ連れてって下さい。灼けて死んでもかまいません。」
オリオンは勇ましい歌をつづけながらよだかなどはてんで相手にしませんでした。
よだかは泣きそうになって、よろよろと落ちて、それからやっとふみとまって、もう一ぺんとびめぐりました。
それから、南の大犬座の方へまっすぐに飛びながら叫びました。
「お星さん。南の青いお星さん。どうか私をあなたの所へつれてって下さい。灼けて死んでもかまいません。」
大犬は青や紫)や黄やうつくしくせわしくまたたきながら云いました。
「馬鹿を云うな。おまえなんか一体どんなものだい。たかが鳥じゃないか。
おまえのはねでここまで来るには、億年兆年億兆年だ。」
そしてまた別の方を向きました。
よだかはがっかりして、よろよろ落ちて、それから又二へん飛びめぐりました。
それから又思い切って北の大熊星(おおぐまぼし)の方へまっすぐに飛びながら叫びました。
「北の青いお星さま、あなたの所へどうか私を連れてって下さい。」
大熊星はしずかに云いました。
「余計なことを考えるものではない。少し頭をひやして来なさい。
そう云うときは、氷山の浮(う)いている海の中へ飛び込むか、近くに海がなかったら、
氷をうかべたコップの水の中へ飛び込むのが一等だ。」
よだかはがっかりして、よろよろ落ちて、それから又、四へんそらをめぐりました。
そしてもう一度、東から今のぼった天(あま)の川(がわ)の向う岸の鷲(わし)の星に叫びました。
「東の白いお星さま、どうか私をあなたの所へ連れてって下さい。灼けて死んでもかまいません。」
鷲は大風(おおふう)に云いました。
「いいや、とてもとても、話にも何にもならん。
星になるには、それ相応の身分でなくちゃいかん。又よほど金もいるのだ。」
よだかはもうすっかり力を落してしまって、はねを閉じて、地に落ちて行きました。
そしてもう一尺で地面にその弱い足がつくというとき、よだかは俄(にわ)かにのろしのようにそらへとびあがりました。
そらのなかほどへ来て、よだかはまるで鷲が熊を襲(おそ)うときするように、ぶるっとからだをゆすって毛をさかだてました。
それからキシキシキシキシキシッと高く高く叫びました。
その声はまるで鷹でした。
野原や林にねむっていたほかのとりは、みんな目をさまして、ぶるぶるふるえながら、いぶかしそうにほしぞらを見あげました。
夜だかは、どこまでも、どこまでも、まっすぐに空へのぼって行きました。
もう山焼けの火はたばこの吸殻のくらいにしか見えません。
よだかはのぼってのぼって行きました。
寒さにいきはむねに白く凍(こお)りました。
空気がうすくなった為に、はねをそれはそれはせわしくうごかさなければなりませんでした。
それだのに、ほしの大きさは、さっきと少しも変りません。つくいきはふいごのようです。
寒さや霜がまるで剣のようによだかを刺しました。
よだかははねがすっかりしびれてしまいました。
そしてなみだぐんだ目をあげてもう一ぺんそらを見ました。
そうです。これがよだかの最後でした。
もうよだかは落ちているのか、のぼっているのか、さかさになっているのか、上を向いているのかも、わかりませんでした。
ただこころもちはやすらかに、その血のついた大きなくちばしは、横にまがっては居ましたが、たしかに少しわらって居りました。
それからしばらくたってよだかははっきりまなこをひらきました。
そして自分のからだがいま燐(りん)の火のような青い美しい光になって、しずかに燃えているのを見ました。
すぐとなりは、カシオピア座でした。天の川の青じろいひかりが、すぐうしろになっていました。
そしてよだかの星は燃えつづけました。いつまでもいつまでも燃えつづけました。
今でもまだ燃えています。
・















