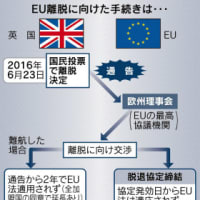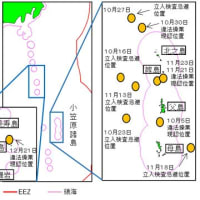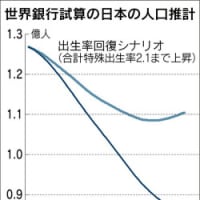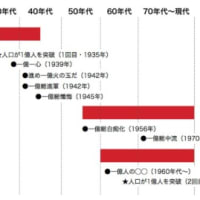『柔構造社会における学生の反逆』(「柔構造社会と暴力」(1971)所収)を分析しながら、「永井陽之助の現代政治社会論」を「成長から“成熟”への軌跡」と題してこれまで5回に亘って記事にしてきた。1回目は主題と副題に両方を並べて書き、2回目以降は、二つのタイトルのうち、どちらか一方を副題にしている。
その中では、経済成長による社会変動の結果として、「柔構造社会」「存在証明を与えない社会」「引きのばされた青春」が社会構造として顕れた。また、E・H・エリクソンの自我心理学の概念、「ライフサイクル」「アイデンティティ」「モラトリアム」がその社会構造に起因するキーワードとして登場した。
では、経済成長の経済社会的な過程と帰結はどうなのか?
それに対する経済学者からの代表的な答が吉川洋「高度成長―日本を変えた六000日」(1967読売新聞社)だ。最近、中公文庫から再度出版(2012年)され、廉価で購入可能になった。
筆者は本を読むとき、先ずは腰帯、カバーから始めて、目次、あとがき、解説、文献等の周辺部分をサッと読み、ある程度、本の内容についてイメージを造る。本書は、巻末に歴史書必須の年表を、それも詳しく書いている。また、文献も豊富に紹介しており、この時代の基本文献となる資格は十分だ。
この本の「おわりに」は、副題「経済成長とは何だろうか」が、更に文庫版では「あとがき」として「経済成長とは何だろうか再論」が付けられている。この再論が全体のトーンを表していて面白い。
そこで吉川は当時、経済企画庁で活躍したエコノミスト・金森久雄氏による書評を取り上げる。ポジティヴな評価をもらったと云いながら、最後に書かれた金森の次の言葉にこだわりを見せる。
「この本のエピローグは「経済成長とは何だろう」という題で、自然破壊や心の変化などを挙げ、私たちにこの高度成長がもたらした変化を「進歩」だと自信をもって言い切れるだろうか、という疑問で結んでいる。もちろん、大進歩に決まっている。これほどいい本を書いた著者が、エフェミネイトな感傷で本書を締めくくったのは、やや残念だ」(エコノミスト1997年1月号P98)。
学生時代の雑談のときだったと思うが、経済学者・エコノミストの中で誰を一番信頼するか、という話になって、永井陽之助は「僕は金森久雄、なんと言っても、予測が当たるから」と答えた。
永井にとって、理論仮説とそこから導き出す予測の当否は学者を判断する重要なポイントだった。これは「多極世界の構造」で述べられている。
戻って、吉川(1951年生まれ)は少年時代を振り返って、「毎日体いっぱい「大進歩」を感じとっていた」と文庫本・あとがきで述べる。しかし、この本を書いた四十年代後半のときは、「経済成長に対してアンビヴァレントな感情を持つようになっていた」とも言って、金森に答える。
筆者(1948年生まれ)も前半は吉川と同感だ。しかし、後半は吉川に対してアンビヴァレントな感情を持つ。経済成長から派生してきた現象は多くの問題を新たに提起しているが、それは新たな課題として考える以外にないからだ。
その中では、経済成長による社会変動の結果として、「柔構造社会」「存在証明を与えない社会」「引きのばされた青春」が社会構造として顕れた。また、E・H・エリクソンの自我心理学の概念、「ライフサイクル」「アイデンティティ」「モラトリアム」がその社会構造に起因するキーワードとして登場した。
では、経済成長の経済社会的な過程と帰結はどうなのか?
それに対する経済学者からの代表的な答が吉川洋「高度成長―日本を変えた六000日」(1967読売新聞社)だ。最近、中公文庫から再度出版(2012年)され、廉価で購入可能になった。
筆者は本を読むとき、先ずは腰帯、カバーから始めて、目次、あとがき、解説、文献等の周辺部分をサッと読み、ある程度、本の内容についてイメージを造る。本書は、巻末に歴史書必須の年表を、それも詳しく書いている。また、文献も豊富に紹介しており、この時代の基本文献となる資格は十分だ。
この本の「おわりに」は、副題「経済成長とは何だろうか」が、更に文庫版では「あとがき」として「経済成長とは何だろうか再論」が付けられている。この再論が全体のトーンを表していて面白い。
そこで吉川は当時、経済企画庁で活躍したエコノミスト・金森久雄氏による書評を取り上げる。ポジティヴな評価をもらったと云いながら、最後に書かれた金森の次の言葉にこだわりを見せる。
「この本のエピローグは「経済成長とは何だろう」という題で、自然破壊や心の変化などを挙げ、私たちにこの高度成長がもたらした変化を「進歩」だと自信をもって言い切れるだろうか、という疑問で結んでいる。もちろん、大進歩に決まっている。これほどいい本を書いた著者が、エフェミネイトな感傷で本書を締めくくったのは、やや残念だ」(エコノミスト1997年1月号P98)。
学生時代の雑談のときだったと思うが、経済学者・エコノミストの中で誰を一番信頼するか、という話になって、永井陽之助は「僕は金森久雄、なんと言っても、予測が当たるから」と答えた。
永井にとって、理論仮説とそこから導き出す予測の当否は学者を判断する重要なポイントだった。これは「多極世界の構造」で述べられている。
戻って、吉川(1951年生まれ)は少年時代を振り返って、「毎日体いっぱい「大進歩」を感じとっていた」と文庫本・あとがきで述べる。しかし、この本を書いた四十年代後半のときは、「経済成長に対してアンビヴァレントな感情を持つようになっていた」とも言って、金森に答える。
筆者(1948年生まれ)も前半は吉川と同感だ。しかし、後半は吉川に対してアンビヴァレントな感情を持つ。経済成長から派生してきた現象は多くの問題を新たに提起しているが、それは新たな課題として考える以外にないからだ。