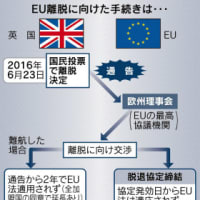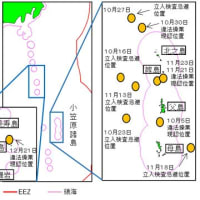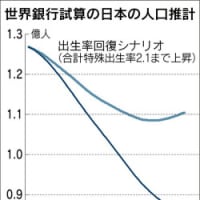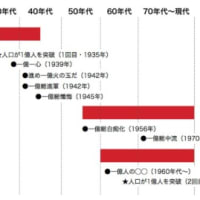理研のSTAP細胞に関する発表のなかで、『…生後の体細胞は、細胞の分化が既に運命づけられており、…』と書かれているのに驚いたと昨日の記事に書いた。
『運命を変えられたSTAP細胞たち140204』
但し、揶揄するつもりではなく、こういう言葉を使わなければ表現できないほどの、研究者としての驚きと喜びが含まれていることを想像させる言葉とも受け取った。それが感動をもたらしてくれたのだが、それでも驚きは大きかった。
一つは「神」を想像させ当然、絶対的な真理を響かせる言葉であるから、科学的な現象で用いられることは無いと無意識に思っていたのだろう。関連して、もう一つは科学の考え方からこれを翻訳すると「確率ゼロ」になると考えたからだ。
しかし、初期化可能ということであれば、分化状態のどこかの過程までは、<可逆反応>であって、引き返しができることになる。それは、昔話の「若返りの水」、おばあさんが赤ちゃんに戻る話、になるのだ。実験結果によれば、酸性溶液がその「水」にあたるのだ。
それはさておき、初期化不可能性は<非可逆反応>とでも言っておけば良かったのだ。しかし、生物であって、未だ神秘性を帯びている細胞の分化状態における画期的な知見を表現するのは、インパクトの強い表現を必要とする。
それは、別の意味でこの限られた分野が、その中にいる研究者の意識を高揚させている状態を示しているとも見えるのだ。「運命」という表現を用いるだけの士気の高さを有する研究集団が現にいるということだ。
その気持ちを自分で考えているうちに、私たちが日常的に使う「運命」という言葉と、生命科学の中で使う「運命」が、互いに重なる部分もありながら、異なる意味合いを含むことに思い当たった。それは日常的世界と科学的世界との違いと言って良い。画期的な科学的成果の公表を示す文章が、科学的世界から日常的世界への橋渡しを行う際に、その言葉を含んでいたのだ。
そこで想い起こしたのが「日常言語と理論言語(科学言語)との間には、何らかのかたちでの橋渡し、繋ぎ手が存在している」との村上陽一郎氏の指摘だ(『科学と日常性の文脈』海鳴社P153)。
高いレベルでの理論言語は「仲間内言語」(jargon)として流通する。従って、閉鎖性・専門性は高いのだが、それが日常レベルまで降りてきたときには対応語ができるはずだ。それが無ければ、流通性に欠けることにならからだ。生命科学の中の「運命」という言葉も、どちらにも通用する言葉だ。
では、今後はどうするのか?小保方さたちの発見により、細胞は必ずしも運命づけられていなかったと言って良いのだろうか。即ち、確率ゼロの世界ではなくなったのだ。しかし、世の中に存在する細胞が、stap細胞になる確率は、圧倒的にゼロに近いのだ。
日常言語的には「運命づけられている」と言っても良い。それは日常言語が曖昧さを含み、多義性を有するからだ。また、日常的環境では、可逆的に初期化を起こすわけではない。しかし、厳密な定義のもとで使用される科学言語は、曖昧さを許さない。
今後はどんな環境において何が起こるか?の問題になる。運命づけられていない部分の世界を明らかにする競争が発生してしまった以上は、科学的世界での「運命」は、今後は使うことが稀な世界へと変わっていかざるを得ない。しかし、高められた士気は継続されていくことは確かであろう。
『運命を変えられたSTAP細胞たち140204』
但し、揶揄するつもりではなく、こういう言葉を使わなければ表現できないほどの、研究者としての驚きと喜びが含まれていることを想像させる言葉とも受け取った。それが感動をもたらしてくれたのだが、それでも驚きは大きかった。
一つは「神」を想像させ当然、絶対的な真理を響かせる言葉であるから、科学的な現象で用いられることは無いと無意識に思っていたのだろう。関連して、もう一つは科学の考え方からこれを翻訳すると「確率ゼロ」になると考えたからだ。
しかし、初期化可能ということであれば、分化状態のどこかの過程までは、<可逆反応>であって、引き返しができることになる。それは、昔話の「若返りの水」、おばあさんが赤ちゃんに戻る話、になるのだ。実験結果によれば、酸性溶液がその「水」にあたるのだ。
それはさておき、初期化不可能性は<非可逆反応>とでも言っておけば良かったのだ。しかし、生物であって、未だ神秘性を帯びている細胞の分化状態における画期的な知見を表現するのは、インパクトの強い表現を必要とする。
それは、別の意味でこの限られた分野が、その中にいる研究者の意識を高揚させている状態を示しているとも見えるのだ。「運命」という表現を用いるだけの士気の高さを有する研究集団が現にいるということだ。
その気持ちを自分で考えているうちに、私たちが日常的に使う「運命」という言葉と、生命科学の中で使う「運命」が、互いに重なる部分もありながら、異なる意味合いを含むことに思い当たった。それは日常的世界と科学的世界との違いと言って良い。画期的な科学的成果の公表を示す文章が、科学的世界から日常的世界への橋渡しを行う際に、その言葉を含んでいたのだ。
そこで想い起こしたのが「日常言語と理論言語(科学言語)との間には、何らかのかたちでの橋渡し、繋ぎ手が存在している」との村上陽一郎氏の指摘だ(『科学と日常性の文脈』海鳴社P153)。
高いレベルでの理論言語は「仲間内言語」(jargon)として流通する。従って、閉鎖性・専門性は高いのだが、それが日常レベルまで降りてきたときには対応語ができるはずだ。それが無ければ、流通性に欠けることにならからだ。生命科学の中の「運命」という言葉も、どちらにも通用する言葉だ。
では、今後はどうするのか?小保方さたちの発見により、細胞は必ずしも運命づけられていなかったと言って良いのだろうか。即ち、確率ゼロの世界ではなくなったのだ。しかし、世の中に存在する細胞が、stap細胞になる確率は、圧倒的にゼロに近いのだ。
日常言語的には「運命づけられている」と言っても良い。それは日常言語が曖昧さを含み、多義性を有するからだ。また、日常的環境では、可逆的に初期化を起こすわけではない。しかし、厳密な定義のもとで使用される科学言語は、曖昧さを許さない。
今後はどんな環境において何が起こるか?の問題になる。運命づけられていない部分の世界を明らかにする競争が発生してしまった以上は、科学的世界での「運命」は、今後は使うことが稀な世界へと変わっていかざるを得ない。しかし、高められた士気は継続されていくことは確かであろう。