『死者の書』といえば、私でさえエジプトの『死者の書』を思い出す。ならば、折口の『死者の書』はエジプトのそれとどういう風に関わっているのだろうか。ジェフリーさんは序文の中で、「エジプトの甦りの神話」(The Egyptian Myth of Resurrection)という章を設けて、様々な説について紹介している。この章でジェフリーさんは紹介者的な位置に止まっているので、私としてもそれをそのまま紹介することになる。
エジプトの『死者の書』の西欧圏における決定訳は、A・ウォーリス・バッヂが1889年に初版を出し、1909年に改訂版を出していて、1920年には田中達という人がそれを日本語に翻訳している。バッヂの本は広く読まれ、影響を与えたようで、ジェイムズ・フレイザーの『金枝編』の主要な源泉になっているというし、ジェイムズ・ジョイスはそれを『フィネガンズ・ウェイク』の構成に借りているという。知らなかった。
アンソニー・V・リーマンという人は、エジプトの『死者の書』と折口の小説がいくつかのライトモチーフを共有していることを指摘しているという。それは、太陽の輝きと神性との間の関連、西方の神聖な土地の存在、そして人間が甦った肉体において神々に合一することが出来るという信仰である。
さらに、エジプトのオシリスとイシスの神話は、折口の大津皇子と藤原南家郎女の物語とパラレルであるという。オシリスは兄弟の裏切りによって殺され、切り刻まれた体はエジプト中に散り撒かれたのだし、大津皇子もまた処刑後、彼が愛した都から遙かに遠い辺境の地に埋葬された。
そして優しく無私の女神、イシスがオシリスの体を集め、布でつなぎ合わせたように、藤原南家郎女は彼女が幻視した、裸の阿弥陀ほとけの体を温めてあげようと、蓮の繊維で巨大な布を織り上げるのである。オシリスがイシスによって甦るように、折口は大津皇子の幽霊を登場させることで、彼を存在の次の領域へと移行させるのである。
折口の『死者の書』というタイトルは、田中達の翻訳のタイトルと同じであり、折口がエジプトの『死者の書』を参考にしなかったはずはない。また、折口の『死者の書』初版には、エジプトのミイラとその頭の上で羽ばたく人間の頭を持った鳥の図が描かれていたという。その鳥は"ba"といって人間の魂を表しているという。
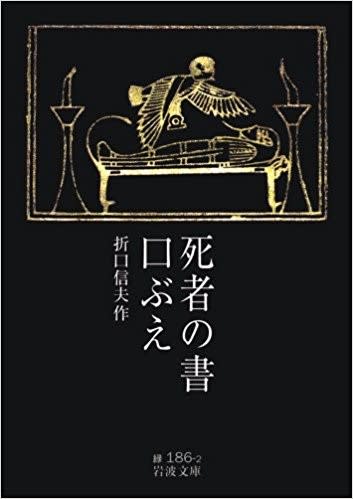
岩波文庫版の装幀に使われている
以下は安藤礼二の『光の曼荼羅』の折口論による解説となっている。安藤は折口の愛人の一人であった、藤無染(ふじむぜん、ジェフリーさんの英語ではFuji Musen)が参加していた仏教改革運動と折口の思想との関連を指摘しているという。藤と折口は、異なった宗教伝統間の融合を図り、世界中の宗教的観念や動機を跡づけることを追求した、一連の思想家たちに興味を持つようになっていったという。
1905年に藤無染が編集した『二聖の福音』という本は、ゴータマ・シッタルダとイエス・キリストの生涯や教えに大きな共通点を見ようとするもので、藤はキリスト教の基本的な観念を引き起こしたのは仏教であると信じる思想家グループの一人であった。
また、浅田隆という学者は『死者の書』において、藤原南家郎女が二上山の間に幻視する神秘的な存在が、黒髪の日本的な男ではなく、よその国から来た金髪で色白の男であることに注意を向ける。それは第4章に藤原南家郎女の見た姿として綴られているが、その部分のジェフリー訳を読んでみよう。
He didn't look like he could possibly be from here in Yamato, but perhaps there were men somewhere in the country who looked like that but whom she hadn't encountered yet. The locks of hair that fell from his temples were the color of gold. His golden hair fell in rich abundance around his fair, white skin, which extended downward toward his beautiful, exposed shoulders.
この部分近藤よう子の漫画版では、二上山の間にそびえ立つ金髪の西洋人の姿に描かれていて、異様にリアルである。それはほとんどキリスト像のようでさえあり、折口の原文からもそれが阿弥陀ほとけであるとはとうてい窺い知ることが出来ないのである。

近藤よう子版『死者の書』より
そこには明らかに仏教的ではないもの、異教的なものが存在している。しかし、仏教とキリスト教がお互いにとって異教であるとすれば、そうではなく、世界宗教的な観念がヨーロッパ的なイコンに写し取られているとでも言ったらいいのだろうか(ここに折口の西洋的な美男子に対する同性愛的な憧れを見るひともいる)。
だから『死者の書』は決して、中将姫の伝説のような仏教説話に止まることがない。より普遍化された生と死と再生の物語でそれはある。
安藤礼二はさらに、仏教改革運動のもう一人の人物、大原嘉吉が1894年に訳した、ジェラルド・マッシーの本にも触れている。マッシーはイエス・キリストの生と死、そして復活の物語はエジプトの神話のモチーフに由来していると言っているという。
また、エリザベス・アンナ・ゴードンという日本に長く住み、キリスト教徒ネストリアニズム(古代キリスト教の教派のひとつ、ネストリウス派の教義。中国に渡って景教)そして空海が中国から持ち帰った秘教的教えの共通性について書いた。安藤は藤無染と折口が彼女の思想に触れることがあったのではないかと推測している。
この後ジェフリーさんの議論は、安藤礼二の『光の曼荼羅』そのものへと進んでいくのだが、煩瑣になるので省略する。とにかくジェフリーさんは、この長い序文で『死者の書』への彼自身の新しい解釈を示すと同時に、それが今日どのように読まれているかについても、目配りの聞いた紹介を行っている、大変読み応えのある序文である。
(この項おわり)










