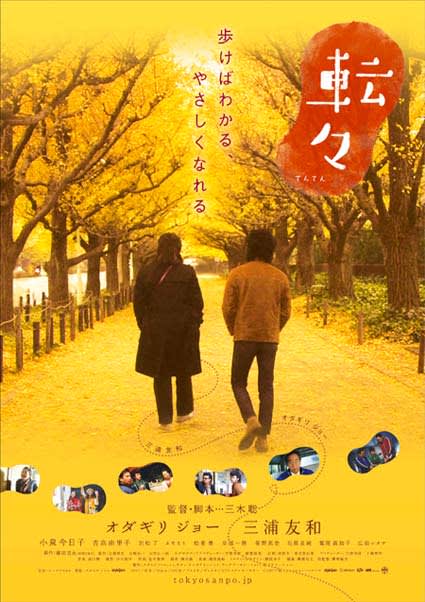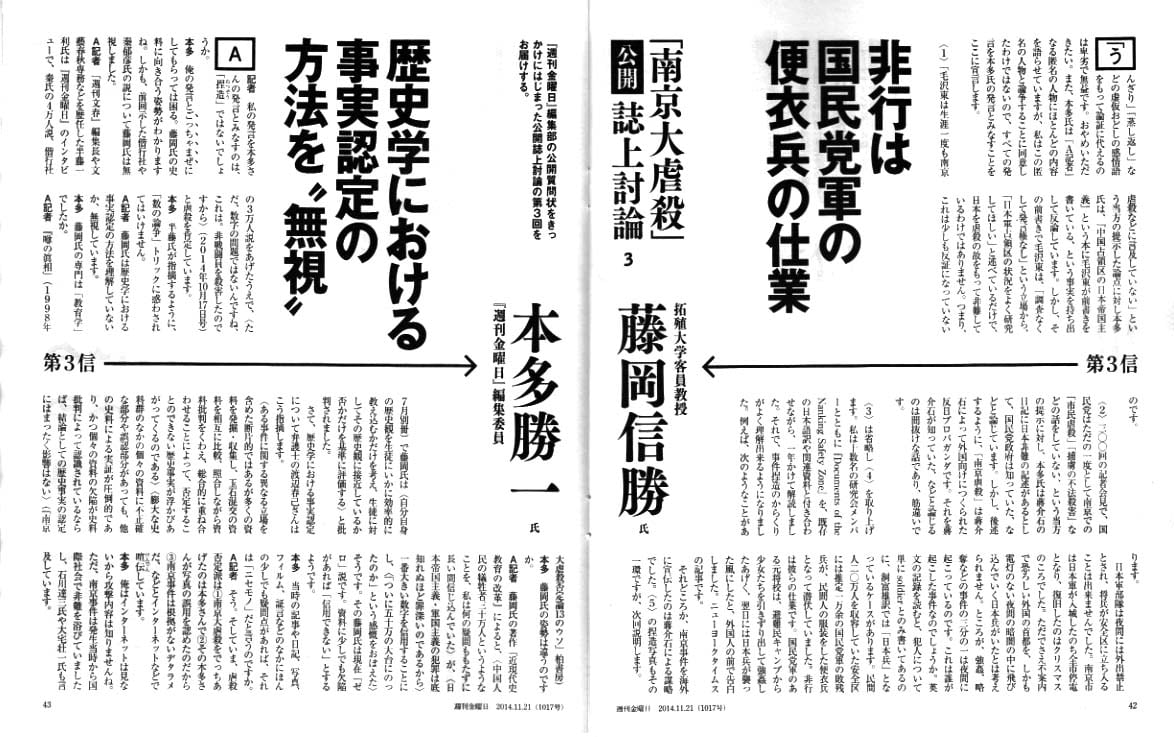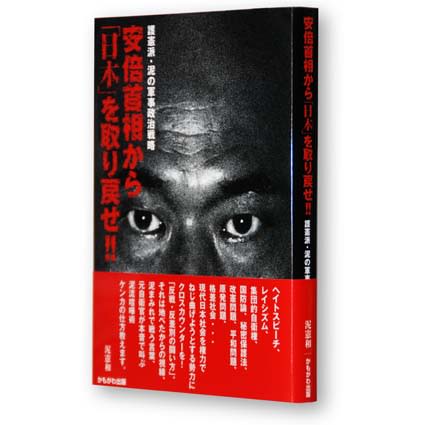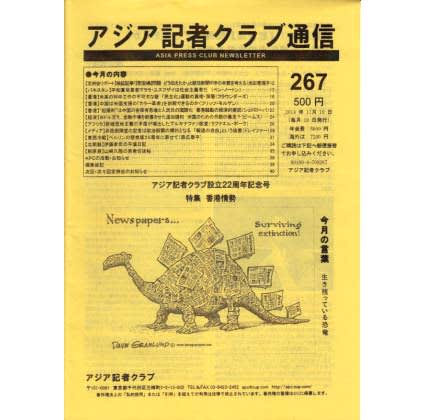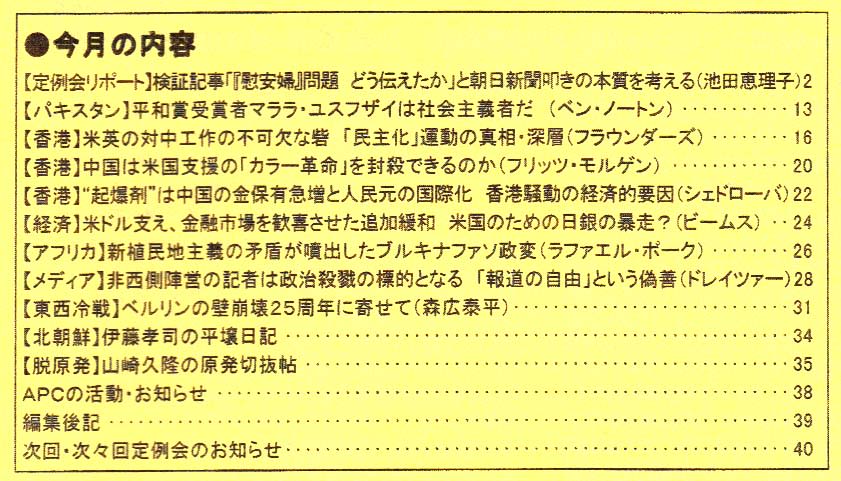渡辺淳一の大ヒット作『失楽園』のドラマ版がDVD解禁され、宝島社から発売された。CS放送の日テレプラスでも、24日から放送される予定だ。
理由はわからないがこのドラマ、何度かDVD化が発表されては立ち消えになっていた。
R指定のない地上波連ドラで、濃密なシーンをたっぷり含んでいれば、今の放送倫理規定にはそぐわないのかもしれない。R指定の後付は聞いたことがないから、放送も販売もどうすべきか判断に苦しんだのだろう。ただし、視聴者が限定されるCS放送であれば、法に触れない範囲で放送可能ということなのだ。
過去のテレビドラマはヌードシーンやベッドシーンは当たり前で、ほとんど問題になったことはなかった。それがいつのまにか規制がきびしくなり、地上波の放送で女性のバスとトップさえ自粛するようになってしまった。写真集などを紹介するときに、司会者が一部を手で隠したり修正をかけたりするのはかえって不自然だと思うのだが。
しかし、ドラマ版『失楽園』が、長くDVD化されなかった本当の理由はわからない。
それにしても、現在のテレビ界の規制は異常だ。障害者を扱ったドラマも、かなり台詞や映像に注意して作らなければならないと聞く。それでも、「どうしてそんなことが」と思われるような当たり障りのない言葉がクレームの対象になったりするそうで、その度にプロデューサーやディレクターが始末書を書かされるそうだから、たまったものではないだろう。
もっとも、障害者問題でクレームをつけてくる大半は、障害者本人ではなく健常者だというから、それもまたふしぎなことである。
渡辺淳一という作家は、エロチシズムをテーマにしていながら、女性のファンが非常に多い。いや、この発言は差別的だ。エロスを好むのが男性ばかりと思うのは女性に対する偏見である。
評判になった役所広司、黒木瞳主演の映画『失楽園』には、女性ファンが殺到したと聴く。

で、映画の『失楽園』はずっと前に見たことがあって、噂ほどではないと感じた。売り物のベッドシーンは薄暗くてよく見えず口ほどでもないし、ストーリーに至っては上映時間に合わせるためにかなりはしょっていて、脚本が無理をしている印象だった。
ドラマ版の『失楽園』はリアルタイムでは観ていない。今回DVDではじめて観た。放送当時、だれだったか女性評論家のような人物が「川島なお美の安い裸」などと評していたのは覚えている。
それが先頃、ホームドラマチャンネルで2時間に再編集した特別版を見ることができた。これはただ単にドラマを短縮しただけでなく、イタリアロケなどのオリジナルシーンを多く含んでいるものだ。そこに出てくる川島なお美が、「安い裸」どころか超一級品であることに驚いた。雰囲気も演技(このドラマに関してだけだが)も観賞素材としての肉体も実に見事だ。人により好みはあるだろうが、客観的に観て黒木瞳を凌駕していると感じた。僕自身はどちらのファンでもない。
そこで、これは一度ドラマ本編を見ておきたいと思っていたら、運良く発売されたというわけだ。しかも非常に安価。(そう言った意味では安い裸だった=冗談である)
テレビドラマは、合計で約10時間ほどあり、詳細な人間関係や両方の家族内のさまざまな問題などがよく描かれている。2時間程度でおさめなければならない劇場映画では不可能だ。
川島なお美演じる松原凛子の夫春彦(国広富之)は、ことあるごとに社会倫理や勤務する病院での立場を口にする。凛子の母親をはじめとした周囲の人間たちの口からは、「ふしだら」とか「汚らわしい」といった言葉が連発される。僕が最も嫌う人間たちだ。既存の常識や周囲の評判に振り回される人間は、軽蔑に値する。
原作は読んでいないからわからないが、ドラマを観て感じることは、久木と凛子のやっていることが、「ふしだら」とか「汚らわしい」というののしり言葉で安易に非難すべきでないということだ。既婚者同士がそれぞれ別の男女と恋愛することは、今の社会では「不倫」と言われ、社会的に非難される。しかしそれでも、「不倫」をする男女は後を絶たない。いったいなぜなのか。
それはただの遊びの場合もあるだろうし、本気の場合もあるだろう。理由もきっかけもさまざまであるに違いない。それを「不倫」という言葉で一括りにし、社会秩序から外れているとか、ふしだらなどという理由で非難するのは、いったい誰のため、何のためだろうか。
人間は永遠に変わらない生き物ではない。当初はうまくいっていた関係が、時とともに変化してどうにも修復できない状態になる場合も当然ある。問題は、一方がそう感じていながらもう一方は現在の関係に固執している状況だ。『失楽園』での久木と凛子はまさにそれである。
男女の関係は、両方が納得しなければうまくいかない。未婚の男女なら何の問題もないが、不幸なのは夫婦同士の片思いである。紙切れ一枚で法律で夫婦と定められると、愛情が冷めてしまっても容易に別れることができなくなる。無理に別れれば必ずといっていいほどしっぺ返しが来る。
だれが決めたかわからない規則や社会常識がまかり通る世の中では、離婚は社会的立場を悪くする原因になるのだ。また、離婚した女性、とくに専業主婦は、離婚した瞬間から経済が成り立たなくなる。日本のような男性中心社会ではとくにそうだ。こうした理由で、愛情が冷めたにもかかわらず表面的には夫婦を演じている「仮面夫婦」がけっこう多いと聞く。
長い人生を我慢し続けて生きなければならないとすると、それは男女ともに不幸なことではないだろうか。
『失楽園』はパラレルワールドである。最後は社会のしがらみを突破できずに死を選んでしまうのだが、二人は結局もとに戻ることはなかった。戻ることは不幸の巻き戻しでしかないからだ。だが、二人が生き続けるには、あまりにも世間の風当たりは冷たかったのだ。
それでも、久木と凛子の二人をうらやましいと感じた男女は、決して少なくはなかったのではなかろうか。結婚外での恋愛の多くは、結局あきらめて別れることになり、やがてただの浮気で片付けられる。それが現実であり、パラレルワールドの第一層だ。そして第二層が久木と凛子の世界である。もしその上の第三層に二人が生きたなら、関わるすべての人も含めて新たな幸福を得ているのではないだろうか。
第三層はあくまで自由であり、社会が取り決めた不合理な道徳や秩序に縛られることはない。そういう世界は全人類の意識が変化しないかぎり不可能なのかもしれない。
パラレルワールドなるものが存在するのであればの話だ。
以前、若松孝二監督が某女性国会議員から「あなたが作った不潔でふしだらな映画を、私は決して観ません」といわれ、「不潔でふしだらなことを、あなたは決してしないのですね」と切り返したというエピソードを聞いたことがある。真実かどうかは定かでないが、本当なら実に見事だ。