*以下の文章は、シュバイツァー寺ホームページほか関連資料を基に書きまとめました。福岡事件の概要と、再審請求運動の歴史について把握する一助にしてもらえれば幸いです。(文責・レイランダー)
*文章中、人物の敬称は略させてもらいました。
福岡事件とは何か
1947(昭和22年)年5月20日、夕闇暮れる福岡市堅粕(博多区)の路上で、中国人と日本人、2人の商人が殺された。庶民がインフレと物資の欠乏にあえぎ、ヤミ流れの食糧や日用品に頼って生きていた、敗戦後の混乱期である。
警察は軍服のヤミ取り引きに絡む「強盗殺人事件」として捜査を開始、現金を持ち去ったとされる西武雄(32)を主犯、2人を撃った石井健治郎(30)を実行犯、他5名を共犯として逮捕した。
西武雄は魚の買い付け・卸売りで一財を成した、今で言う「青年実業家」だった。若くして風格があり、親分肌を見込まれて取り引き物資の持ち主役を依頼されたのだが、石井とは事件の2時間前に会ったのが初対面だったという。持ち去ったとされる現金は手付金として預かっていたもので、事件によって取り引きがご破算になってしまっては、返却を要しない金と考えるしかないものだった。
石井健治郎は戦時中、大陸において数々の命の瀬戸際をくぐり抜けてきた。ノモンハンにおける「人間爆弾」(陸軍の特攻兵器)の生き残りでもあり、射撃の名手だった。終戦後、虚無感漂う祖国に舞い戻り、占領軍関係に物資を動かすブローカーとして危ない橋を渡りながら、この事件にも関わることになったのである。持って生まれた気の強さ、大胆さなどはあるにしても、発砲事件を引き起こした石井の性格の相当な部分は、戦争によって形成されたものと言えないだろうか。
逮捕後、石井は2人の射殺をすぐに認めたが、過剰防衛による誤殺であり強盗目的ではなかったと主張。もとより殺人現場にいなかった西は、強盗殺人の計画も実行も全面否認、軍服取り引きと殺人事件とは無関係であると訴えた。
しかし、石井の射殺した片方の中国人が華僑の重鎮であったことが、取調べや裁判に大きな影響を及ぼす。
当時の日本は独立国でなく、占領下である。戦勝国の華僑の大物を殺した者を厳罰に処しなければ、事件は政治問題化する恐れがあった。裁判には在日中国人の傍聴者が多数押しかけ、「死刑」を要求するシーンもあったという。この時期、戦勝国である国民党系の中国人は、戦時中の日本軍への恨みもあり、意気盛んだった。
またそれ以前に、予断に基づくずさんな捜査や、激しい拷問を含む強引な取調べは、軍隊上がりのならず者を一掃すべしという、占領軍の意向を反映したものでもあった。戦時中は国家のしもべとして「敵性国民」を吊るし上げていた警察は、今や占領軍のしもべとして「反抗分子」「不良国民」の摘発に躍起になっていた。西や石井のような人間が、戦時中いかに国家に奉仕しようとも、警察権力から見れば無価値で有害なヤクザに過ぎなかったのである。
いずれにしろ「強盗殺人」のストーリーは、西を首謀者とし、石井を殺人請負人としなければ成り立たない。裁判では2人の主張は一切取り上げられず、単純な警察側の事実誤認も省みられず、現代日本においても絶えることのない「冤罪」の構図のすべてが粛々と完成させられていった。事件から9年後の1956年、最高裁で上告が棄却、2人は強盗殺人罪での戦後初の死刑囚となった。
福岡拘置所に32歳の僧侶、古川泰龍(のち生命山シュバイツァー寺開山)が教誨師として着任したのは1952年(昭和27年)のことだった。やがて獄中で西と石井に出会い、これが古川の人生を変える。
古川はもと真言宗の僧侶だったが、独特の生命観・宗教観を持った、宗派にこだわらない実践者だった。彼は死刑囚たちを「共に生死解脱の道を求めて励まし合う同行の仲」とするほどに、教誨の職に打ち込んでいたという。
そんな古川は、西、石井2人の訴えを聴くうちに、冤罪の疑いを強く持ち始めた。独自の調査を進め、ついに冤罪を確信し、1961年(昭和36年)、本格的に助命再審運動に乗り出した。
翌年、原稿用紙2千枚にのぼる「福岡事件真相究明書」を書き上げ、自費で出版。時の法務大臣に送るほか、宗教者・文化人にも支援を求めて配った。以後、国会請願のための托鉢行脚、街頭署名活動を全国に展開、再審請求の運動に没頭していく。家族の生計は圧迫され、水道代・電気代も払えないほどに困窮しながら、草の根の支援者の手を借りながら続けられた運動だった。
その甲斐あって、福岡事件は国会で取り上げられ、戦後の混乱期の裁判を見直し、再審を促す法案提出にまでこぎつける。社会党議員主導によるこの法案は、結局は立法化には至らなかった。しかし、時の西郷法務大臣は法案の趣旨を汲み、恩赦の運用によってこれに代えると約束した。
冤罪をはらすという宿願には達しないながらも、命を助けることだけはどうやらできたと、古川ら支援者は安堵した。再審請求に乗り出してから8年目のことである。
それから5年後の1975年(昭和50年)6月17日、古川は恩赦審議促進の托鉢のため、東京に滞在していた。その日、遠く離れた福岡拘置所で、西は突然恩赦却下を言い渡され、その20分後、処刑されてしまった。
同日、石井は恩赦により無期懲役に減刑、熊本刑務所に移された。
法務省はなぜ、実行犯の石井には与えた恩赦を、あくまで西には与えなかったのだろうか?
そこには「冤罪」という概念だけでは説明できない、国家の論理の深い作用が垣間見える。恩赦という発想は、国家がその威信を保ちつつ、国民との決して損にはならない妥協をする、という程度の意味でしかなかったのではないか。それゆえ、あからさまに人を殺した石井には(その罪ゆえに)恩赦を与えると同時に、判決の根幹を揺るがす「無実の」西には、速やかに「退場」願う。つまり西は、事件の裁判においてと、そして再審を阻む国の思惑においてと、二度までも国家の都合に合致しないがゆえに切り捨てられた。
それゆえこの事件は、戦後冤罪事件の原点であるだけでなく、今に続く、死刑制度を維持し続けることの矛盾と無意味と残虐の原点でもあるのではないか。
「一卵性双生児」とまで感じていた西を失った古川泰龍は、1年間は茫然自失の日々が続いたという。だがやがて身を立て直し、日本裁判史上初の、死刑執行後の再審請求に乗り出す。
1995年(平成7年)、古川は西武雄が心痛を忍んで絶縁した遺族の消息をつかみ、遺族から再審請求を起こす委任状が託された。1998年には膨大な事件公判資料の写しを入手、再審請求のための困難な書類作成を進めた。同じ年、ルーマニアの首都ブカレストで開かれた世界宗教者会議に招かれた古川は、映画『デッドマン・ウォーキング』の原作者、シスター・ヘレン・プレジャンに出会う。シスター・ヘレンは古川の思想と活動に深く共鳴し、再審請求応援のための来日を約束してくれた。しかし2001年、シスターが初めてキャンペーンのために日本の地を踏んだのは、古川が逝った翌年だった(その後もシスターは2002年、2005年、2007年と、通算4度にわたってキャンペーンに参加している)。
古川が逝去して後は、その家族が運動を引き継いだ。2005年には「福岡事件弁護団」の協力の下、西武雄の遺族と、42年7ヶ月の拘禁を経て仮出所した石井らによって、40年ぶりの再審請求が福岡高裁に対して行なわれ、現在もこれを審理中である。
*文章中、人物の敬称は略させてもらいました。
福岡事件とは何か
1947(昭和22年)年5月20日、夕闇暮れる福岡市堅粕(博多区)の路上で、中国人と日本人、2人の商人が殺された。庶民がインフレと物資の欠乏にあえぎ、ヤミ流れの食糧や日用品に頼って生きていた、敗戦後の混乱期である。
警察は軍服のヤミ取り引きに絡む「強盗殺人事件」として捜査を開始、現金を持ち去ったとされる西武雄(32)を主犯、2人を撃った石井健治郎(30)を実行犯、他5名を共犯として逮捕した。
西武雄は魚の買い付け・卸売りで一財を成した、今で言う「青年実業家」だった。若くして風格があり、親分肌を見込まれて取り引き物資の持ち主役を依頼されたのだが、石井とは事件の2時間前に会ったのが初対面だったという。持ち去ったとされる現金は手付金として預かっていたもので、事件によって取り引きがご破算になってしまっては、返却を要しない金と考えるしかないものだった。
石井健治郎は戦時中、大陸において数々の命の瀬戸際をくぐり抜けてきた。ノモンハンにおける「人間爆弾」(陸軍の特攻兵器)の生き残りでもあり、射撃の名手だった。終戦後、虚無感漂う祖国に舞い戻り、占領軍関係に物資を動かすブローカーとして危ない橋を渡りながら、この事件にも関わることになったのである。持って生まれた気の強さ、大胆さなどはあるにしても、発砲事件を引き起こした石井の性格の相当な部分は、戦争によって形成されたものと言えないだろうか。
逮捕後、石井は2人の射殺をすぐに認めたが、過剰防衛による誤殺であり強盗目的ではなかったと主張。もとより殺人現場にいなかった西は、強盗殺人の計画も実行も全面否認、軍服取り引きと殺人事件とは無関係であると訴えた。
しかし、石井の射殺した片方の中国人が華僑の重鎮であったことが、取調べや裁判に大きな影響を及ぼす。
当時の日本は独立国でなく、占領下である。戦勝国の華僑の大物を殺した者を厳罰に処しなければ、事件は政治問題化する恐れがあった。裁判には在日中国人の傍聴者が多数押しかけ、「死刑」を要求するシーンもあったという。この時期、戦勝国である国民党系の中国人は、戦時中の日本軍への恨みもあり、意気盛んだった。
またそれ以前に、予断に基づくずさんな捜査や、激しい拷問を含む強引な取調べは、軍隊上がりのならず者を一掃すべしという、占領軍の意向を反映したものでもあった。戦時中は国家のしもべとして「敵性国民」を吊るし上げていた警察は、今や占領軍のしもべとして「反抗分子」「不良国民」の摘発に躍起になっていた。西や石井のような人間が、戦時中いかに国家に奉仕しようとも、警察権力から見れば無価値で有害なヤクザに過ぎなかったのである。
いずれにしろ「強盗殺人」のストーリーは、西を首謀者とし、石井を殺人請負人としなければ成り立たない。裁判では2人の主張は一切取り上げられず、単純な警察側の事実誤認も省みられず、現代日本においても絶えることのない「冤罪」の構図のすべてが粛々と完成させられていった。事件から9年後の1956年、最高裁で上告が棄却、2人は強盗殺人罪での戦後初の死刑囚となった。
福岡拘置所に32歳の僧侶、古川泰龍(のち生命山シュバイツァー寺開山)が教誨師として着任したのは1952年(昭和27年)のことだった。やがて獄中で西と石井に出会い、これが古川の人生を変える。
古川はもと真言宗の僧侶だったが、独特の生命観・宗教観を持った、宗派にこだわらない実践者だった。彼は死刑囚たちを「共に生死解脱の道を求めて励まし合う同行の仲」とするほどに、教誨の職に打ち込んでいたという。
そんな古川は、西、石井2人の訴えを聴くうちに、冤罪の疑いを強く持ち始めた。独自の調査を進め、ついに冤罪を確信し、1961年(昭和36年)、本格的に助命再審運動に乗り出した。
翌年、原稿用紙2千枚にのぼる「福岡事件真相究明書」を書き上げ、自費で出版。時の法務大臣に送るほか、宗教者・文化人にも支援を求めて配った。以後、国会請願のための托鉢行脚、街頭署名活動を全国に展開、再審請求の運動に没頭していく。家族の生計は圧迫され、水道代・電気代も払えないほどに困窮しながら、草の根の支援者の手を借りながら続けられた運動だった。
その甲斐あって、福岡事件は国会で取り上げられ、戦後の混乱期の裁判を見直し、再審を促す法案提出にまでこぎつける。社会党議員主導によるこの法案は、結局は立法化には至らなかった。しかし、時の西郷法務大臣は法案の趣旨を汲み、恩赦の運用によってこれに代えると約束した。
冤罪をはらすという宿願には達しないながらも、命を助けることだけはどうやらできたと、古川ら支援者は安堵した。再審請求に乗り出してから8年目のことである。
それから5年後の1975年(昭和50年)6月17日、古川は恩赦審議促進の托鉢のため、東京に滞在していた。その日、遠く離れた福岡拘置所で、西は突然恩赦却下を言い渡され、その20分後、処刑されてしまった。
同日、石井は恩赦により無期懲役に減刑、熊本刑務所に移された。
法務省はなぜ、実行犯の石井には与えた恩赦を、あくまで西には与えなかったのだろうか?
そこには「冤罪」という概念だけでは説明できない、国家の論理の深い作用が垣間見える。恩赦という発想は、国家がその威信を保ちつつ、国民との決して損にはならない妥協をする、という程度の意味でしかなかったのではないか。それゆえ、あからさまに人を殺した石井には(その罪ゆえに)恩赦を与えると同時に、判決の根幹を揺るがす「無実の」西には、速やかに「退場」願う。つまり西は、事件の裁判においてと、そして再審を阻む国の思惑においてと、二度までも国家の都合に合致しないがゆえに切り捨てられた。
それゆえこの事件は、戦後冤罪事件の原点であるだけでなく、今に続く、死刑制度を維持し続けることの矛盾と無意味と残虐の原点でもあるのではないか。
「一卵性双生児」とまで感じていた西を失った古川泰龍は、1年間は茫然自失の日々が続いたという。だがやがて身を立て直し、日本裁判史上初の、死刑執行後の再審請求に乗り出す。
1995年(平成7年)、古川は西武雄が心痛を忍んで絶縁した遺族の消息をつかみ、遺族から再審請求を起こす委任状が託された。1998年には膨大な事件公判資料の写しを入手、再審請求のための困難な書類作成を進めた。同じ年、ルーマニアの首都ブカレストで開かれた世界宗教者会議に招かれた古川は、映画『デッドマン・ウォーキング』の原作者、シスター・ヘレン・プレジャンに出会う。シスター・ヘレンは古川の思想と活動に深く共鳴し、再審請求応援のための来日を約束してくれた。しかし2001年、シスターが初めてキャンペーンのために日本の地を踏んだのは、古川が逝った翌年だった(その後もシスターは2002年、2005年、2007年と、通算4度にわたってキャンペーンに参加している)。
古川が逝去して後は、その家族が運動を引き継いだ。2005年には「福岡事件弁護団」の協力の下、西武雄の遺族と、42年7ヶ月の拘禁を経て仮出所した石井らによって、40年ぶりの再審請求が福岡高裁に対して行なわれ、現在もこれを審理中である。



















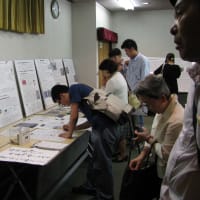
確かに旧刑訴法の時代とはいえ、日本国憲法は既に公布され、そこでは基本的人権の尊重という柱の下、拷問の禁止などがはっきり謳われています。しかるに両人が受けた取調べでの拷問は(逆さ吊りにして水に漬ける等)、明らかに憲法違反でもあったわけですね。
今の時代ならその自白は証拠には採用されないはずで、そうしたことからも、これを再審に付すことなく、また恩赦にするでもなく、途中放棄のような形で西さんを「片付けて」しまった国の責任は重大だと、個人的には感じています。その重大さを、少しでも多くの人に知ってもらうことが、再審への道を開くことにもなると。