カッコウは他の鳥の巣に卵を産みつけ、自分では子育てしません。「托卵」と呼ばれるこの不思議な習性が、日本では『万葉集』に詠まれ、ヨーロッパではもっと古くアリストテレスの『動物誌』に登場することは以前の記事でご紹介しました。
ただ当時は、宿主の卵を巣の外に放り出すのはカッコウの雌親の仕業と考えられていたようです。実際には、以下の動画のように、宿主の卵よりも早く孵化したカッコウのひなが自分で背負って排除します。
この驚くべき習性を発見して学会に発表したのは、エドワード・ジェンナーだそうです。ジェンナーといえば、ワクチンを発明して天然痘を根絶した医学界の偉人。その一方で、博物学者として昆虫や化石を収集しながら動物や植物を研究していたようです。渡り鳥の生態についても論文を発表しています。
生まれたばかりのカッコウのひなの行動を発表したのは1789年。その論文が認められて、エリート科学者の団体「ロイヤル・ソサエティ」の会員になっています。

エドワード・ジェンナー(画像はパブリックドメインン)
ところが、多くの人々はひながそんな行動をとるとは信じなかったようです。130年ほど後の1920年代に托卵行動の映像が公開されて、ようやく一般的にも認められるようになったとのこと。
私自身も本で托卵の話を読んでも信じられませんでしたが、NHKの番組を見て納得しました。百聞は一見に如かずとはこのことでしょう。
托卵行動の解明もワクチンの発明も、多分ジェンナーにとっては「真実を知りたい」という同じ好奇心からだったのでしょうね。
ただ当時は、宿主の卵を巣の外に放り出すのはカッコウの雌親の仕業と考えられていたようです。実際には、以下の動画のように、宿主の卵よりも早く孵化したカッコウのひなが自分で背負って排除します。
この驚くべき習性を発見して学会に発表したのは、エドワード・ジェンナーだそうです。ジェンナーといえば、ワクチンを発明して天然痘を根絶した医学界の偉人。その一方で、博物学者として昆虫や化石を収集しながら動物や植物を研究していたようです。渡り鳥の生態についても論文を発表しています。
生まれたばかりのカッコウのひなの行動を発表したのは1789年。その論文が認められて、エリート科学者の団体「ロイヤル・ソサエティ」の会員になっています。

エドワード・ジェンナー(画像はパブリックドメインン)
ところが、多くの人々はひながそんな行動をとるとは信じなかったようです。130年ほど後の1920年代に托卵行動の映像が公開されて、ようやく一般的にも認められるようになったとのこと。
私自身も本で托卵の話を読んでも信じられませんでしたが、NHKの番組を見て納得しました。百聞は一見に如かずとはこのことでしょう。
托卵行動の解明もワクチンの発明も、多分ジェンナーにとっては「真実を知りたい」という同じ好奇心からだったのでしょうね。

















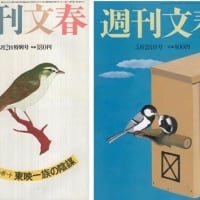
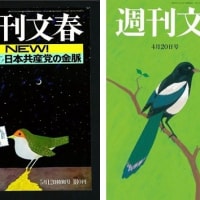





托卵について、このようなことをするまでの進化の過程からして私には想像を絶するものがあります。
今年はツツドリが何かの鳥(センダイムシクイか)に托卵しようとしている様子を耳で聞きました。
ツツドリは姿を見たのですが、それが消えた森の中から2羽の鳥が激しく鳴いているのが聞こえ、きっと抵抗していたのだと思いました。
そういうシーンは耳だけとはいえ接すると緊張しますね。
ツツドリの托卵らしきシーンを目撃されたのですか。そういう機会は少ないでしょう。私は遭遇したことがありません。
昔の人々はそういう経験をして、疑問を持って、托卵に気付いたんでしょうね。
先日、図書館に行ったら、『カッコウの托卵~進化論的だましのテクニック~』という新しい本がありました。つい最近発刊されたばかりで、カッコウの托卵を初めて録画した人の話や写真も掲載されていました。
ジェンナーのことはその本を読む前に知っていたのですが、その論文のことも詳しくかいてありました。