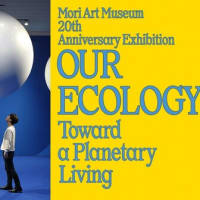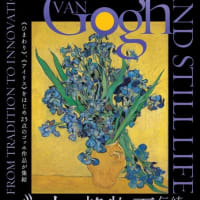アルフォンス・ミュシャ(1860‐1939)は、19世紀から20世紀への転換期に繊細なアールヌーボーのポスターで一世を風靡したが、後半生は一転してスラヴ民族の歴史を描いた連作「スラヴ叙事詩」の制作に没頭した。
チラシ(↑)に使われている作品はその第1作「原故郷のスラヴ民族」(部分)。異民族の侵入・略奪に遭い、スラヴ民族の男女が草むらに隠れている。その頭上を異民族が走り去る。左端にはスラヴ民族の村が焼き払われている。右上で宙に浮かんでいるのは、中央がスラヴ民族の祭司、右が‘平和’の擬人像、左が‘正義’の擬人像だ。
この作品は縦610cm×横810cmの大作だ(先に言ってしまうと、「スラヴ叙事詩」全20点はいずれも同規模のものだ)(※)。その前に立つと、大きさを実感する。だが、不思議なことに、威圧感はない。それは油彩とは異なるテンペラの感触、豊かな物語性、平和主義的なテーマ等の故だろう。
会場でこの作品を見たとき、わたしは「星がきれいだな」と思った。チラシでも確認できると思うが、大きく瞬いている星がいくつもある。実物を見ると、それ以外にも無数の星が小さい光を放っている。満天の星空だ。それらの星がスラヴ民族を見守っているように感じる。わたしは「なんて優しいんだろう」と思った。
以下の19点は、いずれもスラヴ民族の歴史上のエピソードを語っている。興味深い点は、第1作がそうであるように、主人公は英雄や偉人であるよりも、名もない庶民であることが多い点だ。例外的に英雄が中央に描かれている作品があるが、前景に疲れきった女性が大きく描かれ、その存在感が英雄を圧倒している。
もう一つ興味深い点は、第1作の男女のように、画中で起きている出来事と、それを見るわたしたちとをつなぐ‘仲介者’のような人物が、多くの作品に存在することだ。それは母親と子どもであったり、老人と青年であったりする。それらの場合は、次代に未来を託すメッセージが感じられる。
第1作は夜の情景だったが、その他オレンジ色の夕映え、明るい日盛り、嵐をはらんだ曇り空など、様々なヴァリエーションの空の描写が美しい。また野外だけではなく、教会や宮殿の内部の場合もあり、そこに差し込む光の描写が繊細だ。
連作全体を通して、ミュシャの圧倒的な力量と、それを人々のために使おうとする善意とが感じられた。
(2017.3.23.国立新美術館)
(※)「スラヴ叙事詩」全20点の画像(本展のHP)
チラシ(↑)に使われている作品はその第1作「原故郷のスラヴ民族」(部分)。異民族の侵入・略奪に遭い、スラヴ民族の男女が草むらに隠れている。その頭上を異民族が走り去る。左端にはスラヴ民族の村が焼き払われている。右上で宙に浮かんでいるのは、中央がスラヴ民族の祭司、右が‘平和’の擬人像、左が‘正義’の擬人像だ。
この作品は縦610cm×横810cmの大作だ(先に言ってしまうと、「スラヴ叙事詩」全20点はいずれも同規模のものだ)(※)。その前に立つと、大きさを実感する。だが、不思議なことに、威圧感はない。それは油彩とは異なるテンペラの感触、豊かな物語性、平和主義的なテーマ等の故だろう。
会場でこの作品を見たとき、わたしは「星がきれいだな」と思った。チラシでも確認できると思うが、大きく瞬いている星がいくつもある。実物を見ると、それ以外にも無数の星が小さい光を放っている。満天の星空だ。それらの星がスラヴ民族を見守っているように感じる。わたしは「なんて優しいんだろう」と思った。
以下の19点は、いずれもスラヴ民族の歴史上のエピソードを語っている。興味深い点は、第1作がそうであるように、主人公は英雄や偉人であるよりも、名もない庶民であることが多い点だ。例外的に英雄が中央に描かれている作品があるが、前景に疲れきった女性が大きく描かれ、その存在感が英雄を圧倒している。
もう一つ興味深い点は、第1作の男女のように、画中で起きている出来事と、それを見るわたしたちとをつなぐ‘仲介者’のような人物が、多くの作品に存在することだ。それは母親と子どもであったり、老人と青年であったりする。それらの場合は、次代に未来を託すメッセージが感じられる。
第1作は夜の情景だったが、その他オレンジ色の夕映え、明るい日盛り、嵐をはらんだ曇り空など、様々なヴァリエーションの空の描写が美しい。また野外だけではなく、教会や宮殿の内部の場合もあり、そこに差し込む光の描写が繊細だ。
連作全体を通して、ミュシャの圧倒的な力量と、それを人々のために使おうとする善意とが感じられた。
(2017.3.23.国立新美術館)
(※)「スラヴ叙事詩」全20点の画像(本展のHP)