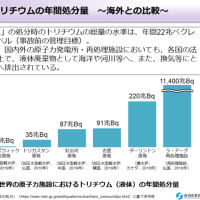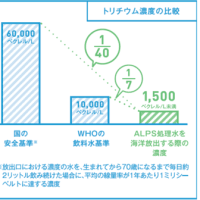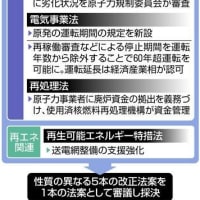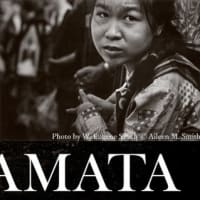母のことばが私を支えた
加賀田一さん「いつの日にか帰らん」P53~P57抜粋
ハンセン病と診断された後、国立の療養所へ入る前に、一度どうしても母親に会って話をしようとしたことを思い出します。田舎へ帰ったのは二年半ぶりくらいでした。夜は二人だけにしてほしいと頼みこみ、母も再婚した嫁ぎ先から来てくれました。会うと、母親は「帰ったか!元気でやっとるか」とただただ喜んでくれました。だから余計に打ち明けにくかったのをよく覚えています。
夜も更けてやっと、私は大阪の日赤病院でらい病の宣告を受けたことを告げました。それを聞いた母は、「そんなこと、ご先祖様にも聞いたことがない」と頑強に否定します。遺伝だと思っていたわけです。
「そんなこと聞いたことがない。何かの間違いだ。おまえは夜間部で勉強をしたり働いたりしてるからそういうことになったんだ。疲れてるんだから帰ってこい。帰ってきて休んだら良くなる」と言いつのります。
「そんなことを言っても、大きな病院でたくさんの先生方が集まって診断したから間違いないんだ」と私は答えました。それっきりお互いものを言わずに、一晩中ため息ばかりついて一睡もできませんでした。外が明るくなってきて、結局母も諦めたのか、涙を流しながら言いました。
「必ず治って、笑っていっしょに話せるときがあるから、それまでわしはおまえのことを一切しゃべらない。おまえの病気が治るまでは口が裂けても言わん。手紙は書かんでもいい。住所がわかって困るから。手紙がこないことは元気でやっていることだと思うようにするから。これだけは頼むよ」と。そして「病気というものに、治らんものはない。治らんのは病気に負けとるんだよ。おまえは島に行って一生懸命治療したらよくなる」と力づけるように言ってくれました。私が自殺するのではないかというような気配を感じたのでしょう。「どんなことがあっても生き抜いてくれ。頼む。頼む」と、繰り返す母の声は今でも耳の底に残っています。
このときの言葉が、今日まで、私が生きてきた一番の支えになっています。
母は明治二十九年生れです。明治の人の気骨なのでしょうか、別れ際に「人間は生れてきた以上、人の役に立つようなことをしなさい。そのために人は生れてきてるんだから、おまえも絶対に生き抜いてくれ。社会に役立つような人になってくれ。元気になってくれ」と言いました。
私が母を尊敬するのは、再婚後(再婚の事情やその状態については後述します)、「人間は真心があれば、言わなくても通じる」と言い続けていたということです。再婚後に生んだ、私にとっての異父妹の二人からそれを聞きました。妹二人と会うとしょっちゅう、「お母さんはこう言った」という話をしますが、「真心があれば必ず通じる、だから腹が立つことがあっても半分までにして、口から出したらあかん。必ず真心は通じるから」と言っていたといいます。
母は再婚先で、私も聞くと涙が出るほどかわいそうだなと思うような苦労をしていました。その母が私に会うといつも同じことを言っていました。幼い私が父母もなく一人でたいへん苦労をしているだろうと、母にはとても不憫に思えたのでしょう。そういう母の言う「真心があれば必ず通じる」は孤児のような私への励ましだったのだと思います。その言葉には、幼心にも胸を衝かれるものがありました。
療養所の中での七十三年間、私が諦めなかったのは、母の「おまえも絶対に生き抜いてくれ。社会に役立つような人になってくれ」という言葉があったからです。隔離されていた私は母と言葉は交わさなくても「真心」のうちでつながっていました。私は母の存在を通して「故郷」とつながっていました。
私はハンセン病と診断されて愛生園に入るまでは風邪をひいたこともないほと健康で、小学校八年間、皆勤賞でした。そんな私でしたが、この九十二年間に死と背中合わせの体験を四度しています。最初は入所して三ヶ月が過ぎたとき、三十九度の高熱が続きベッドで三週間過ごしました。あとで結核性の肋膜炎(胸膜炎)とわかりました。
二度目は戦後、ハンセン病が再発したとき、プロミン注射の副作用と重なって末期症状となり死と背中合わせの状態でした。後述しますが、この瀕死状態のとき、私は、母の自分自身を犠牲にしたような物心両面にわたる援助によって回復でき、それから十年後には、自身が亡くなった後の息子の行く末を心配している母の愛情を知りました。
三度目が七十七歳のときです。胃ガンの手術を受け三分の二を摘出しました。八十九歳のとき、店頭して頭を打ち硬膜内出血を起こしたのが四度目です。ドリルで頭蓋骨に孔を開けて血を二百CCまで吸引したところまでは覚えていますが、脳に空洞ができたため平常にもどるのに約六ヶ月を要しました。完全に認知症になると覚悟しました。この四度の瀕死体験とは別に二度、失明状態になりましたが、奇跡的に弱視ながら視力を保つことができました。
病んだときベッドにいて浮かんでくるのは常に「家のためとはいえ再婚して、四歳のおまえを一人にして済まなかった。許してくれ。どんなことがあっても生き抜いて、人のため社会のために役立つ人になってくれ」という母の言葉でした。幼いときから一緒に暮したことのない母ですが、この世にいなくなってもその母とは心の絆で結ばれています。
家族と故郷から切断された人の孤独と苦しみには想像を絶するものがあるだろうと、私には常に母との心の絆があったからこそ思うのです。
ハンセン病と診断された後、国立の療養所へ入る前に、一度どうしても母親に会って話をしようとしたことを思い出します。田舎へ帰ったのは二年半ぶりくらいでした。夜は二人だけにしてほしいと頼みこみ、母も再婚した嫁ぎ先から来てくれました。会うと、母親は「帰ったか!元気でやっとるか」とただただ喜んでくれました。だから余計に打ち明けにくかったのをよく覚えています。
夜も更けてやっと、私は大阪の日赤病院でらい病の宣告を受けたことを告げました。それを聞いた母は、「そんなこと、ご先祖様にも聞いたことがない」と頑強に否定します。遺伝だと思っていたわけです。
「そんなこと聞いたことがない。何かの間違いだ。おまえは夜間部で勉強をしたり働いたりしてるからそういうことになったんだ。疲れてるんだから帰ってこい。帰ってきて休んだら良くなる」と言いつのります。
「そんなことを言っても、大きな病院でたくさんの先生方が集まって診断したから間違いないんだ」と私は答えました。それっきりお互いものを言わずに、一晩中ため息ばかりついて一睡もできませんでした。外が明るくなってきて、結局母も諦めたのか、涙を流しながら言いました。
「必ず治って、笑っていっしょに話せるときがあるから、それまでわしはおまえのことを一切しゃべらない。おまえの病気が治るまでは口が裂けても言わん。手紙は書かんでもいい。住所がわかって困るから。手紙がこないことは元気でやっていることだと思うようにするから。これだけは頼むよ」と。そして「病気というものに、治らんものはない。治らんのは病気に負けとるんだよ。おまえは島に行って一生懸命治療したらよくなる」と力づけるように言ってくれました。私が自殺するのではないかというような気配を感じたのでしょう。「どんなことがあっても生き抜いてくれ。頼む。頼む」と、繰り返す母の声は今でも耳の底に残っています。
このときの言葉が、今日まで、私が生きてきた一番の支えになっています。
母は明治二十九年生れです。明治の人の気骨なのでしょうか、別れ際に「人間は生れてきた以上、人の役に立つようなことをしなさい。そのために人は生れてきてるんだから、おまえも絶対に生き抜いてくれ。社会に役立つような人になってくれ。元気になってくれ」と言いました。
私が母を尊敬するのは、再婚後(再婚の事情やその状態については後述します)、「人間は真心があれば、言わなくても通じる」と言い続けていたということです。再婚後に生んだ、私にとっての異父妹の二人からそれを聞きました。妹二人と会うとしょっちゅう、「お母さんはこう言った」という話をしますが、「真心があれば必ず通じる、だから腹が立つことがあっても半分までにして、口から出したらあかん。必ず真心は通じるから」と言っていたといいます。
母は再婚先で、私も聞くと涙が出るほどかわいそうだなと思うような苦労をしていました。その母が私に会うといつも同じことを言っていました。幼い私が父母もなく一人でたいへん苦労をしているだろうと、母にはとても不憫に思えたのでしょう。そういう母の言う「真心があれば必ず通じる」は孤児のような私への励ましだったのだと思います。その言葉には、幼心にも胸を衝かれるものがありました。
療養所の中での七十三年間、私が諦めなかったのは、母の「おまえも絶対に生き抜いてくれ。社会に役立つような人になってくれ」という言葉があったからです。隔離されていた私は母と言葉は交わさなくても「真心」のうちでつながっていました。私は母の存在を通して「故郷」とつながっていました。
私はハンセン病と診断されて愛生園に入るまでは風邪をひいたこともないほと健康で、小学校八年間、皆勤賞でした。そんな私でしたが、この九十二年間に死と背中合わせの体験を四度しています。最初は入所して三ヶ月が過ぎたとき、三十九度の高熱が続きベッドで三週間過ごしました。あとで結核性の肋膜炎(胸膜炎)とわかりました。
二度目は戦後、ハンセン病が再発したとき、プロミン注射の副作用と重なって末期症状となり死と背中合わせの状態でした。後述しますが、この瀕死状態のとき、私は、母の自分自身を犠牲にしたような物心両面にわたる援助によって回復でき、それから十年後には、自身が亡くなった後の息子の行く末を心配している母の愛情を知りました。
三度目が七十七歳のときです。胃ガンの手術を受け三分の二を摘出しました。八十九歳のとき、店頭して頭を打ち硬膜内出血を起こしたのが四度目です。ドリルで頭蓋骨に孔を開けて血を二百CCまで吸引したところまでは覚えていますが、脳に空洞ができたため平常にもどるのに約六ヶ月を要しました。完全に認知症になると覚悟しました。この四度の瀕死体験とは別に二度、失明状態になりましたが、奇跡的に弱視ながら視力を保つことができました。
病んだときベッドにいて浮かんでくるのは常に「家のためとはいえ再婚して、四歳のおまえを一人にして済まなかった。許してくれ。どんなことがあっても生き抜いて、人のため社会のために役立つ人になってくれ」という母の言葉でした。幼いときから一緒に暮したことのない母ですが、この世にいなくなってもその母とは心の絆で結ばれています。
家族と故郷から切断された人の孤独と苦しみには想像を絶するものがあるだろうと、私には常に母との心の絆があったからこそ思うのです。