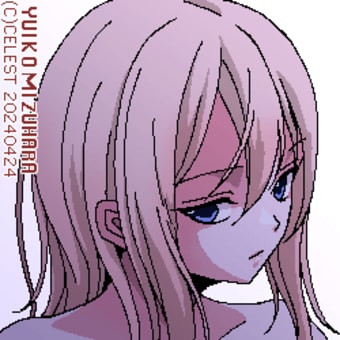十月に入って衣替えもすみ、もうすっかり秋だ。
この一か月で東條は十分すぎるほどクラスに馴染んでしまった。自身のスペックの高さなどまるで意識していない様子で、誰とでも気さくに嫌味なく話をするので、男女問わずに好かれている。
それでいて品の良さも感じられるため、女子のあいだではひそかに「もうひとりの王子様」と呼ばれ始めていた。もちろん元祖王子様は翼だ。ふたりが一緒だと目の保養になると騒がれていたりする。
実際、このふたりは友人として行動をともにすることが多い。厳密には創真もいるので三人だ。席が近いこともあって休み時間にはよく話をしているし、昼には一緒に学食にも行っている。
まさか、こうなるとは思わなかった。
とっとと翼に想いを告げてふられてしまえばいい、そして距離を置くようになればいいと願っていたが、いまのところそうした素振りはない。ごく普通に男友達として接しているように見える。
女扱いしないよう頼んだから律儀に守っているのだろうか。それともまずは友人として距離を縮めようとしているのだろうか。もしかしたら男として生きる翼を尊重してのことかもしれない。
いずれにしても、翼とふたりの時間を奪われて続けているのが現実である。ただ、創真のこともきちんと友人として扱ってくれるので、意外と居心地は悪くない。それがすこしくやしくもあった。
「行けっ、翼!!」
誰かがそう叫ぶより早く、翼は東條からのパスを受けるべく前に飛び出し、その勢いのままサッカーボールを蹴り抜いた。ボールはゴールポストの右上隅に突き刺さり、ネットを揺らす。
「やったな!」
「ああ」
翼は東條やまわりのチームメイトとハイタッチをして、喜びを分かち合った。
体育館から扉を開けてその様子を見ていた上級生の女子たちは、ふたりの王子様の連係プレーとハイタッチに黄色い声を上げている。制服のままなので体育の授業をしているわけではないようだ。
創真も同じチームだったが、ディフェンダーとして自陣にいたので遠巻きに見るだけである。わざわざそのために駆け寄っていくほどのものではないだろう。体育の授業にすぎないのだから。
あれは、オレの役目だったのにな——。
東條が来るまでは創真がミッドフィルダーとして翼をアシストしていたが、そのポジションを彼に譲るはめになった。サッカースクールでミッドフィルダーだったと聞けばそうせざるを得ない。
実際、創真よりはるかに上手いので文句も言えない。九才から十二才までサッカースクールに入っていたらしく、高校でもサッカー部に入ろうかどうしようか悩んでいたが、結局やめたと言っていた。
「え、サッカーやってなかったのか?」
翼のゴールのあとまもなくチャイムが鳴り、授業が終わった。
これで今日は終業となるので、みんなのんびりとサッカーボールやビブスなどを片付けている。そんな中、東條は翼がサッカーを学んだことがないと聞いて目を見張った。
「ああ、体育の授業でしかやってないな」
「それであんなシュートが打てるのか」
「シュートを打つことしかできないんだ」
「いやいやいや、十分すぎるだろう」
翼がサッカーに詳しくないのは事実だが、さすがにシュートしか打てないということはない。ただ、やはり最も得意なのがそれということで、いつもストライカーを希望しているのだ。
「諫早くんは?」
「オレも体育の授業でしかやってない」
「サッカーには興味なかったのか?」
「テレビで代表戦を観るくらいだな」
「そうかぁ」
創真が用具室でビブスを所定の場所にしまっている後ろで、東條は残念そうな声を上げた。その隣でサッカーボールの籠を片付けていた翼が愉快そうに笑う。
「僕らはすこしフェンシングをやってたんだ」
「あ、諫早くんには聞いてたけど、翼もだったのか」
「ああ」
翼は頷き、ちょうど用具室の奥から戻った創真を目にして口元を上げる。
「創真はこう見えてなかなか強いぞ」
「こう見えてって何だよ……」
思わず言い返したが、フェンシングが強そうに見えないという自覚はある。手足が長いほうが有利だと思われがちだし、高貴なイメージもあるので、小柄で地味な創真がフェンシングというだけで驚かれることが多い。
現に、東條もあからさまに意外だという顔をしている。
「翼とだったらどっちが強いんだ?」
「互角だな。勝負は五分五分だったよ」
「へえ、それは見てみたいな」
「ははっ、もうなまってるだろうな」
三人で並んで更衣室のほうに向かいながら、翼は笑い飛ばす。
創真も、中三の夏に部を引退してから丸一年あまり剣を握っていないので、もう昔のように動ける自信はない。体力作りの運動、筋トレ、護身術の練習なんかは軽く行っているが、フェンシングの動きはまた別なのだ。
今後、もうやることはないだろうな——。
もともとフェンシングに思い入れはない。勉強も運動も容姿も何もかも翼に遠く及ばない中、唯一互角に渡り合えるものなので惜しい気はするが、だからこそ翼が続けないのであれば意味がないのだ。
「本当にあなたはやることなすこと派手ね」
若干あきれたような声音が聞こえて振り向くと、翼の姉の桔梗が段ボール箱を抱えて渡り廊下で立ち止まり、こちらを見ていた。同様に段ボール箱を抱える数名の男女を付き従えて。
すぐに翼はにっこりと王子様の笑みを全開にして、歩み寄っていく。
「体育館から見ていたのは桔梗姉さんたちでしたか」
「クラスの一部の女子よ」
桔梗はそっけなく訂正すると、翼のあとをついてきた創真と東條を見やって微笑む。翼が警戒心を露わにしたことに気付いたが、目が合ったのに無視するわけにもいかず、創真は軽く会釈する。隣の東條もつられて会釈した。
「あなたは編入生の東條くんかしら?」
「あ、はい……はじめまして」
「二年の西園寺桔梗よ。よろしくね」
「先輩のことは翼から聞いてました」
「あら、悪口でなければいいのだけれど」
「あ、いや……」
才色兼備だが女王様気質で策士、というのが悪口かどうかは微妙なところだろう。東條は気まずげに口ごもりつつ目を泳がせていたが、隣で翼が笑いを噛み殺していることに気付くと、あわてて話題を変える。
「あ、えっと、先輩たちは体育館で何をやってたんですか?」
「文化祭の準備よ。クラスで演劇をやるの」
文化祭ではクラスで何かひとつ出し物をしなければならない。人気があるのはやはり模擬店で、創真たちのクラスもそれである。逆に演劇は準備が大変なので敬遠されがちだと聞いていた。
桔梗のクラスの出し物については翼も初耳だったらしい。折り合いの悪いきょうだいなのであまり話をしないのだろう。一瞬、驚いたような興味をひかれたような表情を見せたが、すぐさま挑発的な目つきになる。
「もちろん主役は桔梗姉さんなんですよね?」
「ええ、もちろんというわけではないけれど」
「脇役をやる気なんてさらさらないでしょう」
「そうかもしれないわね」
少々棘のある言葉を、桔梗はたいしたことではないかのように受け流す。その余裕のある姿からは女王様の貫禄が感じられた。
「脚本も私が書いたの。衣装や装置はみんなのおかげでいいものになりそうだし、演技も日々頑張っているところよ。午前午後の二回公演で各五十分の予定だから、都合のいいときに見に来てちょうだい」
「ぜひ行かせてもらいます」
間髪を入れずに返事をしたのは東條だ。
単なる社交辞令なのか、本当に興味をもったのか——もしかしたら翼がつっかかるのを阻止したかったのかもしれない。桔梗もそう思ったのか、東條を見つめたまま艶然と目を細めて得心したように言う。
「なるほど、もうひとりの王子様ってわけね」
「あ、いや……そんな柄じゃ……」
「翼よりあなたを好むひとは少なくないのよ」
「そんなことないと思いますけど」
「そういう謙虚なところがいいって聞くわ」
「別に謙虚ってわけでも……」
「ふふっ、思ったよりもかわいらしいのね」
「え、あの……」
東條はしどろもどろで視線を泳がせる。
彼のこんな姿は初めて見たかもしれない。いつもは言い寄られてもそれなりにうまくかわしているのに、相手が女王様だからか、翼の姉だからか、どうにも普段の調子が出せずにいるようだ。
「圭吾をからかうのはやめてもらえませんか」
「あら、思ったことを伝えたまでよ」
冷ややかに睨む翼に、桔梗は素知らぬ顔でとぼけたようにそう返した。しかしすぐに華やかな笑みを浮かべてこちらに目を向ける。
「東條くんや創真くんともっとお話ししたかったけれど、今日のところはこれで失礼するわ。ごきげんよう。またいつかゆっくりと翼のいないところでお話ししましょう」
「あ……えっと……」
東條は翼のほうを気にしながら戸惑っていたが、創真は黙って目礼した。
そんなふたりに、桔梗は段ボール箱を抱えたまま優雅に会釈をすると、黒髪をなびかせながら颯爽と渡り廊下を進んでいく。後ろのクラスメイトたちも軽く会釈をして歩き出した。
「ったく……」
翼があきれたような溜息まじりの声を落としたあと、三人は更衣室へと向かう。急ぐ必要がないことは翼もわかっているだろうが、それでも足早になりながら苦々しげに言葉を吐く。
「僕のものとなるとすぐにちょっかいを出してくるな、あのひとは」
「えっ?」
「僕を孤立させるために、おまえたちを自分の側に引き入れようとしてるんだろう。創真はもうずいぶん前から狙われているんだが、圭吾にも目をつけたみたいだな」
前を向いたまま冷静にそう説明すると、再び溜息をついた。
一方で東條はにやけるのをこらえきれないような顔をしていた。僕のもの——その言葉に深い意味がないことくらいわかっていると思うが、それでもうれしいのだろう。
「だから姉さんに何を言われても真に受けないでくれ」
「わかった」
翼に頼まれるとあわてて表情を引きしめて頷く。
しかし創真としては桔梗がそこまでするとは思えなかった。本気で引き入れるつもりはなく、翼へのちょっとした嫌がらせで声をかけたのではないだろうか。それも憶測でしかないけれど。
いずれにしても自分が桔梗の側につくことなどありえない。桔梗とも良好な関係を築ければとは思っているが、あくまで翼の味方である。必要とされるかぎり翼のそばにいるつもりだ。きっと東條も——。
「俺はどんなことがあっても絶対に翼を裏切ったりしない」
「それならよかった」
真摯な訴えに、翼は安堵したようにほっと表情をやわらげた。つられるように東條も照れくさそうにはにかむ。そんなふたりの隣で、創真はひとり気配を消したままそっと静かに目を伏せた。
◆目次:オレの愛しい王子様