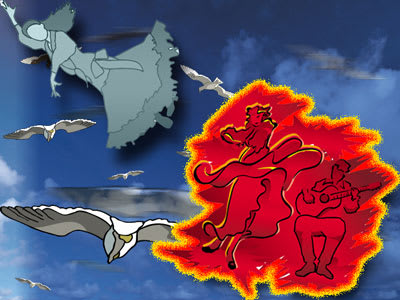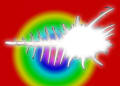Omar Sosa [Sentir/センティール] (Warner/2002) 日本盤 165円 星4つ
~遅ればせながら、このところ当方一押しのピアニスト。彼のルーツであるキューバから飛び出し、モロッコ経由でアフリカに根差した音楽にスケッチとアフリカ音楽の種々の要素をコラージュ・構成しなおした作品である。
英語のラップやアフロのチャント的メッセージを加え、前衛的な音のコラージュを正統派のピアノタッチが後追いしていく。キューバン・ミュージックの背景には、その音楽を支えている多彩なアフロ文化があるのだという点を主張しているようでもある。ここには、ピアニストとしてのソーサではなく、音楽家が考えるワールド・ミュージックとしてのアフロ・キューバンがある。
面白いのは、最後のボーナストラックは不思議な無音のあと楽器(コラ)とバタドラムがアフリカン・チャントによって彩を持ち、ピアノが特に多くを語らない。曲者:ソーサの面目躍如である。
Astor Piazzolla [La Camorra] (Nonesuch/1989) アメリカ盤 165円 星4つ
~NYのラテン狂:キップ・ハンラハンのプロデュースによるもので、病に倒れる2年前のピアソラ66歳の時に吹き込んだノンサッチでの録音。話題を集めた「Tango:Zero Hour」の2年後で、どうやら、ピアソラ自身が気にいっていたアルバムらしい。「Camorra」とは、“口論、口げんか”の意味だが、そうしたイメージはあまり喚起されず、もっと情景が濃く太い。彼のキャリアでの集大成的なアルバム構成になっていて、組曲となっているスタイルはいつものようにガッシリと無駄なく敷き詰められた緻密な音によって、審美的な味わいさえ感じさせる。
予断なしで本アルバムと向き合い、聴きこんでいくとスゴイのは判る。…だが、小生もうこの路線は相当お付き合いして来たので、少々食傷気味。やはり彼によって生み出された作品を他のアーティストがプレイしているアルバムへと興味は移りつつある。美品で安かったから買ってはいるが、数回聞いて棚に鎮座されました、ゴメンナサイ。