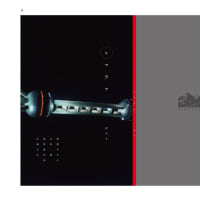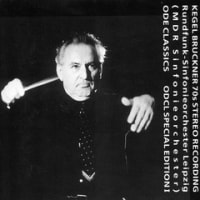エストニアのアルヴォ・ペルトやグルジアのギア・カンチェリの
音楽を一時期、よく聴いた。ロシアとドイツの大国にはさまれた
東欧の小国であるが、激情に根差したパルスや、鬱積した寂寥は
ヨーロッパの正統とは違っている。
どちらも、20世紀の音楽だが、現代音楽の前衛性の底を衝いた
その先の、擬古的な静謐さに至っている。つまりは、現代性を
一周して、なにかにたどりついている感じ。
この安堵感を、「癒し」や「安息」などといって、一種の環境音楽のように
語るのは、少し違うように思われる。
たとえば、バッハやベートーベンやモーツァルトにないものが
これらの音楽にはある。
さきに聴いた、ニールセンのデンマークや、シベリウスのフィンランドなども
そうだが、そこには、民族的な怒りの衝動がある。
このパルスが瞬発していく、褶曲が、いってみれば
ジャズに似ていなくもない。まあ、その類似については語っても
意味がないが、ジャズを聴いたあとにカンチェリやペルトを聴いても
なんの違和感もない。
角度を変えれば、彼らの音楽を発信するECMレーベルの眼目も
そんなところにあるのだろう。
根底にあるのは、民や国土や日常への信があり
その代弁者としての誇りもあるのだろう。
ニールセンという名が日本ではどちらかといえばマイナーであるが
彼らは、紙幣に肖像が描かれるほどの、国民的な創造者であること
にもそうしたことは表れている。
もちろん、私たち、私にはそれを心底理解することはできない。
だからこそ、「癒し」の音楽として受容されるのだろうが
それはしょうがないし、作曲者の意図と違って、どう受け取られようが
音楽自体の魅力は変わらないだろう。
カンチェリの音楽は、寂しく、悲しい。その悲しみの審級は、聴く主体である
己の感性の芯にとどき、深いなにかをもたらす。
そうした「私よりも悲しく寂しい」という理解が
つまりは、「癒し」の正体なのかもしれない。
それとも、今を生きる私たちにとっての「癒し」は、ただ静謐であるだけでなく
どこかに、歪んだ衝動がないともう満足しなくなっているのだろうか。
音楽を一時期、よく聴いた。ロシアとドイツの大国にはさまれた
東欧の小国であるが、激情に根差したパルスや、鬱積した寂寥は
ヨーロッパの正統とは違っている。
どちらも、20世紀の音楽だが、現代音楽の前衛性の底を衝いた
その先の、擬古的な静謐さに至っている。つまりは、現代性を
一周して、なにかにたどりついている感じ。
この安堵感を、「癒し」や「安息」などといって、一種の環境音楽のように
語るのは、少し違うように思われる。
たとえば、バッハやベートーベンやモーツァルトにないものが
これらの音楽にはある。
さきに聴いた、ニールセンのデンマークや、シベリウスのフィンランドなども
そうだが、そこには、民族的な怒りの衝動がある。
このパルスが瞬発していく、褶曲が、いってみれば
ジャズに似ていなくもない。まあ、その類似については語っても
意味がないが、ジャズを聴いたあとにカンチェリやペルトを聴いても
なんの違和感もない。
角度を変えれば、彼らの音楽を発信するECMレーベルの眼目も
そんなところにあるのだろう。
根底にあるのは、民や国土や日常への信があり
その代弁者としての誇りもあるのだろう。
ニールセンという名が日本ではどちらかといえばマイナーであるが
彼らは、紙幣に肖像が描かれるほどの、国民的な創造者であること
にもそうしたことは表れている。
もちろん、私たち、私にはそれを心底理解することはできない。
だからこそ、「癒し」の音楽として受容されるのだろうが
それはしょうがないし、作曲者の意図と違って、どう受け取られようが
音楽自体の魅力は変わらないだろう。
カンチェリの音楽は、寂しく、悲しい。その悲しみの審級は、聴く主体である
己の感性の芯にとどき、深いなにかをもたらす。
そうした「私よりも悲しく寂しい」という理解が
つまりは、「癒し」の正体なのかもしれない。
それとも、今を生きる私たちにとっての「癒し」は、ただ静謐であるだけでなく
どこかに、歪んだ衝動がないともう満足しなくなっているのだろうか。