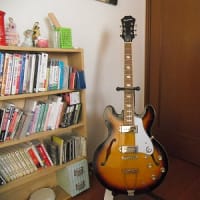「光悦の楽焼茶碗」 作 大山哲生
一
吉川六郎は峠山中学校の校長であった。
吉川は、最近楽焼きの茶碗に少し興味が出てきたのである。別に楽茶碗を収集しているわけではないが、雑誌で楽焼きをみるとなんとなく惹かれるものがあったのである。
楽焼きとは、京都聚楽第の土から焼き物を作ったのが始まりとされる。だから、最初は「聚楽焼」と呼ばれた。特徴としてはろくろなどは一切使わず、手で成形し、へらで整える。
その後、秀吉から正式に認められ「楽焼き」と呼ばれ現在に至っている。
その楽焼きの中で最高峰とされるのが、江戸時代の本阿弥光悦(ほんあみこうえつ)の作った「楽焼白片身変茶碗(らくやきしろかたみがわりちゃわん)である。現在国宝で諏訪湖畔のサンリツ服部美術館にある。
この茶碗はかつていろいろな人の手をわたってきた。一時は、新選組六番隊隊長の井上源三郎の手にわたったこともある。その後、姫路藩主の酒井家に伝わり近年まで所有した。そして、セイコーという企業をつくった服部氏が所有することになり現在に至っている。
二
ある年の四月一日。峠山中学校に新採用が一名配属された。
下川幸夫。初々しい新卒の新採用であった。なにもかもが未熟ではあるけれど、とにかく元気が取り柄とばかり声が大きく元気がいい。
年度初めの儀式も一段落した五月のある昼休み、吉川は持参した国宝図鑑を広げ、光悦の作った白片身変茶碗(らくやきしろかたみがわりちゃわん)の写真を眺めていた。妥協してなるものかという風情の茶碗を眺めていると、のめり込むほどすばらしく感じる。
そこに下川教諭がノックをして入ってきた。
校長室には、大金庫が二つ、小金庫がひとつある。大金庫には全学年の指導要録が入っていて常に鍵がかかっている状態になっている。
各担任は年度当初の時間をあるときを利用して指導要録を作成する。このときも下川教諭は指導要録をとりにきたのである。指導要録は職員室内までの持ち出しを認めている。作業がおわれば、再び校長室の金庫に戻す。
だから、校長室には入れ替わり立ち替わり教員が入ってくる。下川教諭が入ってきても吉川は顔も上げず「はい」と生返事をした。
下川教諭は、私の広げている茶碗の写真をみるなり、「あ、その茶碗ですか。ぼくの実家に似た茶碗がありますよ」と言った。
吉川は驚いて顔をあげ、「え、似た茶碗って」と聞いた。
「その茶碗は長い間酒井家が所有していました」
「うん、そうだね。そう書いてあるよ。でも、どうして知ってるの」
「ぼくの実家は、酒井家の親戚筋にあたるんです」下川教諭は、さわやかに笑うと校長室を出て行った。すぐに昼休みおわりのチャイムがなり、多くの教員が授業にいったのか職員室には静寂が戻ってきた。
三
ある日の夕方、その日は生徒が早く帰る日で、午後五時を過ぎると校内はいつになく静かである。
下川教諭がいたので、吉川は職員室に出向いて聞いてみた。
「この間の光悦の楽茶碗と似たのがあるってどういうことなの」
「ああ、あれですか」下川教諭はあたりをうかがうように見回すと、「写真を撮ってきましたから見てください」といって、一枚の写真をとりだした。
そこには、光悦の楽茶碗とうり二つの茶碗が写っていた。
「これは、光悦の楽茶碗でしょ」
「違います。それは、ぼくのひいひいじいさんが、光悦の楽茶碗をまねて作った『写し茶碗』なんです」
光悦の楽茶碗は下半分が焦げ茶色で上半分が白色である。そして、写真の茶碗も同じ色合いで、形もうり二つなのである。
「これは、複製だとしても実によくできた複製ですね。本物と見間違いました」
「その写真の茶碗については、いろいろと話があります。まあ聞いてください」
下川教諭は少し声を落として語り始めた。
四
大正十二年、下川才太郎は美術学校の学生だった。
才太郎には見初めた人がいた。おおっぴらに会うことができない時代てはあったが、二人はこっそりと会っていた。そしてやがて結婚を意識するようになる。
才太郎は、相手の父親・新島宗佑に会って、娘さんを嫁にほしいと申し出た。父親は、
「おまえは、美術学校の学生だそうじゃないか。どうせろくでもない学生に違いなかろう。おまえのくだらない作品を一度見てやるからもってこい」と言った。
才太郎は「ならば一年待ってください。一年後には立派な作品をお目にかけます」と言った。
才太郎は、楽茶碗を作ろうと考えた。しかし、どういうものをこしらえればいいのか見当がつかない。
「そういえば、親戚の酒井家に本阿弥光悦の作った『楽焼白片身変茶碗』があったな。あれを一度見せてもらって写し茶碗を作ろう」
才太郎は、なんとしてもいい茶碗を作って新島宗佑をうならせてやろうと思ったのであった。
ある日、才太郎は酒井家に出向き、何度も土下座して光悦の茶碗を見せてもらった。才太郎はその場で光悦の茶碗を詳細にスケッチした。
それから才太郎の悪戦苦闘が始まった。数百の茶碗が失敗作として捨てられた。ある日、冷えた窯から茶碗をだしてみると、たったひとつ本物と見間違うほどの茶碗があった。
才太郎の顔がぱっと明るくなった。しかし、見ているうちにその出来映えのよさに才太郎自身になんとも言えない罪悪感のようなものが湧いてくるほどのものなのであった。一年後、できあがった茶碗を持って、新島宗佑の前に進み出た。箱から出して布をどけると、楽焼きの茶碗を新島宗佑の前に出した。
「こ、これは」と新島は驚きの声をあげた。「これは、酒井家の家宝の光悦の茶碗ではないか」
「いえ、私が写し茶碗として作ったものでございます」
「いや、これは酒井家の茶碗だ」新島は信用しなかった。
後日、酒井家で二つの茶碗を前にして才太郎と新島宗佑がいた。
新島は言った。「下川才太郎君。私は大変失礼なことを言ったようだ。君にこれほどの楽茶碗を作る才能があるとは驚いた。君は、日本の美術界を引っ張る人材となるだろう。どうか、娘をもらってやってくれ」
才太郎は笑顔になって「はい、ありがとうございます。必ず娘さんを幸せにします」と答えた。
その後、才太郎の作った茶碗が光悦の作った国宝の茶碗とあまりに酷似しすぎていたため、下川家はこの写し茶碗を門外不出にした。そして、才太郎は、写し茶碗作りに精魂を傾けすぎたのか、その後これという作品を生み出すことはできなかった。結局才太郎は美術学校の会計掛として定年まで勤め上げた。
五
「そして、この写真が下川家から出ることがなかった写し茶碗だね」と吉川は言った。
「はい、そういうことです。この写真もすぐに処分します。世に出てはならない茶碗ですから」そう言うと、下川教諭ははさみで細かく切り始めた。
校長室に戻った吉川は、光悦の作った茶碗と、才太郎の作った写し茶碗の話をもう一度考えて見た。本物とあまりにも似すぎた写し茶碗を作ったため自分の才能を世に知らしめることができなかった下川才太郎。
しかし、なぜ門外不出にしたのだろう。それだけすばらしい茶碗なら、人に見せてもっと自慢すればいいのに。そうか、持ち出すと本物と思われて混乱するからか。そんな馬鹿な、本物だから門外不出にするなら話はわかるが。
え、本物、入れ替わった ? 。そうか、茶碗が二つ並んだ時に本物と写しが入れ替わったならどうなる。
もしも、入れ替わったなら、すべてのことの説明がつく。
吉川は、夢ともうつつとも知れない思考の中で、真相を知ったような気がしたのであった。
「校長先生、お客様です」
吉川を揺り起こす者があり、振り向くと下川教諭がいた。
下川教諭は言った。「校長先生、新島才太郎と言う方がお見えです」