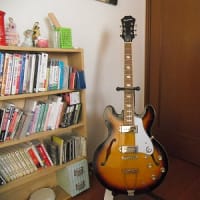~メインサイト「古都旅歩き」~
第90回古都旅歩き 小説
「高山の茶せん」 作 大山哲生
一
天正二年のことであった。
大和の国の北部の大名、高山正影は陣の中に家臣を集めた。
「皆もわかっていると思うが、此度の戦は我が軍に利がない。筒井氏をあなどっていたわけではないが、ここまで攻められるとは思わなかった。明日の朝には、最後の攻勢をかけてくるであろうと思われる。わしは大名として恥ずかしくない戦いをしようと思う」
高山正影の影がろうそくの光にゆらゆらとゆれていた。
家臣たちは皆涙をながして、主君・正影の話に聞き入った。
「今から、申しつけることはわしの最後の命令じゃ。心して聞け」
家臣たちは、はずかしくない死に方をしろと言われると思い、腹帯をぐっと握りしめた。
二
しかし、正影の口から出た言葉は意外なものであった。
「おまえたちも、おまえたちの家来も生き残った者は決して死んではならぬ。思い起こしてみれば、今から百年前、城主の二男・高山宗砌(そうせい)が、この高山の竹を使って茶せんというものをこしらえた。村田珠光をはじめ多くの茶人から愛された茶せんであった。そしてなにより、この茶せんは後土御門上皇に絶賛され『高穂』という名前まで賜ったのである。この高山の高はこの『高穂』の一文字をいただいたものである。生き残ったものは、ここ高山の茶せんの技術を子々孫々末代まで伝えていってもらいたい。よいか、決して軽はずみに腹など切ってはいけないのである。高山の家は途絶えても、高山の茶せんの技術は途絶えることなく残していくのだ。これが高山城主・高山正影の最後の命令じゃ」
家臣たちは、涙ながらに正影の言葉を聞き、こぶしを握りしめて「そうじゃ。我が地には、茶せんというものがある。日本一の技がある。これを途絶えさせてなるものか」とお互いにうなづきあいながら誓い合ったのであった。
三
次の日、筒井氏の大攻勢の前にあっけなく高山城は落ちた。高山正影は城内で腹を切った。ここに高山氏は滅んだのであった。
生き残った家臣たちは、農民となり追っ手を避けるため各地に逃げ延びた。やがてほとぼりがさめると、元家臣たちは高山の地に舞い戻り、農業に精を出すとともに茶せん作りに精をだしたのであった。
かくして茶せん作りの技は、一子相伝の技として伝えられることになった。
正影の命令は忠実に守られ、数百年経った今でも、茶せん作りの技は途絶えることなく伝えられている。高山の茶せんは繊細で美しく多くの茶人に愛用されてきたのである。
高山の茶せんで立てた茶には、高山一族代々の一途な思いが込められていると、人々は語り伝えたとか。