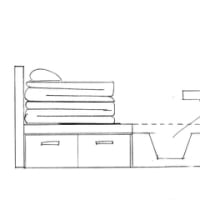私は東京の市部地域で生まれ育ったのであるが、自分や周囲をみていて、ひとつの傾向があるように感じている。中学か高校で都心の私立に進んだ人に地元について「田舎で嫌だ」と言う人が多い、というものだ。人の出入りが多い東京では明確でないが、どこにも住む地域で漠とした階層のようなものがある。同じ地域で通すと階層の違いを意識する機会は少なく、東京市部は情報や住環境の面で大きな不足はないから、満足度は高い。他方、中学高校の思春期に都心の層と接する経験は、ひとつの葛藤を生む契機になるだろう。
大学で上京した地方出身の学生について同じような葛藤が多く語られており、「文化資本」といった用語もよく目にする。これらの「格差感体験」が、個々人にどのように影響を与えるかは人それぞれであるが、私の場合、ある屈折を生み出したように感じている。大まかに言うと、(1)自分の地元を絶対に否定したくない→上の階層に行くことへの抵抗感、(2)とはいいながら上の階層の文化体験もある→他者との関係で優越性の一部を形成しているように感じる、となる。
(1)は要するに成り上がりの人生ストーリーの拒否であり、主に中学高校の頃の体験が元になっている。私は中学受験で都区内にある国立の中高一貫校に進んだ。私立より層の広い人の集まりであったと思うし、受験では外国人家庭の子供とも触れ合い、リベラルな視点をもつ基礎になったと感じているので、よい部分のほうが多い。もっとも、吹奏楽部に入り、楽器をやるということで良家の子息が集まりやすいということもあって、そこでは階層的な劣等感を感じやすいというのはあった。夏休み外車で別荘に連れて行ってもらったりとあったが、私の家は車がなかった。
私は学内での成績がよかったので舐められることはなかった(これにより成績が自我の存立基盤になってしまうのが問題だと思っていた)のだが、学業では塾通いをしていて私立でたくさん塾も通い遊びもたくさんやってるような他校の生徒と接することになった。「少ない投資で彼らと同等以上の成果をあげている」というのが励みになることもあった。地元の標準的な家庭というのを背負って対抗心を燃やすという意識である。将来像として上の階層に行くべく邁進するという思いはなかった。それは自分の育ちを否定してしまうことで,自分自身を否定してしまうという感覚があったからだ。
(2)とはいえ、客観的には学業にしても趣味にしても上の階層に適合的な体験を積み重ねてきた。受験と教育を与える側の目的のひとつでもあるから当然である。そして大学に入り地方出身の方とも触れ合うようになると、自分がいかに恵まれているかを意識するようになる。東京の中高一貫出身となれば格差感の対象として位置付けられる典型例である。実際,塾通いもしていたわけだし、奨学金も借りていなければ、アルバイトを重ねて苦学することもない。相変わらず遊びなどにお金は使わず質素に生活したが、そうして物質的・金銭的な面で控えめでいると、趣味や物腰,雰囲気といった文化資本的なものが最も簡便な優越性や個性として機能することになる。だが、自分の中で肯定していないものが自身の位置付けとして使われることには歯切れの悪さがあり、他者に対し十分に自分を見せている,すなわち自己開示できているという感覚が持てず,積極的になれないことが多くなった。
以上の点から自分の中で屈折した感情があり,どこにも落ち着く場がないという所在なさを抱えることになった。職業選択においても,何を目指していくかという点が定まらず,競争や選抜と可能な限り無縁であることが理想と考えていた。今では,物事の社会的な位置づけを脇に置いてそれ自体の意義を見据えて感じるようにすること,動機が本意でないにしても取り組んだことにより得るものがあり活かすこともできることなどを意識し,随分と克服されてきたように思う。振り返ってみて,早期に将来の覚悟と野心と意欲が固まれば,違う人生になっただろう,大きな浪費をしたという感覚もある。しかし現在,法律家という,仕事自体に公共的意義も感じられ,階層横断的に人と接し価値観が狭くなりにくい仕事を得ることができたのは幸福なことであるし,割り切れなさを抱えながらも学びを続けてきたからこそ来れたものだと思っている。
大学で上京した地方出身の学生について同じような葛藤が多く語られており、「文化資本」といった用語もよく目にする。これらの「格差感体験」が、個々人にどのように影響を与えるかは人それぞれであるが、私の場合、ある屈折を生み出したように感じている。大まかに言うと、(1)自分の地元を絶対に否定したくない→上の階層に行くことへの抵抗感、(2)とはいいながら上の階層の文化体験もある→他者との関係で優越性の一部を形成しているように感じる、となる。
(1)は要するに成り上がりの人生ストーリーの拒否であり、主に中学高校の頃の体験が元になっている。私は中学受験で都区内にある国立の中高一貫校に進んだ。私立より層の広い人の集まりであったと思うし、受験では外国人家庭の子供とも触れ合い、リベラルな視点をもつ基礎になったと感じているので、よい部分のほうが多い。もっとも、吹奏楽部に入り、楽器をやるということで良家の子息が集まりやすいということもあって、そこでは階層的な劣等感を感じやすいというのはあった。夏休み外車で別荘に連れて行ってもらったりとあったが、私の家は車がなかった。
私は学内での成績がよかったので舐められることはなかった(これにより成績が自我の存立基盤になってしまうのが問題だと思っていた)のだが、学業では塾通いをしていて私立でたくさん塾も通い遊びもたくさんやってるような他校の生徒と接することになった。「少ない投資で彼らと同等以上の成果をあげている」というのが励みになることもあった。地元の標準的な家庭というのを背負って対抗心を燃やすという意識である。将来像として上の階層に行くべく邁進するという思いはなかった。それは自分の育ちを否定してしまうことで,自分自身を否定してしまうという感覚があったからだ。
(2)とはいえ、客観的には学業にしても趣味にしても上の階層に適合的な体験を積み重ねてきた。受験と教育を与える側の目的のひとつでもあるから当然である。そして大学に入り地方出身の方とも触れ合うようになると、自分がいかに恵まれているかを意識するようになる。東京の中高一貫出身となれば格差感の対象として位置付けられる典型例である。実際,塾通いもしていたわけだし、奨学金も借りていなければ、アルバイトを重ねて苦学することもない。相変わらず遊びなどにお金は使わず質素に生活したが、そうして物質的・金銭的な面で控えめでいると、趣味や物腰,雰囲気といった文化資本的なものが最も簡便な優越性や個性として機能することになる。だが、自分の中で肯定していないものが自身の位置付けとして使われることには歯切れの悪さがあり、他者に対し十分に自分を見せている,すなわち自己開示できているという感覚が持てず,積極的になれないことが多くなった。
以上の点から自分の中で屈折した感情があり,どこにも落ち着く場がないという所在なさを抱えることになった。職業選択においても,何を目指していくかという点が定まらず,競争や選抜と可能な限り無縁であることが理想と考えていた。今では,物事の社会的な位置づけを脇に置いてそれ自体の意義を見据えて感じるようにすること,動機が本意でないにしても取り組んだことにより得るものがあり活かすこともできることなどを意識し,随分と克服されてきたように思う。振り返ってみて,早期に将来の覚悟と野心と意欲が固まれば,違う人生になっただろう,大きな浪費をしたという感覚もある。しかし現在,法律家という,仕事自体に公共的意義も感じられ,階層横断的に人と接し価値観が狭くなりにくい仕事を得ることができたのは幸福なことであるし,割り切れなさを抱えながらも学びを続けてきたからこそ来れたものだと思っている。