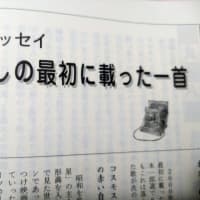今日は、知人のMさんからお知らせとお誘いを頂き、藝大オペラ定期第52回 G.ロッシーニ作曲オペラ「セヴィリアの理髪師」のAプロを鑑賞してきました。
冒頭、ステージ上にふたりの男が銅鑼をかついで登場し、おもむろにじゃんけんをします。負けたほうが耳栓をして銅鑼を押さえる役になり、勝ったほうがバチを一振り、銅鑼が打ち鳴らされてドラマがスタート。。。
第零場(?)は、序曲演奏に至るまでの寸劇。序曲の作曲がなかなか仕上がらなくて劇場関係者たちからやいのやいのと催促を受けているロッシーニが舞台上に登場。。。今回の公演の本物の指揮者トレムメル氏も舞台上にあらわれてみんなと一緒になってロッシーニを責め立てます、、、とうとう追い詰められたロッシーニは、「わかりました、じゃあ、僕の旧作の『パルミーラのアウレリアーノ』の序曲でやってください、、、」といいます。。。そこで、指揮者トレムメル氏は、そのスコアを受け取り、ステージ上からオーケストラピットに降ろされた梯子を危なっかしい足取りで降りて、指揮台に立ち、オーケストラに向かって指揮を始めます。。。いよいよオペラ『セヴィリアの理髪師』序曲の始まりです、、、という演出。。。もともと『セヴィリアの理髪師』はこんな「笑劇」だったっけ???と思うほどに、随所に観客の爆笑を誘う仕掛けが凝らされていて、集中力の途切れる暇がありませんでした。楽しかったです。
といいますか、とにかく今回の公演は、歌もオーケストラもすべてがすばらしかったです。終幕した後も感動したまま席を立ちたくなかったほどでした。その中でもとりわけ巧さが目立っていたと思ったのは、やっぱり滑稽味と渋味とをあわせ持った難しい役どころのバルトロ役の今尾氏の好演かもしれません。凄味のある名演だったと思います。
Mさん、素敵な公演を見る機会をくださってどうも有難うございました(^^)
+++++
日時 2006年10月8日(日)<Aプロ>、9日(月・祝)<Bプロ>
両日共 13:30開場 14:00開演
会場 東京芸術大学奏楽堂(大学構内)
《演目》
G.ロッシーニ作曲「セヴィリアの理髪師」全ニ幕(原語上演/字幕スーパー付)
指揮 アントン・トレムメル(本学客員教授:ウィーン国立音大にてカラヤンとアーノンクールの下で学び、指揮と合唱指揮のディプロマを取得。)
演出 粟國淳(あぐに・じゅん)
出演 本学大学院音楽研究科声楽専攻生、本学音楽学部オペラ研究部
オーケストラ 本学音楽学部管弦楽研究部
合唱 声楽科学部3年生(オペラ実習Ⅰ履修生)、声楽科学部2年有志
《キャスト》
<8日>:Aプログラム
西村悟(アルマヴィーヴァ伯爵)、今尾滋(バルトロ)、谷原めぐみ(ロジーナ)、大山大輔(フィガロ)、川田知洋(バジーリオ)、郷家暁子(ベルタ)、谷友博(フィオレッロ)
<9日>:Bプログラム
馬場崇(アルマヴィーヴァ伯爵)、木村善明(バルトロ)、相田麻純(ロジーナ)、渥美史生(フィガロ)、小野和彦(バジーリオ)、小畑朱実(ベルタ)、萩原潤 (フィオレッロ)
8日、9日両日出演
永塚節(ギター弾き)、又吉秀樹(ロッシーニ、アンブロージォ)、加来徹(兵士隊長)、吉田侍史(公証人)
http://www.geidai.ac.jp/facilities/sogakudou/info/061008.html
+++++
「マンスリーとーぶ」2004年11月号掲載:演出家粟國淳氏へのインタビュー記事
http://www.tobu.co.jp/monthly/november2004/human11.html
●あぐに・じゅん
1967年、東京生まれ。70年に父の留学に伴い、家族と渡伊。ローマ・サンタ・チェチーリア音楽院入学。父の死がきっかけとなり、以後オペラ演出家への道を歩む。藤原歌劇団、新国立劇場などの国内公演で高い評価を得ているほか、次代を担う演出家として、海外でも将来を期待されている。
父はオペラ演出家の故・粟國安彦さん。親子二代で、本誌「マンスリーとーぶ」にご登場願うことになった。インタビューは2時間近くになり、そのすべてを伝えようとこちらも躍起になったが、そんなに焦ることはないんだ。この若き演出家に話を聞く機会は、これからいくらだってあるにちがいないのだから――。
【M】 インタビューさせていただきたいと、一年ほど前から狙っておりました(笑)。何度かご連絡差し上げたんですが、留守番電話がイタリア語で応答されるもので、手も足も出ませんで。
粟國 すみません(笑)。いま、日本とイタリアを行ったり来りの生活なものですから。まあ、私たち家族はずっとそうでした。父が……そうでしたから。
《父が望んでいたこと・ぼくがやりたかったこと》
【M】 お父様の粟國安彦さんもオペラ演出家でいらっしゃって、本誌の1989年5月号でインタビューさせていただきました。その翌年、48歳という若さで他界されたことは、ほんとうに残念です。その息子さんが、日本でオペラ演出家としてデビューされたと知り、これはぜひお話を伺いたいと。親子二代で本誌にご登場いただくのは、初めてのことです。
粟國 父と同じ誌面に、と声をかけて下さったこと、とてもうれしかったです。
【M】べつに美談めいた構成にする意図はないんですが(笑)、そうは言っても、志半ばで亡くなられたお父様の遺志を継いで息子さんも、と。
粟國 いえ、ご希望に添えなくて心苦しいんですが(笑)、ぼくの内ではそう簡単に出せた答えじゃありませんでした。
【M】 その辺のところから、まず伺わせてください。
粟國 父がオペラの演出を勉強するために、母とぼくを連れてイタリアへ留学したとき、ぼくはまだ3歳になってなかったと思います。家にはいつも歌い手さんたちやオペラ関係の人たちが出入りしていて、音楽への情熱や野心について語り合っていました。どの人も、抱えきれないほどの希望や夢を背負っているように、子供のぼくには見えたものです。
【M】 若き日のお父様も、その中のひとりだったんでしょうねえ。
粟國 当然、父もそうだったでしょうね。そういう環境にぼくは育ったものですから“音楽”を学ぼうと思うようになっていく自分を、不自然だと思ったり、疑ったりしたことなんか、なかったわけです。でもそれは、父のようにオペラの演出を勉強したいといった、具体的なものじゃなくて、もっと漠然としたものだったような気がします。
【M】 お父様が演出家として日本デビューされたのは藤原歌劇団公演「秘密の結婚」だったと、以前のインタビューで直接伺った記憶があります。そのとき淳さんはお幾つだったんですか。
粟國 小学校5年生くらいだったと思います。そこから父は、日本とイタリアを行ったり来りの生活になるわけです。母とぼくはそのままローマで、父の帰りを待つ生活ですね。ぼくの学校のことがありましたから。ところが父も忙しくなってきて、なかなかイタリアへ戻って来られなくなるんです。半年に一度が年に一度になり、二年に一度とか、ですね。
【M】 どう思ってらしたんでしょうね、淳さんの将来について。話し合われたことはあったんですか。。
粟國 父と、ですかーー。自分が演出したオペラを、息子のぼくが指揮する。そうなれば親子で共演できるねーーと。そんな希望を、父がぼくに持っていたことは知っています。でも、だからといって指揮者になるための勉強をしなさいとか、そういうことを父から強制されたことはなかったですね。
《父からもらった電話がぼくを“音楽”につなぎとめた》
粟國 運よくコンセルバトーリオ(音楽学校)のヴァイオリン・コースに合格し、弦を勉強しておくことは将来のためにも無駄にはならない、ということで通いはじめたんですが、プロの演奏家になるつもりはなかったんです。父の希望は知ってましたから、できれば指揮の勉強をしたかったけれど、そのためには、作曲も勉強しないといけない。ところがぼく、ピアノが苦手で(笑)。国家試験もありますし、そういうシステムなんですね、コンセルバトーリオは。まわりの連中はみんな本気だし、必死です。中途半端な気持ちでは、とても無理だと感じたとき、音楽を学ぶことをまったく疑わなかった自分に、はじめて疑問を持つようになったんです。それが18歳を過ぎたころだったかなあーー。
【M】 お父様に相談されたんですか。
粟國 たぶん母から、ぼくが迷っているというようなことを聞かされたんでしょうね。あるとき、父から国際電話がかかってきたんです。本当に自分のやりたかったことが何なのか、音楽を学ぶということが、自身の意思だったのかどうかも分からなくなっていたぼくは、ありのままを父にぶつけたんです。すると黙って聞いていた父が、「そう。そんなに嫌だったら、やめてもいいよ」ってアッサリと言うんですよ。驚いて聞き返すと「だけど淳、おまえから音楽を取ったら何が残るのかな」って。
【M】 あっ、それはかなり効きますね。
粟國 そう、そうなんですよ。相手は演出家ですからね(笑)。でも、その電話が切れたあと、いまの自分から音楽を取ったら、いったい何が残るだろうと考えて、かなりゾッとしたことを憶えてます。
【M】 お父様の勝ちですね(笑)。
粟國 そうなるんでしょうね。実際にそれで立ち直ったというか、もう少し続けてみようという気になったわけですから。それからしばらくして、自分でもいくらか落ち着いたなと思えるようになったころですよ、父が癌に侵されていることを知らされるのはーー。
《父の死は、ぼくの人生の予定にはなかったことだった》
粟國 担当の医師は父の余命について、はっきりしたことは言いませんでした。でも口ぶりから、あと半年くらいなのだろうと感じました。父にはそのとき、まだオペラ演出の予定が2本ありました。「スペードの女王」と、「アイーダ」です。もう治る可能性がないなら、その2本の舞台だけはやり遂げてもらいたかった。演出の最中に倒れるようなことがあっても、それはそれで、父の本懐だろうと考えました。だからふたつのオペラを最優先させるために、癌のことは、父に一切告知しませんでした。ぼくがそう決めて、母にも了解してもらったんです。
【M】 そうでしたか。ご本人は知らなかったんですねえ。
粟國 それが正しい選択だったかどうか、それはいまも分かりません。本人も気がついていたのかもしれませんし、隠し通せたと思い込んでいるのは、ぼくら家族だけだったのかもしれない。とにかく少しでも長く、体力を維持できる治療をと、担当医にお願いしました。
【M】 そこからお母様とふたりで、ずっと付き添うことになるわけですか。
粟國 そうはいきません。母が付き添うのは当然としても、ぼくまでイタリアへ帰らないのは、父にとっては不自然でしょう。淳の学校はどうなっているんだ、とか。そっちの心配をはじめた父に「また来るね」と言って、ぼくはいったん、ローマへ戻るわけです。
【M】 じゃあ最期の2本の舞台は……。
粟國 ぼく、どっちも観てないんですよ。オペラ演出家・粟國安彦は予定の舞台を仕上げ、ほぼ半年後に亡くなりました。無念さはあったでしょうが、やり遂げたという思いもあったはずだと、家族としては思いたい。でもね、問題はぼくでした。奇妙な言い方に聞こえるかもしれませんが、こんなに早く父と別れることは、ぼくの人生の予定にはなかったんですよ。父が亡くなって、そのことに気づいたとき、もう呆然としました。運命に裏切られたなーーそう感じましたね。それから2年以上、ダメだったですね。音楽も嫌だし、オペラなんか観る気にもなれない。いま思うとあのころのぼくってのは、なんだか抜け道のない迷路にはまり込んだ感じですよね。
《演出家としての父の仕事を実はほとんど知らない》
【M】 だとすると、お父様が亡くなった後に、オペラ演出への道を選択されていくわけですねえ。
粟國 ええ。父はひょっとしたら、ぼくがいま、こうやってオペラ演出の仕事をしていることに驚いているかもしれない。父が生きていたら、ぼくはこの仕事をしていなかったかもしれません。もっと言えば、もし父が生きていて、ぼくが演出の勉強をしたいと言い出したら、どうだったでしょうね。父にとっても、ぼくにとっても、まるで予定にないことだったんですからーー。
【M】 じゃあ演出家として、お父様の仕事を意識されることはないと?
粟國 ぼく、父の舞台をほとんど観てませんから(笑)。でも、この1989年5月号のインタビュー記事を読ませてもらって、本当によく似ているんでビックリしたんですよ(笑)。ああ、ぼくもたぶん、こう答えるだろうなってところがいっぱいあって。自分の言葉を読み返しているみたいでしたもの。だから、演出家の粟國安彦さんとぼくが出会うのは、これからなんでしょうねえ、きっと……。
【M】 そうでしょうね。きっとそういうことになるんでしょうねえ。
《開演前のベルが鳴り、第一幕が始まったばかり》
【M】 淳さんの日本デビューは、お父様と同じく藤原歌劇団の公演でしたね。
粟國 ええ。「愛の妙薬」を演出させてもらいました。
【M】 藤原歌劇団も今年で創立70周年だそうですが、ふたりの“粟國さん”が歴史の一部として刻まれるわけですねえ。
粟國 とても光栄に思っています。
【M】 去年は「アンドレア・シェニエ」でイタリア・デビューも果たし、先月の新国立劇場「ラ・ボエーム」の再演も大きな成果をあげられました。年齢的なことでいえば、もうひとりの“粟國さん”より、少しペースが早いですね(笑)。
粟國 いや、とにかく幕は上がったというか、いま、始まったばかりですよ。それにしても「ラ・ボエーム」というオペラには、ぼくはちょっと運命的なものを感じていまして。
【M】 お父様が昭和54年度の芸術選奨文部大臣賞新人賞を受けられたのも、たしかこのオペラでしたよね。
粟國 はい。ぼくにとっては、ほとんど突然みたいに父が目の前からいなくなって、精神的に相当マイッていた時期があるというお話をさっきしましたが、どうやって這い出したかといいますとねーー。
【M】 そうでした。そこをお聞きしないと。
粟國 日本から来た親戚の人間をローマ座へ案内することになって、2年半ぶりでオペラを観たんです。それがゼフィレッリ演出の「ラ・ボエーム」だったんです。あのときの不思議な感覚をいまも憶えてますが、まるで生まれて初めてオペラを観たような、すごい衝撃を受けました。たぶん父が亡くなった後、2年半“音楽”から離れていたことで、粟國淳として、いったんリセットできたのかもしれません。そのときにね、ぼくはオケピットにいたいわけじゃなく、指揮棒を振りたいのでもなく、つまり舞台の上にいたいんだなってことが、自分で分かったんです。でも役者ではない。歌い手でもない。どうやら自分は演出がしたいんだと分かったとき、何かが吹っ切れたんですよ。
【M】 ああ、想像していた成り行きとは、ぜんぜんちがいますね、たしかに(笑)。
粟國 そこから先は、父が残してくれた人間関係がぼくの財産なんだと、痛感していく毎日です。また、舞台の上からもオペラの骨組みを見てみたかったので、ローマ座のオーディションを受けました。これも運良く通って助演で舞台に出ることができたんですが、それもゼフィレッリの「ラ・ボエーム」でした。日本で演出スタッフとして、最初にかかわった作品も「ラ・ボエーム」でしたから。
【M】 淳から音楽を取ったら、何が残ると。
粟國 そう、そこへ戻るんですね(笑)。。
(了)
冒頭、ステージ上にふたりの男が銅鑼をかついで登場し、おもむろにじゃんけんをします。負けたほうが耳栓をして銅鑼を押さえる役になり、勝ったほうがバチを一振り、銅鑼が打ち鳴らされてドラマがスタート。。。
第零場(?)は、序曲演奏に至るまでの寸劇。序曲の作曲がなかなか仕上がらなくて劇場関係者たちからやいのやいのと催促を受けているロッシーニが舞台上に登場。。。今回の公演の本物の指揮者トレムメル氏も舞台上にあらわれてみんなと一緒になってロッシーニを責め立てます、、、とうとう追い詰められたロッシーニは、「わかりました、じゃあ、僕の旧作の『パルミーラのアウレリアーノ』の序曲でやってください、、、」といいます。。。そこで、指揮者トレムメル氏は、そのスコアを受け取り、ステージ上からオーケストラピットに降ろされた梯子を危なっかしい足取りで降りて、指揮台に立ち、オーケストラに向かって指揮を始めます。。。いよいよオペラ『セヴィリアの理髪師』序曲の始まりです、、、という演出。。。もともと『セヴィリアの理髪師』はこんな「笑劇」だったっけ???と思うほどに、随所に観客の爆笑を誘う仕掛けが凝らされていて、集中力の途切れる暇がありませんでした。楽しかったです。
といいますか、とにかく今回の公演は、歌もオーケストラもすべてがすばらしかったです。終幕した後も感動したまま席を立ちたくなかったほどでした。その中でもとりわけ巧さが目立っていたと思ったのは、やっぱり滑稽味と渋味とをあわせ持った難しい役どころのバルトロ役の今尾氏の好演かもしれません。凄味のある名演だったと思います。
Mさん、素敵な公演を見る機会をくださってどうも有難うございました(^^)
+++++
日時 2006年10月8日(日)<Aプロ>、9日(月・祝)<Bプロ>
両日共 13:30開場 14:00開演
会場 東京芸術大学奏楽堂(大学構内)
《演目》
G.ロッシーニ作曲「セヴィリアの理髪師」全ニ幕(原語上演/字幕スーパー付)
指揮 アントン・トレムメル(本学客員教授:ウィーン国立音大にてカラヤンとアーノンクールの下で学び、指揮と合唱指揮のディプロマを取得。)
演出 粟國淳(あぐに・じゅん)
出演 本学大学院音楽研究科声楽専攻生、本学音楽学部オペラ研究部
オーケストラ 本学音楽学部管弦楽研究部
合唱 声楽科学部3年生(オペラ実習Ⅰ履修生)、声楽科学部2年有志
《キャスト》
<8日>:Aプログラム
西村悟(アルマヴィーヴァ伯爵)、今尾滋(バルトロ)、谷原めぐみ(ロジーナ)、大山大輔(フィガロ)、川田知洋(バジーリオ)、郷家暁子(ベルタ)、谷友博(フィオレッロ)
<9日>:Bプログラム
馬場崇(アルマヴィーヴァ伯爵)、木村善明(バルトロ)、相田麻純(ロジーナ)、渥美史生(フィガロ)、小野和彦(バジーリオ)、小畑朱実(ベルタ)、萩原潤 (フィオレッロ)
8日、9日両日出演
永塚節(ギター弾き)、又吉秀樹(ロッシーニ、アンブロージォ)、加来徹(兵士隊長)、吉田侍史(公証人)
http://www.geidai.ac.jp/facilities/sogakudou/info/061008.html
+++++
「マンスリーとーぶ」2004年11月号掲載:演出家粟國淳氏へのインタビュー記事
http://www.tobu.co.jp/monthly/november2004/human11.html
●あぐに・じゅん
1967年、東京生まれ。70年に父の留学に伴い、家族と渡伊。ローマ・サンタ・チェチーリア音楽院入学。父の死がきっかけとなり、以後オペラ演出家への道を歩む。藤原歌劇団、新国立劇場などの国内公演で高い評価を得ているほか、次代を担う演出家として、海外でも将来を期待されている。
父はオペラ演出家の故・粟國安彦さん。親子二代で、本誌「マンスリーとーぶ」にご登場願うことになった。インタビューは2時間近くになり、そのすべてを伝えようとこちらも躍起になったが、そんなに焦ることはないんだ。この若き演出家に話を聞く機会は、これからいくらだってあるにちがいないのだから――。
【M】 インタビューさせていただきたいと、一年ほど前から狙っておりました(笑)。何度かご連絡差し上げたんですが、留守番電話がイタリア語で応答されるもので、手も足も出ませんで。
粟國 すみません(笑)。いま、日本とイタリアを行ったり来りの生活なものですから。まあ、私たち家族はずっとそうでした。父が……そうでしたから。
《父が望んでいたこと・ぼくがやりたかったこと》
【M】 お父様の粟國安彦さんもオペラ演出家でいらっしゃって、本誌の1989年5月号でインタビューさせていただきました。その翌年、48歳という若さで他界されたことは、ほんとうに残念です。その息子さんが、日本でオペラ演出家としてデビューされたと知り、これはぜひお話を伺いたいと。親子二代で本誌にご登場いただくのは、初めてのことです。
粟國 父と同じ誌面に、と声をかけて下さったこと、とてもうれしかったです。
【M】べつに美談めいた構成にする意図はないんですが(笑)、そうは言っても、志半ばで亡くなられたお父様の遺志を継いで息子さんも、と。
粟國 いえ、ご希望に添えなくて心苦しいんですが(笑)、ぼくの内ではそう簡単に出せた答えじゃありませんでした。
【M】 その辺のところから、まず伺わせてください。
粟國 父がオペラの演出を勉強するために、母とぼくを連れてイタリアへ留学したとき、ぼくはまだ3歳になってなかったと思います。家にはいつも歌い手さんたちやオペラ関係の人たちが出入りしていて、音楽への情熱や野心について語り合っていました。どの人も、抱えきれないほどの希望や夢を背負っているように、子供のぼくには見えたものです。
【M】 若き日のお父様も、その中のひとりだったんでしょうねえ。
粟國 当然、父もそうだったでしょうね。そういう環境にぼくは育ったものですから“音楽”を学ぼうと思うようになっていく自分を、不自然だと思ったり、疑ったりしたことなんか、なかったわけです。でもそれは、父のようにオペラの演出を勉強したいといった、具体的なものじゃなくて、もっと漠然としたものだったような気がします。
【M】 お父様が演出家として日本デビューされたのは藤原歌劇団公演「秘密の結婚」だったと、以前のインタビューで直接伺った記憶があります。そのとき淳さんはお幾つだったんですか。
粟國 小学校5年生くらいだったと思います。そこから父は、日本とイタリアを行ったり来りの生活になるわけです。母とぼくはそのままローマで、父の帰りを待つ生活ですね。ぼくの学校のことがありましたから。ところが父も忙しくなってきて、なかなかイタリアへ戻って来られなくなるんです。半年に一度が年に一度になり、二年に一度とか、ですね。
【M】 どう思ってらしたんでしょうね、淳さんの将来について。話し合われたことはあったんですか。。
粟國 父と、ですかーー。自分が演出したオペラを、息子のぼくが指揮する。そうなれば親子で共演できるねーーと。そんな希望を、父がぼくに持っていたことは知っています。でも、だからといって指揮者になるための勉強をしなさいとか、そういうことを父から強制されたことはなかったですね。
《父からもらった電話がぼくを“音楽”につなぎとめた》
粟國 運よくコンセルバトーリオ(音楽学校)のヴァイオリン・コースに合格し、弦を勉強しておくことは将来のためにも無駄にはならない、ということで通いはじめたんですが、プロの演奏家になるつもりはなかったんです。父の希望は知ってましたから、できれば指揮の勉強をしたかったけれど、そのためには、作曲も勉強しないといけない。ところがぼく、ピアノが苦手で(笑)。国家試験もありますし、そういうシステムなんですね、コンセルバトーリオは。まわりの連中はみんな本気だし、必死です。中途半端な気持ちでは、とても無理だと感じたとき、音楽を学ぶことをまったく疑わなかった自分に、はじめて疑問を持つようになったんです。それが18歳を過ぎたころだったかなあーー。
【M】 お父様に相談されたんですか。
粟國 たぶん母から、ぼくが迷っているというようなことを聞かされたんでしょうね。あるとき、父から国際電話がかかってきたんです。本当に自分のやりたかったことが何なのか、音楽を学ぶということが、自身の意思だったのかどうかも分からなくなっていたぼくは、ありのままを父にぶつけたんです。すると黙って聞いていた父が、「そう。そんなに嫌だったら、やめてもいいよ」ってアッサリと言うんですよ。驚いて聞き返すと「だけど淳、おまえから音楽を取ったら何が残るのかな」って。
【M】 あっ、それはかなり効きますね。
粟國 そう、そうなんですよ。相手は演出家ですからね(笑)。でも、その電話が切れたあと、いまの自分から音楽を取ったら、いったい何が残るだろうと考えて、かなりゾッとしたことを憶えてます。
【M】 お父様の勝ちですね(笑)。
粟國 そうなるんでしょうね。実際にそれで立ち直ったというか、もう少し続けてみようという気になったわけですから。それからしばらくして、自分でもいくらか落ち着いたなと思えるようになったころですよ、父が癌に侵されていることを知らされるのはーー。
《父の死は、ぼくの人生の予定にはなかったことだった》
粟國 担当の医師は父の余命について、はっきりしたことは言いませんでした。でも口ぶりから、あと半年くらいなのだろうと感じました。父にはそのとき、まだオペラ演出の予定が2本ありました。「スペードの女王」と、「アイーダ」です。もう治る可能性がないなら、その2本の舞台だけはやり遂げてもらいたかった。演出の最中に倒れるようなことがあっても、それはそれで、父の本懐だろうと考えました。だからふたつのオペラを最優先させるために、癌のことは、父に一切告知しませんでした。ぼくがそう決めて、母にも了解してもらったんです。
【M】 そうでしたか。ご本人は知らなかったんですねえ。
粟國 それが正しい選択だったかどうか、それはいまも分かりません。本人も気がついていたのかもしれませんし、隠し通せたと思い込んでいるのは、ぼくら家族だけだったのかもしれない。とにかく少しでも長く、体力を維持できる治療をと、担当医にお願いしました。
【M】 そこからお母様とふたりで、ずっと付き添うことになるわけですか。
粟國 そうはいきません。母が付き添うのは当然としても、ぼくまでイタリアへ帰らないのは、父にとっては不自然でしょう。淳の学校はどうなっているんだ、とか。そっちの心配をはじめた父に「また来るね」と言って、ぼくはいったん、ローマへ戻るわけです。
【M】 じゃあ最期の2本の舞台は……。
粟國 ぼく、どっちも観てないんですよ。オペラ演出家・粟國安彦は予定の舞台を仕上げ、ほぼ半年後に亡くなりました。無念さはあったでしょうが、やり遂げたという思いもあったはずだと、家族としては思いたい。でもね、問題はぼくでした。奇妙な言い方に聞こえるかもしれませんが、こんなに早く父と別れることは、ぼくの人生の予定にはなかったんですよ。父が亡くなって、そのことに気づいたとき、もう呆然としました。運命に裏切られたなーーそう感じましたね。それから2年以上、ダメだったですね。音楽も嫌だし、オペラなんか観る気にもなれない。いま思うとあのころのぼくってのは、なんだか抜け道のない迷路にはまり込んだ感じですよね。
《演出家としての父の仕事を実はほとんど知らない》
【M】 だとすると、お父様が亡くなった後に、オペラ演出への道を選択されていくわけですねえ。
粟國 ええ。父はひょっとしたら、ぼくがいま、こうやってオペラ演出の仕事をしていることに驚いているかもしれない。父が生きていたら、ぼくはこの仕事をしていなかったかもしれません。もっと言えば、もし父が生きていて、ぼくが演出の勉強をしたいと言い出したら、どうだったでしょうね。父にとっても、ぼくにとっても、まるで予定にないことだったんですからーー。
【M】 じゃあ演出家として、お父様の仕事を意識されることはないと?
粟國 ぼく、父の舞台をほとんど観てませんから(笑)。でも、この1989年5月号のインタビュー記事を読ませてもらって、本当によく似ているんでビックリしたんですよ(笑)。ああ、ぼくもたぶん、こう答えるだろうなってところがいっぱいあって。自分の言葉を読み返しているみたいでしたもの。だから、演出家の粟國安彦さんとぼくが出会うのは、これからなんでしょうねえ、きっと……。
【M】 そうでしょうね。きっとそういうことになるんでしょうねえ。
《開演前のベルが鳴り、第一幕が始まったばかり》
【M】 淳さんの日本デビューは、お父様と同じく藤原歌劇団の公演でしたね。
粟國 ええ。「愛の妙薬」を演出させてもらいました。
【M】 藤原歌劇団も今年で創立70周年だそうですが、ふたりの“粟國さん”が歴史の一部として刻まれるわけですねえ。
粟國 とても光栄に思っています。
【M】 去年は「アンドレア・シェニエ」でイタリア・デビューも果たし、先月の新国立劇場「ラ・ボエーム」の再演も大きな成果をあげられました。年齢的なことでいえば、もうひとりの“粟國さん”より、少しペースが早いですね(笑)。
粟國 いや、とにかく幕は上がったというか、いま、始まったばかりですよ。それにしても「ラ・ボエーム」というオペラには、ぼくはちょっと運命的なものを感じていまして。
【M】 お父様が昭和54年度の芸術選奨文部大臣賞新人賞を受けられたのも、たしかこのオペラでしたよね。
粟國 はい。ぼくにとっては、ほとんど突然みたいに父が目の前からいなくなって、精神的に相当マイッていた時期があるというお話をさっきしましたが、どうやって這い出したかといいますとねーー。
【M】 そうでした。そこをお聞きしないと。
粟國 日本から来た親戚の人間をローマ座へ案内することになって、2年半ぶりでオペラを観たんです。それがゼフィレッリ演出の「ラ・ボエーム」だったんです。あのときの不思議な感覚をいまも憶えてますが、まるで生まれて初めてオペラを観たような、すごい衝撃を受けました。たぶん父が亡くなった後、2年半“音楽”から離れていたことで、粟國淳として、いったんリセットできたのかもしれません。そのときにね、ぼくはオケピットにいたいわけじゃなく、指揮棒を振りたいのでもなく、つまり舞台の上にいたいんだなってことが、自分で分かったんです。でも役者ではない。歌い手でもない。どうやら自分は演出がしたいんだと分かったとき、何かが吹っ切れたんですよ。
【M】 ああ、想像していた成り行きとは、ぜんぜんちがいますね、たしかに(笑)。
粟國 そこから先は、父が残してくれた人間関係がぼくの財産なんだと、痛感していく毎日です。また、舞台の上からもオペラの骨組みを見てみたかったので、ローマ座のオーディションを受けました。これも運良く通って助演で舞台に出ることができたんですが、それもゼフィレッリの「ラ・ボエーム」でした。日本で演出スタッフとして、最初にかかわった作品も「ラ・ボエーム」でしたから。
【M】 淳から音楽を取ったら、何が残ると。
粟國 そう、そこへ戻るんですね(笑)。。
(了)