身体均整師法学園FBページhttps://www.facebook.com/Qinsei
身体均整募集中!http://ameblo.jp/kinseihou/
内臓調整療法師会http://www.naizouchousei.jp/
手技療法にとっての21世紀
わたしは、1990年に姿勢保健均整専門学校(現在、東都リハビリテーション学院)を卒業しました。「手技療法」をはじめてかれこれ25年が経過したことになります。
この間、ヒトゲノムの解析結果が明らかになり、タンパク質の構造解析の技術が開発され、機能的MRIを使った活動中の脳の機能の研究が進み、遺伝子を使った腸内細菌の解析、免疫の機能解明などがおこなわれました。

文科省の構造生物学データベースの公開(ヒトゲノム、タンパク質の構造解析の検索ツール)
http://p4d-info.nig.ac.jp/mediawiki/index.php/%E6%A7%8B%E9%80%A0%E7%94%9F%E7%89%A9%E5%AD%A6%E3%81%AE%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%99%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%81%A8%E3%83%84%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%81%AF%E3%81%93%E3%81%A1%E3%82%89
これは医学の進歩、人間の健康にとって大きな意義を持つものです。
では手技療法の世界にこの25年間どの程度の進歩が見られたのかというと正直きわめて乏しいと考えます。
単純に量の問題ではありません。手技療法のなかにもすぐれた成果、発展があります。しかし、それを束ねてゆこう、一般化してゆこうという動きが欠けているのです。
たとえば体幹力、インナーマッスルへの注目は、手技療法の分野と関わりの深い問題です。手技療法のなかには、整形外科とかスポーツ科学などにはない多くの知見の集積があります。
背骨の関節運動、神経学的な意義について、手技療法のなかにははるかに掘り下げられた知見があります。研究においては、「掘り下げる」ことと「広げること」「一般化すること」の両面が必要です。
ヒトゲノムの解析やタンパク質の構造解析は、医学そのものの進歩というよりは、医学を支える基礎科学の進歩です。医学は、その成果を「広げること」「一般化すること」に取り組んでいるといえます。
手技療法も、小さな殻に閉じこもっているべきではありません。
消去法で浮かび上がってきた手技療法の価値
そのために、手技療法の成り立っている地盤をちゃんと見定めることが必要です。あやまった設計図をもとに突き進んでも、しっかりした建物を建設することはできません。
かつて感染症の脅威が猛威を振るっていた時代がありました。たとえばクリミア戦争(ナイチンゲールが活躍した戦争)では、実際の戦闘で亡くなるよりも多くの人が怪我や手術などによる感染症で亡くなっています。
致死性の細菌やウィルスによる伝染病と、怪我や手術後の感染症は現象としてはだいぶ違いがありますが、細菌やウィルスなどの小さな生き物(ウィルスは厳密には生き物といえない)によってもたらされるという点では共通です。
パストゥールやコッホなどの研究で細菌学が確立されてくると、伝染病の予防には、感染者を隔離したり、食べ物や飲料水を制限するといった基本的人権の制限が社会的に必要だということが理解されるようになりました。
伝染病の予防という観点からみると、伝統的な医療は効果がないばかりか、合理的な伝声病対策のさまだけになることが少なくないことから、禁止するのが当たり前のように考えられるようになりました。
たとえばエボラ出血熱の蔓延では、現地の人々が発病した家族を病院から連れ帰ったり、伝統的な食事の変更に抵抗するといったことが起こりました。
しかし、抗生物質の発達によって、感染症の脅威が取り除かれてゆくと問題の本質がはっきりと見えるようになってきました。
伝染病は、じつは政治経済のグローバル化(16世紀のスペイン、ポルトガルにとよる「世界分割」に端をはっする)によって長い年月をかけて作り上げられた人と環境との伝統的な共生関係を破壊されることによって発生したのでした。
著名な人類学者クロード・レヴィ・ストロースは、人類学の対象なった原住民族の大半が、ヨーロッパ型の異文化との接触により感染症によって絶滅に近い状態に追い込まれたことを報告しています。

感染症への対策が確立されたことによって、逆に、感染症以外にも多くの健康の脅威が存在することが理解されるようになりました。
その結果として医療の分野で、「治療から予防へ」、「メディカルヘルスケアからプライマリーヘルスケアへ」という大きなパラダイムチェンジが発生しました。
病気になってから治療するのではなく、予防に取り組むことが医療胃の点でも、健康の質という点でも、はるかに価値が高いことが理解されるようになったのです。
1978年、WHOのプライマリヘルケアの世界大会では必要があれば伝統的治療師の力を借りることが改めて宣言されました(アルアマタ宣言)。今日、WHOのなかで、カイロプラクティックの『カイロプラクティックの基礎教育と安全性に関するガイドライン』が定められたり、「経穴部位国際標準化公式会議」が開催されて経穴(ツボ)の国際標準が定められたりしているのは、このような流れを受けてのことです。
伝統的医療の提起するサイエンスのパラダイムシフト
科学的医療の立場に立つ人の多くは、仮に伝統的医療の価値が再評価されるとしても、その再評価は科学的なものでなければならないと考えています。これは当然のことです。
日本においては、プライマリヘルスケアやWHO『運動器の十年』の運動は、医師など公的資格をもつ医療関係者と考えられています。 科学的な知見に基づいて、科学的な検証をへてサービスを提供できるのは、公的な医療資格をもった専門家であると考えるのも当然のことでしょう。
しかし、にもかかわらず伝統的な医療、あるいは、わたしたちが行っている近代的な手技療法は、駆逐されるどころか幅広く社会的な支持を受けています。
なぜそういったことがおこるのか、伝統的医療の側が科学的な視点に立って情報を発信することが求められていると思います。
伝統的医療は、すくなくとも現在の科学とはことなる経験の上に成り立った技術です。現在の科学的な方法論と、これらの手技療法の技術の間にどのような壁があるのかを、科学的な視点にたって原理的に明らかにすることが必要だと思います。
「手技療法の地盤をを建設する」ためにも不可欠な作業です。
統計学で明らかにできることとできないこと
伝統的医療の内側に立ち入らなくとも、有効性は統計学的に判定できると考えている人がいます。各国の政府機関やWHOにおける伝統的医療の評価は、基本的にこのような視点に立っています。
医療統計が整備され、EBM(根拠に基づいた医療)が提唱されている時代、統計学は医療制度を支える重要な基盤です。
制度医療では、レセプト請求や電子カルテ化などで自動的に大量のデータ(ビッグテータ)が蓄積されますが、伝統的医療の側には制度的に蓄積されたデータは存在しません。個人個人の院で集積されたデータも、多くはデータ化されていませんし、記録されている内容にもばらつきがあります。
しかし、統計学の意味を理解しし、伝統医療のとるべき方向を明らかにすることは重要です。
統計的な検証には暗黙の前提が置かれています。それは「採取したデータのなかに、すべての事象が写りこんでいるという」前提です。この前提条件が検証結果の限界でもあります。
伝統的医療と一般の人々の間にはさまざまな事象が発生します。これは世界中で将来にわたって無限に発生する事象です。データを取るということは、表本を取り出してこの「無限にある事象」の性質を類推しようとすることになります。
では、統計的解析のもとになるデータは、どの程度、その全体を反映しているでしょうか?
統計学は「場合分けの科学」ともいわれます。たとえば、喫煙している人と喫煙していない人で肺がんの発生率に差があるか否か、ある治療法は喘息に対して有効か否か、といったように具体的な「場合」に対して統計的な検証がおこなわれます。
「場合分けの科学」というわれるのは、場合分けの仕方によって結果が大きく左右されるからです。
たとえばある治療法の有効性を、喘息に対して検証するのか、逆流性食道炎に対して検証するのか、椎間板ヘルニアについて検証するのでは意味が全く違います。
問題は、その場合分けの基準はどこからくるかです。次のような例を考えて見てください。
データから完全に恣意性を排除すること=客観化することはできない
20人の人を集めて、バスケットボールのシュート練習をさせ、練習量とシュートの成功率の相関性を検証しようとしたとしましょう。
その結果、両者の間には全く相関性がなかったという結論が出たとします。そんなことはあるわけないと思われでしょうが、少し、この仮定にお付き合いください。
もしシュートの成功率は練習と相関がないとすれば、シュートの上手な人と下手な人といった違いは、身長とか性別とか遺伝的特性といった努力によって超えられない壁によって100%決定されていることになります。
さて、20人の対象者を調べてみると、18人は乳幼児で2人が大学生だったとします。この場合、先にあげたように練習とシュートの成功率に相関性が見られないのは当然だということになります。乳幼児ではそもそもバスケットボールを投げることができません。
もし2人の大学生を「場合分け」して調べてみれば、おそらく練習量とシュートの成功率の相関性ははっきりとした数値として出てくるであろうと予測されます。
乳幼児と大学生を分けるという「場合分け」は、普通に考えれば当たり前です。しかし、そのような基準が、伝統的治療師には見えていても、世間的な常識では見えないといった場合もあり得ます。少なくとも理論的にはありうるのです。
統計学では、極端なデータははずして顕彰することが一般的です。これは「まぐれ」を排除するのです。
ここで明らかなことは、なにが「まぐれ」で、なにが「本質的」なのかは、データのなかに写りこんでこないということです。一見「まぐれ」としか思われないできごとのかに、「本質的なもの」を読み取るかどうかは、調べる人の思い一つ(恣意性)によることになるのです。
データを集め因子分析と重回帰分析など、さまざまな解析手法を用いて自動的に結果が浮かび上がってくる検証結果ももちろんあるのですが、それはあくまで採取されたデータのなかに潜む傾向性であって、無限に存在する事象のすべてではありません。
どこで「場合分け」をするかはたえずあらたな研究課題なのです。伝統的医療の価値は、すでに統計調査によって結果が出て居ると考えている人は、このような基礎的な部分で誤りを犯しています。
じつは、この問題はクルト・ゲーデルの「不完全性の定理」によって厳格に証明されている問題です。
最初にいったように統計学的な検証は標本調査です。データはたえず不完全で、本質的なものが抜け落ちている可能性があるということを考えないと、わたしたちは常識の輪のなかを、ただぐるぐるとまわっているだけになります。
あらゆる科学的発見は「まぐれ」と「本質的なもの」の間のパラダイム転換によって起こりました。伝統的医療は、まだその本質が開示されていない医療(身体的アプローチ)なのです。

手技療法の「経験」を理解する
では、はたして伝統的治療師は「大学生における練習量とシュートの成功率の相関性」のような明白は場合分けの基準を取り出しうるのだろうか?
このこそが、ここで考えるべき最も重要な課題です。
タンパク質の全構造解析が進み、ヒトゲノム構造が終り、かたや核磁気共鳴によって体内の水素原子の原子核(陽子=プロトン)の位置解析から体内が透視できる時代に、人間の五感にたよって成り立つ知識など、些末な時代遅れのものにすぎないと、常識的な人は考えるのは当然のことかもしれません。
しかし、科学の進歩は、人間の手の持つ能力、脳の持つ能力、さらに生物の持つ能力についても多くのことを解明しました。生物応用技術という分野では、エアコンのファンの能力、掃除機の吸い取り能力など、従来技術では考えられないレベルの性能の向上が達成されています。
このことを象徴的にあらわしているのが献血でしょう。生きている以上、だれの身体も血液をつくる能力を持っています。
しかし、現在の科学技術では、血液をつくることはできないのです。
次回はこういった点を踏まえて、伝統的医療がプライマリヘルスケアの分野でもつ積極的な価値について、科学的な視点に立って検討してみたいと思います 。
それは、現代の科学の根底に横たわる主観的なものと客観的なものとの原理的な対立の問題なのです。
(つづく)










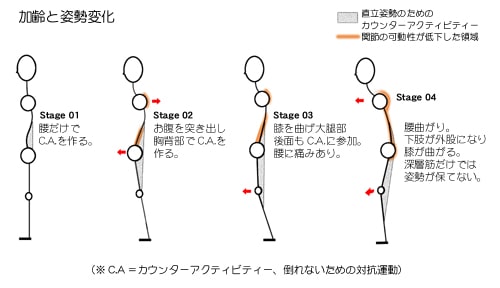





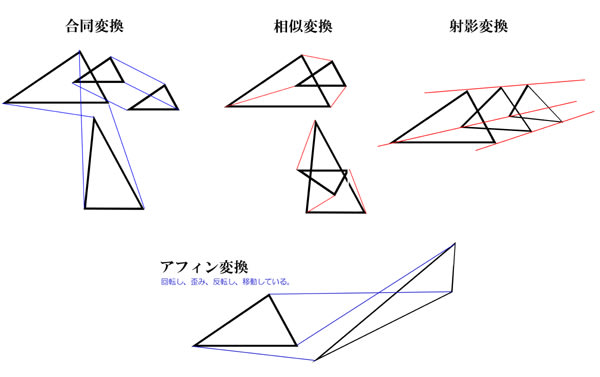







 、
、 
 、
、 

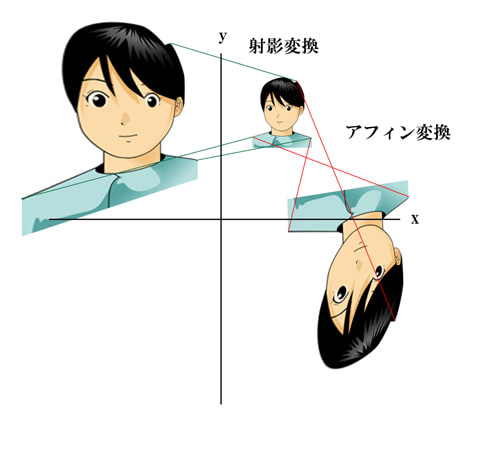






 運慶の仁王像
運慶の仁王像