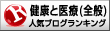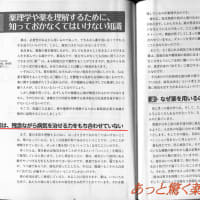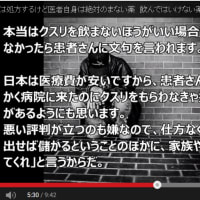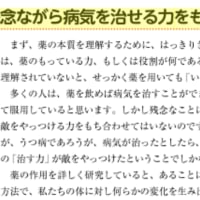予防接種については参考に予防接種神話の嘘 統計上のトリックだった!?の記事も
予防接種 『罪なきものの虐殺』への追補●BCG禍人間モルモット――『罪なきものの虐殺』への追補貧しい国からの搾取●『マザー・ジョーンズ』より●ヨハネ・パウロⅡ世のメッセージ
より転載
この「世界医薬産業の犯罪」は1985年までの資料から書かれたものです。
ーーーーーーーーーー以下引用ーーーーーーー
予防接種 『罪なきものの虐殺』への追補
予防接種の効果を正確に評価するのは困難である。接種されたグループとされないグループ(対照グループ)を十分な人数で実験し、統計的に有意な分析結果を出すことが不可能だからである。
それゆえに、予防接種の効果は好意的に解釈しても、はっきりしないというところだろう。
一方で「衛生」の効果には、はっきりと歴史的評価が与えられている。中世以降、ヨーロッパを荒廃に追い込んだ度重なる疫病の大流行がようやく下火になった原因は、予防接種ではなく衛生観念の普及だった。疫病が衰えを見せ始めたのは予防接種の始まる半世紀も以前だった。しかし衛生観念の導入と疫病の衰退はちょうど時を同じくする。この点に関して、医学史の専門家たちの見解は一致する。
予防接種の効果の評価が曖昧であるという状況は、また、化学・医学・動物実験シンジケートに手前勝手な主張を言いやすくさせる状況でもある。
つまり、
効果ありの統計的証明ができないということは
効果なしの証明もできないということだからである。
( ※ 参考に → 予防接種が感染症死亡率を減少させたという嘘
ところが、手前勝手な主張も、それが医学エスタブリッシユメント――大学教授、研究所長、保健官僚など――から出されると、国民はその主張が事実であり真実であると頭から信じ込んでしまうものなのである。
ポリオを例にとってみよう。ポリオが予防接種によって根絶されるものではないという決定的証拠が医学文献を賑わしている。
むしろ、集団接種が導入された地域ではどこでも、ぶり返し、あるいは初期増加が見られるという。この顕著な例がブラジルだろう。ブラジルでは、集団接種が始まるや否や、空前のポリオ大流行がおこったのである。
にもかかわらず、このような事実は医学界では故意に無視される。というのも、予防接種神話は、化学・医学シンジケートにとっては、癌鉱脈にも匹敵する確実な収入源だからである。
ジュネーブのWHO(世界保健機構)は、セービンワクチンこそがポリオ撲滅の立役者であるとするセービン自身の論文を発表し、同様の内容のソークの論文も出している、ということを申し添えておこう。一方フランスでは、ソークワクチンもセービンワクチンも両方とも問題にされない。
というのは、パスツール研究所自前のワクチンを差しおいて、よその国のワクチンにお金を出すことなど考えもしないというだけの理由である。自前のワクチンとは、研究所のかつての所長ピエーマール・レピンの名をとってレピンワクチンと呼ばれているもので、ソーク、セービンをはじめとするこれまでに生み出された各種のワクチンと同様、まったく無益かつ危険な代物である。
動物の細胞から作られたこれら各種のワクチンが危険なのは、それが動物に由来するからに他ならない。中には発癌性が証明されたものもある。これが、ヒト細胞を使ったワクチンを生み出すきっかけとなった。このヒト細胞ワクチンには発癌性はまったくない。とは言うものの、すべてのワクチンには危険性がつきものであることは否定できないが。
フィラデルフィア(後にスタンフォードに移転)のレナード・ヘイフリック博士によって開発された、このヒトニ倍体細胞株を使ったポリオワクチンについては『罪なきものの虐殺』に詳しいので御参照いただきたい。はじめから動物を使う方法が法律で禁止されておれば、このような危険のより少ないワクチンがもう何十年も前に作り出されていたことだろう。アメリカのメルク研究所のウィルス生物学研究部長モーリス・R・ヒルマン博士が『アメリカ呼吸器疾患評論』(90:683,一九六四年)に書いたものを御紹介しよう。
二倍体細胞のもうひとつの利点は、動物培養細胞には自然に存在しているウィルスの汚染がないという点である。事実、もしこのような二培体細胞がもっと以前に入手できていたならば、ポリオその他のワクチンにサルの腎臓が使われたかどうか大いに疑問である。
さらにヒルマン博士によれば、二倍体細胞は動物細胞では増殖しないウィルスを増殖させるという。
これは、普通の感冒の原因とされ、特別なコントロール方法のないライノウィルスなどの不活性化ウィルスおよび生ウィルスワクチンの開発の可能性を開くものだろう(『サイエンス』143(3606):976,一九六四年二月二十八日)。
***
アメリカでの豚インフルエンザ予防接種禍についてはお聞きになったことがあるだろうか。大流行すると宣伝されたにもかかわらず、流行らず、かえって予防注射による死者までが出てしまい、フォード大統領にとっては思わぬ失点になってしまった事件である。何千人という犠牲者やその家族がアメリカ政府を相手どって訴訟をおこし、多額の補償金を勝ち取っている。
この種の予防接種禍は、医学界がその権力をほしいままにしているような国では珍しくもない。
毎年秋になると、ヨーロッパ中の薬屋にはこんな広告が出るではないか。「インフルエンザの大流行間近か!予防注射を受けましょう!」。そして、宣伝に乗せられやすい人々は列をなして予防接種を受けるのである。今では医学体制派でさえも、インフルエンザの予防注射は大きな危険が伴う割には、予防の効果がないという点を認めているのに、この有様なのである。
一九八一年十月一日、フランスで開かれていた予防接種禍裁判において、パスツール研究所前所長メルシエ教授に、なぜ研究所がその無用性が広く認識されているインフルエンザワクチンの製造販売をいまだに続けているのか、という質問が向けられた。その時の教授の正直すぎるほどに正直な答である。「研究費の助けになるからです」。
●BCG禍
製薬業界の番犬とも言うべきマスコミが、ポリオワクチン禍の全貌を明らかにするまでには、まだ二〇~三〇年は待たねばならないだろう。
しかしポリオ同様に一般的なワクチンである結核ワクチンBCGの実態は、現在明らかにされつつある。BCGの問題がもはや無視できる段階ではなくなってしまったためである。
一九五〇年、BCGの無用性危険性を主張する医師グループの激しい反対を押し切って、フランス政府はすべての学童にBCGの接種を義務づけた。これはパスツール研究所にとっての、莫大なたなぼた式利益を意味した。
当時、国民にBCGを押しつけようと画策していたフランス政府のあの手この手を、医療関係者たちが記録に残している。その中でも目を引くのがマルセル・フェルー博士の『BCGの失敗』だろう。フェルー博士は一九八一年現在八八歳。ポワティエ出身の小児科医で、国立医学アカデミーの会員である。七七年『BCGの失敗』を自費出版した。この中で彼は、BCG義務化の初期の頃は彼自身も関係者たちの宣伝にのせられ、自分の子供たちにもBCGを受けさせたこと、しかし下の方の子供の時には接種を拒否し、孫たちの頃には接種を妨害さえした、との体験を綴っている。
これは彼自身、そして同僚たちの経験を総合して出した結論だったという。
さらにこの本には、ポワティエ医学校学長選挙立候補とりやめの経緯も出てくる。同僚に強く推されての立候補で、当選は確実と見られていたが、立候補を取り下げない場合は拒否権を発動するとの保健相からの圧力がかかったという。理由はフェルー博士のBCGに対する姿勢にあったのは言うまでもない。
イギリスの製薬・医学シンジケートの御用雑誌『ニューサイエンティスト』が、七九年十一月十五日、「インドの裁判で結核ワクチン敗訴」という長文の記事を多少当惑げに掲載した。インド政府が要請したある調査の結果を、それまで隠していたが、公表せざるを得なくなったのである。記者はニューデリー、K・S・ジャヤラマンとなっている。
インド南部で開かれた結核ワクチンBCG評価の裁判で、驚くべき事実が明るみに出された。
ワクチンは「バチルス性結核には予防効果がない」というものである。この徹底的かつ仔細な調査は、WHOおよび米国の協力を得て、インド医学研究協議会(ICMR)が一九六八年から行なっていたものである。
この発見によって引きおこされた現場の困惑は、次の文からも伝わってくるではないか。
このBCG裁判は昨年終了していたのであるが、その余りにも驚くべき結論のために、インド政府は、インド、WHO双方の専門家が、ニューデリーとジュネーブで数度の会合を重ね、その結論のもつ意味を十分に分析し終わるまで、発表を遅らせていたものである。
次の文面はさらに興味深い。
BCG接種を受けたグループでの結核発病率はわずかながら、対照グループ(BCG接種をしないグループ――訳注)のそれよりも高い。ただし統計的に有意な数字とは言えない。これにより、BCGの予防効果は「ゼロ」と結論された。
「統計的に有意でない」と言いわけがましく付け加えてみても、BCG未接種の人々よりも接種した人々の方が、結核罹患率が高いという事実を糊塗することはできないだろう。実は、この結核発生率のパターンは、一般的伝染病発生率パターンを踏襲しているにすぎない(ただし医学界体制派はこれを見て見ぬふりを決め込んでいるが)。
すなわち、ある伝染病の集団予防接種が開始されると必ずその発生率は急上昇する、その後下降に転じて徐々に接種以前のレベルに落ち着くというものである。そのため、発生率をグラフにする場合、接種直後の急上昇の頂点を初年度にとれば、その後は発生率が下がっていると読めるのは当然だろう。その際初年度以前の発生率が低かったという点を指摘する人などいないのである。
この数字のごまかしは、ポリオに関してとくに甚だしかった。ソーク、セービンワクチンが導入された時には、ヨーロッパでのポリオ流行はすでに一段落した後だったのである。一方、熱帯を中心とする地方では、ワクチンが用いられているにもかかわらず、あるいはワクチンが用いられているがゆえに、今日なおポリオは増加の傾向にある。
しかしながら、司法官であると同時に行政官でもあると自認している化学・医学・動物実験コンビナートにとって、自らの敗北を認めなければならない理由などまったく見出せなかった。八一年一月末、WHOさえも思いのままに操っている彼らは、ようやく例のインド発のニュースのショックを和らげる方法に辿り着いたらしい。「国際連合」の名のもとに、スイスのマスコミが次のように報じたのである。「さきのインドのBCG裁判について調査を行なっていたWHOのふたつの専門家グループは、BCG接種をこのまま継続するのが適当であるとの結論に達した」(まったく同じ時期に、母乳の代用として粉ミルクを使用することを、WHOの三〇名の委員が承認した、と報じられている)。
人間モルモット――『罪なきものの虐殺』への追補
単純に人道主義的立場から発言する人々というのは、医学研究者からは、感情的すなわち非科学的と見くびられがちである。しかしそれらの人々とは一線を画する、十分な医学的素養を持った人人も、動物実験に反対し、同時にすべての人体実験に対し、反対の声を上げている。
今日行なわれている医学実験の大部分はまったく無益だと言えよう。その理由として、第一に、健康を支配する基本原理は実験で確かめなくとも、常識として理解されているからである。
第二に、実験では過激な手段によって人工的な病気状態を作り出すが、このような不健康状態は、生体の内部から自然発生的におこるそれとは決して同じではないからである。
それでもなおかつ、実験による医学研究は増加し続けている。これは、この方法が確実に経済的プラスをもたらすからだろう。そして、たとえ医学の正道からはずれ、健康をよりひどく損なわせることになったとしても、少なくとも研究者個人の好奇心を満たすことができるからだろう。
実験者たちは「イヌか赤ん坊か」という殺し文句を使って、自分の無意味な実験を弁護してきた。
しかし現実には、彼らはイヌも赤ん坊も使う。赤ん坊の方はもちろん事なく済ませられる場合だけである。実験者の多くは、イヌでは正確な解答が出せないことを知っている。それで赤ん坊を使いたがるのである。公共施設に収容されている孤児、身よりのない呆け老人、刑務所の囚人、場合によっては心理的経済的に圧力をかけやすい弱い立場の人、そして何も知らない一般の病人をだますということすらある。この問題に関しては『罪なきものの虐殺』の中で、完全とは言えないまでもかなり詳しく述べたつもりである。しかし『罪なきものの虐殺』以後、状況はさらに悪化している。
現在アメリカでは、少なくとも二五の州で囚人を医学実験に使うことが認められている。ペンシルヴァニア州だけでみても、バックス郡刑務所、ランカスター郡刑務所、ホルムズバーグ刑務所、バークス郡刑務所、ノーザンプトン刑務所、デラウェア郡刑務所、レバノン郡刑務所、フィラデルフィア教護院、チェスター郡農場刑務所などが実験に参加している。
一九七八年八月号『ナショナル・インクワイアラー』に、クリス・プリチャードの「製薬会社、患者をだましてモルモットに」と題する記事が載った。
食品医薬品局、科学調査部の医官であるマイケル・ヘンズレイ博士が明らかにしたところによれば、生まれてくる赤ん坊に呼吸障害をおこす可能性があるということを知らせずに、妊婦たちに、ある種の鎮痛剤を与えていた研究者がいたという。実際に、この研究の目的は「新生児に軽度の呼吸機能低下をおこさせる」ことにあったという。そしてさらに別の薬剤がその治療に有効かどうかを調べるために……。
***
「動物実験はサディズムである。そしてこのサディズムによって教育された医者たちは、大衆にとっての最も深刻な懸念さえも正当化してしまう」と言ったのは、フランス人医師G・R・ローランである。今から二〇~三〇年ほども前のことである。さらにそれよりかなり以前、一九一二年に、ドイツ人医師ヴォルフガング・ボーンは次のように書いた。ローラン、ボーン両者の言葉は、今日見ても予言的だったという他はない。
「動物実験の公に言われている目的は、どの分野においても達成されておらず、将来においても達成されないであろうと予言できる。それどころか、何千人もの人間を殺してきた。動物実験の拡大がもたらしたものは唯ひとつ科学の名を借りた拷問と人殺しのみである。おそらくは、この人殺しは今後も増え続けるだろう。なぜならば、それが動物実験の論理的帰結なのだから」
実験室内で日常的に行なわれている動物実験は、実験者の医学的理解力を鈍らせる以上に人道的感性を鈍らせる。これを証明するリポートは、医学文献中には目白押しだが、一般の人々の目に触れるような報道はほとんど行なわれない。次に引用するのは、一九七九年二月一日、オーストラリア、シドニーの『シドニー・シャウト』に載った例外的とも言える記事である。
シドニーで、数名の多動児の異常行動を抑えるための脳外科手術が行なわれた、と州政府に報告があった。「頭を壁に打ちつける癖のあった少年に脳手術が行なわれたが、この手術によって少年は廃人同様になる可能性がある」とニューサウスウェールズ州人権擁護委員会コーディネーターのレックス・ワトソン氏が本紙記者に語った……。
このような手術の副作用のひとつとして考えられるものに視野の二五パーセント狭窄がある。
またワトソン氏によれば、一般の手術に比べ死亡率も格段に高いという。
人権擁護委員会の調べで、これらの手術はすべてプリンス・ヘンリー病院神経精神科で行なわれたことが確認された。手術は大脳辺縁系に対し行なわれるもので、これは記憶や思考に影響を与える旧式のロボトミーとは異なる。しかし医療関係者の中には、この手術は、人間の基本的本能を歪めるものだと考える人々もいる。
現在調査中の患者の一人は、手術後、四回も自殺を図っている。
『精神衛生』一九七三年三月号に、ワシントン大学精神医学部精神医学技術調査グループの代表であり、開業医でもある、ピーター・ロジャー・ブレギン博士が次のように書いている。
またまたロボトミーと精神外科手術のニュースである。フィラデルフィアでひとりの黒人男性がヘロイン中毒で死亡したが、この男性の頭部に奇妙な傷あとがあるのに気づいた新聞記者がいた。これは、彼の脳の一部が、麻薬中毒治療のための試験的手術で灼かれた時できた傷だった。
記者は執刀した神経外科医を捜し出した。この医師は死んだ中毒患者の男性に手術を試みる前に、サルで実験を行なっていたというが、その実験は不完全なものであったことを認めた。
ケンタッキー州ルイスヴィルでは、三〇歳の女性が前頭葉白質切裁術が原因で失明した。患者は医師を相手どって訴訟をおこしているが、原告側の証言によれば、この女性の頭痛の原因は心因性であったにもかかわらず、精神療法のチャンスをまったく与えられないままロボトミーが施されたという。
ミシシッピ州ジャクソンでは、神経外科医が、多動児数人(最年少は五歳)に脳の切除手術を行なった。そのうちの一人には、電気凝固を五~六回行なったと執刀医は話している。この子供は手術後かなり扱いやすい患者にはなったものの、知能は低下しているという。手術を受けた子供たちの人種について、医師は明言を避けているが、病室を垣間見た人の証言よれば、三人は黒人だったという。
うつボストンでは、鬱病の女性が電極の埋め込み手術を数回受けた後、それ以上の手術を拒否し、外科医、精神分析医両者に激しい怒りをあらわにした。この女性はその後すぐに自殺したが、医師たちはこれを「満足のいくケース」と報告している。すなわち、この女性は鬱病からは回復していた、さもなくば自殺するエネルギーもなかったはずだから、というのである。
さらにボストンで、ふたつの大きな電極で脳を串ざしにされたまま一年間放置された患者たちがいる。この電極にはさらに四〇個ほどの小さな電極がついており、それらで脳を刺激したり脳波を記録したりした。リモコン実験のために一年間そのままの状態が続けられた後、神経外科手術が行なわれた。
タラヴでは、同性愛好者にポルノ映画を見せ、彼らの「快楽中枢」に刺激を与えるという実験を行なった神経外科医がいる。彼らを異性愛好者に転換させるために行なったのだという。この神経外科医は、「人の患者に同時に一二〇もの電極を埋め込むという非公式「記録」ももっている。
ボストンの神経外科医グループが『アメリカ医師会誌』に、スラム街での暴動は政治要因のみによって引きおこされるのではなく、暴徒たちには何らかの脳障害があると考えられるという主旨の論文を載せた。司法省は、個人のうちに潜むその暴力的性向を見つけ出す「検査法」と神経外科的治療法の開発に研究助成金を出した。国会までもがその年に五〇万ドル、翌年一〇〇万ドルの助成金を立法化した。
このような手術を行なっているのは一握りの変質者ではない。ボストン、ハートフォード、ニューヨーク、フィラデルフィア、ニューオリンズ、ルイスヴィル、サンフランシスコ、サンタモニカ、それに国立衛生研究所などの権威ある医療機関に勤務するれっきとした神経外科医や精神分析医なのである。
脚注には次のようにある。
これらの報告のうち、新聞紙上や法廷で公開されたもの以外は、国会議事録一九七二年二月二十四日、E一六〇二~一六一ニページに詳細に記録されている。
次の引用は『タイム』一九七九年四月二十三日、「精神病院での極秘手術」より。
先週、バトリック,マーフィー弁護士がシカゴで訴状を提出した。訴状によれば、一九五〇年代から六〇年代にかけ、イリノイ州マンテノ精神病院の患者二五名ないし一〇〇名に対し「非公靭興極秘」の精神外科手術が、シカゴ大学ビリングズ病院において実施されたという。手術では患者の副腎が摘出された。副腎というのはコルチゾンその他のホルモンを作る器官である。手術の責任者は、癌のホルモン治療法でノーベル賞を受けたチャールズ・B・ハギンズ博士(七七歳)だったという。
ここで、シカゴ大学側は憤然としてこの告発内容を否定したとある。しかし記事はさらに次のように続く。
マーフィー弁護士は、人民保護官として、法的に無力な立場の人々を護る責任があるとして、大学側の否定に対して、反証を示している。すなわちマンテノ病院が事実上「人体実験室」だったと証言する、ある精神分析医のメモを公開したのである。
「人間モルモット、失明の男性に二九〇万ドル」一九八一年一月二十七日、ニューヨーク発UPIより。
生後まもなく失明した二七歳の男性が、医療過誤の賠償として二九〇万ドルを受け取ることになった。医師が両親の了解を得ずに、国家予算のバックアップを受けた医療実験にこの男性を使ったのだという。
この男性は、ニュージャージー州ユニオンシティに住むダニエル・バートンで、彼の弁護士は「このケースは人間モルモット隠しだった」という。ダニエルは一九五三年ニューヨーク病院で未熟児で生まれ、二八日間保育器に入れられていた。ダニエルの両親はそれまでにも一人子供を亡くしていたが、医師たちは今度の赤ん坊は大丈夫だと太鼓判を押した。が、ダニエルは失明した。
二七年間、両親は運命だと諦めていた。しかし二人の考えが変わったのは、未熟児に大量の酸素を与えるという、国家予算補助の医療実験についての記事を雑誌で見つけた時だった。これらの未熟児は皆、ダニエルと同じ一九五三年生まれで、その多くが失明していた。
マンハッタンの州最高裁判所陪審は、ダニエルの失明の原因は酸素実験にあるとの評決を下し、月曜日、二九〇万ドルの賠償を認めた。
ダニエルの弁護士、マーク・ワイゼンは、病院からダニエルのカルテを入手し、彼が保健省の未熟児研究プログラムに組み入れられていたことを立証した。医師たちは未熟児に、誕生後一カ月間純濃度の酸素を与えることが救命に効果があるかどうかを実験していた。しかし、この高濃度の酸素が赤ん坊の網膜に通じる細い血管を収縮させ失明に至らせた、とワイゼン弁護士は言う。
***
「日本の戦時人体実験隠蔽にアメリカが協力」一九八一年十一月二日付『インターナショナル・へラルド・トリビューン』より。フィリップ・J・ヒルツ署名の記事、以下はその全文。
[ワシントン発]第二次大戦中、日本はアメリカ人捕虜をも含む約三〇〇〇人を、生物兵器実験で殺害した。しかしアメリカ軍上層部が日本側と秘密協定を結び、この実験の事実を隠蔽したと最新号の『原子物理学会報』が伝えている。
この秘密協定は、関係者の戦争犯罪免責の含みもあるものだったが、アメリカ側がこの協定に同意したのは、貴重な実験結果をアメリカも利用できるようになるからだった、と『会報』の記者は書く。
生物兵器開発用の実験動物として使われた犠牲者たちは、大量のペスト菌、炭疽菌、天然痘菌などによって殺された。さらに、病原菌だけではなく、放射線、馬の血液の輸血、生体解剖などさまざまな殺され方をされたらしい。
『会報』の記事を執筆したジョン・ポウエル氏は、膨大な量の日米間の秘密協定文書を、情報公開法に則って国防省から入手したと述べている。そしてこれらの文書のうち六つの文書からの引用を記事の中で行なっている。
当時、日本と妥協したアメリカ側関係者は、実験でアメリカの兵士が多数殺されているため、もし問題が表面化すれば、「アメリカ軍内部の高官の責任追及というこみ入った状態にもなりかねない」という危惧を持っていたという点がそれらの公式文書から明らかになるとポウエル氏は言う。
軍そのもののコメントはいっさいない。またアメリカ人兵士の犠牲者の数、名前なども明らかにされていない。この点につき、ポウエル氏は、軍部はこれらを日本側に詰問すればことの全貌が公の目に触れる可能性が大きくなるのではないかと考えて、あえてしなかったのだろうと推測している。
まず実験期間中に提出されていた古い報告書によれば、当時日本には非常に高度な生物戦プログラムが存在していたこと、そして石井四郎軍医中将指揮下で実験が行なわれていた三カ所のキャンプで大量の戦死者が出ていたことが確認できる。
一九四七年五月六日、東京からワシントンに宛てた極秘電報がある。それによれば、戦争犯罪の免責が保証されるならば、実験の全情報を提供する旨の石井中将の意向が伝えられている。さらにポウエル氏が引用している別の文書によれば、石井中将から入手した実験情報は生体実験に伴う「良心の呵責」を考えると、「評価できない」ほどのものであり、アメリカにとってこの機会を逃せばもう二度と手に入れることができない種類の情報だったという。
また、この情報の値段は、日本が実験を実施するために支払った現実のコストに比べると、まったく取るに足らないほどに「安あがり」だったともいう。
エドワード・ウェッター博士およびH・1・スタブルフィールドという二人のアメリカ人のメモによれば、その後、石井中将はBW(生物戦)実験の犠牲者の検死の際に使われた八〇〇〇枚の細胞標本など具体的なものの提供をし始めたことが分かる。さらにそのメモにはこうある。
「戦犯裁判が行なわれれば、この種のデータが世界中に完全に公開されることになるだろう。アメリカ合衆国の防衛と安全のためにも、公表は避けるべきだと考える」。
さまざまな実験が捕虜を対象にして行なわれたことがうかがえる。たとえば、まず捕虜を病気にカカらせる、しばらく病状の自然な進行過程を観察した後、病原菌の与えたダメージの程度を観察するため病人を「犠牲」に検死を行なうのである。
メリーランド州キャンプ.デトリック(後にフォート・デトリック)基礎科学部長エドウィン,V.ヒルが、この実験結果の持つ価値の大きさに注目し、一九四七年十二月に出したリポートの中で次のように述べている。「この情報を自らすすんで提供してくれた日本人は、この価値の大きさのゆえに、辱めから免責されるべきだろう。また我々は、この情報が他の国の手にわたらぬよう最大限の注意を払わねばならない」。
さらに東京の米軍司令部からの別のメモにはこうある――日本に「戦争犯罪免責」を与える利点は、それにより「石井中将とその忠実な部下たちの過去二〇年間の貴重な蓄積を我々が利用できるようになる」という点である。
***
『罪なきものの虐殺』で、アメリカやイギリスでは、研究者たちが、堕胎されたばかりの胎児を実験材料として病院から買っているという話を書いた。表向きの禁止にもかかわらず、この胎児売買はその後も広がり続けている。
最近は、アメリカ政府の支出する研究費が、フィンランドの病院から買った生きた胎児を使った実験に費やされているという噂も耳にする。なぜフィンランドかと言えば、フィンランドでは妊娠五カ月までの人工流産が法的に認められているが、五カ月の胎児は人工流産手術後保育器内で生かしておくことが可能なのである。そのような生きた胎児が研究用に売られているのである。
いつものことながら、このような恥ずべき事実をあえて社会に知らせようとする報道機関はほとんどない。その数少ないひとつがコネチカット州グリニッジの『グローブ』である。一九八〇年八月十九日「人工流産胎児、実験用に生かされる」という見出しの、チャールズ・ラクマン署名の記事が掲載された。
フィンランドのある病院で、生きた人間の胎児を使ったぞっとするような実験が行なわれている。それを資金援助しているのがアメリカ政府である。
『グローブ』が入手した情報は、胎児の首を切り落したり、腹部を切り刻んだりして実験が行なわれている。それも胎児には麻酔さえかけられていない、という非常にショッキングな内容である。
オランダ人ジャーナリスト、ハンス・ペルケルの調査によれば、人工流産児はヘルシンキの病院から一万二〇〇〇ドルで買われており、その費用の出所はアメリカ政府なのだという。オハイオ州クリーブランドのアメリカ人研究者ピーター・アダム博士がフィンランドに送金したもので、アダム博士はヒト胎児研究助成金として、アメリカの国立衛生研究所から六〇万ドルを受け取っているのである。
当のアダム博士は、先月、脳腫瘍のため四四歳で亡くなっている。未亡人の小児科医キャサリン・キング博士が『グローブ』に語ったところでは、アダム博士はもう随分前にフィンランドの研究グループとの縁を切っており、今はアメリカの資金が彼らの研究に使われている事実はないという。また、アダム博士はクリーブランドの自分の研究室でも胎児を使った実験は止めていた、とキング博士は言う。
元来、フィンランドがこのような実験の場として選ばれたのは、フィンランドの中絶法が非常にリベラルで、妊娠五カ月までの中絶が法律で許されているからである。五カ月の胎児は中絶後も生きのびる場合が多い。生きのびた胎児は保育器に入れられ、ヘルシンキからトウルクという港町に運ばれ、その恐ろしい運命に弄ばれる日を待つ。
トウルクの実験室で働いていた一人の看護夫は、フィンランド人研究者マルティ・ケコマキ博士のもとで行なわれたこれらの実験のひとつを目撃したという。彼のぞっとするような証言は、『グローブ』の姉妹誌『ナショナル・エグザミナー』に今週掲載された。
「博士たちは胎児を取り出しておなかを切り開きました。肝臓が欲しいのだと言っていました。赤ん坊を保育器から出した時はまだ生きていました。男の子でした。体は完全で、手も足も口も耳もありました。尿さえ分泌していました」。おなかが切り開かれた時、赤ん坊には麻酔注射は打たれていなかったという。
この惨劇についての説明を求められたケコマキ博士はこう答えた。「人工流産児なんてゴミですよ」。そしていずれにせよ、このような胎児が生きのびる可能性はほとんどないのだ、と彼は言う。「それならば、社会のために役立てた方がずっといいんじゃないですか?」。
ケコマキ博士もお決まりの人道主義を振りかざしたのである。これはすべての動物実験者が自らの血なまぐさい殺害行為を正当化するために使う決まり文句である。『グローブ』はさらに続ける。
博士はこの新しい方法ですでに何人もの赤ん坊の命を救っているという。彼の胎児実験の目的は、未熟児の脳への栄養供給の方法を見つけることである。そのために胎児の頭部を切り取り脳を隔離し、栄養を与える実験を行なう。「未熟児を救おうと思えば、人工流産胎児の脳や肝臓が要るんだ」と博士は言い、実験が残酷で野蛮だとは思わないか、という問いかけには、ただ肩をすくめただけだった。
ここで蛇足ながら付け加えておくと、前述のアメリカ人医師ピーター,アダム博士は、ケース,ウェスタン・リザーブ大学の小児科教授であり、クリーブランド・メトロポリタン病院の小児代謝部長だった。このふたつの医療機関は、ロバート・ホワイト博士が有名なサルの脳移植実験を行なった場でもある(「ついに脳の移植」の項参照)。このホワイト博士の脳外科医としての技術と経験をもってしても、アダム博士を脳腫瘍から救うことはできなかったのである――それも四四歳という若い死だった。
貧しい国からの搾取
貧しい発展途上国は、欧米の製薬業界にとって、格好の猟場である。健康教の宣教師を装った精鋭セールスマンを送り込み、政府高官を賄賂で抱き込んだり言葉たくみにだましたりして、先進国ではその有害さのためにすでに売れなくなってしまった薬さえも売りつけるのである。販売活動が思い通りに運ばない場合は、恐喝や政治的暴力といった非常手段に訴えることさえもいとわない。
暴力? まさか、と思われるだろうが、その例がチリで起こっている。一九七二年、自身医師でもあったサルヴァドール・アジェンデ大統領が指名した薬事委員会が、治療効果が立証しうる薬品は二〇~三〇種しかなく、国際処方薬は削減されるべきである、という答申をまとめた。この二〇~三〇種というのは中国のいわゆる赤脚医生(裸足の医者)の用いる薬品類とほぼ一致する。ところが、この答申を実行に移そうとした少数派医師のほとんどが、一九七三年九月十一日、クーデターをおこしてアジェンデ政権を倒した軍事政権によって、その週のうちに暗殺されてしまったのである(アメリカのCIAがこのクーデターに手を貸していたということは、ワシントンが認めている)。
このクーデターによって成立した軍事政権は以前よりさらに苛酷な独裁政権だった。しかし、ことアメリカとの貿易、そして化学工業製品、とくに医薬品の輸入にはオープンな市場となったのである。
もちろん、アメリカ製医薬品の洪水に反対したチリ人医師たちの殺害にCIAが手を下したという証拠はない。しかし同時に、なぜ政治革命でそれほどまでに多くの医者が殺されたのか、とくにある特定の医者たちが、という疑問に説明もつかない。余談ながら、CIAの仕事には殺人も含まれると言われている。CIAというイニシャルは「国際暗殺センター(Center of Intrenatoonal Assassination)を指すのだという話もある。
次の意味深長な引用は、一九八〇年八月二十二日付『ニューヨーク・タイムズ』と『インターナショナル・ヘラルド・トリビューン』に載った、アンソニー・ルイスの「秘密の代価」という記事からのものである。
通常のキッシンジャー氏の発言の傲慢さは、それが活字になってみると、御当人さえも気恥ずかしさを感じるほどのものである。しかし今回の四〇人委員会における発言内容は、個人レベルの問題として片づけられるようなものではない。武力、経済力そして殺人計画による他国への密かな介入をもいとわないという、CIAおよびホワイトハウスの、このところの姿勢を反映する発言だったからである(傍点著者)。
チリのケースがとくに例外的というわけでもない。もうひとつ別の例を挙げてみよう。一九七八年、当時社会主義政権だったスリランカ政府が、同国薬事委員会の答申を受けて、医薬品の輸入を大幅に削減しようとした。その時、駐スリランカ、アメリカ大使が、アメリカからの食料援助を差し止めると、スリランカ政府に脅しをかけたのである。詳しくは以下をお読みいただきたい。
***
一九七九年、BBC(英国放送協会)のリッチー・コーガンをはじめとする三人のリポーターは「病気と富」という番組の中で、医療従事者への国際アンケートに基づく驚くべき事実を報道した。
イギリス国民は、快適な居間のテレビを通し、自称「倫理的」多国籍企業が、貧しい国々を餌食にして、恥さらしな行為をしているのを知った。一〇億人もの飢えて病に冒された人々が、「国際援助」という名の偽善の降り注ぐ中、健康に生きるという基本的人権を奪われている姿を見たのである。
スリランカでは、バンダラナイケ首相の社会主義政権時代、薬理学者のセネカ・ビビレット教授が、政府の協力も得て、同国の医薬品の種類をそれまでの数千から二〇〇~三〇〇種へと削減するのに成功した。さらに、重症の病気に対応するには、三四種の非銘柄薬品で十分であると結論した。
そこで財政的に逼迫していたスリランカ政府は、自国内で必要な薬剤を製造すれば安くつくと考え、原材料だけを輸入することにした。
これに対し強く反発したのが、スリランカに子会社をもつアメリカの製薬会社ファイザー社だった。その頃たまたまスリランカでコレラが流行したが、ファイザー社は見せしめのためコレラの薬テトラサイクリンの製造を中止してしまった。困ったスリランカ政府は、ファイザーを国営にするとゆさぶりをかけた。ここで、アメリカ大使が仲裁に入り、もしそのような措置が取られたならば、アメリカ政府は緊急食料援助を打ち切るだろうと告げた。
こうして、結局、スリランカはビビレットの三四医薬品プロジェクトそのものを破棄せざるを得なくなったのである。
その後スリランカでは社会主義政権が倒れ、資本主義になった。とみるや、スターリング・ウィンスロップ製薬会社(ロックフェラー一族〉が、スリランカ最大の医学雑誌『ファミリー・ドクター』に次のような広告を出した。「ブランド薬品市場へようこそ再び――これから始まる健康な自由競争は、必ずやスリランカ国民に利益をもたらすことでしょう――」(引用ママ!)。
BBCの番組で、一人のスリランカ人医師が、憤懲やる方なしといった口調で外国の製薬会社のやり方を糾弾していた。ある会社がウィンストロールという名の小児用液体ステロイド剤を押しつけてきたという。この薬は成長を促進させるとされており、禁忌もなく入手がたやすい。スリランカではスターリング・ウィンスロップの子会社がこれを製造しており、かなりよく売れているという。
しかしこれには、子供に性転換をおこす可能性があるとされている。性転換をおこすような薬は、長期的には深刻な混乱を生体に与えるであろうことは容易に想像できよう。しかも成長促進のために用いるということは、明らかに長期使用を念頭においているわけである。これに関し、アメリカのウィンスロップ社はノーコメントだった。
イギリスの製薬業界は『ミムズ』というマニュアルを月刊で発行しており、それには現在流通している薬剤の禁忌や副作用が記されている。
ところがアフリカ版ミムズには、すでにヨーロッパでは廃棄処分になった薬や安全レベルを越える用量が堂々と載っているのである。アフリカでは、貧しい人々が団結して裁判に薬害を訴えるなどということはあり得ないからだろうか。
タンザニアでは、薬の販売量が驚くべき数字だという。薬そのものに、あまりにも多額の費用が使われるために、病気予防にまではとてもまわらず、病院や診療所さえも資金不足で次々と閉鎖されている現状だという。かえって病気を引きおこすことさえある薬の宣伝にはお金がかけられるのに、栄養不良、不潔な水、どろんこ、といった根本的な問題の解決は放置されたままなのである。
そのようなことにお金をかけたところで、製薬会社の利益にはならないからである。
バングラデシュは「世界でもっとも貧しい国」と言われるが、本来は新鮮な野菜の育つ地味豊かな土地なのである。ところが国家予算の四分の一は何と合成ビタミン剤に費やされている。しかもそのビタミン剤は、多くの子供にとって死を招く結果にさえなり得るのに。欧米の薬セールスマンから薬を買わされた町の薬屋は、薬を買うだけのお金も持たない人々に、薬の危険性も教えずに売りつけているのである。
コンビオテイックというストレプトマイシンとペニシリンの混合抗生物質がある。これはあらゆる病気に効く――切り傷にさえ――万能薬のようにして、イギリスとアメリカの会社から販売されているが、実は、耳と腎臓には甚だしいダメージを与え、とくに結核患者にとっては非常に危険な薬なのである。これはアメリカ本土ではもう一〇年も前に禁止されたにもかかわらず、アメリカ・ファイザー社は、地域を限っていまだに生産を続けているのである。
現在、このような先進各国の製薬企業による搾取から貧しい国の人々を護ろうと奔走しているのは、医療奉仕のボランテイアグループである。中国の赤脚医生(裸足の医者)のやり方を真似て、医療技術の訓練を受けた看護夫や保健婦たちが、薬草を主成分とする薬すなわち製薬企業の搾取とは無関係の薬を携えて辺鄙な地方へと出かけて行く。
しかしこのような文明の手の届かない辺鄙な土地に住む人々でさえ、現代医学に対する信仰という点では、今や欧米人と変わるところがない。彼らも現代医学とその司祭たる医師の持つ奇跡の治癒力への盲目的信仰を植えつけられてしまっているのである。赤脚医生たちは、古い迷信ばかりでなく、このような新しい形の迷信をも乗り越えなくてはならない。
欧米の人々は今、ようやく、薬の過飽和状態とその破滅性とに気づき始めている。一方で、薬の洪水は貧しい第三世界の人々を飲み込み始めた。国民は薬を買うほどに豊かでないにもかかわらず、無智で邪悪な国家支配者の加担した先進国の搾取の前に、なすすべもないのである。
●『マザー・ジョーンズ』より
『マザー・ジョーンズ』というのは、アメリカで発行されている、ある雑誌の名前である。世の中の真実一般、とくに化学製薬業界の犯罪的行為に関心のある人にとっては、なかなか読みごたえのある雑誌と言えよう。ただ、この種の雑誌の常であるが、販路はほとんど閉ざされており、発行部数はきわめて少ない。
まず手始めに、一九七九年十一月号の「二〇世紀の組織犯罪」を読んでみることにしよう。この雑誌には『ニューヨーク・タイムズ』『タイム』『リーダーズダイジェスト』などでは決してお目にかかることのない種類の記事が出る。この号は、化学製薬業界のダンピングに焦点をあてている。
もう少し具体的に言うと、製薬企業が、いかにして発展途上国に自国ではすでに禁止になっている化学製品を投げ売りしているか、またどのようにして自国では明記を義務づけられている注意書きを、これらの国向けの製品では省略しているか、といった内容である。
数年前に、サンフランシスコにあるカリフォルニア大学医療センター薬理学講師ミルトン・シルバーマン博士が、のっぴきならない証拠を公表している(ただし、反響はほとんどなかったが)。
彼は二人の同僚とともにある比較調査を行なった。すなわち、製薬会社が薬を医者に紹介する際に、合衆国でとラテン・アメリカ諸国(製薬会社の格好のカモ)でとは、どう違っているかの比較である。以下二~三の例を挙げてみよう。
〈テトラサイクリン〉レダリー社製抗感染症用抗生物質。合衆国での副作用表示 嘔吐、下痢、吐き気、胃の不調、発疹、腎障害、胎児に害を与える可能性あり。中米およびアルゼンチンでの副作用表示――なし。
〈オヴレン>C・D・ソール社製避妊用ピル。合衆国での副作用表示-吐き気、抜け毛、神経過敏、黄疸、高血圧。ブラジルおよびアルゼンチンでの副作用表示――なし。
〈イミプラミン〉チバ・ガイギー社製抗諺剤。合衆国での副作用表示-高血圧、脳卒中、よろめき、幻覚、不眠、しびれ、視覚のぼやけ、便秘、かゆみ、吐き気、嘔吐、食欲不振、下痢、発汗。
中米、ブラジル、アルゼンチンでの副作用表示――なし。
同種の情報は、アメリカの医師たちの標準的手引書となっている『医師用卓上レファレンス』(製薬会社の出している製品説明書である)からも抜き出せるだろう。もちろん、アメリカに限らず、他の国の同様のガイドブックからでも可能だろう。
かくのごとく、先進国製薬業界による、発展途上国民殺しの陰謀は、着々と進行しているのである。
●ヨハネ・パウロⅡ世のメッセージ
一九八〇年五月、アフリカ各地を旅行中だったローマ法王ヨハネ・パウロⅡ世は、ザイールで外交官や学生たちに、正直な市民たれ、そして同時に、彼ら第三世界を支配する目に見えぬ権力に敢然と立ち向かえ、と語りかけた。「この大陸は重荷に苦しんでいる。自らの内部からの重荷と、ある権力の支配によって外部から負わされる重荷とに」(『Corriere della Sera』)。
ローマ法王という特殊な立場にある人物の話す言葉は逐一、世界中に報道され分析される。従って発言は常に外交的であらねばならず、特定の個人を名指しで批判することなど不可能だろう。
しかし、故モリス・ビールをはじめとする我々名もなきジャーナリストにはそれが可能なのである。
さて、ではアフリカ大陸に、外部から重荷を負わせる「ある権力」とはいったい何者なのか。ロックフェラーセンターでアメリカの外交政策を操り、アメリカ製品に対し門戸を閉ざす国の民主政府をくつがえし、CIAを通じその国の独裁政権と手を組む――かのオールマイティ、製薬シンジケートこそが、法王の胸のうちに秘められていた名であったに違いない。
ーーーーーーーーーーーー引用終わりーーーーーーーーーー