
小説 「春とカレー」
この部屋に、カネ目のものなんてほとんどない。
そこそこ高価なものといえば、昼間に佳孝が買ってきて鴨居にぶらさげていたスーツくらいなもので、それはいま、オレが七へん催促してようやく、うやうやしげに主に袖を通されているところだ。
「どうかな」
鏡に向かい、嬉しげに何度もネクタイを結び直す佳孝へ「全っ然似合わねぇよ」と応えたオレの笑い声は、ちょっとわざとらしかっただろうか。
実際、一日がかりで選んだというだけあってそのスーツはよく似合っていたし、そもそも、もうずいぶん前から腰回りがヤバイと言われ続けているオレとは違い、佳孝の体つきは最近のタイトなスーツと相性がいいのだ。
「もう脱げよ。飯にしようぜ」
「浩ちゃんが着ろって言ったくせに」
テレビのほうに向き直りながらも、オレの目は、窓ガラスに映る佳孝がネクタイをゆるめる姿を追っていた。
「なあ」
「なに」
「こっち来いよ」
「なんで」
「いいから」
「待ってよ、いま着替えるから」
「いいって」
腰を上げるまでもなく、ちょっと体をひねりさえすれば、すぐ後ろには鏡に向かう佳孝のスネがある。六畳一間にごちゃごちゃと物が置かれたこの部屋では、たいていのものは手を伸ばせば届くところにあった。
「な、なに」
強引にオレの膝の上に引き倒された佳孝は、ゆるめかけたネクタイをほどいてしまうべきか締め直すべきか迷うように手の動きを止め、オレは、佳孝の両脇から腹に回した手を、その手に重ねた。
「ご飯、作んないと」
「いいよ。まだ」
佳孝の背中に鼻っつらを押し当てると、真新しいスーツの匂いがする。
「放してよー」
甘えるように嫌がる佳孝の手からネクタイを奪い去り、そのままシャツの中に滑り込ませようとしたオレの手は、とたんに佳孝の手に押しとどめられた。
「なんだよ」
「スーツ脱いでから」
「なんで」
「シワになるし」
「いいじゃん」
そのままぐるりと体を反転させ、仰向けに押し倒すと、あっけないほど簡単に佳孝の抵抗は終わった。下から伸びてきた両腕が、オレの頭を引き寄せる。
「シワになるよ?」
逆に言ってやると、佳孝は仰向けのまま器用にオレのシャツを脱がせながら、「しょうがないよ」と笑った。
佳孝の部屋に寄るのは、たいてい仕事帰りだ。
だから、くたびれてヨレヨレのスーツを着たオレの姿は、この部屋の風景にすっかり馴染んでしまっていることだろう。
しかし今夜は、いつもは安っぽいパーカーを羽織っている佳孝が、真新しいスーツに身を包んでいる…それだけのことなのに、不思議といつもとは違う空気が部屋に満ちているのだった。
その空気に混じるものは、見知らぬ男と肌を重ねる背徳感にも似ていたし、あるいは、買ったばかりのスーツにシワを作る愚行感みたいなものだったかもしれない。それとも、この先どれだけプレミアがつくか分からないワインを、出荷する前に味見するような贅沢感だったろうか。
そしてそういったささやかな、しかしぞくぞくするような罪悪感をはらんだ空気は、いつも以上にオレを興奮させ、理由は少しばかり異なっていたかもしれないが、佳孝をも興奮させたのに違いなかった。
***
「あと十日かあ」
途中まで見ていたテレビ番組のエンディングとタイミングを合わせたかのように事が済み、しばらくすると、佳孝が用意した夕飯はカレーだった。
昨日もおとといも同じ激辛カレーで、いったい今まで、オレたちは何度この部屋でこうして汗を拭きながらカレーを食べたろうか…と考えても、ちょっと見当がつかない。
「二年なんて、あっという間だったな」
「そうだね」
あっという間に二杯目に取りかかっている佳孝にとって、この二年間はどんな重さを持っているのだろう…。たぶんその答えは、佳孝自身にも、今ここで出せるものではないのだと思う。
「どうせ付き合うなら、もっと早く出会っときゃよかったよ」
「二年が四年でも、やっぱりあっという間だったって言ってるね、絶対」
「そりゃそうだけどさ」
「おかわりは?」
「いる」
腹は一杯だったが、食べなければもったいないような気がした。昨日もおとといも食べた、いつもと同じカレーなのだが。
ただ、同じではあったが、こないだまであんなにゴロゴロ入っていた具はいつの間にか溶けてしまって、見当たらない。そしてその分、コクが増しているように感じる。
「こっちで就職すればよかったのに」
辛さで口が麻痺していたせいかもしれない。ずっと言わずにいて、言うつもりもなかった言葉が、グラスのお茶を飲み干した拍子に飛び出してしまった。――どうして、東京なんかに帰るんだよ。
声にしてしまった言葉をとりつくろう言葉が見つからず、思わず、普段は手をつけない福神漬けに箸をのばしてしまう。佳孝は、「しょうがないよ」と淋しげに笑いながら、三杯目の自分の皿に、オレがもてあますであろう福神漬けを入れるスペースを空ける。
なんとなく気まずくなって視線をさまよわせると、鴨居にさがるスーツが目に入った。真新しいスーツには、さっきつけられたばかりのシワが、くっきり残っている。
「スーツってさ」
視線の先を辿った佳孝が、二年の節目に横たわった小さなぬかるみに足をとられまいとするかのように、そっと呟く。
「今は似合わなくても、毎日着てればみんなも見慣れてくれるよね、きっと」
「そうだな」
応えるオレは、なんとなく分かってしまっている。
たぶん自分には、佳孝のスーツ姿を見慣れる日は来ないのだろう、ということが。
そして、いまスーツに残るシワもいつか消え、その後には、オレの知らない新しいシワが出来るのだろう、ということが。
「ゴールデンウィークにはまた、こっちに来るから」
「ああ」
「浩ちゃんも、東京出張とかあるでしょ?」
「そうだな」
「おかわりは?」
「もういい」
「…離ればなれになるけど、でも、これでお別れじゃないんだから」
佳孝が泣いている気がしたが、顔を見る勇気はない。
黙って肩を引き寄せようとすると、佳孝は「待って」と言って部屋の隅に足を伸ばし、ティッシュケースを引き寄せた。
「カレーがついてる」
オレの口を拭ってから、佳孝はオレの肩に頭をのせた。
あと十日したら、佳孝は新しい生活をスタートさせる。
東京で。
新しくスタートさせるものがないオレは、どうしたらいいのだろう。
手を伸ばしてみたところで、何かを掴めるとは思えない。何にでも手が届いたこの部屋は、もう、なくなってしまうのだ。
「毎日電話するね」
「ああ」
「モーニングコールも、ちゃんと続けるから」
「お前こそ起きれんのか?」
「だーいじょーぶだって」
「夜遊びばっかりすんなよ」
「しないよ、夜遊びなんて」
「まあ、たまにはいいけどさ」
「うん」
「…来月、様子を見に行こうかな」
「じゃあ、初任給で御飯おごってあげる。美味しい店探しとくから」
「いいよ、店なんて」
「どうして」
「お前のカレー食うから」
「そんなんでいいの」
「それが食いたいんだよ」
いろんな言葉や約束を、カレー鍋の中に投げ込んでいるようだった。今はこんなに確かなオレたちの言葉も、いつか溶けて、どれだけ探しても見えなくなってしまうのだろうか。
たぶん、そうなんだと思う。
それでも今はただ、鍋が冷えぬよう、煮立たぬよう、じっくりと弱火で煮込むときなのだ、きっと。いつか、何ひとつ具が見えなくなったときに、コクのあるカレーができあがっているように。
「荷造り、始めないとな」
何から片付けたらいいのだろう。
山のように転がる大切なガラクタを運び去った後の、がらんとした部屋を想像してみる。
何故か、ちょっとシワになったスーツだけは、いつまでも鴨居にぶら下がっているような気がした。
(おわり)


















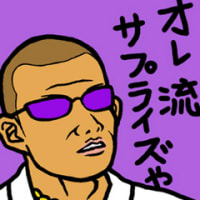

いくつか読ませていただいたコラムも良かったですが
小説もっと読みたいです
更新長くされてないようですが
少しずつ過去ログ読ませていただきます
また更新される日も待ってます