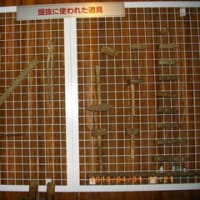昨日の水曜日ブログは所用のため休みました。さて本日の木曜日ブログ、前回(4/20)は全国的な「枯村」現象についての話でした。これは百姓の退転(出奔・欠落・不斗出)によって生じる農村荒廃のことです。度々の利根川洪水によって前橋城が被害を受け、ついに明和四年(一七六七)に川越への移城が許され、それ以来、善養寺領を含む前橋藩領は江戸期を通して川越藩前橋陣屋の支配を受けることになりました。それを川越藩の他領地と区別して「前橋領分」と呼んできました。また以下の引用のように「前橋藩」と書いてあるものは、川越藩「前橋領分」のことです。さて、「枯村」現象は前回の引用によれば、十八世紀中頃にはすでに全国的な現象だったことになります。土地があってもそこに耕す百姓がいなくなる、このような事態に前橋陣屋はどのような手を打ったのか。これが今回の話ですが、五三歳の林八右衛門が再び名主になり藩の政策に協力していくことになるのが、文政二年(一八一九)のことですから、この枯村現象は十九世紀になっても続いていたことになります。
≪前橋藩は、このような状況に対して手を打たなければならない。そのまま放置しておけば、年貢収奪の基盤が崩壊してしまう。文化十年(一八一三)に、幕府から公金一四六二両を六ヶ年賦で借り入れて、領内に囲籾(かこいもみ)策をすすめたのはその一つだが、そのような備荒対策だけで切りぬけるには村と百姓の疲弊はあまりにも深かった。
八右衛門が名主に復帰した文政二年に設置された勧農役所は、前橋藩なりの抜本的な対策をおしすすめるための機構であり、期待は大きかったと思われる。この勧農役所は前橋役所とはいちおう別個の機構であったらしい。勧農役所には、石川茂登造、小川銀蔵という二人に代官が任命されてやってきた。二人の代官の下に、附属と呼ばれる役職を設け、五人の百姓・町人をえらんで配置した。どんな場合でも、農村復興の鍵は、村々の百姓たちに対して実際に経済的な実力を中心にした支配力を持っている富裕な百姓や町人を、藩の政策に協力させうるかどうかにある。「枯村」の状況は、原因がなんであるにせよ、直接のきっかけは借金が返済できないということにあるのだから、一方に多数の没落農民を生み出すと同時に、他方に高利を貪って富裕になる少数者を生み出す。矛盾した考えなのだが、藩からみれば。結局この少数者を掌握して村の立て直しをはかる以外にないのである。前橋藩が勧農役所の附属役に任命した木暮村の須田六郎右衛門と須田祐右衛門向領国分村の住谷武兵衛、前橋領力丸村の羽鳥幸五郎、前橋竪町の大嶋久兵衛の五人は、そういう少数者にはいる者たちだったと考えてさしつかえない。
この五人の附属の下に野廻(のまわ)りという役が設置され、前橋領内の各支配区域から一人ずつ、計八人が任命された。善養寺領の野廻り役に、新しい林本家の名跡者で名主に復帰したばかりの八右衛門が選ばれた理由はなんだったろうか。任命の基準はわからないが、ともあれ八右衛門は東善養寺村の名主になるとともに善養寺領全体にわたる日常的な在村指導者として野廻り役をひきうけている。前橋市立図書館におさめられている『前橋藩日記』──正しくは『記録』という──には、八右衛門が野廻り廻村出精(しゅっせい)の理由で褒美金を得ている記事がある。八右衛門は熱心な野廻り役の一人だったにちがいない。
八右衛門と同時に野廻り役を命じられた他の七人は、八崎村田中清六、横室村金沢銀二郎、片貝村弥兵衛、大室村山田萬蔵、小相木村梅山弥左衛門、玉村下新田大黒屋清兵衛、公田村石原忠次である。
勧農役所が最初にとりかかった農村復興策は、作り手がなく村々で手余(テアマ)りになっている荒地に、越後・信濃から「御雇人(おやといにん)」を入れて開発させ、工作させることであった。これは、いわば藩直営の農場経営とでもいうべきもので、おそらく八右衛門らにとってもはじめて経験する奇妙な仕法(しほう)であったろう。しかし、その結果は、食糧代、種籾代、肥料代、諸道具代、農具代などの支出額と収入になる収穫穀物をひきくらべてみると、藩の大きな損失になった。
このとき、八右衛門の村では上(アガ)り地が一町六反一二歩におよんでいた。上り地というのは、百姓が耕作を放棄して領主に返還した土地、したがって年貢を領主にもたらさない土地である。上り地という状態は、一つは耕地の真の所有者が領主であると考えられているということと、もう一つは一年かぎりの荒地としてではなく無年貢地になったことを農民の要求によって領主に認めさせたということの二つの前提がある。しかし、たとえ土地に対する領主の所有権が明確であっても、このような、百姓の「土地緊縛」を維持できなくなった土地になんの意味があろうか。前橋藩勧農役所は、このような土地の生産力を回復するために領主直営方式でのぞんだのである。このことを八右衛門は、
「数年来荒地に相なり候所、その年、御領主へお引請(ひきうけ)になられ」(巻之一)
と記している。百姓が放棄した土地を領主が「お引請」になるというのはいぶかしいことだったろう。≫(深谷克己『八右衛門・兵助・伴助』朝日新聞社 一九七八 三二から四頁)
覚書にしておきたいのは三つ。一つは、「一揆」や「打こわし」の爆発的な高揚期をイメージするときの百姓や都市困窮民の集団について、です。かの闘争集団は一枚岩で矛盾のないものと思いがちだけれども、実際に平常でもそんなことはありえない、「一揆」という言葉そのものが喚起するような、一時的であれ、全体利害が一致することなどそうそうありえない、ということです。「枯村」の状況の「原因がなんであるにせよ、直接のきっかけは借金が返済できないということにあるのだから、一方に多数の没落農民を生み出すと同時に、他方に高利を貪って富裕になる少数者を生み出す。矛盾した考えなのだが、藩からみれば、結局この少数者を掌握して村の立て直しをはかる以外にない」という現実が招く矛盾を念頭におくべきことです。この富裕な少数百姓と借金が返せない多数の没落農民のあいだには、上下どちらの層にも利害関係を持っている一定の中間層が存在するはずです。とすれば、復興策が結局どの階層に役立っていくのかは、その具体化のなかでねじ曲げられていく可能性を観察する必要があります。このことは闘争が集団化して行けばいくほど顕在化していくはずです。
二つは、「上(アガ)り地」を認めざるをえないという事例は、全国的にはどの程度あったのだろうかという疑問もここで記しておきたい。幕藩制の原則が百姓を土地にきつく縛り付けておかなくては成り立たないという認識は、どこでどのような契機によって崩されていったのか。農村における消費地(町)の誕生や、あるいは、田畑が売買の対象になったことがその契機になったのだろうか。素人は色々考えるが、どうなのか知りたい。これに関連してもうひとつ。
三つめは、「土地緊縛」を絶対だと思ってきた百姓にとっては、「家相続の願い」はこれとセットになっている要件のはずです。「家相続」(家督)が崩れていく契機を、柳田國男はたしか、親がどの我が子も愛しいと思い始め、その幸福を実際に援助し始めたときだと述べていた(『明治大正史世相篇』)と記憶しているけれど、これはどの程度実証されているものなのか。身近な実際例を知る私としては、この仮説はかなり当たっていると思うが。確かめてみたい。